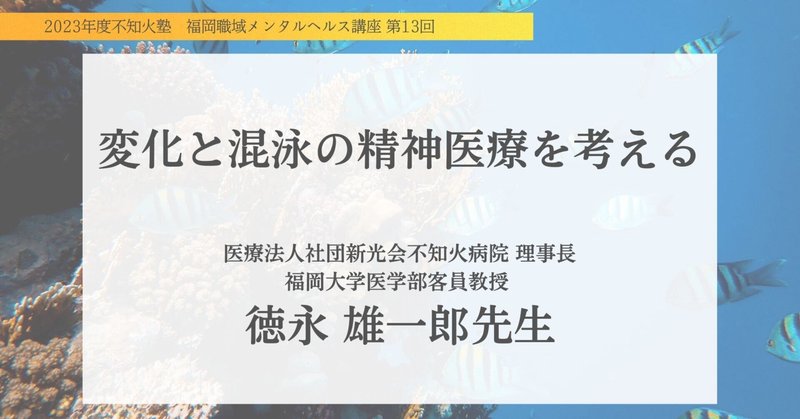
多様性の時代における精神疾患の病態変化とは
不知火塾 第13回目は、医療法人社団新光会不知火病院 理事長/福岡大学医学部客員教授 徳永 雄一郎先生による「変化と混泳の精神医療を考える」がテーマでした。
「混泳」という聞きなれない言葉から始まった今回の不知火塾。
混泳とは多くの種類の魚を飼うことを意味しますが、 どう猛な魚の場合、他の魚を食べてしまったり、口先などで突いてしまったりするため魚種の選定に注意が必要なんだそう。
精神医療の現場では、病態の混泳が生じているそうです。
実際には、どういった状況なのでしょうか。
治療方針の個別性が必要に
徳永先生は病態の混泳により、従来のマニュアルでは充分ではなく個別的な治療が必要だとおっしゃいます。
発達障害やADHDなどの問題も加わり、病態は複雑化しているそう。
精神疾患に関わる変化について説明いただきました。
◆ 時代とともに変わった3つのこと
①産業構造の変化
現在、対面からオンラインへの移行が進んでいます。
IT化により目や手、脳が偏在活用され、耳、鼻、皮膚、足、口、筋肉などがほとんど使用されなくなったため、五感への刺激の乏しさ、身体や脳の使用しない部位の衰退が懸念されているそうです。
②平均寿命の変化
平均寿命の延伸により、自己イメージや就労イメージも変わり、思春期も延長しているという見解もあるとのこと。
③感情の変化
統合失調症や双極性障害は遺伝負因が高いと言われてきましたが、現在、統合失調症や興奮の強い双極性障害患者は減少傾向にあるそうです。
うつ病も自責から他罰へと相手を攻める自己愛型の要素が現れているとおっしゃいました。
こうした変化の結果どういった状況が起こっているのでしょうか。
はびこる安易な他者批判
批判的態度・自己批判のメディアは少なく、教師は保護者から、公務員は市民からの批判が増え、国民総批判の時代になったとおっしゃいます。
◆ クレーマー心理と増加の意味
クレーマーは自身の問題が大きいにもかかわらず、問題をすりかえ他者を批判する(外在化)と述べられます。
悲しさ・淋しさの感情を、自分で受け止めきれない背景があるのではないかとおっしゃいます。
徳永先生はクレーマーの増加と抑うつ感情を抱える人の増加の関連をお考えでした。
◆ 攻撃性はどこから来るのか?
S.フロイト、E.フロムは「親から攻撃を受け、傷ついた子供は成長するに従って、親と同じ行動を他者に行うようになってくる」と述べていますが、現代の攻撃には、感情を抑えられ傷つけられた経験も含まれるのこと。
親から健康的に大事にされた体験があると「いじめ」がおこらない、問題があってもその後の修正体験があると職場や学校で、愛情を注げるようになるとおっしゃいます。
親との課題については以下のことを説明されました。
● 直接的暴力、いじめ
● 間接的いじめ:過干渉、無視
● 体験不足:死別、離別、親の多忙
成長段階で修正体験がなく、親との問題を持ち越すと職場や学校で「いじめ」や「無視」が発生する可能性を示唆され、いじめの世代間連鎖についても触れられました。
*
若年層の減少による労働力不足やIT化が進む現代社会では、特に若い世代のメンタルヘルス課題が深刻化すると話されます。
コロナ禍の影響で増加している自殺の問題、希死念慮についても示されました。
希死念慮への対応とポイント
希死念慮に関してもさまざまな変化がみられているとのこと。
◆ うつ病=希死念慮ではない
特に若年層においては、症状を呈する前から希死念慮が出現していることがあるため、いつから希死念慮があるかをカルテに記載することをポイントとして挙げられました。
うつ病=希死念慮ではない時代になり、希死念慮の確認ミスは医療事故に直結してしまうおそれがあるとのこと。
責任問題や裁判への意識もふまえて、希死念慮の確認が重要だとおっしゃいます。
◆ 希死念慮は隠れやすい
希死念慮をチェックする質問表において、対面式と自記式で希死念慮の有無には、大きな差があると話されました。
対面式で希死念慮が「なし」と回答した77%の人に、自記式で確認すると約50%の人が希死念慮が「あり」と答えたそうです。
年代別にみると特に、30代、40代、50代において希死念慮が隠蔽されやすいことがわかったとのこと。
希死念慮の確認には慎重にならなければならないと指摘されました。
◆ 「自殺は回復期に起こりやすい」は本当?
うつ病入院患者の50%が入院から1ヵ月以内の初期に希死念慮がみられたという研究結果を紹介いただきました。
「自殺は回復期におこりやすい」と言われていますが、再検討の余地があるとおっしゃいます。
24時間以内に、自殺既遂者は重要な相談をしていることも判明しているそう。
◆ 若年層のうつ病
若年層ほど希死念慮が残りやすいことも説明いただきました。
家庭や学校で人と向き合う、直面化体験が少ないと問題が発生しやすいと事例を通して示されました。
自己愛傾向や他罰性によって、積極的な治療が必要な患者も少なくないとおっしゃいます。
症状の状況依存的変化、攻撃性や他罰性、自己愛性と回避などの特徴がある若年層にTEG診断(東大式エゴグラム)を実施したところ、その特徴とは反して感情表出を抑え、周囲との協調が目立った結果になったとのこと。
家族意識が薄れる現代社会で、家族よりも仲間にアイデンティティの主軸を移行し始めているのかもしれないとお考えでした。
薬物療法からみた初診時対応
うつ病では「頼りたい」と「依存したくない」というアンビバレントな感情が発生するとのこと。
◆ 情報化社会による患者意識の変化
最近ではインターネットなどで事前に情報収集し、自己診断して来院する患者さんも多いそうです。
初診時の一錠の服用にも警戒的で、依存性の有無や離脱症状について聞かれることもあるとおっしゃいます。
徳永先生は、初診の段階で「減薬にも離脱症状の少ない薬です」と伝えることが患者さんとの信頼関係構築に繋がると説明されました。
初診時から抗うつ剤投与する場合もあれば、警戒心が強い時は眠剤のみを投与、反応をみて2回目からの抗うつ薬を投与するなど患者さんに合わせて対応してらっしゃるそうです。
今回の講座では、入院から1ヵ月以内の初期に自殺既遂がみられたということが特に印象に残りました。うつ病の自殺=回復期におこりやすいと看護学校時代から当たり前に学んできたため目から鱗でした。
時代とともに病態も変化しており、変化に敏感でなければならないと感じさせられる内容でした。
また、対面式と自記式における希死念慮の有無の違いにも驚きました。希死念慮は言葉に出しにくいことを念頭に置いて患者さんと関わっていきたいと思います。
貴重なお話をありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
