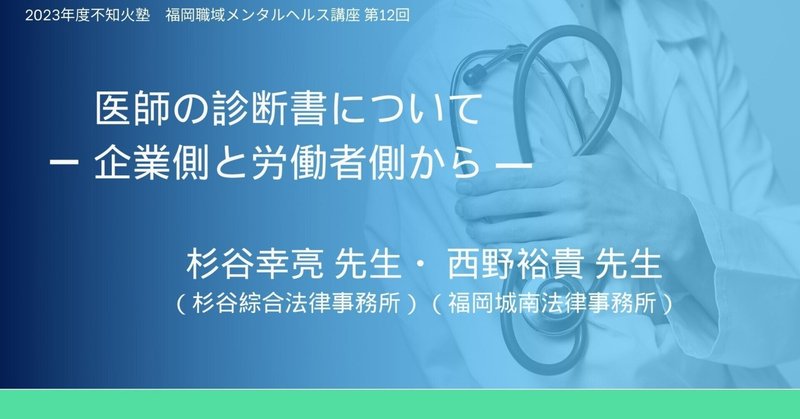
増加する産業医の裁判事例~法的ポイントとは?~
労働者がメンタルヘルス問題から復職する場合、労働者・事業者間で問題が起きやすく、産業医が関与する裁判例が増えています。
産業医の役割や法的責任を今一度確認し、どういった点に注意すればいいのか学んでみましょう。
不知火塾 第12回目は、弁護士の杉谷幸亮先生(杉谷綜合法律事務所)、西野裕貴先生(福岡城南法律事務所)による「医師の診断書についてー企業側と労働者側からー」がテーマでした。
産業医の役割・法的責任
前半は、労働事件(使用者側)などを取り扱われていらっしゃる杉谷先生からのお話でした。
産業医が関与した裁判例は、平成26年1月から令和5年1月までの10年間とその前の10年間を比べると、約2倍に増加しているそうです。
これは産業医が「被告」としてではなく「裁判に関わる事例」の増加を意味しますが、産業医も「被告」となり得るとおっしゃいます。
休職中の従業員との面談で産業医の発言が、従業員に対する注意義務違反に認定された例もあるそう。
産業医が被告になることや、企業が労働者に対して損害賠償責任を問われた際に、産業医の意見や行為が裁判で問題とされる可能性を示されます。
あらためて、産業医の役割を確認させていただきました。
◆ 産業医の役割
産業医と臨床医の役割は下記のように整理されます。
● 産業医の役割
:事業者・産業医間における契約に基づき、事業者が労働安全衛生法上の安全健康確保の義務や労働契約法上の安全配慮を果たすための意見を述べること。
● 臨床医の役割
:医師・患者間における医療契約に基づき、健康問題に対して診断と治療を行うこと。
「産業医」は所定勤務時間の就労が可能か、可能とした場合の適切な配属先や勤務内容、必要となる就労上の配慮はどのようなものかという観点から意見を述べるのに対し、「臨床医」は主に、患者の体調が回復したか、症状が改善したか、安定して日常生活を送ることができるかなどの観点から診断を行うと説明されました。
このような役割の違いを考えると、臨床医が作成した診断書内容が肯定できるとしても、職務における労働者の健康問題(復職等)の判断にあたって産業医と労働者の面談は行われる必要があると述べられます。
◆ 産業医と事業者の法的関係
産業医と事業者は産業医契約を締結しますが実体上、準委任契約に最も近いと言われているそうです。
労働安全衛生法と労働安全衛生規則には、以下の内容が産業医の職務として規定されているとのこと。
● 産業医の職務は労働者の安全と健康の確保、労働環境の改善、快適な職場環境を形成するために、事業者に対して勧告、助言、指導を行うこと。
● 事業者は産業医の勧告を尊重しなければならない。
● 産業医が勧告・指導・助言をしたことを理由に、産業医に対して解任その他不利益な取り扱いをしてはならない。
このように産業医は法的に中立的で独立的な立場で職務に当たることが義務付けられています。
つまり、雇用契約とは異なり、産業医は自身の裁量をもって業務を遂行するものとされているようです。
また労働者の労働安全衛生について【事業者】が労働者に対して義務を負い、【産業医が履行補助者】として、事業者の義務の履行を行うと解釈されるため、産業医や事業者が職務内容を実施しない場合、事業者の安全配慮義務違反になる得るとのこと。
事業者が産業医の助言を得ることなく従業員を職場復帰させた結果、従業員が自殺に追い込まれた事案を紹介いただき、産業医の医学的意見の重要性を述べられました。
そのため産業医への期待も年々高まっているようです。
◆ 産業医への期待
2019年4月1日に改正された働き方改革の関連法により、産業医機能が強まったのこと。
そのポイントは以下の2つだと説明されました。
● 独立性・中立性の強化
● 産業医への権限・情報提供の充実・強化
このように産業医に対する期待が高まり、長時間労働やメンタルヘルスの問題による健康リスクが高い労働者を見逃さないことを目的として法改正がなされたとのこと。
今後はそういった労働者を「見逃した」ことや、労働者の症状を増悪させたとして、産業医が責任を問われるケースが増加する可能性を示唆されました。
現在、産業医が訴訟に関わる代表的なケースは3つとのこと。
● 復職判定
● 企業の安全配慮義務
● 労働者のプライバシーに関するケース
今回はこれらのうち、復職判定について取り上げていただきました。
復職の意義・基準
後半は九州労働弁護団や日本過労死弁護団に所属されている西野先生からのお話でした。
復職可能という判断には、医学的な概念と法的な概念とあるとのことで、後者の概念についてお話しいただきました。
◆ 復職の法的概念
法的な意味での「復職」は休職事由の消滅を指しており、原則として休む前に行っていた業務を通常程度で遂行できる状態を指すそうです。
法的な意味での復職の定義を紹介いただきましたが、重要なのはこの原則に当てはまらない例外とのこと。
◆ 注意すべき例外
復職の基準には<例外も視野に入れて復職の可否を判断しているかが重要>であると話されます。
元の業務を通常程度にできない場合でも、裁判例上は復職の要件を満たすと考えられてる場面を2つ紹介いただきました。
※ 例外の2つの場面
【1】当初軽作業に就かせればほどなく通常程度にできる状態になっている場合
【2】①職種限定がなく②他業務へ配転の現実的可能性があり③その提供の申出がある場合
産業医としては、労働者の状態を詳細に評価し、回復の見込みや必要な配慮について法的観点からも意見を求められているとのこと。
事案を交えて、それぞれ説明いただきました。
医師の意見の法的評価
裁判所は以下の7つの要素において医師の意見の信用性を判断すると思われるとのことです。
1.患者または労働者が従前に従事していた業務内容やストレス要因を正確に把握しているか。
2.その業務内容を通常程度に行えるかについて、検討が行われているか。
3.患者または労働者のリワークプログラムの結果が、会社での言動にどのように影響しているかが考慮されているか。
4.休職後の治療状況や改善状況が考慮されているか。
5.患者または労働者の意見や移行に関する配慮が適切に行われているか。
6.診察回数や診察時間が十分であるか。
7.診断内容、医療内容、改善状況が裁判所に分かりやすい形で伝えられているか。
それぞれ裁判例をもとに説明いただきました。
主治医から見えやすいもの見えにくいもの、産業医から見えやすいもの見えにくいものがあるため、見えにくいものをいかに見たうえで意見を出すことが重要だと述べられました。
法律の知識に触れる機会はなかなか少なく、難しい部分もありましたが多くの裁判例を紹介してくださり、法的な視点での理解が深まりました。
看護師は診断書を書く立場にはありませんが、医療に関わる者として、厚生労働省の心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きをあらためて読んでみようと思いました。
貴重なお話をありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
