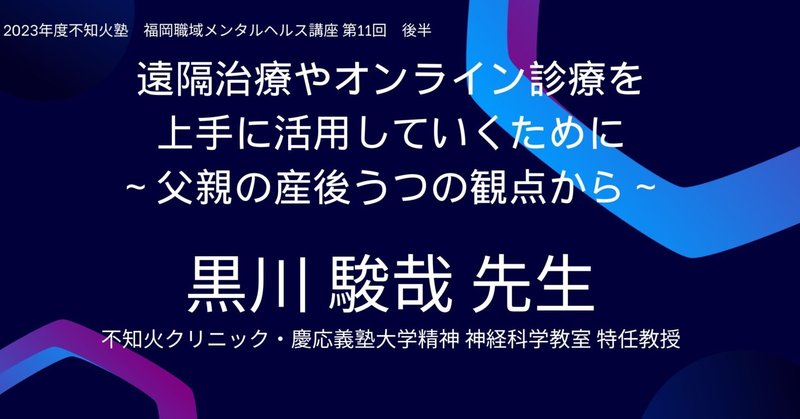
産業医からみた”父親の産後うつ”その背景と実態
SNSでも話題になった”父親の産後うつ”。
私は正直その言葉を聞いたとき、ピンときませんでした。
女性と違って、身体的な負担やホルモンの乱れがあるわけじゃないし……、と。
しかし、今回の講座を受講して考え方が変わりました。
不知火塾 第11回目は二部構成でした。
後半は不知火クリニック・慶応義塾大学精神 神経科学教室 特任教授 黒川駿哉先生による「遠隔治療やオンライン診療を上手に活用していくために~父親の産後うつの観点から~」がテーマ。
前半はこちら。
女性の家事・育児の負担
黒川先生は他の先進国と比較し、日本は女性が家事と育児にかなりの負担を担っている傾向があると説明されます。
この背景から2020年までに、育児時間を150分に増やそうというキャンペーンが展開され「イクメン」という流行語が生まれたと説明されます。
2022年に父親の育休取得キャンペーンも行われ、父親の育休取得促進のため、男性版産休「産後パパ育休」が新設され、大企業では育休取得率の公共が義務化されるまでになったそう。
日本の父親の裏の真実
ある調査によると、日本の父親が家族に費やしている時間は海外9カ国中で最も多いことが示されており、実際には限られた時間で精一杯育児に取り組んでいることも明らかにされているとのこと。
男女ともに育児に関与していることで有名なスウェーデンと比較すると、日本の父親は仕事時間・通勤時間が長く、限られた自由時間のなかで家族・家事に費やす時間の割合が大きいと判明したそうです。
このようなデータから、政府の目標を達成するためには、父親の労働時間や通勤時間を減らす必要があるという提言がなされていると話されます。
しかし、実際の仕事関連時間は父親の約70%が10時間以上、36%が12時間以上もあるそうです。
産業医の視点と父親の産後の抑うつリスク
産業医活動のなかで、育休取得への現場理解がまだ追いついていないことを
感じているようです。
妻の妊娠や出産を会社に伝えた男性正社員の63%は、会社からの説明や働きかけが得られなかったとのこと。
しかし、父親の役割は確実に変化をしています。
◆ 父親の役割の変化
数年前の海外の状況と似た経過をたどるかのように、日本も父親の役割が一家の大黒柱+母親のサポート+育児の主体者としての役割が強まっていると話されました。
一方で、父親が男性として肉体的・精神的に強くなければならないというステレオタイプのプレッシャーもあるとのこと。
父親役割が変化しつつも、このような『母親の方が大変なんだから……』『父親なんだから……』といったステレオタイプのイメージもあるため、父親の産後うつリスクが高まっているようです。
◆ 産後の抑うつリスクは母親だけではない
母親の産後うつの有病率は10~15%、父親も同様の確率で産後うつのリスクがあるとの報告がされており、夫婦のどちらかがメンタル不調に陥る例は15%にも上るとのこと。
父親の10人に1人が産後うつのリスクがあり、産前から産後1年においては、特に注意が必要と述べられました。
直接的に「育児が」と話せない父親の「隠れ産後うつ」がいる可能性にも触れられます。
父親の産後うつは母親と同程度に存在し、男性版産後育休の普及により、今後増加することが予想されるものの、産業保健領域では気付かれにくいことをご指摘。
周産期の父親には、夫婦のコミュニケーション、妻のサポートや父親自身の大変さに寄り添いサポート資源に繋ぐことが大事だと話されました。
これからの親子支援には父親も含め、知識不足や孤立を防ぎ、父親にも抑うつのスクリーニングを実施し、介入していく必要性を説かれました。
オンライン診療・AI活用のメリット
産業保健と産後うつにおけるオンライン診療・AI活用のメリットを以下のようにまとめられました。
オンライン診療やAIを活用したスクリーニングは、今後の医療の展開で非常に重要な役割を果たすとのこと。
特に地方に住む人や、時間が限られている人にとって、オンラインでの医療サービスの提供は通院往復と待ち時間を含めると約97分の時間短縮にもなり、非常に有益だと述べられます。
生体データやAIを用いたスクリーニングやオンライン診療によってリスク者を拾い上げることが可能になる可能性も説明されました。
社内でのオンラインでの交流・相談の場の検証が必要なこと、産業保健スタッフが注意深く背景情報に意識を向けることが重要だと話されました。
共働き夫婦が増えるなか、女性にばかり家事・育児負担がかかっているという個人的なイメージがありました。
日本の父親が限られた自由時間のなかで家族・家事に最も時間を割いているというお話は目から鱗でした。
「男性」というステレオタイプが、育児の辛さを話しづらくさせている点についても考えたことがありませんでした。
そういった育児の辛さを男性も共有し合える場が必要であり、それがオンラインであればより参加できる人も増えるのではないかと思いました。
実体験に基づいた非常に説得力のあるお話を、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
