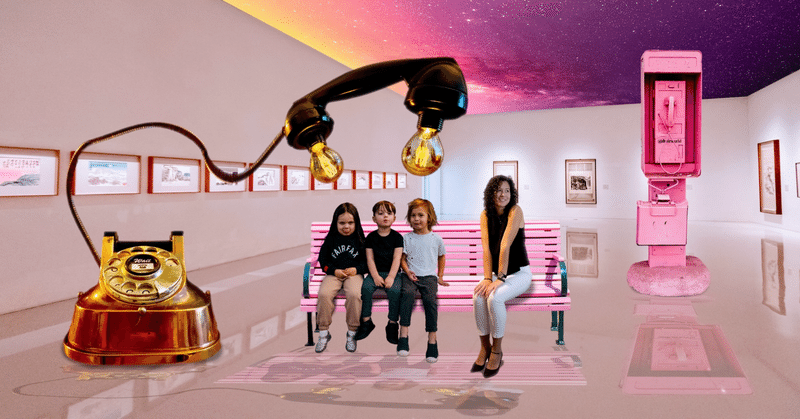
企業である以上、事業に対して何かしら集客(方法)を行っているので、これらに対しての「反響」(お客様からの問い合わせ等)を得ているはずです。当然ながら、新規契約率(OB含む)を出していると思いますが、単純に契約率を向上させろ!という掛け声だけでは根拠がありません。それこそ精神論や根性論になってしまうでしょう。
ここで少し数値的に見て生産性を講じることができるかどうか分析をして見ましょう。
反響内容等は既に把握しているはずなので、これらの反響内容からカテゴリー別に契約率を算出し、自社の強い部分や弱い部分、その反響率と整合性を掛け合わせて見ましょう。
そうすると、月単位含めその集客方法による反響効率というのが見えてきます。すなわち「反響総額」(仮造語)である。これが算出できれば、どんなに頑張っても契約率が上がらない(競合には勝てない)内容等が見えて来ます。ここを無理をしてでも強化するより、逆に強味が活かせる契約率が高い内容の反響にこだわる方が賢明である。
つまり、自社の取組み事業において優越が把握できるのである。こうすることで、当月の反響からの売上(見込み)が必然的に見えてくるので(精度が上がれば上がるほど確実性が高まる)、足らない部分などは、広告を強化するか、又は店ごとにイベント等(SLM(ショップレベルマーケティング))を開催するなど調整ができます。これはマネージャーの仕事です。(SLM=利益のピラミッドを参照)
「科学する」という事は「分析」を行い、その結果に対して的確に生産性を講じることができる対策を事前に組むことです。
すなわち事前に「見込み顧客」(定義付けられた)という件数と内容がわかって入れば、当月含め三ヵ月(最低でも)単位くらいで、勝算が高い売上数字が見込めるという事である。
リーダーが存在してもマネージングができなければ、最終日を向かえる(終える)までは、
その月の数字も分からなければ、翌月の見込み数字も把握できていない事になる。この繰り返しを毎月行っているようでは、当然ながら目標数字は絵に描いた餅であり部下が困惑することになるでしょう。
毎月未達成で目標から累積された数字など、かけ離れた目標設定が降りかかるだけで、スタッフのモチベーションアップには繋がらない。どんなに無理をしても到底達成できない目標数値など、部下は鼻っから相手にしていないのである。目標達成させるためには、あと少しで手が届くくらいの、頑張れる範囲を設定しなければモチベーションは上がらないどころか、マイナスに転じてしまう可能性があり弱体化することは見えている。
商談にも手順やルールがあるが、基本的には心理を上手く利用(活用)することである。
好感度が良ければ信頼度への道が早くなるのである。そこでは誠実性など(もちろん嘘はダメ)、信頼度と好感度を高めることに努めた方が良いでしょう。一度落ちた信用度を回復させることはクロージングよりも困難です。つまり好感度と信頼度を無くして、クロージングスキルだけで、一気に持ち込めるほど商談もお客様も甘くないのである。昔はこのへんをすっとばして、根性論や精神論で補って来たでしょうが、売るロジックにも売れるロジックにも、普遍性の法則は変わらないのです。
売れるスタッフは、一所懸命に質問(訊く)しています。そして、損をする(デメリット)こともしっかり伝えています。一方で売れないスタッフは、一所懸命でありながらも説明(話し)するばかりで、しかもメリットしか伝えていません。
同席や同行、OJTなどは、単に横に座っているだけではないのです。教育の場であり、先輩や上司は優越感もあるでしょうが、逆に大恥をかくところの場でもあるのです。私も管理職として現場に出て行っていましたが、そのプレッシャーは良く受けていました。もちろん必死になって商談をまとめようとしますが、ある時から思考を変えてみました。これは誰の商談なのか、、、と。
良い商談もあれば悪い商談もあるかも知れません。それでもセオリーをないがしろにしない限りは、良い商談だと肯定することです。つまり「任せる」ことが必要なのです。この「任せる」というミッションこそが、担当者のモチベーションアップに繋がるのです。経営陣であれば、スタッフに任せた時点で不評に終わるかも知れませんが(恐らく半分くらいの確立で)、そうしないと育っては行けません。その「責任」を取る上司の姿勢こそが、企業姿勢にも繋がるし組織強化にもなっていることを知るべきでしょう。トップ判断である経営手腕も同様でしょう。任せることの不安よりも、任せられるスタッフを育て上げることです。
我々の仕事や行動等は、確かに数字的に「科学」できる分析を持っていますし、効率、非効率とはどういうことかなど、生産性を問われ責任を取っていきます。
しかしながら「科学」では解明できない、分析指標では判明できない事があります。
「情熱」や「心意気」、「コミュニケーション」などは、メンタルな部分です。組織であれば嫌いな人や合わない人とも仕事をしなければなりません。家族が入れば本人含め生活を守って向上させなければならないでしょう。住宅ローンや教育費などは、給料がUPしないことには成し得ない生活です。
ただツールが多い事も功罪になるケースがある。丁寧にすることがツールに繋がらないのである。確認することは大事だが、ツールの説明だけにこだわってしまい、目的であるお客様の意思決定を逃してしまうのである。ツールを説明することが目的でなく、真の目的達成の為にツールが存在すること、目的達成の為にツールを利用することの「目的」を明確に指導しなければなりません。幾度となくこの場でも伝えて来ましたが、最近の企業ではこの「目的」を十分に伝えることが苦手なようです。むしろ伝えていないのでしょうか。本人もその目的を掌握していないケースが大半なのでしょうか。
成功事例を共有させるということはどういう事なのか。成功事例は何を意味することなのかを理解しよう。成功事例モデルの教科書であることから、即効性の再現性を求めているのである。また、成功事例を発表する登壇者のプレゼンテーション強化であり、自信を持たせることで自己肯定感を高めることに繋がり、会社全員で共有することで一体感高めモチベーション(士気)を向上させるのです。
こういう言い方をすると「これをやろう!」とか「あれを決めよう!」ことになり兼ねないが、膨大な情報量の中から最適なモノを選択しなければならないから、時間も労力もかかる。大事なことは、むしろ「やってはいけないこと」「禁止」を決める方が早いのである。それは「制限」であったり、それは「禁止」であったり、それは「推奨」など、哲学や流儀を決めることは、これらの「法則」を決めることである。
我々は住宅や建築という、ある意味、規模の大きい仕事を行っていると思いますが、大事なことは規模の大きさではなく、価値の大きさを重視しましょう。
ゴールで失敗しているという事は、プロセス段階で既に失敗していること。営業を科学するという本質の部分を見誤った見解を見極めよう。マネジメントするということは「最適化」をおこなうことであるということを理解して欲しい。
