
義務教育のオンライン化はいつ頃になりますか
ようこそ、お越しくださいました。
はじめましての方から頻繁に起こしいただく方まで、ようこそ。 どうも、えんどう @ryosuke_endo です。
このnoteでは、特に読む必要がないと感じられることかもしれないけれど、ぼくがだれかと対面して話したい”雑談”を文字化するものなので、そんな雑談にお付き合いくださる方は、ぜひ読み進めてください。
今回の話題は、我が家でぼくの隣に座り続ける長男くんを見ながら思っていることの一つである義務教育のオンライン化。放送大学みたいに高等教育では社会実装されているのだから、義務教育期間もオンラインで推奨すればいいのに…なんて心持ちから考えていることについて。
▶︎ 義務教育にだって個人の環境に対する合う合わないはある
我が家の長男くんが不登校化してから半年ほど経過しました。特段、心配をするわけでもないのですが、仲のいい友人と交友できていない部分に関してはかわいそうに思うぐらい。
それだって、当人たち同士でやり取りができるような工夫なんていくらでもネットの恩恵を授かればできるはずなので、大して心配はしていません。
ただ、義務教育だからといって学校に出向かなければならないわけでもないでしょうし、代替する学習方法はいくらでもあります。我が家もBenesseの通信教育を受けておりますが、能動的な学習をするって意味では大変よくつくられているなぁ...と感心してしまいます。
義務教育を課せられているのは保護養育者たる大人たちであるわけで、彼らに教育を受ける準備を整えることに義務が課せられているわけです。ところが、子どもたちも人格を保有する一人の人間ですから環境に合う合わないはどうしても生じてくるでしょう。
成人になっていたとしても会社への合う合わないや社会生活への不適合があるように、子どもたちにだって向き不向き、得手不得手ってのがあるのだから「学校に行くべき」だなんて口が裂けてもいえません。
むしろ、いうべきではないのではないかとすら思っている次第です。
▷ 年々増加する不登校
義務教育における不登校の状況を文部科学省がまとめているのですが、年々増加傾向です。この数字はおそらく更に増えていくでしょうし、減少することがあるのだとしたら学校への登校方法が見直された時でしょう。


R2児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要 _文部科学省.pdf
つまり、現状の学校教育システムにおける登校状態を見直すことになれば、いわゆる「不登校」なんてステータスが解消される児童・生徒の数が増えることになるため、結果的に不登校はなくなっていくことになります。
現状はまだ母数に対して大きな割合にはなっていませんが、学校の中で「生きづらさ」や「ここではない感」を味わっている児童・生徒は不登校となっている数値よりも多いことは想像に難くありません。(まぁ、想像でしかありませんが…)
潜在的な不登校予備軍はさらに多くの割合なのだと仮定すると、仮に30%以上もの児童生徒がそのように学校への違和感や生きづらさみたいなものを実感しているようならば、すでに学校教育のシステム自体が人間に適合していないということすらできます。
そら、明治時代から何にも変化していないって時点で「そりゃそうだよね」って話になるのですが、そうならないのは学校生活のおかげで充実した人生を送れていると実感している人たちが教育システムを構築しているからっていうどうしようもない理由からでないことを願いたいです。
▷ 国際平均よりも多い現場にいる教員の勤務時間
TALIS(Teaching and Learning International Survey:国際教員指導環境調査)でOECD加盟国内に向けて行われる学校の学習環境と教員の勤務環境に焦点を当てた調査をみてみると、日本国内で活動する現場の教員が大変に忙しいことがわかります。
教員の一週間あたりの仕事時間をみてみると、国際平均は38.3時間であるのに対し日本のそれは小学校で54.4時間、中学校で56時間と大きく上回っています。
週に8時間労働を原則とした場合、40時間を原則だとしたら15,6時間の超過勤務をしていることになり、日に3時間以上の残業をしているといえます。月に換算すると216時間ですから、160時間をベースとして考えると月の残業時間は56時間となります。

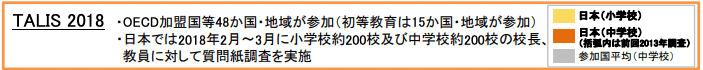
教員の抱えるストレスに何があるのかって調査項目を見てみると、「事務的な業務が多すぎること」があがってきています。

ぼくなんかは紙で扱うような事務仕事や紙での書類制作をやめてしまえばいいのに…って簡単に思ってしまうわけですが、現場はそう簡単に変わらないから困っているのでしょうか。
ただ、非効率な運営になってしまっていることは日常的に子どもたちが持って帰ってきたり配布されるプリント類をみれば一目瞭然です。
彼らに配布されているタブレット端末でいかようにもなるはずなのに、どうしてそれを利活用しないのか。もちろん、活用されていることは知っています。授業内で大いにタブレット型端末が活躍していることは承知しているのですが、まだまだ過渡期だからなのか、中途半端さを否めません。
教員のみなさんに余裕がなければ、本質的に子どもたちに向き合うってことができなくなるでしょう。本来であれば、教員が余裕を持って子どもたちに接する時間を増やすことこそが現場教員の果たすべきことであるはずで事務作業に時間を割かれるだなんてことは本末転倒もいいところです。
▷ 義務教育の目的とか目標ってなんだ
とはいえ、学校に出向くことが出来ない子がいる事実は変わらないでしょうし、これからも増えていくことでしょう。
果たして、義務教育の目的とか目標ってのはどんなものなのでしょう。
ぼくも目にしたことがなかったので、多くの方は目にしたことはないのだろう「文部科学省の定める義務教育の目的、目標」ページを見ていきます。
ここに義務教育の目的と目標が記載されていますが、内容を閲覧してみると政策審議会で出された意見が箇条書されており、それをまとめる形で2点ほど列挙されていました。
• 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。 つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。 これは,「生きる力」として文部科学省が教育 改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。
上記以外にも記載があるのですが長くなるので省きまして、以下のようにまとめられております。
国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障
要約すると、日本国憲法第25条に定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための資質を身につけるための期間であり機関であることとすることが目的だということでしょうか。
社会に出るための準備期間であるというところかもしれませんが、だったら余計に授業を外部人材に委託するとか科目別担当制にするなど、いくらでも対応すべき事項はありそうなもの。
ここまでみていると、明らかに現行の制度が現在の子どもたちに追いついてないってことが如実になっていることが伺えますし、何なら目的や目標と現場の実情が乖離するような事態にまで陥っているのではないかとすら思えてきます。
ぼくは社会システムによって3割がこぼれ落ちるような事態になってしまったら、そのシステムは破綻していると考えています。新卒入社した社会人が3年で3割やめるってのが定常化していますが、これは新卒社会人が悪いのではなく社会システムが破綻していると捉えているのです。
学校の中も教員の離職などを始めとした実情をさらに深ぼっていけば、実態に則さない状態が浮き彫りになり、結果的に破綻してまーす!みたいな結果が出てきそうなものですが、それを置いておいても義務教育のオンライン化を推奨することぐらいはやってほしい気もします。
現状はそこを公教育によってカバーできているのかといえばできていないわけで、そこから取り残されるような状態を作っているのは現行の教育制度だといえます。
代替しようと思えば代替できますが、それを保護養育する当事者だけに丸投げするような状態となっているのはいかがなものかと思わざるを得ません。
そんなわけで、オンライン化、お待ちしてまーす。
ではでは。
えんどう
▶︎ おまけ
▷ 紹介したいnote
勉強はつまらないけど学習はたのしい。大人になってから新しい知識やスキルを習得する時に実感することと、勉強でいい点が取得できた際の喜びはまったくことなるものでした。この辺りを丁寧に分析していくと、ゲーミフィケーションで文科省は任天堂をうまくつかえばいいのに…とか思ってしまうのでした。
乙武さんが「いたみ」を語るって点と、中学生がそれを受けるって形は何だかいいですよね。正直、社会的なハンディを背負ってると社会人たちは思ってしまうのですが、当事者である乙武さんからすると「当然」であり「普通」であることが多々あるでしょう。そのギャップを埋めるってのはいい体験が出来たのではないでしょうか。
「義務教育は地面のようなもの」だと記載されており、どこかグッと来るものがあった。ぼくも別に義務教育事態が嫌いなわけでもなんでもない。むしろ、甘酸っぱい初恋の記憶を想起すれば「良かったなぁ…」と美化すらしたくなる。あ、それは義務教育と関係ないや。
▷ えんどうのTwitterアカウント
僕の主な生息SNSはTwitterで、日々、意識ひくい系の投稿を繰り返している。気になる人はぜひ以下から覗いてみて欲しい。何ならフォローしてくれると毎日書いているnoteの更新情報をお届けする。
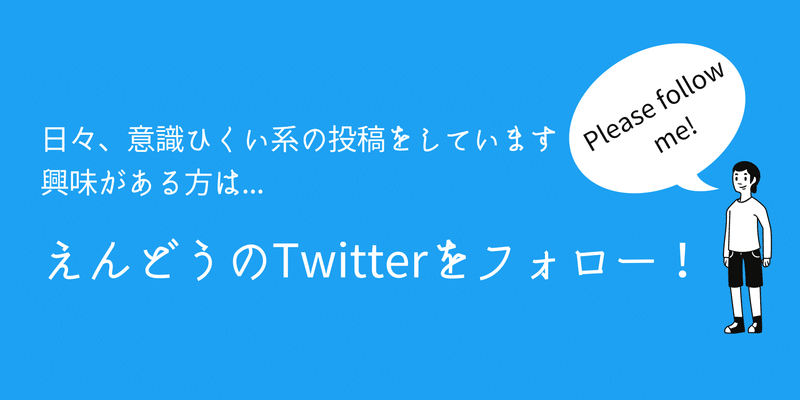
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
