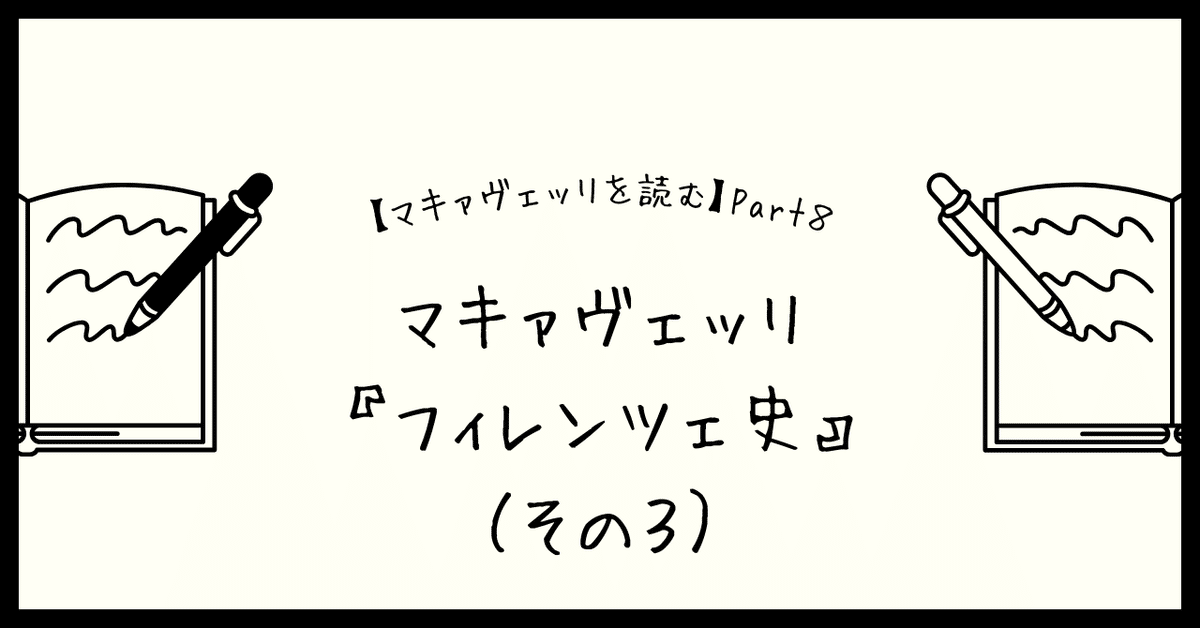
マキァヴェッリ『フィレンツェ史』(その3・『フィレンツェ史』におけるマキァヴェッリの政治思想)〜【マキァヴェッリを読む】Part8
今回は、『フィレンツェ史』のなかの理論的記述、マキァヴェッリの政治思想が表現されたものを、自分なりに分類して抜粋したものになります。
『フィレンツェ史』読書ノート(注目ポイントの引用)「政治思想」篇
支配領域の拡大と従属都市への対応について
マキァヴェッリの時代のイタリアの国家とは、まだら状の国家でした。
都市が中心となって周辺領域をまとめ、その都市たちを全領域の中核となる都市が束ねる。
各都市が独自の法や慣例にしたがっており、中核都市が自分の勢力圏を一元的に支配できるわけではない。
時には、中核都市に反旗をひるがえす都市も出て来る。
後に絶対主義国家が克服しようとする一種の連邦体制のようなこの状況が、マキァヴェッリの政治論の前提です。
(その意味では、現代の我々はみな絶対主義国家のもとで生きています)
このような「国内」状況では、今日なら国際関係に見えるような都市際関係が、国内政策として重要でした。
『フィレンツェ史』の前面には出てきませんが、フィレンツェは支配圏を拡大させてきた都市です。
この拡大した領域内政策のツケが、1494年以降のピサ離反など後々で効いてきます。
マキァヴェッリも従属都市対応について言及しています。
従属都市への対応
1340年代に複数の従属都市がフィレンツェの支配下から離脱した際の対応について、こう述べています。
(歴史的に存在していない対応方針なので、マキァヴェッリの思想に由来する内容と推定されます)
もはや彼ら〔引用註:離反した都市アレッツォの人々〕を従属民とすることはできないので、フィレンツェの友人として認めたのである。
ほかの都市とも、最善の策として、友好関係を維持することを条件に、このような協定を結んだ。
諸都市は、自分を自由にしてもらえれば、フィレンツェ人が自由を維持することも支援できるようになるであろう、と思われたのである。
賢明にも採用したこの方策は、きわめて素晴らしい結果を生んだ。
というのも、アレッツォは、それから何年も経たないうちにフィレンツェ人の支配権のもとに戻り、ほかの都市も、数カ月のうちにかつての従属に戻ってしまったからである。
こうして、それらを〔従属から〕解放することによって、大兵力をもって執拗に追求した場合よりも、何倍も早く、また少ない危険と費用で、目的を達成できたのである。
一方、反旗をひるがえした都市ヴォルテッラに対して、宥和ではなく戦闘によって屈服させた事件について、歴史上の人物に仮託して述べた箇所もあります。
「ヴォルテッラを手に入れた今、貴殿は何と言うのですか?」
これに対し、トンマーゾ殿はこう答えた。
「わたしには、ヴォルテッラを失ったように思われる。
というのは、あなた方がそれを和平協定によって手にしたのであれば、あなた方は、そこから利益と安全を引き出せるが、それを武力で手に入れてしまったので、それは危機には弱みと悩みの種となり、平時には損害と支出を引き起こすからだ。」
これらの引用を見ると、マキァヴェッリは宥和政策の信奉者に見えます。
しかし、先日引用したマキァヴェッリの戦争観を見ると、戦闘によって屈服させるなら相手を徹底的に破壊すべきで、破壊せずに戦闘と宥和の間の中途半端なことは怨恨を残すので避けるべきというのが真相のようです。
植民政策
むしろ、マキァヴェッリの理想とする国内政策は植民都市を築くことです。
相手を滅亡させた地域、あるいは敵から割譲させた地域に植民都市を築くことを推奨します。
私たちの時代にはすたれてしまった、古代の共和国や君主国の他の偉大な驚くべき制度にまじって、あらゆる時代に、それによって多くの城塞や都市が新しく建設されていた制度があった。
なぜなら、最高の君主やよく治められた共和国にとって、人びとが防衛や耕作に便利なように、そこに退避できるような城塞を新たに建設すること以上にふさわしい事業はないし、またある属州にとっても、それ以上に有益なことはないからである。
彼らはそうしたことを、敗戦を喫したか、さもなくば無人となった土地に、植民と呼ぶ新しい住民を派遣する習慣を持つことによって、容易に実行できた。
というのは、この制度は新しい都市を建設するための契機となっただけでなく、勝利者に対して敗戦国をより安全にし、無人の土地を住民で満たし、属州では人間の適当な分布を維持していたからである。
その結果として、ある属州によりいっそう快適に定住することによって、人びとはそこでいっそう人口を増加させ、攻撃においてはより敏速に、防御においてはより安全になることとなった。
今日こうした習慣は、共和国や君主の悪しき習性のためにすたれてしまい、結果として属州の崩壊や弱体化が生じた。
なぜならこの制度だけが、帝国〔引用註:支配〕をより安全にし、すでに述べたとおり、そのおかげで国々が豊富な人口を維持したからである。
安全性というものは、新たに国を占領した君主によって、人びとに忠誠を守らせるための砦、または番人としての植民地が設立されるがゆえに生じるものなのである。
そのうえ、この制度以外の方法では、属州全体に住民を維持することができないし、またそれなしでは住民を適切に配置しておくことも不可能である。
なぜなら属州におけるあらゆる場所が、多産で健康的だというわけではないからだ。
だから、ある場所では人口が充満し、他の場所では不足する事態が発生する。
人びとを密集している場所から連れ出して、不足している場所に導く手段がなければ、その属州は間もなく崩壊してしまう。
ある部分は人口が少ないため無人化し、他の部分は人口過剰のために貧困化するからである。
自然はこうした混乱を補正できないので、人間の働きによってその埋め合わせをする必要がある。
経済的なことに言及することが少ないマキァヴェッリが、人口論を通して貧困に言及している数少ない箇所でもあります。
また、人口については、黎明期のフィレンツェが近隣の都市フィエーゾレを破壊して吸収することで人口を増やし、発展の礎となったことも見落とせない点です。
党派対立について
『フィレンツェ史』の全体の記述を覆っているのは、党派対立です。
イタリアのあらゆる都市に共通している腐敗は、私たちの都市をも腐らせましたし、今も腐らせています。
なぜなら、このイタリアが皇帝の勢力下から独立して以来、それを匡正してくれる強力な抑制がないために、イタリアの都市は、自由な都市というよりも党派に分裂した都市として、それらの国家や政府を制定してきたからです。
このことから、それらの内に現れる、あらゆる悪とあらゆる混乱が生まれたのです。
前回の記事で概観したフィレンツェの歴史でも、党派対立が繰り返されていました。
永続する党派対立
党派対立によって団結できないことは問題です。
しかし、党派対立がなくなることで、優勢な党派が傲慢に振る舞うことができるようになってしまうことも問題です。
また、党派対立は、一方の党派が他方に勝利するという形で終結することは好ましくないとマキァヴェッリは言います。
そのような党派対立の終結は、勝利した党派の分裂の始まりであり、次の党派対立へのインターバルでしかないからと見ているからです。
悪人は貪欲と野心から、善人は必要から、党派に追随します。
党派の中核や首領が、彼らの意図や目的をもっともらしい言葉で正当化するのが見受けられますが、それは大きな害をもたらします。
といいますのも、彼らは皆、いつでも自由の敵であるにもかかわらず、最上層の体制あるいは民衆の体制を守るという名目で、自由を抑圧するからです。
また、 勝利の成果として彼らが望むのは、自由になった都市を手にするという栄光ではなく、 相手を打ち負かし、その主だった者たちから強奪するという満足感だからです。
その行き着くところ、不正、残忍、強欲のいずれも、彼らは手控えることがありません。
このことから、秩序も法も、公共のためではなく、自分の利益のために役立てられるのです。
ですから、戦争、平和、友好、そのいずれも全体の栄光のためではなく、少数の満足のために決議されるのです。
ほかの諸都市が、このような無秩序に満ちているとすれば、われらの都市は、ほかのどの都市よりももっとそれに汚染されています。
といいますのも、ここでは常に法も、規定も、都市の機構も、自由に暮らすためではなく、権力を手にする党派の野心に従って制定されてきたし、また現に彼らが制定しているからです。
こういう有様ですから、ある党派が追放されて、一つの敵対関係が消えると、いつでも別のものが生まれてくるのです。
なぜなら、この都市は、法によらずに、党派によって秩序を維持しようとしているので、一つの党派は、市内に反対する者がいなくなると、必然的にその内部で分裂してしまうからです。
フィレンツェの敵意は、常に党派を生み出したので、常に有害なものであった。
敵対党派が活動していない限り、勝利した党派は団結することがなかった。
支配党派は、敗北した党派が消滅すると、それを押さえ込む必要がもはやなくなり、自派を抑制する内部の秩序も必要なくなるので、党派が分裂する。
コジモ・デ・メディチの党派は、一四三四年に勝ち残った。
しかし、敗北した党派が大きく、きわめて有力な人々を多数抱えていたので、コジモの党派はしばらくの間、それへの恐れから団結し、節度のある振舞いをした。
だから、この党派の人々は、党派内部でどのような過ちも犯さなかったし、悪辣なやり方で人々の恨みを買うこともなかった。
党派対立の終息と自由の確立
では、一方の党派の勝利ではなく、どのように党派対立は終息するべきとマキァヴェッリは考えるのか。
都市、 とりわけ共和制の名のもとに統治されて、秩序の確立していない都市は、その政府と体制がしばしば交代する。
しかし、その交代は、多くの人が思うような自由と隷属の間での交代ではなく、隷属と放縦の間での交代である。
というのも、自由は、大衆という放縦主義の使徒によって、また貴族という隷従主義の使徒によって、その名のみが讃えられるものであり、そのどちら側の誰も、法に対しても、人に対しても、服従することは望んでいないからである。
とはいえ、その都市にとって幸運なことに、そこに賢明で、善良で、強力な人物が出現して、彼が法を制定し、その法のおかげで貴族と平民の対立が鎮まり、あるいは悪事ができなくなるという状態になったら (稀にしかそうはならないが)、そのときは、その都市は自由だと言えるし、その体制は安定し確立していると評価できる。
なぜなら、良き法と良き秩序に立脚する都市は、一人の人物の力量〔に頼ること〕を必要としないが、力量のある人物を必要とする都市は、そうではないからである。
このような法と秩序をもつ多くの古い共和国は、長くつづく体制を享受している。
このような秩序と法をもたなかったし、今ももたないすべての共和国は、専制的な体制から放縦な体制へ、 また後者から前者へと交代したし、今もしている。
なぜなら、この場合は、体制がどちらになっても、体制に反対する強力な敵が存在するので、どのような安定もありえないからである。
一つの体制〔隷従の体制〕は善人に嫌われ、もう一つの体制〔放縦の体制〕は賢人に嫌われる。
一つの体制では悪事をおこなうのが容易であり、もう一つの体制では善事をおこなうのが困難である。
一つの体制では傲慢な人々が過度の権限をもち、もう一つの体制では暗愚な人々がそれをもつ。
このいずれの場合も、一人の人物の力量や幸運によって維持されなければならないが、この人物は、あるいは死によって力を失い、あるいは奮闘したあげく無用になる。
一方の党派の勝利ではなく、双方の対立をおさめるような法の制定によってこそ、安定した秩序が確立するとマキァヴェッリは言います。
貴族の寡頭政も平民の民主政も、一方が勝利して支配しようとしても、その立役者の力量に依存する以上は、体制として安定せず、別の政体へと変化しうる。
それを回避するなら、法によって対立をおさめるしかないわけです。
(とはいえ、この「法」とやらがどんなものなのか、ここでは具体的には不明です。
また、そもそも「双方が妥協する」というのは解決法の提案になっていない疑いもあります。
妥協できないないほど党派対立が根深くなったからこそ、一方の勝利に行き着くしかなくなったとも考えられるのですから。
妥協しないことが党派対立の消滅に繋がらないとしても、だからといって妥協できるかどうかは別問題です)
古代ローマとフィレンツェの党派対立の比較
貴族と平民との党派対立が、話し合いと法によって抑えられた古代ローマと、一方の勝利によって決着したフィレンツェが比較されます。
貴族がもつ命令したいという願望と、平民がもつ隷従したくないという願望。
この両者の間に横たわる深刻かつ当然の敵対関係が、諸々の都市で生じた災厄すべての原因である。
というのは、人々の間にあるこの気質の違いこそ、諸々の共和国を混乱に陥れたそのほかすべての出来事の生みの親であったからである。
これが、ローマを分裂した状態のままにした。
これが、 もし小さなことを大きなことに〔フィレンツェの例をローマの例に〕たとえることが許されるなら、フィレンツェを分裂した状態のままにした。
とはいえ、あの都市とこの都市とでは違う結果に終わった。
というのも、ローマの初期にあったこの対立は、話し合いによって決着がついたが、フィレンツェの対立は、戦いによって決着がついたからである。
ローマのそれは、法によって終結したが、フィレンツェのそれは、多数の市民の追放と死によって終結した。
ローマのそれは、常に戦士の美徳を高めたが、フィレンツェのそれは、この美徳をすべて消し去った。
ローマのそれは、その都市を市民間の平等から巨大な不平等に導いたが、フィレンツェのそれは、市民間の不平等から驚くほどの平等に導いた。
結果のこの違いは、二つの都市の平民がもった目標の違いに由来するものであろう。
ローマの平民は、最高の名誉を貴族とともに享受したいと望んだのであるが、フィレンツェの平民は、政権を貴族の参加しない、自分たちだけのものにするために戦ったからである。
ローマの平民の望みは、より理性的なものであったから、貴族に対する彼らの攻撃も、より我慢のできるものとなり、貴族のほうでも、容易にかつ武器を手にすることなしに譲歩した。
その結果、いくらかの異議はあったにせよ、一つの法が制定され、それによって、平民は満足し、貴族はその特権を保持することができた。
他方、フィレンツェの平民の望みは、傲慢で不公平なものであったので、貴族がたいへんな力で自己防衛に努めた結果、市民の流血と追放を引き起こした。
その後で制定された法は、全員の利益のためではなく、すべて勝者に都合のよいように規定されていた。
このことから、都市ローマでは、平民が勝利したことによって、平民が、 貴族と並んで執政機関の管理に参加できるようになり、貴族と同じ権限をもって職務を遂行したので、この都市では、人々の士気が上がり、力が増した。
しかし、フィレンツェでは、平民が勝利を手にすると、貴族は官職を剥奪されてしまった。
官職就任権を再び手に入れようとすると、挙措動作にせよ、精神にせよ、暮らしぶりにせよ、その内実のみならず、外見においても平民と同じようになる必要があった。
このことから貴族が、平民に見えるようにと、家族の紋章を変えたり、家族の姓を変えたりする、ということが起きた。
その結果、貴族がもっていた武勇の美徳や精神の鷹揚さが消えてなくなり、それをもたなかった平民はそれを継承することがなかったので、フィレンツェは、ますます下賤に、ますます卑屈になっていった。
そして、ローマでは、平民の美徳が傲慢へと変質してしまったので、ついには一人の君主〔皇帝〕をもつことなしには〔社会秩序を〕維持できない状態になったが、フィレンツェでは、一人の賢明な立法者によって、どのような政体にでも容易に改変してしまえる状態になった。
平民が貴族と支配にともに与ろうとした古代ローマと、平民が貴族から支配を奪おうとしたフィレンツェとが対比されています。
また、両者の差異が、武勇の存続(イタリアでの傭兵制の導入)、市民間の平等/不平等、政体の変化と結びつけられています。
党派とはなにか
貴族と平民、支配する側と支配される側の妥協による法の制定という解決策以外にもマキァヴェッリは注目します。
党派とはなにかを規定することで、良い対立と悪い対立を分けています。
共和国というものが団結できると期待した人々はひどく間違っていた、ということについて少し言っておきたい。
ある種の分裂が共和国にとって害となり、またある種の分裂が益となったのは、事実である。
害になったのは、党派や派閥をともなう分裂であり、益になったのは、党派や派閥をともなわずにつづいた分裂である。
共和国の創設者は、そこに敵意が生まれなくするような対策をとることまではできなくても、少なくとも党派が生まれなくする対策はとるべきなのである。
そのためには、その都市の市民が、二つの方法のうちどちらで、つまり公的な方法、私的な方法のどちらで、名声を手にするかを知らなければならない。
戦闘に勝利する、都市を獲得する、迅速かつ慎重に使節の役目を果たす、賢明かつ適切に共和国に助言するという公的な方法で、それを手にするのか。
誰彼なしに市民に恩恵をばら撒く、彼らを当局の手から庇護する、彼らに金銭の援助をする、不公正なやり方で要職を当てがう、見世物や公的な贈り物で下層民の機嫌を取るという私的な方法で、それを手にするのか。
この私的な方法からは、党派や派閥が生まれてくる。
この方法で手にする名声が害になるのと同じくらい、公的な方法で手にする名声は、そこに党派の利害を入り込ませなければ、益となる。
なぜなら、それは私的な利害ではなく、公共の利害にもとづいているからである。
公的な方法で名声を手にした市民の間でさえも、きわめて深い憎悪がないとは決して思われないが、彼らは自分の私的な利益のために追従してくる支持者がいないので、共和国にとって害になることはありえない。それどころか、益になる。
というのも、この方法の場合、市民の賞賛を勝ち取るためには、共和国を賛美する姿勢が必要になるし、市民としての限界を超えた行為が生まれないように、お互いに注意深く監視し合うからである。
(これを現代にそのまま適用した場合、いわゆる利益誘導政治とポピュリズムの対立のような話になってしまいそうです。
国家が領域を広げ、産業化が進んだ社会では、何が公益なのかは明確ではなくなります。
それをふまえると、現代への応用の難しい話のようにも思えます。)
単独者支配について
『君主論』での君主政論と『ディスコルシ』での共和政論との関係がどうなっているかというのは、マキァヴェッリの政治思想解釈で扱われる定番の命題となっています。
『フィレンツェ史』は、共和国フィレンツェについて書かれたので、共和政(特に党派対立)の話が多いですが、君主政など単独者支配についての言及もいくつかあります。
君主政の欠点
『フィレンツェ史』には、君主ミラノ公の殺害を教唆したガチガチの共和政主義者が登場しています。
ミラーノでは、学問に通じた野心家のコーラ・モンターノが、その都市の指導的な若者たちにラテン語を教えていた。
この人は、公の生き方や素行を嫌っていたからか、ほかの〔個人的な〕動機がそうさせたのか、彼が論ずるときはいつも、君主のもとで暮らすのは不幸だと非難し、共和国に生まれて暮らす人々は人間本来の生き方をするので幸福だと認めて、彼らを栄光に包まれた幸運な人々だと称した。
共和国は有徳な人物を育てるが、君主はそうした人物を抹殺し、一方は他人の徳から利益を得るのに、他方はそれを恐れるので、有名な人々はすべて、君主のもとではなく、共和国で育ったのだ、と説いた。
(中略)
彼ら〔引用註:若者たち〕とは何度も、君主の悪しき本性、君主に統治される人々の不幸について論じ合った。
そして、この若者たちの精神と意図に確固たる信念を吹き込み、彼らがそれをできる年齢になったら、祖国をこの君主の専制政治から解放することを、自分に対して誓わせた。
力量ある人物への君主たちの対応については、マキァヴェッリの主張と重なってもいます。
しかし、マキァヴェッリはこれほど単純には君主政や共和政を見ていないように思われます。
ミラノ公国の場合
ミラノ公ヴィスコンティ家が断絶した際、一時的にミラノは共和政を樹立しました。
登場人物の口を借りてですが、この共和国の行く末についてのコメントが『フィレンツェ史』にはあります。
コジモはこう思ったのである。
ミラーノ人が自由〔共和政〕を維持できると考えるのは、賢明ではない。
というのも、ミラーノの市民の性質、その生き方、その都市の根深い諸党派〔間の対立〕は、共和政による統治には、それがいかなる形態のものであれ、向いていないからである。
だから彼らには、伯〔引用註:後にミラノ公となるフランチェスコ・スフォルツァ〕がその公になること、あるいはヴェネツィア人がその支配者になることが、必要なのである。
ここでは、君主政か共和政かの問題は、それを採用する人々との兼ね合いで考えられています。
そして、実際に戦争が差し迫ると、ミラノの民衆は君主政を選択するのでした。
戦争の脅威を取り除きたければ、伯を招聘する以外にないことを、はっきり説明した。
なぜなら、ミラーノの民衆は、将来の援助についてのわずかな希望ではなく、目の前の確かな平和を必要としているからだ。
(中略)
それから、自分たちの自由〔秩序と安寧〕を委ねなければならないとしたら、その者は自分たちのことを知り、自分たちを守れる人物でなければならない。
そうすれば、自分たちが彼に服従することで、もっと大きな損害やもっと危険な戦争ではなく、少なくとも服従することで平和がもたらされるのだ、と。
フィレンツェのアテネ公の場合
フィレンツェで君主になろうとしたアテネ公の場合はどうでしょうか。
君主になることを彼に思い止まらせるために行われた長文の(創作)演説が『フィレンツェ史』にはあります。
殿は、これまでいつも自由に暮らしてきた都市を、女奴隷にしようとしておられます。
と申しますのも、われらはこれまでナポリの王族方に支配権を委ねたことがございますが、それは仲間として委ねたのであり、女奴隷としてではございません。
このような都市では、自由という名が、どのように大切で、どのように強い響きをもつものか、またそれは、どのような力でも押さえることができず、どのように時が経っても消えることがなく、どのようなものでもそれに釣り合うものがない、ということをお考えになったことがおありでしょうか?
殿よ、このような都市を女奴隷として置くには、どのくらいの軍隊が必要になるか、お考えになってください。
(中略)
どんなに時間が経っても、自由への欲求が消えてなくなることはない、これは絶対に確かです。
というのは、自由を味わったことはないけれど、父祖が残してくれた自由の記憶だけで、自由を愛するようになった者たちの手で、都市において自由が回復され、それゆえにこの回復した自由を強い決意で、危険をものともせずに守り抜く、ということをよく耳にするからです。
父祖が自由を記憶していなくとも、共和国の庁舎が、その役人たちの役所が、自由な体制の象徴が自由を記憶しています。市民は、こうしたものを知っており、この上なく強く望んでいます。自由に暮らすという甘美さと釣り合う、どのようなことを、殿はなさるおつもりなのでしょうか?
あるいは、現状を維持したいという望みを人々から奪い去ってしまう、どのようなことをなさるおつもりなのでしょうか?
たとえ殿が、この領土にトスカーナ全体を加えられたとしても、また連日われらの敵に勝ってこの都市に凱旋されたとしても、そのようにはなりません。
そうした栄光は、この都市のものではなく、殿のものだからです。
そして市民は、〔殿の勝利で敵を〕手に入れても、それは自分の従属者ではなく、自分と同じ奴隷であるので、彼らを見れば、自分の奴隷状態がひどくなったことを知るのです。
殿の生活が聖人のようであり、物腰が優雅であり、判断が公正であっても、市民から愛されるには十分ではございません。
もし殿が、彼らはそれで満足していると思われるのであれば、自分を騙しておられるのでございます。
というのも、束縛なしに暮らすのに慣れた者には、どのような鎖も重く、どのような束縛も窮屈に感じられるからでございます。
さらに、良き支配者をいただく暴力的な国家などというものは、見当たりません。
なぜなら必然的に、支配者と国家は性格が似てくるか、でなければ良き支配者と暴力的な国家は、その一方がすぐに他方を破壊してしまうからです。
でありますから、殿は、この都市をもてる限りの暴力で支配なさるか(それには要塞、護衛兵、外部の味方を何倍に増やしても、十分ではないでありましょう)、われらが殿に託した権限で満足なさるか、どちらかになさらなければなりますまい。
支配は〔それを是認する〕 住民の自発意思があるときだけ継続できることを、殿に思い出していただき、この権限で満足なさることをお勧めいたします。
(後略)」
自由を経験した都市においては、君主政の導入が困難であること、もし君主政を実現しても人々が支配者の栄光を自身のこととして分かち合えないことが述べられています。
この演説に対するアテネ公の反応も続いて記述されています。
これらの言葉も、公の頑なな心を動かさなかった。
彼はこう言った。
この都市から自由を奪うつもりはなく、自由を与えるつもりでいる。
なぜなら、分裂した都市だけが奴隷状態になるのであり、団結していれば自由だからである。
自分の命令で、フィレンツから党派の野心や敵対が取り除かれたとしたら、それから自由を奪うのではなく、それに自由を与えることになる。
この任務に就いたのは、自分の野心によってではなく、多くの市民が懇願したからである。
だから、ほかの人々が同意したものには、閣僚諸君もよろしく同意すべきである。
このことで自分が負わざるをえなくなるかもしれない危険は、気にしていない。
悪い面を恐れて良いことを放棄する者、少しでも懸念があれば栄光ある事業にも手をつけない臆病者は、この任務にふさわしくない。
諸君は、自分のことを信頼せず、恐れすぎていたのにまもなく気づくことになる と自分は確信している、と。
君主が党派対立を抑制するという理屈が述べられています。
これが直接話法の演説ではなく、間接話法で書かれているのをどう評価すればいいのでしょうか。
この理屈で君主政を正当化することをマキァヴェッリが好ましく思っていなかったことを示すのか、それとも単にアテネ公の行動がこの発言と一致しなかったからなのか、判断に迷うところです。
ちなみに、その後のアテネ公の記述は、アリストテレス『政治学』が描くような僭主のステレオタイプにのっとったものとなっています。
〔引用註:アテネ公は〕誰に対しても武器の携行を禁止し、都市内部の人々から身を守るために、外部の人々と仲良くした。だから、アレッツォ人や、そのほかのフィレンツェに従属する都市のすべての人々に、多くの恩恵を施した。
メディチ家の位置づけ
フィレンツェを牛耳ったメディチ家を、マキァヴェッリが『フィレンツェ史』の中でどう位置づけているかは、読んでいてもいまいちハッキリしないところがあります。
その名声の獲得方法は、悪しき党派対立を招く、共和国にとって害となるやり方の例になっています。
フィレンツェには、わたしが何度も述べてきたように、コジモ・デ・メディチとネーリ・カッポーニという二人のきわめて有力な市民がいた。
二人のうち、ネーリは名声を公的な方法で手にした市民の一人であり、友人は多いが追従者はほとんどいなかった。
他方、コジモは権力への道を公的な方法と私的な方法で切り開いたので、友人も追従者も多かった。
この二人はどちらも生存中は団結しており、人々には恩恵に権力を混ぜ合わせて対処したので、何の問題もなしに人々から自分たちの望むものを手に入れていた。
ただし、これらはコジモの死後の党派対立との関連で述べられています。
共和政での党派対立という文脈の延長なので、それはメディチ家の君主化という文脈と繋がるかどうかはまた別問題です。
メディチ家が公然と自分に刃向かったすべての敵に打ち勝った後の、この家の権
力について述べよう。
当家は市内で唯一の権威をもつが、市民生活をつづけながら他家から抜きん出ることを望んだので、自分たちに対してひそかに策謀をめぐらす家々を乗り越えることも必要となった。
メディチ家が、権威や名声の点で同等な他家のいくつかと争っていたときには、当家の人々の勢力を妬んでいた市民は、敵対した途端に弾圧されるという恐れなしに、公然と彼らに反対することができた。
(中略)
しかし、一四六六年の〔メディチ家の〕勝利の後は、すべての権力がメディチ家に集中したので、その家族は大きな力を手に入れた。
そこで、それに不満を抱く人々は、我慢してそのもとで暮らすことを耐え忍ぶか、あるいはそれをなくそうと望むのであれば、陰謀によってひそかにそれを試みるしかなかった。
敵対党派ではなく陰謀の対象になったという点では、メディチ家は従来の共和政の枠組みからははみ出しているのでしょう。
ピエロが長男ロレンツォをローマの名門の娘と婚姻させたり、ロレンツォが次男ジョバンニを枢機卿にしたり、メディチ家が「他家から抜きん出ること」を推し進めたのは確かです。
これらは当時でも君主化と受け取られることでした。
このこと〔引用註:ロレンツォの婚姻話〕は、彼を中傷するさらに大きな口実を皆に与えた。
息子をフィレンツェ人と縁組みさせるのを拒否したいというのであるから、彼〔引用註:ピエロ〕は、もはやフィレンツェに市民としておさまる気がなく、君主になる準備をしていることが明らかである、というわけである。
同胞市民を姻戚にしたいと思わない者は、彼らを従者にしたいと思っているので、〔ピエロが〕彼らを友人にしたいと思わないのは筋が通っている、と。
ただ、これらの言及からは、メディチ家が君主化を狙ったとまでは言えても、君主のように支配したとまで言えるわけではないのです。
メディチ家支配自体の位置づけがハッキリ読み取れないと私が思ったのは、共和政以上君主政未満なこの中途半端な位置づけによるものです。
権力の獲得と維持
メディチ家当主のピエロが死去し、若輩のロレンツォたちだけが残されたとき、フィレンツェの有力者が、メディチ家を擁護しました。
その理由は、国家の安全の問題でした。
〔引用註:有力者が〕その場で、フィレンツェの状況、イタリアの状況、イタリアの支配者たちの本心について、長い重厚な演説によって解き明かし、結論として、フィレンツェで一致団結して平和に暮らしたいと思い、内部の分裂や外部との戦争から身を守りたいと思うのなら、この若者たち〔引用註:ピエロの息子たち〕を尊重して、 メディチ家の名声を維持することが必要である、と述べた。
なぜなら人々は、するのが習慣になっていることをするのには不満をもたないからである。
新たなことは、それに手を着けるのが早ければ早いほど、それを捨て去るのも早い。
権力は、長く持続することで嫉妬を消し去るものであり、嫉妬は、新たな権力を生み出す動因となるが、そのような権力は、きわめて多くの原因によって容易に消滅しうる。
だから、〔旧来の〕権力を維持することは、〔新たな権力を創出することよりも〕常にいっそう容易なのである。
ミラノの君主政維持や、共和国へ君主政を導入する困難についての言及と合わせると、近代以降なら保守主義に分類されそうな言説です。
権力(新しい都市や国家)を獲得する話がメインの『君主論』でも、獲得より維持の方が容易であるという話は出てきます。
ただし、国内融和や外国への対抗という理由は、君主の生存戦略と結び付いた『君主論』とは、また少しだけ毛色が異なっている印象を受けました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
