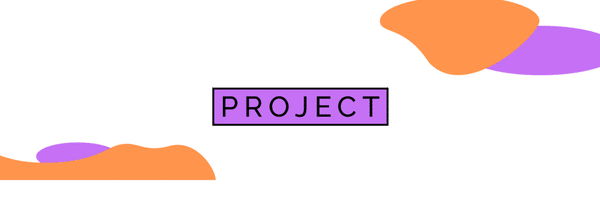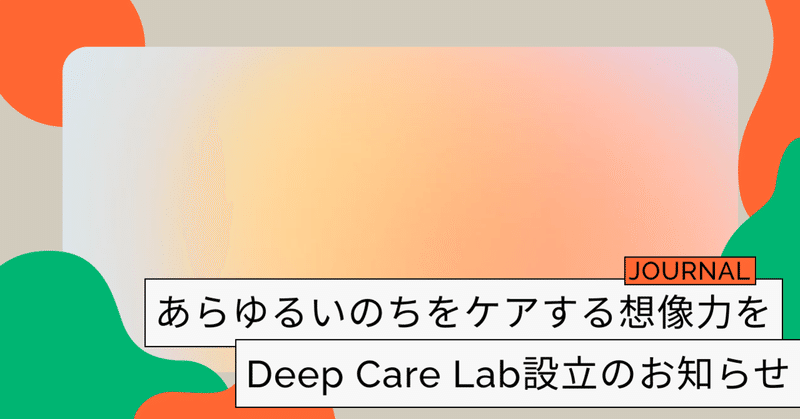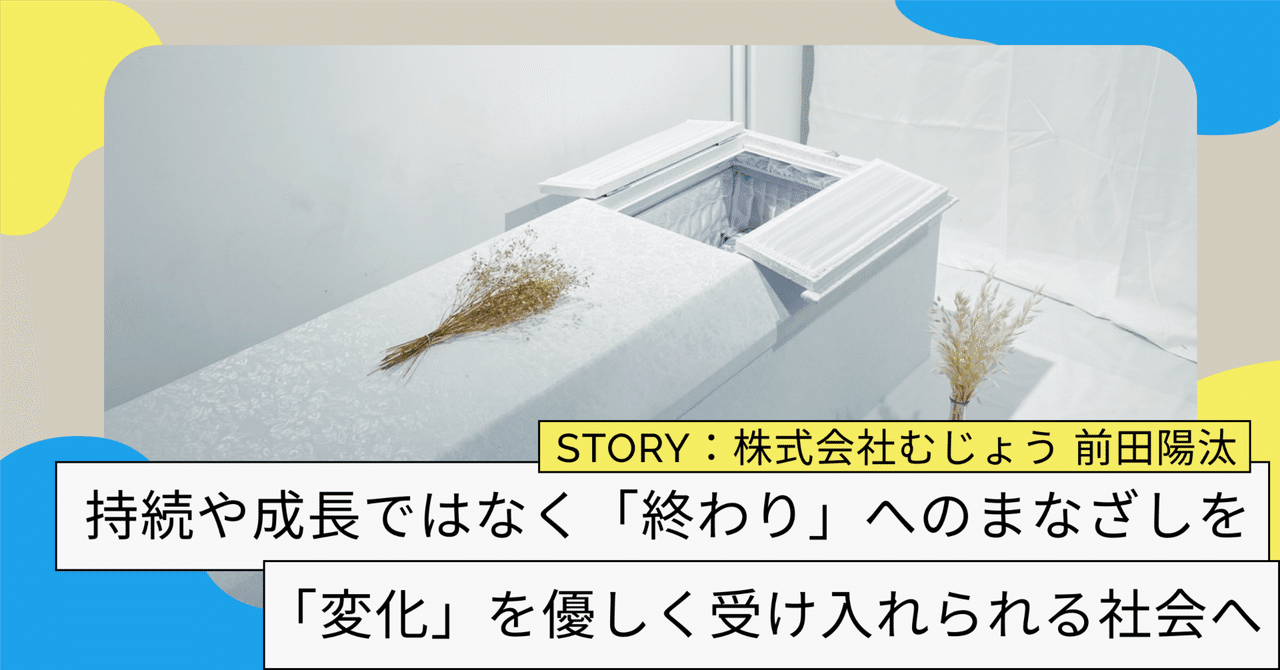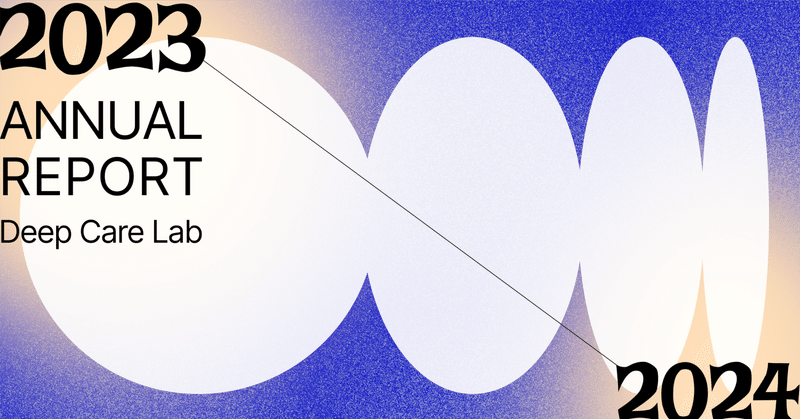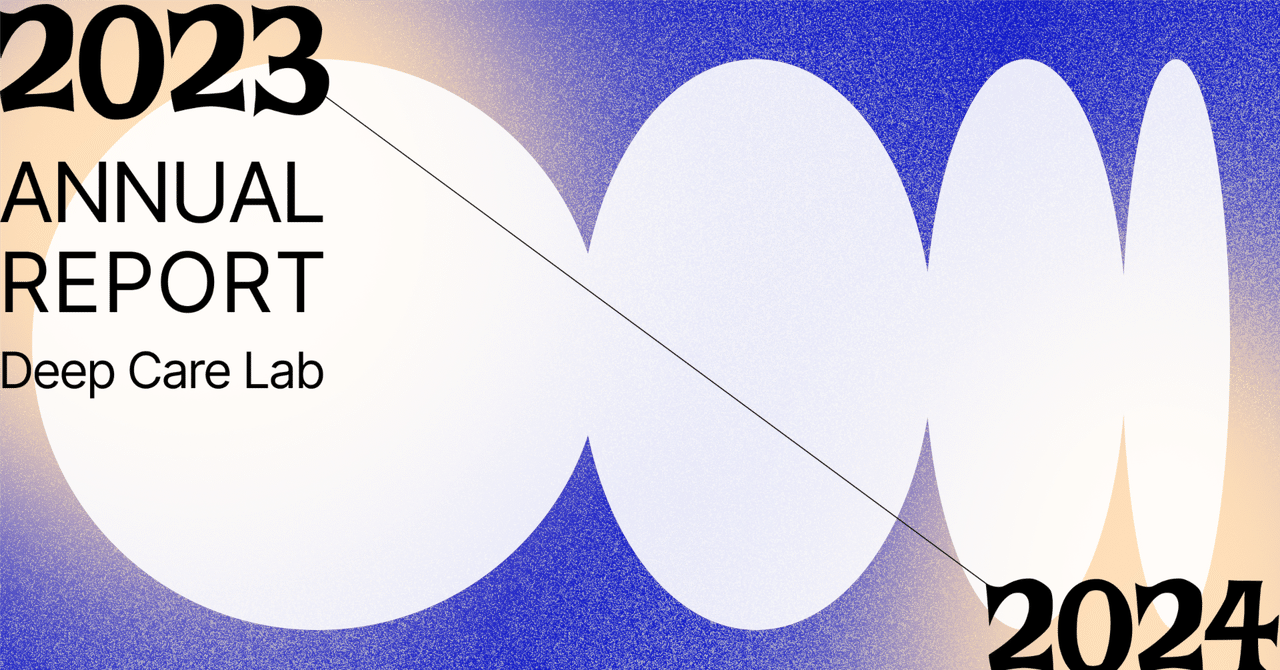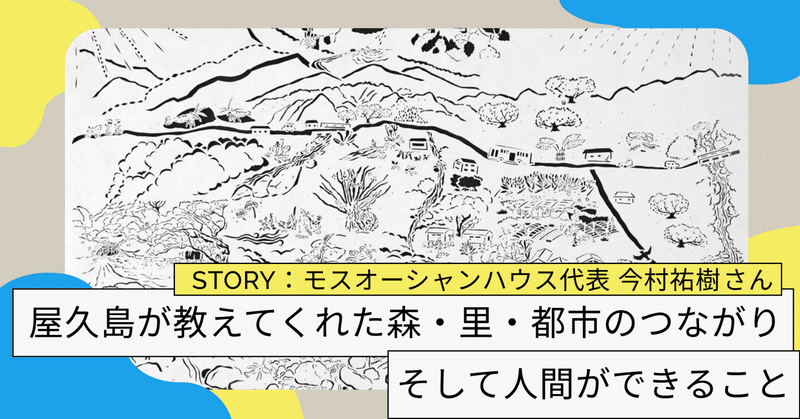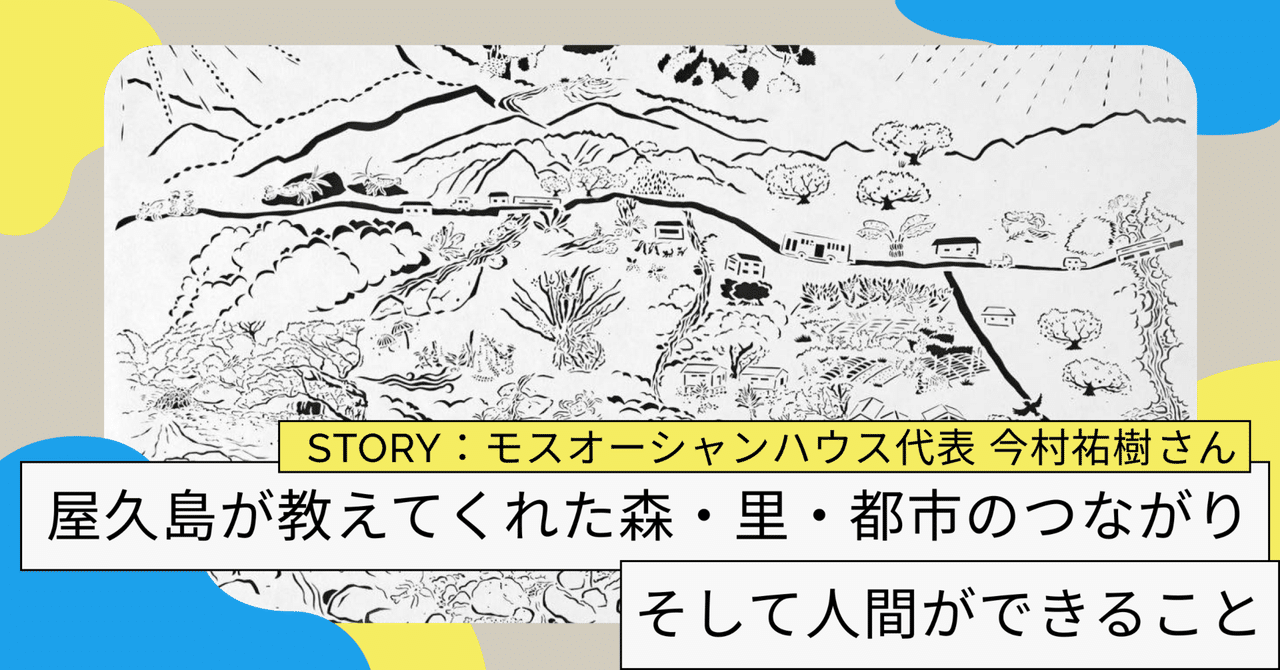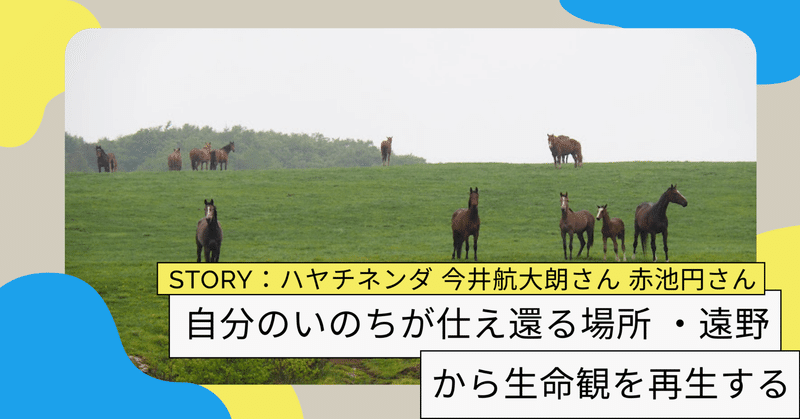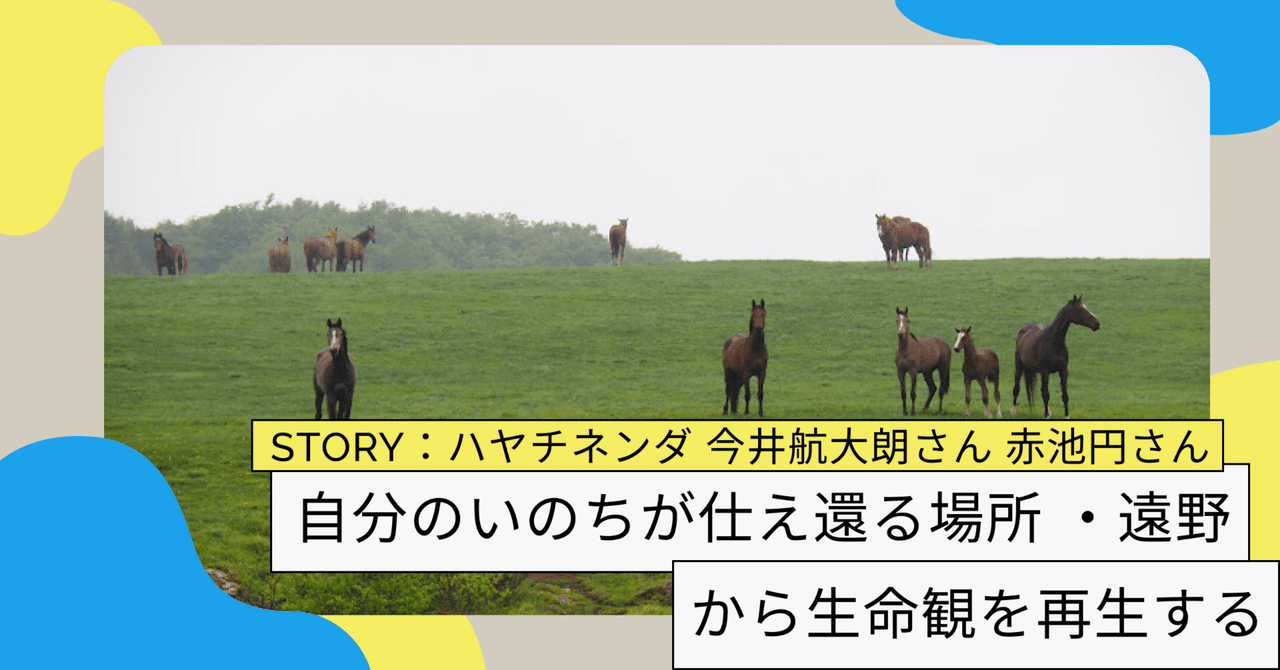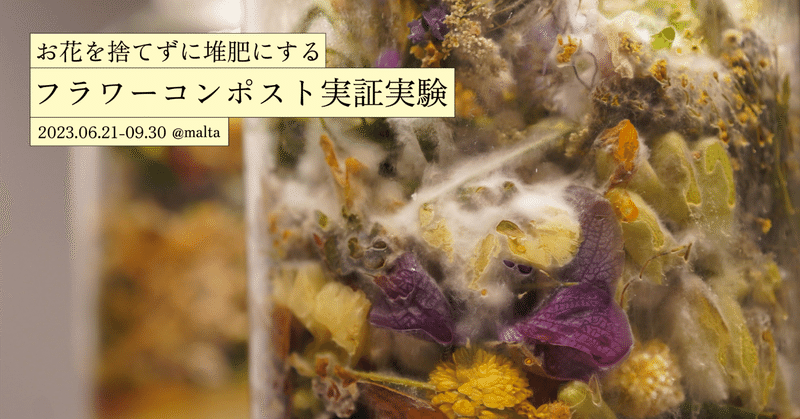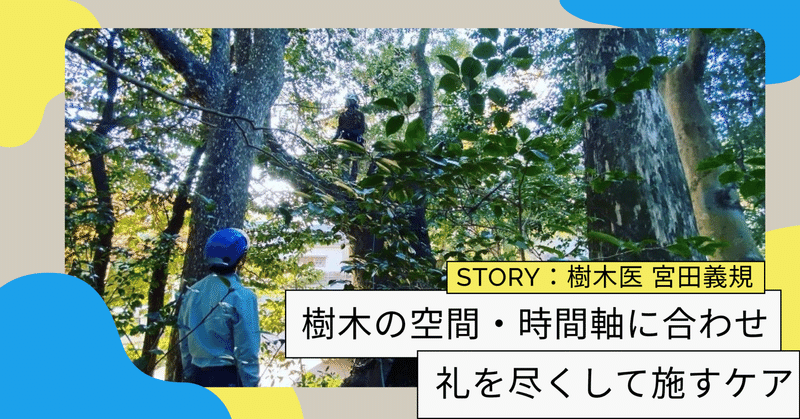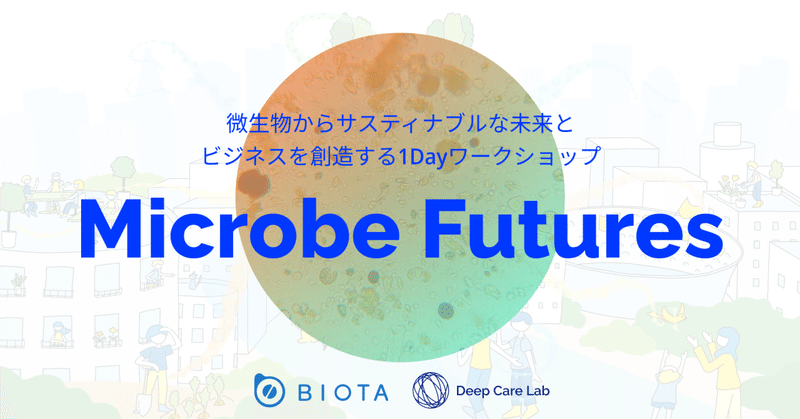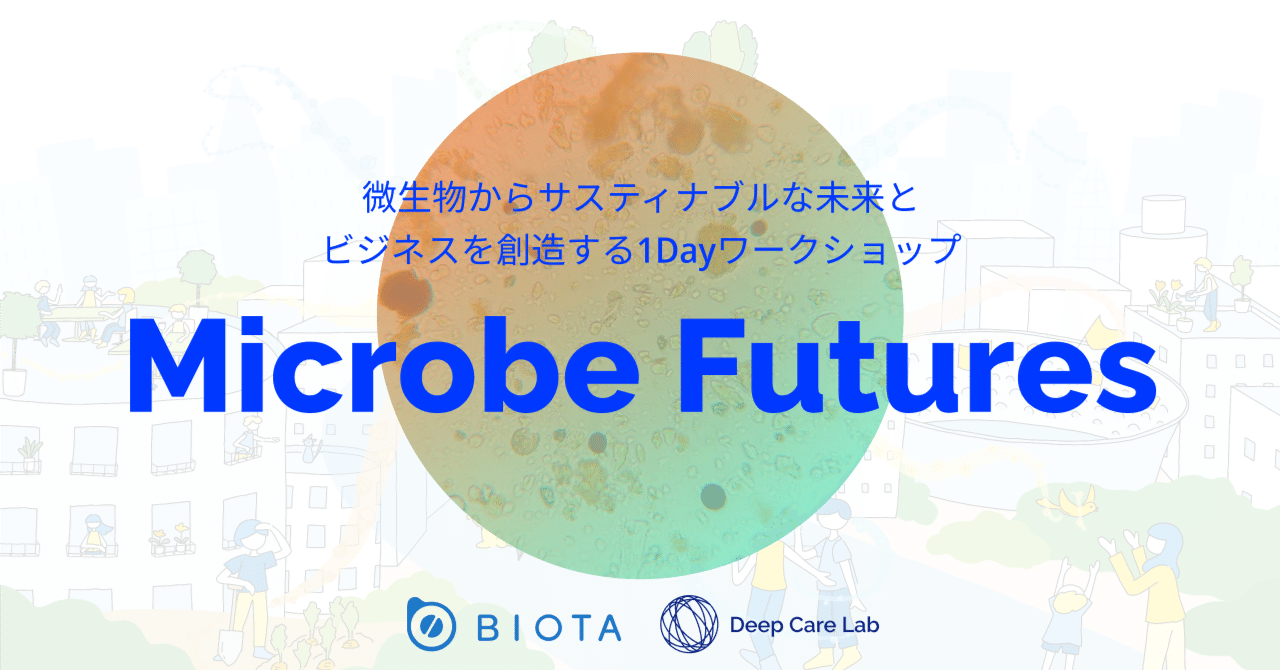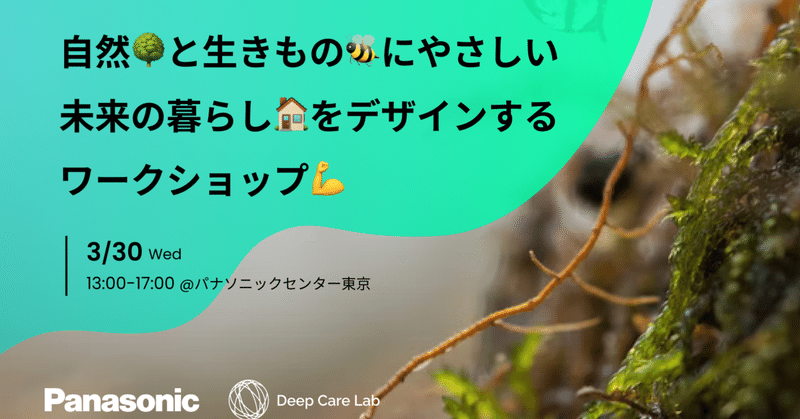最近の記事
- 固定された記事

変わりゆく植物、そして人との関わり合いから“生きがい”を見出す。園芸療法で「Meaningful life」を追求する|インタビュー: 晴耕雨読舎 石神洋一さん
子どもの頃、学校で野菜を育てたり、畑に行って野菜を収穫したりした記憶はありませんか? 毎日水やりをするたびに大きく育っていく姿に驚いたり、自分で採った野菜が「こんなにおいしいのか」と感動したり。大人になって忙しい日々を送っていると、植物と触れ合う時間はどうしても少なくなりがちです。 もし「心の余裕がない」「仕事ばかりで人生がつまらない」と感じているのであればあらためて植物と向き合ってみると、人生における豊かな時間を取り戻せるかもしれません。 Deep Care Labが

東洋医学に学ぶセルフケアの技法──自然の一部として、心身一体で無理なく生きる|インタビュー:CoCo美漢方 田中友也さん
なんとなく心がざわついたり、身体のしんどさを感じたりと、不調を感じる日はありませんか? 瞑想して呼吸を整える、今の気持ちを紙に書き出す……セルフケアの技法への関心が高まる中、不調を健康へと導くヒントが「東洋医学」にもあるかもしれません。 Deep Care Labがお届けする、サスティナブルな未来をひらくクリエイティブマガジン 『WONDER』では、持続可能性につながるビジネスやプロジェクト、気候危機時代の生き方のヒントになる創造的な実践や活動をされている方にお話を聞くイン
- 固定された記事
マガジン
記事
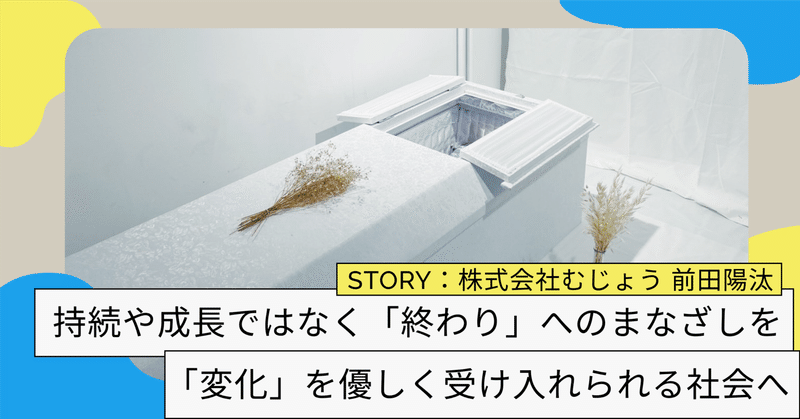
持続や成長ではなく、「終わり」へのまなざしを。「変化」を優しく受け入れられる社会へ|インタビュー: むじょう 前田陽汰さん
「人口が減った集落をどう存続させるか」「事業をどう成長させるか」……昨今、「持続」や「成長」のための議論はあらゆる分野でさかんになされています。一方で、「どのように終わらせるか」「いかにして閉じるか」といった議論がなされることは多くありません。 しかし、常に「持続」や「成長」を志向し続けることが、本当に望ましいことなのでしょうか?ときには、「終わり」を受け入れるべき場面もあるのではないでしょうか? Deep Care Labがお届けする、サスティナブルな未来をひらくクリエ