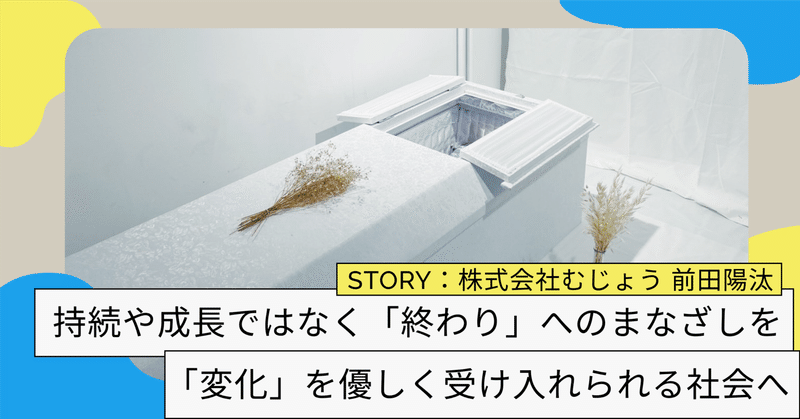
持続や成長ではなく、「終わり」へのまなざしを。「変化」を優しく受け入れられる社会へ|インタビュー: むじょう 前田陽汰さん
「人口が減った集落をどう存続させるか」「事業をどう成長させるか」……昨今、「持続」や「成長」のための議論はあらゆる分野でさかんになされています。一方で、「どのように終わらせるか」「いかにして閉じるか」といった議論がなされることは多くありません。
しかし、常に「持続」や「成長」を志向し続けることが、本当に望ましいことなのでしょうか?ときには、「終わり」を受け入れるべき場面もあるのではないでしょうか?
Deep Care Labがお届けする、サスティナブルな未来をひらくクリエイティブマガジン 『WONDER』では、持続可能性につながるビジネスやプロジェクト、気候危機時代の生き方のヒントになる創造的な実践や活動をされている方にお話を聞くインタビューシリーズを連載しています。
今回は、「変化にもっと優しく」をビジョンに掲げ、追悼サイトや自宅葬など人々が「終わり」と向き合うための事業を展開する、むじょうの前田さんに話を聞きました。前田さんはなぜ「終わり」や「変化」に着目するのでしょう。その価値観や軌跡についてのインタビューからは、いまの時代だからこそ求められる、「終わり」や「変化」との向き合い方のヒントが浮かび上がってきました。
今回のインタビューのお相手

前田陽汰(まえだひなた)
2000年生まれ、東京都杉並区出身。島根県立隠岐島前高校卒。2019年に慶應義塾大学総合政策学部に進学。清水唯一朗オーラル・ヒストリー研究会に所属し、「終わりという変化」に優しい眼差しを向けるための研究を行っている。2020年に株式会社むじょうを設立。3日で消える追悼サイト「葬想式」や自宅葬専門ブランド「自宅葬のここ」の運営といった葬祭関連事業のかたわら、死んだ父の日展、棺桶写真館などのイベント事業を手掛ける。「若者のための死の教科書」著者。
「持続」や「成長」ばかりが重視されることへの違和感
ーーむじょうは追悼サイトから自宅葬までさまざまな事業や活動を展開されていますが、ビジョンには「変化にもっと優しく」を掲げられていますよね。これはどういうことなのでしょう?
一言でいえば、私たちは「物事をソフトランディングさせるプロ」になることを目指しています。
昨今、多くの人が「持続させる」「成長させる」ことに意識を向けていますよね。一方で、「いかにして終わらせるか」について考えている人はあまり多くないと思うんです。結果として、終わりや死といった「変化」に対する免疫が育まれず、いざ変化のときが来ると痛みや苦しみが強くのしかかり、苦しんでしまっている人が多いように感じます。
これから人口が減っていく中で、すべてを今まで通り維持することは不可能です。そうなると、否応なしに終わりや死といった変化に向き合わざるを得ない局面も増えてくる。だからこそ、「いかにしてソフトランディングしていくか」という発想が重要になっていくと思うんです。
ーー「持続」や「成長」ではなく、「終わり」に目を向けていると。なぜそうした問題意識を抱くようになったのでしょうか?
原点には、島根県海士町の高校に通った経験があります。海士町は地域活性化に力を入れており、UターンやIターンによって町全体の人口は増えているのですが、集落単位で見ると必ずしもそんなことはなくて。存続の危機に直面している集落もありましたし、地元住民の中には活性化を望んでいない方もいるんです。
海士町に限らず、日本全体に「活性化こそ正義」といった風潮があり 、「集落を終わらせてはいけない」という価値観が強いと感じています。そんな中で、活性化できていない集落やそこに住んでいる方々は、罪悪感や後ろめたさを背負わざるを得なくなってしまっている。そのことに違和感を覚え、「終わり」について考えるようになったんです。
「思い出の品」や「事業」との別れまで
ーー「物事をソフトランディングさせるプロ」として、具体的に展開している事業についてもお話しいただけますか?
一つ注力しているのは、ご遺族が持っていない故人の写真や、メッセージを集められる追悼サイト「葬想式」です。最近ではスマホで撮影する人が多いので、ご遺族が持っていない故人の写真を友人が所有しているケースも少なくありません。亡くなった方の家族や友人が、それぞれ持っている写真をサイト上にアップロードし、故人宛てにメッセージを送るという体験を、3日限りで提供しています。
葬儀には行けないけれど亡くなった人に向けてメッセージを書いたり、カメラロールを遡って写真を投稿したりと、何らかのアクションを起こすことが、一つの死との向き合い方になるはず。インターネットだからこそ体験できる、死との向き合い方になるといいなと考えているんです。

また、一都三県を対象とした自宅葬専門の葬儀ブランド「自宅葬のここ」にも力を入れています。ここ数年、自宅で亡くなる方がまた少しずつ増えている一方で、自宅で葬儀まで行うという選択肢は未だに多くありません。そうした選択肢を広めていくことに貢献できればと思い、このサービスを立ち上げました。

他にも、父の日や母の日に亡き父・亡き母に向けて感謝や近況などを伝える手紙を綴るオンライン展示会や、思い出の品を棺桶に入れて燃やして供養するイベント「供養RAVE」など、さまざまなサービスやプロジェクトを企画・運営してきました。
ーー思い出の品、ですか。アプローチしているのは「人の死」に限らないのですね。
はい。最近は、事業のたたみ方に関するコンサルティング「終わりコンサル」にも取り組んでいます。サービスやブランドを閉じるときに、そこに関わっていた人たちがどういう気持ちで次の事業に取り組むかは、企業にとって重要なことだと思うんです。
「終わりコンサル」では、まずサービスやブランドを閉じるにあたって、どういった課題や懸念があるのかをお聞きします。たとえばヒアリングを通して、「このケースだったら、この本を読むといいかも」とパッと浮かんだら、「この本のこの部分を読んできてください」と輪読をおすすめする。そして、輪読の中で出てきたアイデアをいろいろと試していただいています。
ーー事業のたたみ方のコンサルというのはユニークですね。クライアント企業は、どういったケースで「たたみ方」にかかわる課題に直面するのでしょうか?
たとえば、事業が上手くいっているにもかかわらず、会社の都合でやめざるを得ないときです。特に大企業は新規事業に見切りをつけるのが早いケースも多く、自分や事業が悪いわけではないけれど、上から「もうこれは終わりね」と言われてしまうことがあります。
そういった理不尽な終わりと直面したときに生じる、やり場のない感情を受け入れる方法を、私たちは一緒に模索しているんです。大抵の場合は、ただひたすらそのことについて喋ったり、誰かに聞いてもらったりするしかありません。しかし、それを続けると次第に「誰も悪くないじゃん」「しょうもない問題だったな」といった空気感になってきて、いわば問題が移り変わり、変容が生じていきます。
なぜ「3日でデジタルデータが消える」設計なのか
ーーそうした「変化」に寄り添うさまざまなサービスやプロダクトを運営していく中で、留意しているポイントや気づいた点などはありますか?
「死」が持つ特性を、インターネットとどう接続するかを意識しながらサービスを設計することは多いですね。
たとえば、「葬想式」のコンセプトは、3日で消えること。デジタルの良さはアーカイブできることですが、それは死別とあまり相性が良くないなと思っています。ずっと残っていると、「新しい写真が投稿されたかな」「誰かコメント書いてくれているかな」と気になってしまいますよね。それが長いこと続くと、これからを生きる人の足かせになってしまう可能性がある。ですから、デジタル上に残せる期間は最長でも30日までしか延ばせないようにして、それ以降は紙のアルバムの販売に切り替えています。
それから、事業を展開していく中で、多くの人々の中に「死について話したい」という潜在的なニーズがあるということもわかりました。
入棺体験イベント「棺桶写真館」や、亡き父・亡き母のいる人に向けた父の日・母の日の過ごし方を提案するオンライン展示会を実施したとき、それらの様子をTikTokに流すと、コメントがたくさんついたんですよね。死にまつわることは、普段あまり話さないからこそ、みんなの中にそれぞれ言いたいことがあるのだと感じました。
ーー変化を受け入れる人々だけでなく、変わりゆく、あるいは終わりゆく対象の側についてはいかがでしょうか?
終わりゆく対象に、便宜上として人格を付与することはあります。たとえば人の死であれば、故人の立場に立って「こうかな?」「ああかな?」と考えることは、残された人のケアにもつながりますから。
ただ、終わりゆく対象に目を向けすぎると、残された人や新しい道を歩み始める人の足かせになってしまうこともある。ですから、サービスやプロジェクトを考えるときは、これから生きる人のほうをより意識するようにしています。
「しょうがない」という無常観を取り戻すために
ーー人だけでなくさまざまな対象の変化を受け入れる支援をされていますが、対象によってアプローチの仕方は異なるのでしょうか?
たとえば、公共財か私財かによって変わってきますね。自分が持っている家などの私財であれば、終わり方を自分で決められる方がほとんどですが、町や自治体などの公共財になると、意志を持って終わり方を決められる人がいないんです。
脈々とみんなで築いてきた町や自治体を、最後にどう閉じるのか。一人では決められない問題だからこそ、誰も語ろうとしなくなってしまう。公共財をどう閉じていくのかは、これからどんどん出てくる課題だと思います。
仮に、みんなの合意が取れて「最後は自分たちがいなくなっても大丈夫なように、みんなで墓じまいしよう」と決めても、最後の一人が死ぬまでこの村はあるんです。だから、最後は関係のない誰かが看取ることが必要なのではないかと思います。
ーーそもそも人間にとっては「終わり」であっても、村そのものは残り続けますよね。
おっしゃるとおりです。自分たちは「集落が終わった」と思っているだけで、その土地はずっと残り続けているんです。それも一つの変化であり、人間はそれらを「終わり」ではなく「無常」だと捉えたほうが良いと考えています。
終わりは一つの変化であって、善し悪しの判断ができるものではありません。とはいえ、終わりに伴う変化はネガティブに捉えられがちです。だからこそ、終わりや変化に対して優しい眼差しを向けられるようなメンタリティ、すなわち無常観を持つことが重要だと思うんです。
その点、自然と触れながら仕事をしている人は、無常観を強く持っている人が多いなと思います。たとえば、漁師さんは自然が相手なので、「今日は海が荒れているから、しょうがないわ」とよく言うんです。
しかし、都会に住んでいると「しょうがない」という言葉は通用しなくなる。「今月の売上目標営業目標達成できませんでした。しょうがないね」って言ったら、ビジネスは成り立たないですよね。
ーーたとえば山に行ったら「死ぬかもしれない」と思うことができますが、とはいえ多くの人が自然に触れて暮らせるわけではありません。都市生活の中で「しょうがなさ」をどう再構築していくのかが課題になる気がします。
本来はわざわざ山に入らなくても、「自分も自然の一部なんだ」と感じられる瞬間があるはずです。その代表的なものが「生老病死」という「内なる自然」でしょう。
都会や田舎など、どこに住んでいようと内なる自然は感じられるはずなのに、その出会い方すらも現在はコントロールされ、隔絶している気がします。老いないようにする、施設に入る、病院に入る……老いや病、死を日常から切り離すことで、「人間も自然の一部なんだ」と強く感じる瞬間が減ってしまっている。それによって、いっそう自然に対する奢りが強まってしまうのかもしれません。
ですから、自然との出会い方をリデザインすることは、終わりという変化と向き合うための大きな一歩になるのではないでしょうか。そう思って、私たちも死にまつわる事業に取り組んでいるんです。
日常に「意思を持って終わらせる場」を
ーー最後に、今後の展望についても聞きたいです。「変化にもっと優しく」というビジョンを実現していく上で、最近注力していることはありますか?
最近、改めてモノの供養はすごく可能性があるなと思っていて。人の死と向き合うことは重いですが、モノであれば「身軽に生きよう」くらいの感覚で向き合える。
何かしら意思を持って終わらせる場が日常的にあることは、優しい眼差しを醸成していくことにつながっていくと思います。終わりに対するライトな興味を入り口として、最終的には無常観を得ることにつながってほしい。そう考えて、私たちは「供養RAVE」や「棺桶写真館」を企画・運営しているんです。
ーー「モノ」との別れが、「別れ」への免疫をつけるための入り口になると。
そしてもう少し長い目では僕自身が、人に限らず、さまざまな物事を看取る経験を積み、積極的に関わっていきたいです。
その一つがお墓です。近年、離島にある先祖代々のお墓をどうすべきか問題になっています。たとえば、70〜80代の人が離島に住んでいて、40〜50代の子供が都市で家を買い、もう島に帰ってこないとなったとします。自分が死んだら島にある先祖代々の墓に入るのか、子供の家の近くに墓を買うのか悩みますよね。
きれいに墓じまいして「故郷の海に帰りましょう」と海洋散骨するのが良いのか、なんとかしてお墓を島に残すべきか。そういった、難しいけれどもやりがいのある課題に、どんどん取り組んでいきたいですね。
おわりに
「終わり」という言葉には、どこか影を帯びたネガティブな印象が一般的には想起されます。ただ、木々も葉が色づき、そして散った後にふたたび芽を出すように、終わりからまた、はじまっていく円環にある。そう考えると「終わり」とはとても自然な現象です。また、前田さんとの対話で気付かされたのは、終わりがあるとは、有限な生を生きることでもあり、ぼくら自身がまた終わっていく「自然な」身体をもついきものである、ということ。
ただ、そうは分かっていても、なかなか執着は手放せないし、何かの終わりは切なく寂しく、痛みを伴います。ゆえに、その終わりをソフトランディングさせていく。痛みを無くすことはおそらくできない。多分、不自然で歪です。ただ、それを柔らかな痛みに変容していくための、そうした意味でのケア的な関係や装置、触媒といったものをDeep Care Labとしても考えていきたい、そう感じられた時間でした。(Deep Care Lab 代表 川地真史)
(構成:大畑朋子、取材・編集:小池真幸)
・・・
Deep Care Labは、祖先、未来世代、生き物や神仏といったいのちの網の目への想像力と、ほつれを修復する創造的なケアにまつわる探求と実践を重ねるリサーチ・スタジオです。人類学、未来学、仏教、デザインをはじめとする横断的視点を活かし、自治体や企業、アーティストや研究者との協働を通じて、想像力とケアの営みが育まれる新たなインフラを形成します。
取り組み、協業に関心があればお気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
