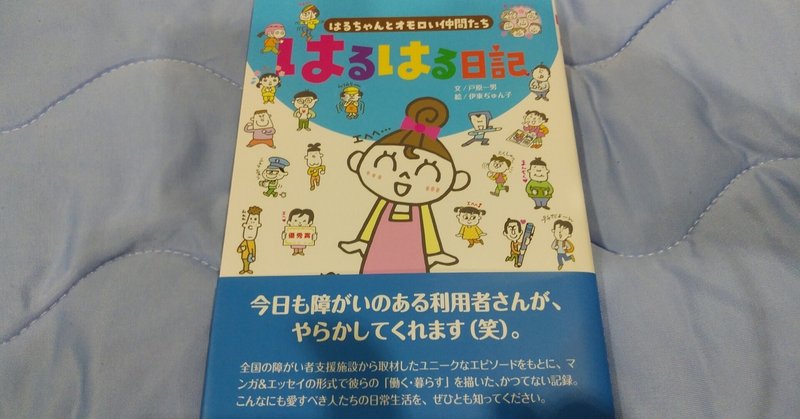
はるはる日記-はるちゃんとオモロい仲間たち-/戸原一男
この本は知的障害者(自閉症)のエピソードを主として描かれている本だ。
障害者福祉施設の利用者の方のエピソードが全国から寄せられ
それを元に書かれた
エッセイ集に近い(名前は仮名である)。
見開きで
右ページが漫画
左ページがその補足といった形式になっている。
1エピソードに対し
2ページしか描かれていないので(漫画1ページ、補足1ページ)
サクサク読みやすいし
様々な事例に触れることができる。

私のように障害者福祉施設で働いていたり
障害がある方を家族にもつ方
関わりがあるボランティアの方にとっては
あるあるのエピソードばかりで
読んでいて微笑ましくなるだろう。
(バスの座席にこだわりがあり、そこ以外座らない、てんかん発作の方が偽発作をする、水道の水を出しっぱなしにする、普段穏やかでも苦手な物を見ると逃げ出す、たくさんの人の誕生日を覚えている、時刻表が好きで乗り替えパターンを暗記している等)。
逆に障害者と関わりがない人が読むと
「変わった人達ばかりだなぁ。」という印象を抱くかもしれない。
栃木県の某施設では
各利用者の方に売上目標があると書かれていた。
しかも、利用者の方が自発的に考えたというので驚きだ(どこだろう?)。
また
以前販売に関する研修に出席した際
資料に描かれていた
【プロの販売担当者が福祉施設の製品を売るなら、こんな風に売る!】というエピソードもこの本に載っていた。
木製版画の手作りカレンダーが制作に一年半もかかること等をボードを使って積極的にアピールするやり方で
たくさん売れたらしい。
読んでいて驚いたのが
ヘラルボニーの方のエピソードも載っていたことだ。
「小林覚さん」でググると
見覚えのあるエコバッグなどが表示されて驚いた。
※ヘラルボニーとは会社名で、障害者アートをグッズ展開している場所である。
グッズはお高めで万単位や数千円もザラだが、デザイン性の高さから今は高級ホテルのルーム内デザインに起用されることもある。
読んでいて感じたのは
利用者の長所をどこかで活かせないか、という点である。
施設や家庭では困っていたり、課題のように感じている利用者の性格や特技、こだわりが
仕事に活かせないか、ということである。
私の知っている方で
ひらがなを速読できないが
歌詞を暗記している方や
1+1ができないが
みんなの誕生日や年齢、CDの発売日を丸暗記している方がいた。
現実問題としては
ひらがな等文字が理解できたり、計算ができる方が
仕事に有利である。
だが
自分の好きなことでは記憶力を発揮できる能力は
職員以上で
それが悩ましかった。
この記憶力をどこかで活かせないか、と。
また、同じようにひらがなや計算は苦手だが
手先が器用な方もいた。
おそらく
障害者福祉施設で働く職員は皆
利用者の長所や特技を仕事や作業に活かせないか、と何度も考えたはずだ。
活かす場所が見つかった方々は
賃金が上がったり、やりがいを感じるだろう(障害者の平均月額工賃は16000円である)。
利用者がよりよく生きられるように
福祉職員はまだまだ頑張らなければいけない。
そんなことを改めて感じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
