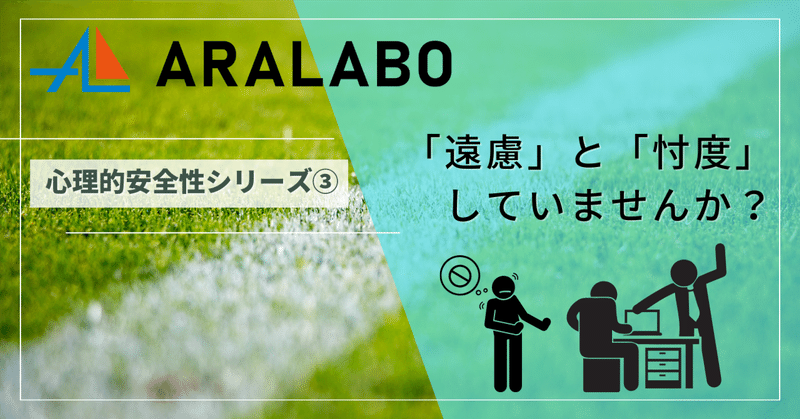
「遠慮」と「忖度」していませんか?
ARALABOファンの皆様。
ご機嫌いかがでしょうか?
10月も本日で終わり(投稿日時は10月31日)
下手なことを言いますが、今年も残すところ、あと2ヶ月となりますね。
年末に向けて忙しくなってくると思いますが、多忙さはあらゆる面で余裕を奪います。
だからこそ、「今のうちから」「日常から」が大事になってきますよね
さて、心理的安全性シリーズの最終回として綴っていきたいと。
心理的安全性シリーズはこちらこら☟
組織開発においての心理的安全性
心理的安全性とは、組織文化や風土とも置き換えられます。なぜ、心理的安全性を高めるのか。その理由は良い組織(この良い組織の定義がめちゃくちゃ大事だと思いますが、定義はそれぞれにあると思うので、割愛並び想像にお任せします。笑)で働いたり、活動したりしている方が、個人に良い影響を与えるということです。良い組織、風土や文化から人は育っていきます。
人が育つと言うことが、企業や組織においてとてつもない財産になります。
1つは人材開発がされ、能力が上がったり、スキルが身に付いたりして、生産性の向上が見込まれます。
2つ目は、教育するということに関して、企業や組織に自然に定着することで、ノウハウが出来上がります。そして、教育ができると言う事は、離職率の低下にもつながります。
管理職のリーダーシップの重要性
良いリーダーは、企業や組織、チームに良い影響を与えますよね?
管理職や役職上位者、リーダーと呼ばれる人たちが、組織において、憧れられる存在になれていたら、いかがでしょうか?
おそらく、若い社員やメンバーが目指すモデルとなり、頼れる存在であると思います。つまり、文化や組織風土を醸成する重要な要因となります。
まとめると
組織開発の観点から、心理的安全性の高い組織、風土や文化づくりを知ることで個人に与える影響が良いものになり、そこで育った個人、特に管理職やリーダーたちが憧れられる存在となり、組織、風土や文化の醸成の一端を担う。
そうすることで、組織やチームとしての戦略浸透だったり事業成果につながりやすくなると考えられます。つまり、心理的安全性に注目したり、焦点を合わせることで成果を生む人材開発と組織開発の良きサイクルが回ります。
心理的「非安全」な状態
これまで心理的安全性について綴ってきましたが、逆の「非安全」な状態とはなんぞや、そして、どうなるのかを記していきたいと思います。
企業や組織において非安全な状態の典型例は
①上司や役職上位者が部下やメンバーに「遠慮」すること
②部下やメンバーが上司や役職上位者に「忖度」すること
これらの状態になると企業や組織内のヒエラルキーを強化され、組織において、イノベーションが起きなかったり、既得権益主義になったりと組織を壊すサイクルに突入しやすくなります。
①の場合
・萎縮させてしまう可能性があるから、やめとこう
・任せられないから、自分でやってしまおう
↑特に後者はプレーヤー時代の成績や結果を出して、管理職に昇進パターンの典型ですね
②の場合
・上司は話を聞いてくれない、ならばこっちでやるしかない
逆に
・上司は忙しそうだから、余計な負担をかけないようにこっちで全て整えなきゃ…
これらの「遠慮」と「忖度」が組織に存在している事は、心理的安全性は確保されていません。
まとめ
心理的安全性シリーズいかがだったでしょうか?
学習する組織=成長する組織ですよね。
どんな時に頑張れるのかが=努力の源泉が何から来るのか、湧き上がるのかが大事です。

図の右下の「きつい職場は」怒られないためが努力の源泉になりがちですが
右上の「学習する職場」は図上部に書いてあるサポート・意義・見返り・配置が存在すると、成長する組織になっていきます!!
人は、ハッピーな出来事があると行動量がが増やそうとします。アンハッピーな出来事があると行動量が減らそうとします。
その為にも、心理的安全性を確保しながら、、その時々にあった最適解を見いだすために、ぜひともARALABOのコーチングをご活用いただき、皆様の組織の成果につなげていただきたいと思います。
お後がよろしいようです。
日常に活力と笑顔
あなただから作れる未来がある
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
