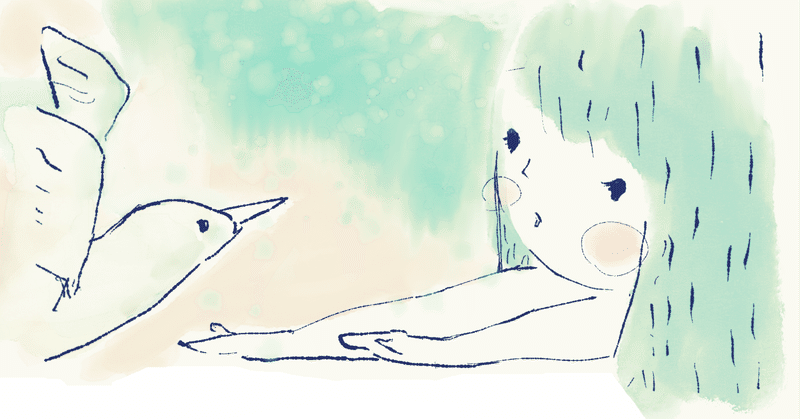
幼き日の遠い記憶
幼い子どもの頃、隣のさやちゃんとよく遊んだ。
さやちゃんは同い年だけど大きなお姉ちゃんがいたせいか、ませて僕のことをいつも子ども扱いしていた。だから遊びはいつもおままごとで、僕は子どもの役ばかりだった。本当は嫌だった。けど当時の僕は幼い子どもで、さやちゃんに嫌だって言えなかった。だからさやちゃんがお母さんになって、ご飯を食べたり、一緒に横になって寝たりして遊んでいた。
その日も相変わらずのままごと遊びで、僕は昨日テレビで見た怪獣のことが頭から離れなかった。さやちゃんは怪獣なんで乱暴だって、話にもならずお母さん役を演じてた。でも僕が心ここに在らずで、つまらなそうにしているのに気付いたのか、
「ねえ、今度はお父さんになってみたい?」
って聞いてきた。僕はおままごと遊びは好きじゃなかったけれど、子どもの役じゃないだけで嬉しくなった。
「うん、やる。」
さやちゃんは、僕が乗り気になったのが分かったようで、得意な顔でお母さん役を続けた。僕はお父さん役がどんなのか知らなかった。でも夕食の風景は子ども役と何も変わってないように思えた。
「ねえ、お父さんと子どもって、同じなの?」
口をとがらせた僕がそう聞くと、さやちゃんは物知り顔で答えた。
「同じなわけないじゃない、だって子どもはお仕事しないし」
さやちゃんは辺りを見回すと、僕のほうに近づいた。顔がくっつくくらい近くなった。
「大人なんだから、」
そう言ってさやちゃんが目を閉じて僕にキスした。柔らかい唇の感触が初めてで、すごく驚いた。
「どう?」
悪戯っぽくさやちゃんが微笑んだ。
さやちゃんがキスするなんて僕は考えてもいなかった。何となく、いけないような気がした。
「ダメだよ…」
思わずさやちゃんのことを両手でついてしまった。僕は絞るような声でそう言った。
「しかたない子ね。」
さやちゃんはつまらなさそうな顔でそう言うと、お母さん役に戻っておままごとを続けた。僕は居心地が良くなくて、早く終わってほしいってずっと思ってた。母が帰ってきて、さやちゃんも隣の家に帰った。僕は母の前でも何だか気まずくて、きっと様子がおかしかったのかもしれない。母がいつもより長く抱きしめてくれた。僕はさやちゃんのことが分からなかった。さやちゃんがいなくなればいいって、そんなことを考えてた。
幼い記憶は途切れ途切れで、断片しか思い出せない。でもその後さやちゃんとは遊ばなくなっていて、母にさやちゃんのことを聞いたことがあった。
「さやちゃんはね、悪い人に連れていかれたんだよ。」
僕は母の言葉の意味がよく分からなかった。でもさやちゃんがいなくなったことだけは分かった。僕がいなくなれって、そうお願いしたからだ。そう考えた僕は悪いことをしたんだって思って動けなくなった。見かねた母が、お腹に抱え込むように抱きしめてくれた。
大人になって、さやちゃんのことは顔も声もほとんど思い出せない。その頃の記憶で思い出せるの、はしばらくして仲良くなった男の子と毎日怪獣ごっこをしたことだけだ。母にもさやちゃんのことは何だか聞いてはいけないような気がして、ずっと聞けずにいた。
あれは本当の記憶だったのだろうか。僕の記憶には母の柔らかいお腹の感触だけ、僅かに残っている。
(イラスト ふうちゃんさん)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
