
「Art Festival 2022 ~大地の芸術祭と瀬戸内国際芸術祭を考える」ディスカッション編
channelによる、みなさんとの対話と交流の場、PLAZA。
日本や海外で実施されている芸術祭にフォーカスし、その実態や内容についての知識をシェアしながら、様々な切り口からディスカッションを行っていくPLAZAの芸術祭企画の第1弾となる今回は、大地の芸術祭と瀬戸内国際芸術祭の比較と考察をしました。
プレゼンテーションはこちらからご覧いただけます↓
☆瀬戸内国際芸術祭プレゼンテーションレポート
☆大地の芸術祭プレゼンテーションレポート
さて今回は、プレゼンテーション終了後に行った3つのトピックを元にしたディスカッションの様子をお届け!様々な立場の人からの多様な意見が出た現場をぜひ感じてください。
*発言者は、その人の立場とイニシャルにてお届けしています。
トピック1:「芸術祭の両面性について」
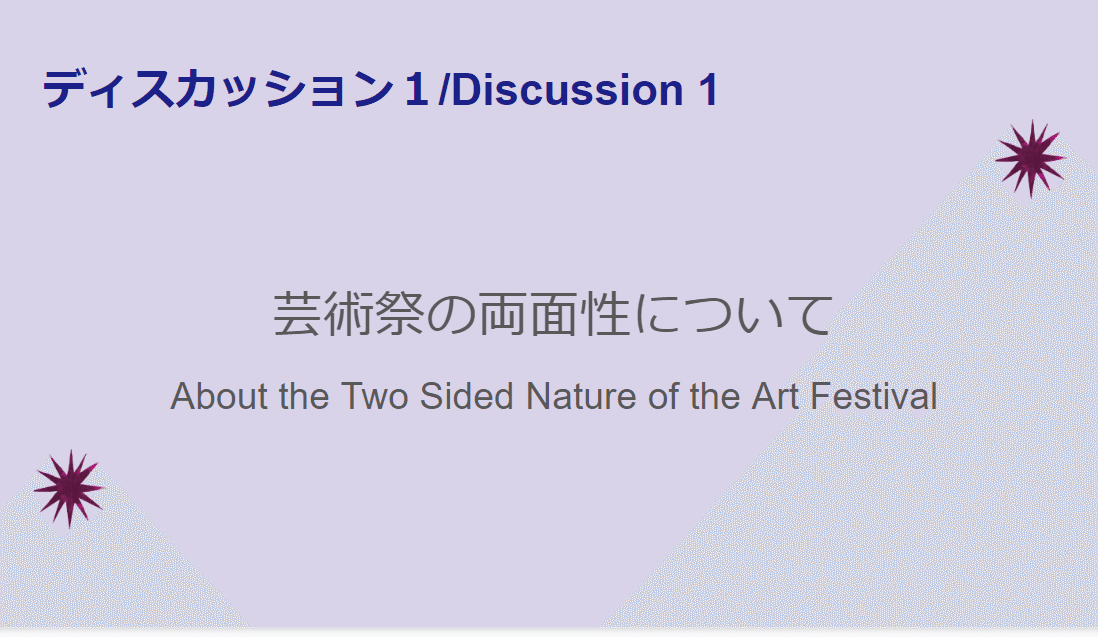
ー
”効率とお金一辺倒の社会(資本主義経済社会)において、それとはことなる生き方や社会のあり方を提示するために、芸術祭を始めようとした”というアートディレクターの北川フラムさんとプロデュ―サーである福武總一郎さんの思いが両芸術祭に通底する要素です。しかし、特に瀬戸芸では顕著ですが、芸術祭がアートツーリズムとなるように、現行の社会の中でアートを取り入れていくと現代観光という消費行動と結びつく側面が出てきます。こうした両面性が生じていることを、リサーチを進める中で私たち(コレクティブ運営メンバー)は感じました。そこで、このトピックを扱い、参加者の皆さんの意見を聞いてみることに…!
ー
アートディレクターHさん
北川さんは、アグレッシブな問題提起もするけれども、現実的というか政治力もある人です。芸術祭を手掛けるようになる前も、ギャラリーもやるけれどパブリックアートもやるしキュレーションもやるなどしていました。業界的には、作品をキュレーションすることと作品を売ることというのは立場が違うから、両方やるのは微妙と言われていたりしていたりもします。
だから、そもそも常に両面性を持っている人だったのではないかと思います。
また、よくおっしゃられているのは観光の側面が強くなるメリット、デメリットは両方あるけれど、どんな事業よりも変な道路を作るよりはよっぽど良いなど、大多数の人を納得させやすいことを発言されているんですね。
それから北川さんが地域芸術祭を始めたことで、フィールドが増えたことはあると思います。
アート業界で若手、中堅でバリバリ仕事ができているのも、新卒で働いている人が増えたのも、半分以上が芸術祭やAFGのような現場だったりします。
両方を横断する人は少ないけれどいます。ディレクター系だと、南條さん(南條史生/横浜トリエンナーレなど創始)や、瀬戸芸の人だと大巻(大巻伸嗣/作家)さん。そのような人が増えていて、少ないけれど貴重な存在だと思います。
▶なるほど。参考になります。
では、今後の地域芸術祭や芸術祭はどのようになっていくと思われますか?
北川フラムさんと同じような仕事ができる人はかなり出てこないと思うし、時代的に違うやり方になっていかざるを得ないのではないかと思います。
現在は一応、公的資金が大きく出ていて、香川県はその中でも観光の予算が結構出ています。
観光は、瀬戸内界隈は説明がつきやすいです。岡山県も芸術祭を立ち上げようとしていますが。
現場を作れるディレクターよりも、もしかしたらプロデュ―サーの仕事もそうだと思うけど、限られた文化予算をどういった形で繋いでいくのか、外部の資金をどう取ってくるかなどに長けた文化行政プロデュ―サーなど、本来あまり名前が出てくる仕事ではないところの可能性を探ってみるのはどうでしょうか。
調べてみれば分かりますが、行政がこれから何をしようとしているか政策の計画や進行ビジョンも結構出しています。
行政も課題意識はあり、リアルな現場に繋がっていくにはどうなったらいいのかを考えながら仕事をしています。
重要なポジションみたいなのも変わってくるのではないでしょうか。。
トピック2:「労働問題について」

ー
芸術の現場では、よく耳にする「労働搾取」。今回のプレゼンテーションの中でも、大地、瀬戸芸の両者共に同じ課題が真っ先に上がりました。
今回は、両芸術祭に関わった経験のある方にお越し頂いたので、現場の生の声をお届けします。
ー
▷県職員として働きながらベテランこえび隊として瀬戸芸に長年コミットされているGさん
事務局などの運営本体はあまり気にしている問題ではないと思います。人が来るからそれでいいのでは?というのがスタンス。
直した方がいいとは思うけれど、このスタンスは変わらないのではないでしょうか。
でも、人がこないのは間違いないと思います。
今までは海外からの人が来ていたからよかったが、このまま人手不足は続くと思います。
もちろん、お金だけが全てではないのでそうでない部分でケアできればいいけれど、変わらないと思います。
こうした意見も出る中、ボランティアとして芸術祭に関わることに対してプラスの意見を持っていたのが、
▷観光を学ぶ大学生のYさん
大学の方から、こういうボランティアがあるよ、どう?という感じで声がかかって瀬戸芸に参加しました。アートからではなくて、観光の現場を見られるからという理由でこえびに行こうと思っていました。
また、瀬戸芸の春会期はGWを挟むから、GWに帰省しなくていい理由ができたという不純な動機で、会期中の土日を全部入れるくらいでした。
私は、お金をもらわなくても全然いいし、タダで自分のいったことのない島に連れて行ってもらえて作品も見れて、色んな人と話すこともできる。お金なんかいらない、そんなのいいですよ、という感じです。
秋会期では雇われて、遊撃(運営スタッフのこと)のアルバイトをしていました。
結果的にお金をもらっちゃいましたが、秋会期に遊撃の話を頂かなくてもすごく行っていたと思います。
でも、私のような人はあんまりいないと思います。周りは皆、1回行っとくかという感じでで。同世代のこえびがいなくて、どこにいっても最年少でした。
また夏会期は、地元の他の大学生が1回ボランティア行ったら単位あげるよという感じで来ていました。
そのときに思ったのは、価値観が違いすぎてしんどかったということです。
好きで来ている人間と、単位のために来て、1日そこにいて座っておいたらいいや、みたいな人間が一緒に受付したらすごいしんどいんです。
だからと行って、門戸を狭めてしまったら、人手不足も解消されないし…。
▷ベテランこえびGさん
最初の頃の刺激とか学びの刺激とか繋がる刺激があるころはいいけれど、それがなくなると来なくなってしまいますね。
大地の最初の頃も、その頃は人が沢山来ていました。ただ段々年数がが経つことに、来てくれることが当たり前になってくると減ってきます。
瀬戸芸も、初期メンバーのベテラン勢はモチベーションが高いが、若い人が入ってこないということは致命的な問題です。
▷アートプロデュ―サーHさん
アートの現場だけでなく、どんな現場でも、ボランティアや労働に関する考え方が変ってきていると思っています。
僕の世代は、大地の芸術祭が始まったころが大学生で、同世代の人が、そういうところで作品の解説をさせられたとか、英語が喋れるだけで空港に作家を迎えにいかされたなど、やらされたという感じがなかったし、実際そういうのを仕事にしている人も多いです。
でもやっぱりそういうのもなくなってきています。
一方、擁護するとしたら、突き詰めるとアーティストも労働ですよね、という話になってきて非常にややこしいんですね。
ボランティアでもいいから関わる、とか関わる選択肢の一つとしてのボランティアなのかなと。
そういう仕組みがあるから、交流の場になって、むしろそれが一番の価値なんだと、北川さんも言ったりもしています。
でも、温度差は現場で出ますね、それは分かります。
でもそういう温度差もある社会を知る、という経験でもあるのかもしれません。
▷瀬戸芸関係者Mさん
色んな価値観を持っている人がいて、人によってボランティアの定義って違いますよね。
そういう中で、何がベストなのだろうといつも思います。
お金じゃないこともありますし、全員ハッピーになることは無理だなと思うけれど、どうしたらいいのか。どういう形だったら納得できるのかは、人によって定義が違うし、どうやったら建設的な方向に行けるのかを考えています。
トピック3:「それぞれの芸術祭の好きなところ、改善すべきだと思うところ、もしくはこれからどうなると思うか」

ー
これまで、両芸術祭の様々な側面について話し合ってきましたが、今度は率直に好きなところを聞きつつ、改善したらよいなあと思うところやそれぞれが考える今後について聞いてみました。
ー
▷こえび経験者でまちづくりを学ぶMさん
好きなところは、私が今済んでいるのが横浜で、大阪にも住んでいたこともあったため、地方に行く機会になることがいいなあと思っています。
大阪に住んでいたときも、初めての一人旅で訪れるみたいな感じの感覚になれるのが、地方で開催することに対していいなと思いました。
また芸術祭自体については、今まで美術館の中でしかアートに触れたことがなかったから、島を巡りながらとか船に乗って、など冒険している感じが個人的にはすごく好きだなと思います。
改善点については、私はこえび隊に参加した際に豊島の新聞を配るという活動をしました。アートが展示されていない本来の島の中に入って島民の方に届けるということだったのですが、芸術祭で回らない部分に沢山人が住んでいて、そこが区別されているなと感じました。
同じ島でも、男木島は、巡っているとそこに住んでいるところがあって、という感じでしたが。
島の本来の姿って何なんだろう?と思いました。改善すべきところなのかどうかも含め考えていきたいと思っています。
▷大地の芸術祭に作品制作とスタッフとして参加したHさん
大地の芸術祭は移動が不便だけど、作品を見に行った時にこのご飯やさんがあるとかこの温泉がある、など地域を知れるところが良かったです。
ただ、アルバイトをしているときにマニュアルがなく、不測の事態に対応できないことがあったので改善点かなと思います。
▷大地では作品制作、瀬戸芸では豊島で施設作りのアルバイトをしていたIさん
都会に住んでいるから、地域の人たちと触れ合ったり、外国人の人とも言葉が通じないので手でジェスチャーしてコミュニケーションをするなど人々のつながりのあたたかさを得られる良い機会でした。人々の繋がりが感じられる場所でした。
▷今回台湾から参加してくれたこえび隊として関わったAさん
地元の方と話せたり繋がれたりするところが好きです。
ただ、これから人口が減少し高齢化が進む中で、3年後、6年後には芸術祭が開催できるのかが心配です。
質問コーナー
また、ディスカッションの他にも主に瀬戸芸に関して質問があがりました。
質問には、瀬戸芸のプレゼンテーションを担当したコレクティブメンバー、CHISATOが答えています。
質問1
瀬戸芸では、島の人たちが芸術祭をどのように考えているのですか?
まず、大地の芸術祭での成功例があるからこそ、瀬戸芸ではやりやすかったということがあります。
また、島によって文化や性格が全く異なるものなので、単純比較が難しいです。隣の島であっても、こんなに違うのか!と驚くほど違います。
例えば、私がいた女木島は比較的静かで大人しく外の人を受け入れる性格の方は少ないです。一方、隣の男木島は移住者を積極的に受け入れていたり、オープンな傾向があります。
また、外(外部)から見たら、例えば女木島は高松からも近く地形も平らでキャンプなどもしやすいというように観光資源に溢れているように見えます。
ですが、実際には島の人たちは高齢化が進んでいて、新しい変化を積極的に望んでいる訳ではないという現状もあります。外部の目線や期待と内部の人たちの求めていることは必ずしも一致する訳ではないのだろうということを感じました。
ー
質問2
瀬戸芸のプレゼンの中で、地域の人に受け入れられているなと感じるときもあれば、境界を感じるときもあると言っていたが、どういうことが具体的にありましたか?
春会期に、女木島に来た人がコロナに感染したという情報が発表された後に、島民の方からかけられる言葉が「おはよう」から「コロナは大丈夫か?」という挨拶に変わったり、小さな共同体だからこそ境界線がはっきり出やすかったことを感じました。
それに対して、
過疎化や高齢化が進んでいるけれど、そういう問題を共有しているのかなと思っていたが、新しい人を受け入れることに前向きではない人がいることを不思議に感じたという意見が質問者の方から上がりました。
PLAZA 4th「Art Festival 2022 ~大地の芸術祭と瀬戸内国際芸術祭を考える」まとめ
当日は、両芸術祭の関係者やアート関係者の方、どちらも行ったことがないけれど地方芸術祭について気になっている方、たまたま空いていて来られた方…など多くの方にご参加頂きました。
時間と人数、そしてオンラインという環境上、どうしてもオープンな場にすることが難しく、参加者全員の声を聞くことができなかったのですが(反省&改善していきます)、その中でも上がった意見は様々な切り口から論じられているもので、多様な視点から芸術祭を見直すきっかけとなりました。
日本で著名なこれら2つの芸術祭ですが、今後ますます高齢化が進んでいく問題と合わせて芸術祭の行方が気になるところです。
アートで大きく社会を変えることは難しいかもしれませんが、それでも何か、アートを通してでしかひらくことができないもの、紡ぐことができない関係性があるのではないでしょうか。
特に地方芸術祭は、その土地の人々や行政、協賛企業など多様な人々を巻き込んで実践されていきます。
ディレクターの北川さんはよく、立場の違う人と協働するからこそ意味がある、と仰っています。美術を美術の現場に留めず、社会に開いて関係性を結んでいくこと。そうしたことが、芸術祭という媒体を通じてであれば可能であることを、両芸術祭は示しているように思います。
著書、『直島から瀬戸内国際芸術祭へー美術が地域を変えた』では、「美術は今の私たちのいる社会や文明と私たちの生理のずれを教えてくれる」と北川さんは語られています。
芸術祭は、
「発見」「交渉」「交流」「協働」「伝達」
が同時に行われていく現場です。
様々な人が関わり大きなお金も動くからこそ、地方で現代アートの祭典を行うことに対してプラス、マイナスそれぞれの意見を持つ人がいて、問題も発生していきます。
大地の芸術祭は始まってから約20年、瀬戸内国際芸術祭は約12年ほど経ちますが、社会状況に合わせて今後の芸術祭の在り方も変わっていくことが予想されると同時に、トップダウン型で行われてきた両芸術祭を今後誰が指揮していくのか、どのように運営されていくのかなどの問題もあります。
労働に関する状況などは、組織の構造から起こっている問題でもあるので今後どのような体制が取られていくのか、また人口減少による地方の過疎化といった現状に対して芸術祭はどのように向き合っていくのか、逆にどのようなことをもたらせるのかなどについて、考えていくことが必要ではないでしょうか。
ー
今後もPLAZAを通じて、日本及び世界の芸術祭について情報を共有し、皆さんの意見を交換していける場づくりを続けていきます!
その他にも、芸術に関することから社会に関する問題まで、幅広いトピックを取り扱ったPLAZAも開いていく予定です。
ご興味を持っていただいた方は、ぜひ各種SNSをチェックしてみてくださいね*
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
