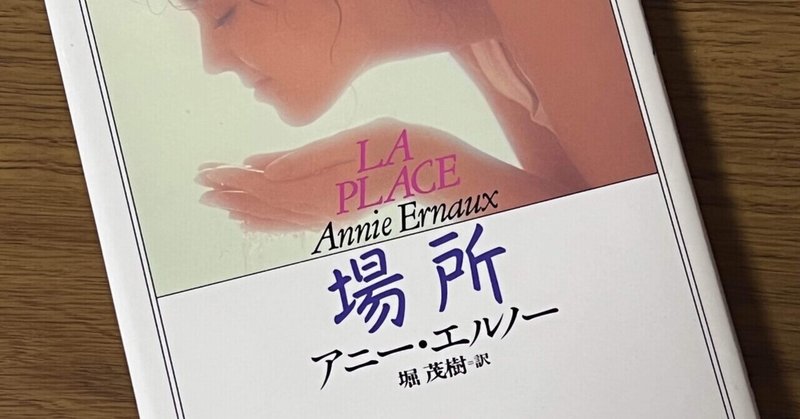
場所 アニー・エルノー
私は以上で、自分が教養あるブルジョワたちの社会に入った時に、その入り口の手前に置きざらなければならなかった遺産を、明らかにし終えた。
ヨーロッパの長い貴族社会の歴史を振り返れば、だからこそナポレオンのフランス革命があったりしたのだし、日本では中々理解し難い、社会階級格差が今もあるだろう。
僕は家庭の事情で子どもの頃スペインとフィリピンにいたことがある。
どちらも今思うと、日本よりもかなりはっきりとした社会階級格差がいたるところにあった。
エルノーの生まれ育った土地の歴史的背景や生い立ちを鑑みれば、エルノーが抱き続けた葛藤は想像に難くない。
その葛藤を「父」という他者の小さな歴史を辿ることで、彼女は自身の葛藤を文章化し、乗り越えようとしたのかもしれない。
シンプルな情熱、The years、と本書の場所を読んで僕が彼女から感じたことは
・愛を渇望していたこと。
・社会的格差とくに性差にフォーカスしていること。
・贅沢の概念
・たとえ小さな個人的葛藤であれ、自分自身と闘ったことを書いておかないと死にきれない、そのような強い意志、信念があったのだろうということ。
葛藤と対峙するときは勇気がいるし、孤独にならないとできないこともある。
とりわけ文章化することは、葛藤と対峙し乗り越える上で客観視もできる為最良の手段にもなり得る。
自己を見つめるいくつかの視点として、「では身近な社会ではどうだろうか?」といった視点を持ち、絡めていくことも極めて重要だろう。
少し前に読んだ、アリ・スミスの四季四部作もそうだが、個人的な小さな歴史と葛藤に社会問題という視点を持つ作品はその時々の社会風潮も浮き彫りにしやすい。
いずれにせよエルノーは女性特有のもしくは彼女の「パッション」や目の当たりにしてきた格差社会格差と葛藤しながら向き合い、死にものぐるいで書かなければ自分自身を納得できなかったのかもしれない。
そうしたことは自分で自分を乗り越える、と言う点だけでも素晴らしいことだと僕は思った。
僕は僕なりの視点でしかそのプロセスを読み取れない。
重複になるが、本作の感想を述べると、エルノーは書くことで愛情に飢えている自己を補完しようともがいている感覚がする。
本作は父のことを回想している。
父と自分とのさまざまなギャップを埋めたくて、社会階級格差を照射しているのは本当に素直に「何か」を訴えているのだろうか?
愛を渇望するのは誰しもある。
渇望をひとつステップアップして、愛を分け与えることに踏み出せていたら、どうだろう。
さまざまな格差の与えられた環境を受け止めつつも、周囲や自ら起こした遠心力──出会い、努力や葛藤など──によってその土壌からスピンアウトすること。
そうして身近にある格差を見いだすアニー・エルノー。
『場所』で父にフォーカスし、父とのギャップを埋めようともがいたりしながらも、父の生きた証のようなもの──存在をエクリチュールとして羽ばたかせたように思う。
JE SUIS LE SOLEIL, il en résulte une érection intégrale, car le verbe être est le véhicule de la frénésie amoureuse.
「私は太陽である」の「である」は愛を伝達するbe動詞。
常にこのバタイユの言葉を胸に今いる場所を照らしながら、僕も葛藤を乗り越えなきゃいけない。
愛を持って。
スピンアウトし信念を持って書き続けることは裏切りとは限らない。
ときには、社会の中で見えずらいものや、見たくないもの、忘れ去られたものの存在を再び誰かに認めさせるための視座を上げることもある。
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
