
【本が読めなくなった】 11月の読書記録と記憶。
想いを書くのではない。むしろ人は、書くことで自分が何を想っているかを発見するのではないか。書くとは、単に自ら想いを文字に移し替える行為であるよりも、書かなければ知り得ない人生の意味に出会うことではないだろうか。
本が読めなくなった。悲しいとき、苦しいとき、本が読めなくなる。だから今は、そっと積んでおくことにする。
自分の日記が精一杯で、誰かに宛てた文章も書けなくなった。心が萎える日々。崩れ落ちそうな自分の精神状態を正しく保つことで精一杯だった。毎日『自分がどう在るか』が常に問われ続けていたように思う。身体と心に与えるもの、目に見えるもの・目に見えないものも含めて、ひとつひとつに意識を向け与え続けた。眠れない日もあり、一睡もできずに翌朝を迎える日もあった。それでも朝が来ると、太陽の光を浴びて、深呼吸をした。あぁ、と深い感嘆の、言葉にならない空気のような声が漏れる。今日も一日がはじまる。新しい朝が、希望で、一筋の小さな光だった。毎朝、鏡の前で自分に掛けた言葉は、すべて明るいものに、プラスものだけにした。都会を離れ、緑あふれる自然のなかに身を置くとほっとした。ある日の夕陽が、あまりにも美しくて感動して泣きそうになった。
葉は、空は、水は、常に私たちの目を清める。
本は静かにその時を待ってくれている。ある夜は、ひとり、本棚の前に静坐して、ぽたぽたと涙を流し続けた。本が読めなくて泣いているのではない。与えられたこの運命に向き合い歩んでいる、この自分になんだかとても泣けてきた。本の背表紙を眺めて、本の内容を思い出していた。それを読んでいた日の自分や、これを書いた著者のことを思った。
11月の上旬に2冊を読んでいた。そのとき読んで、印象に残っていた言葉は、半ば以降のわたしを支えてくれていたのかもしれない。2冊とも一言でこんな本ですと語りきれないほど、深く沁み入る本だった。
死なないでいる理由 鷲田清一
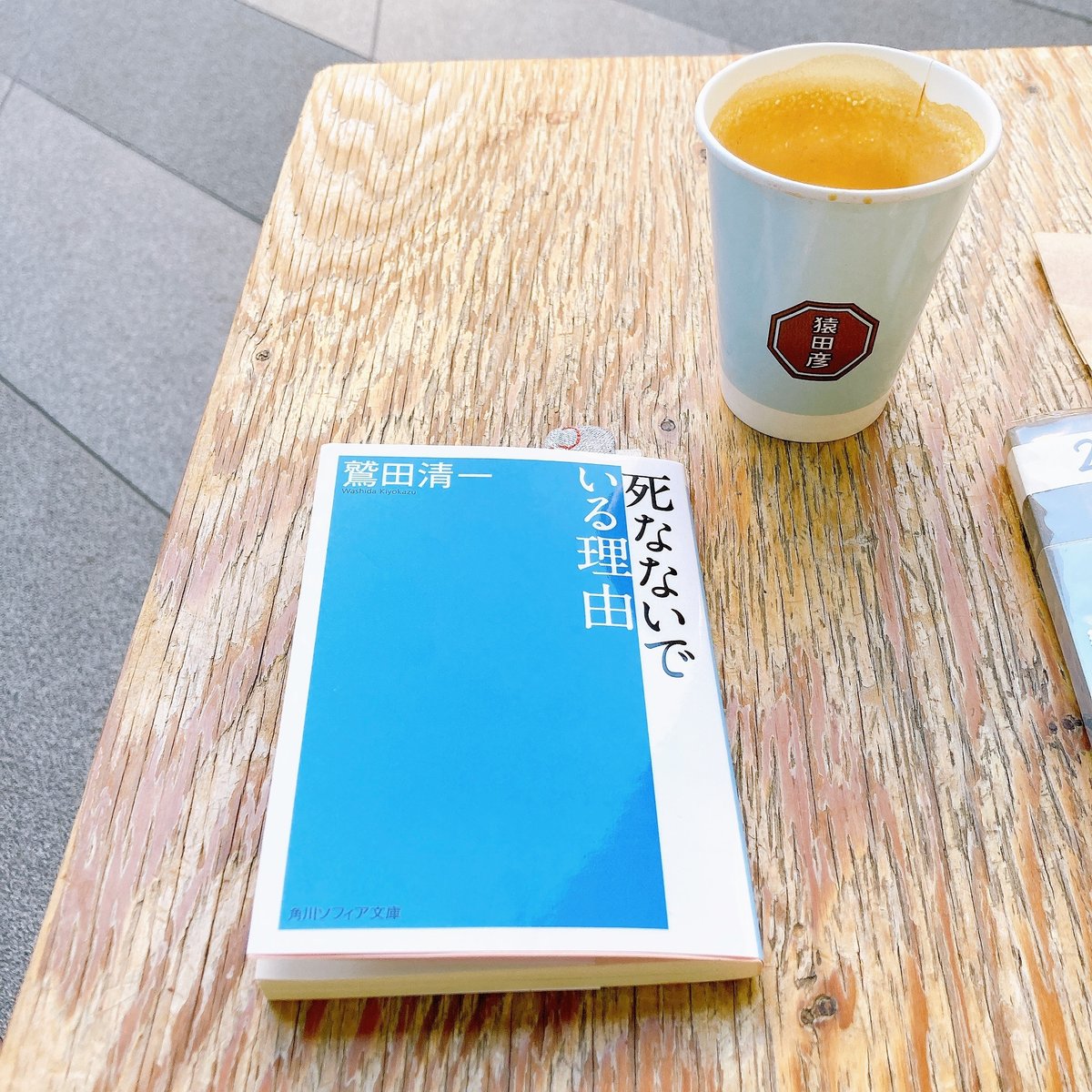
<本の内容>
生きること、老いることの意味。現代はそういう問いを抱え込んでいる。<わたし>が他者の宛先でなくなったとき、ひとは<わたし>を喪う。存在しなくなる。そんな現代の<いのち>のあり方を滋味深く綴る哲学エッセイ。
わたしがじぶんの存在<わたし>として意識するのは、すでに述べたように、自分の存在が他者の思いの宛先となっていることを感じること、自分の存在が他者になんらかの効果をおよぼしていることを知ることきっかけとしてである。わたしがここにいるというプレゼンスの感覚が生まれるのは、他者の眼差しを浴びることによって、他者のそれに刺さることによってである。
『水中の哲学者たち』(永井玲衣)から、『聴くことの力』(鷲田清一)を読んで、そして「死なないでいる理由」を読んだ。本から本へバトンが渡されてゆく読書体験。確かな答えはないのだけれど、結局は大事なのは、自分で問うてゆくこと。考えてゆくこと。それ自体がきっと大事なんだろうと思った。そしてそれを、はっきりと分からなくてもいいから、自分の言葉で語ることが出来たら嬉しいなと思う。
藍色の福音 若松英輔

<本の内容>
作家と出会い、言葉と出会う 生きることの傍には、常に「言葉」があった
言葉が語らない「あわい」にこそ たしかなる人生の道標がある
「あの日、この本を机の上に置いたとき、のちに自分がこれとほとんど同じ経験をすることになるとは 思いもしなかった」 (本文より)
生涯の伴侶となる女性に『深い河』を渡した日から、妻を喪い、死者に託された「何か」を生きる今に至るまで。河合隼雄、須賀敦子、小林秀雄、柳宗悦、堀辰雄――自らの軌跡と重ねて綴る、特別な一冊。
未来に何が起こるかは、誰も知り得ない、だが、あとになってみると、あのときの出来事は、のちの日々の到来を告げ知らせていたと感じることはある。何かが予告されていたにもかかわらず、見過ごしていたことを知らされるのである。人はおそらく、幾度となく、そうしたことを繰り返す。しかし、同じ轍を踏んでいることに気がつかないこともあるだろう。だから、いつもきまって後悔する。時には悔恨とはこういうことかと、生の実感を確かめることがある。分かっていたはずなのに、何もしなかった自分を恨むのである。
第一章から第十五章〜終章へ続く、著者若松さんの物語。一言では語れないほど、すべての章が、広くて深い。そして温かい。奥様の話のところは泣けて泣けて、涙が止まらなかった。読了後、言葉にならない、簡単に語れるものではない何かを抱きしめていた。心の中で静かに抱きしめることだと思った。この本は、冬の読書には良いのかもしれないと思う。部屋に篭り、自己内省する時を。そして誰かを想う時を。
今ペラペラと読み返して『自分の生を生きるとは、誰の真似もできない現実に、足を踏み出すことに等しい。』という言葉に目が止まった。そう、私にしか見つけられない(生きられない)この道を歩んでいる、と思う。
そしていつか私にも訪れるであろう、悲しみ、哀しみ、愛しみ、の種子を、読みながらずっと温めていたように思う。
▼『聴いてもらうこと』の大切さ
私の言葉を真に受け止めてもらえる。じっと聴いてもらえる。つぎの言葉を待ってもらえる。そこに、アドバイスも、出来事の良いも悪いの評価も、あなた視点の意見も、何もいらない。ただただ、私が話している言葉を心から受け止めてくれる。その宛先として、あなたに『聴いてもらえる』『聴いてくれる人がいる』そのことが、ほんとうにほんとうに、ありがたくて、嬉しくて、心が軽くなった。救われていた。
あなたとその時を共有する、その場をまた空気を共有する。DMでメッセージで共有する。『いつも大切なお便りをありがとうございます。』『そんな大切な話をしてくれてありがとうございます。』・・・と、受け止めてもらえる、この安心感は、その人の心に、身体に、静かにそっと力を与えてくれる。わたしの一番の救いとなった。

今積んでる5冊読み切りたい。
いつもありがとうございます!
お身体を大切に、今日もお元気でいてくださいね。
