
画角とデザイン
最近新しくカメラを購入しました。
そのカメラを購入して画角の奥深さや面白さがだんだんとわかってきた気がするので、今回は画角についてのお話です。
それではここから本編です↓
画角による考え
1. 写真
一般的なアスペクト比
異なる比率の使用について

▶︎アスペクト比 一覧表
1:1 (正方形)
利用例:Instagramの投稿、正方形の写真フレーム。
特徴:正方形の比率は視覚的に均等で、コンパクトなデザインに適しています。Instagramの投稿ではこの比率が一般的で、レトロ感と新しい雰囲気があります。
4:3 (横長)
利用例:テレビ、プロジェクターの画面、一般的な写真フレーム(スマホ)。
特徴:4:3比率は横長であり、昔からテレビや写真フレームで使用されています。一般的な写真の表示に適しており、クラシックな印象があります。
16:9 (ワイドスクリーン)
利用例:テレビ、映画、YouTubeなどの動画プラットフォーム。
特徴:16:9比率はワイドスクリーンで、映画やテレビの標準的な比率です。広い視野を提供し、動画コンテンツに適しています。
3:2 (一般的な写真)
利用例:一般的な写真(カメラ)、35mmフィルムカメラの標準的な比率。
特徴:3:2比率は一般的な写真の比率で、多くの一般的なカメラで使用されます。自然な視野を捉え、写真を美しく表示します。安心感や安定感などの印象があります。
5:4 (縦長)
利用例:印刷物、一部のウェブデザイン。
特徴:5:4比率は縦長で、ポートレート写真や印刷物で使用されます。垂直のコンテンツに適しています。
9:16 (ポートレートモード)
利用例:スマートフォンのポートレートモード、縦向きのコンテンツ。
特徴:9:16比率はスマートフォンのポートレートモードに適しており、縦向きのコンテンツを表示するのに最適です。
---------------------------------------------------------------------------
1.85:1 (ワイドスクリーン映画)
利用例:映画の一般的なワイドスクリーン比率。
特徴:1.85:1比率は映画のワイドスクリーン映像の標準的な比率です。
2.35:1 (シネマスコープ)(21:9)
利用例:シネマスコープ映画の超ワイドスクリーン比率。
特徴:2.35:1比率はシネマスコープ映画の超ワイドスクリーン映像の比率で、迫力のある映像を提供します。
また、21:9もこの画角に近くdp Quattroシリーズに搭載されている比率です。

▶︎異なる比率の写真を使用する際
写真の縦横比(縦と横の寸法の比率)が異なる写真を、同じデザインプロジェクトやウェブページなどで使うことがあります。異なる比率の写真を使うことで、デザインの柔軟性や視覚的なバリエーションを得ることができます。
利点:柔軟性の向上 デザインやレイアウトに柔軟性を持たせることができます。特定の比率に拘束されず、さまざまなコンテキストで写真を活用できます。
視覚的なバリエーション 視覚的なバリエーションを生み出すことができます。単調さを防ぎ、デザインを魅力的に保つのに役立ちます。
特定のプラットフォームへの適応 異なるソーシャルメディアプラットフォームやウェブサイトに投稿する際、各プラットフォームの要件に合わせた比率の写真を使用できます。これにより、コンテンツが最適に表示されます。(Xなど…)
注意点:切り取りの検討 一部を切り取る必要が生じるかもしれません。写真の重要な要素が失われないよう、切り取り位置を慎重に検討しましょう。
コンテキストの一貫性 コンテキストやメッセージが一貫性を持つように注意が必要です。異なる写真がまとまりを持たないように見えないようにしましょう。
画質の注意 写真を異なる比率に調整する際、画質の劣化に注意が必要です。特に拡大する場合、画像がぼやけたり荒れたりしてしまうので、高解像度の写真を使用しましょう。
2. 映像
映像の構成
感情や視覚的な体験の影響

▶︎映像におけるアスペクト比
1.85:1 (ワイドスクリーン映画)
利用例:映画の一般的なワイドスクリーン比率。
特徴:1.85:1比率は映画のワイドスクリーン映像の標準的な比率です。
2.35:1 (シネマスコープ)(21:9)
利用例:シネマスコープ映画の超ワイドスクリーン比率。
特徴:2.35:1比率はシネマスコープ映画の超ワイドスクリーン映像の比率で、迫力のある映像を提供します。また、21:9もこの画角に近くdp Quattroシリーズに搭載されている比率です。

▶︎映像作品における比率の選択で、どのような効果を与えるか…
主に比率の選択では、視聴者にどのような感情を与えたいのかが重要です。たとえば、上段で取り上げたシネマスコープ画角と呼ばれる映画でよく使用される画角は、視聴者に映画的な体験を提供し、物語性や感情を強調します。しかし、身近なデバイスでは上下でクロップされてしまうことが多くその特性を活かせないこともあります。
一方、スタンダード画角は親しみやすいですが、上記のシネスコープ画角と比較した場合、視野が制限されるため画角内に収めるため、情報の整理や工夫が必要です。
その反面、現在使用されているスマートフォンの一般的な画角とマッチしており、目的によってはこちらの画角を選択する方が良い場合もあります。
このように、映像制作者は物語や表現方法に合わせて適切な比率を選択し、視聴者の感情と視覚的な体験を意図的に調整することでより高い効果を得られるかもしれません。
3. 歴史
画角比率の歴史的な変遷
今後のデザインや映像制作のトレンドとして予測される比率
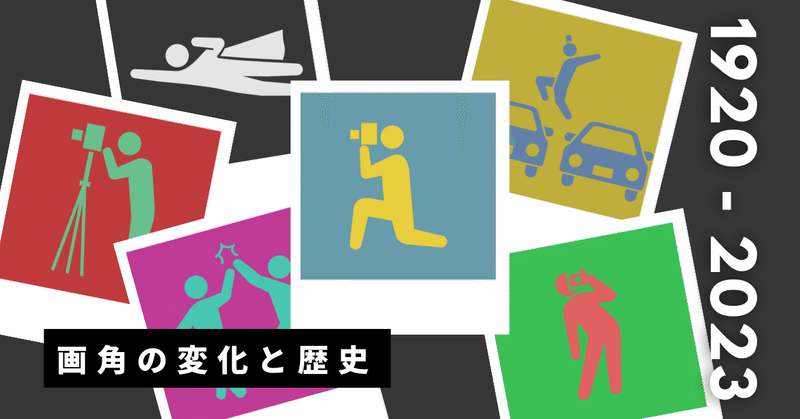
▶︎画角比率の歴史的な変遷について
▶︎映画初期から1950年代
1.33:1(4:3) - スタンダード画角(Standard Aspect Ratio)
テレビの初期もこの画角比率を採用していました。
4ユニットの横幅に対して3ユニットの縦幅を持つ画角です。
▶︎1950年代から1960年代
1.85:1 - ワイドスクリーン画角(Widescreen Aspect Ratio)
190年代ごろに、映画業界で導入された画角です。
画面がより広がり、横の幅が広がったことにより、映像が迫力のある映像体験が可能となりました。
▶︎1950年代
2.39:1 - シネマスコープ画角(CinemaScope Aspect Ratio):
1950年代にワイドスクリーンの画角が登場し、シネマスコープなどの新しい映画フォーマットが登場し、この画角比率が多く使用されました。
ワイドスクリーン画角よりも、広い画面で迫力あり没入感のある映画が観ることができるようになりました。
▶︎〜2000年代初頭
16:9 - HDTV画角(High-Definition Television Aspect Ratio):
デジタル時代に入り、ハイビジョンテレビが普及するとともに、16:9の画角比率が標準となりました。
ワイドスクリーンのテレビやモニターが一般的になりスマートフォンでも日ロック使用されていました。
▶︎2000年代初頭〜現在
2.00:1 - ウルトラワイド画角(Ultra-Wide Aspect Ratio):
近年、シネマやテレビのコンテンツにおいて、より広い画面領域を活用するために導入されています。
▶︎現在〜未来?
メタバース(仮想空間):
仮想アバターを通じて、自由に仮想世界を探索できます。
この探索は、通常の物理的な制約を受けず、360度の自由な画角を提供します。ユーザーは上下左右、あらゆる方向に視点を移動させることができるため、もう画角とは呼べないのかもしれません…

▶︎今後のデザインや映像制作のトレンドとして予測される比率
今後の映像や画角においてAIやARといったものは必要不可欠になると思います。今まで通り変わらない写真や映像がある一方、常に進化し続ける(特に映像業界)においては、アンテナを貼って情報を入手することが重要です。
拡張現実(AR)と仮想現実(VR): 拡張現実と仮想現実技術は、画角の未来に大きな影響を与えるでしょう。ARとVRは、現実の画角を拡張または完全に置き換え、新しい視覚体験を提供します。これにより、教育、エンターテイメント、デザインなどの分野で革命的な変化が期待されています。
360度の画角:360度ビデオは、視聴者に360度の画角を提供し、コンテンツに没入感をもたらします。将来、より多くのインタラクティブコンテンツが開発され、ユーザーが自分自身の視点を操作し、ストーリーに参加することができるでしょう。
ユーザーエクスペリエンスのカスタマイズ:画角のカスタマイズは、ユーザーエクスペリエンスの重要な要素となります。将来、ユーザーは自分の好みに合わせて画角を調整し、情報を効果的に取得できるようになるでしょう。
AIと画角最適化:人工知能(AI)は、画角の最適化にも活用されます。AIは、ユーザーの嗜好や行動に基づいて最適な画角を提案し、個別にカスタマイズされた視覚体験を実現します。
エンターテイメントとストーリーテリング: 映画やゲームなどのエンターテイメント産業では、より広い画角が物語の表現に新たな可能性をもたらします。将来の映画やゲームは、より没入感のある視覚体験を提供し、視聴者やプレイヤーを新しい世界に引き込むでしょう。
4. おすすめの本
構図の法則
『構図の法則』は、写真の構図について基本的な原理を説明している本です。なので、人が写真を見たときの視点や感じ方に焦点を当てています。
主役と脇役の配置についての原理や、構図を選択する際の意図が説明されているため、この記事の上位互換と言えるのではないでしょうか…?
見栄えや他の写真との差別化だけでなく、写真に意味や目的を持たせることができるようになるため、写真や映像に興味がある人だけでなく、
デザイナーなんかにもすごくおすすめできる一冊です。
終わりに
今回は「画像比率について」を今後の予想と重要性の視点で書いてみました。少し飛躍してしまったかもしれません(反省です)が…
少しでもお役に立てたら幸いです。
今後の内容や気になったことなどぜひコメント頂けますと嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
