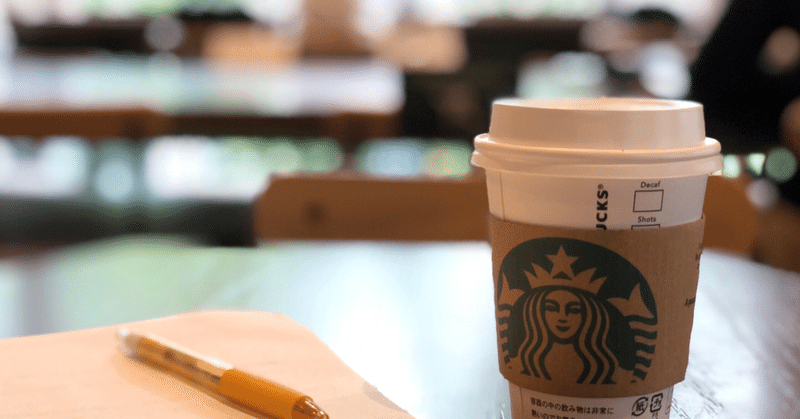
行政書士試験、司法書士試験、司法試験の勉強に行き詰ったときに読んでもらいたい話
これは、私が司法試験受験生のときに、受かる人、落ちる人を見ていて、また自分の勉強法を見直して、感じたことである。行政書士試験と司法書士試験は、実は受けたことはないのだけれども、きっと共通するところがあると思う。
はじめに結論を言ってしまうと、何度受験しても(十分勉強しているのに)落ちる人、というのは頑固である。自分自身の考えに執拗に固執する傾向があると思う。
法的判断というのは、科学的に証明された唯一無二の正解を追い求めることではない。例えば、最高裁において、DNA鑑定で血縁関係が否定された場合であっても法律上の父子関係を取り消すことはできないとする判決が言い渡されたことは比較的記憶に新しい。自分と血縁関係のない子(他の男性と自分の妻との間に生まれた子)を法律上自分の子であるとされることは、当事者にとってかなり抵抗があると思うが、法的にはそのように評価されるということである。なお、最高裁が、民法をどのように解釈してそのような判断をしたかについては、民法の条文と判決文を読んでみてほしい。
私が思うに、行政書士試験、司法書士試験、司法試験というのは、日本の法律を、他の法律実務家と同じように解釈、運用できる能力を問うているに過ぎない。あなたの頭の良さや、オリジナリティーを問うているのではない。勉強に行き詰っている人は、そのことに気が付いてほしい。
では具体的にどうすれば・・・とため息が聞こえそうなので、私が良いと思っている方法を紹介する。最高裁判決については、調査官解説を読むといい。高裁判決や地裁判決についても、法律雑誌で解説されているものがあるので、読むといい。択一問題で何度も引っかかるところやよく理解できないところは、コンメンタール(逐条解説)を読み、該当箇所だけでもいいので、基本書(有名どころであれば何でもいい)を読むことをおすすめする。できる人の真似をすればいいのだ、オリジナリティーは実務家になった後に、しかるべきところで発揮すればいい。
択一問題集の解説や、答練(模擬試験)の解答を熟読しても、イマイチ成績が上がらないときに上記を試してみてほしい。あらゆる判例や条文について完璧にこなそうとするのではなく、目についたもの、少し興味を惹かれたものについて、試してみてほしい。
おすすめをいくつか貼っておく。大学の図書館には必ずあるはずだ。佐久間先生の民法は、勉強始めの頃は全く意味が分からなかったが、次第に「すごくいいこと書いてあるな!特に小さい字のところ!」と思った基本書である(債権総論以降がないので困るのだけれど)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
