
大國魂神社を美的面から見つめる
こんばんは。今日は総集編です!
1.大国魂神社の歴史
大国魂神社は東京都の府中市にある神社です。東京であっても多くの自然に囲まれた神社です。
この神社の起源について今日は書こうと思います。この神社の主な祭神は大国魂大神です。
時は景行天皇(日本武尊の父)の治世、西暦でいうと4世紀ぐらいに、大国魂大神が「自分を祀れ、さもなくば海は荒れるだろう」と神託したことからこの神社は武蔵国(旧国名、今の東京も位置する)に建てられました。大国魂大神はこれまでの記事でも出てきたスサノオノミコトの息子です。
そして、武蔵国の国のリーダーである国造(くにのみやつこ)に任命された出雲臣天穂日命(いづものおみあめのほひのみこと)の子孫が代々大事に祀っていました。ちなみにこの天穂日命という神様は、日本神話の国譲りの場面でオオクニヌシノカミにアマテラスオオミカミへの国譲りを説得するために高天原から派遣された神の一人で、オオクニヌシノカミの人の良さに負け、オオクニヌシノカミの家来となった人です。
日本神話に出てくる有名な神様の子孫が祀りを行うということは、大国魂神社は古代からとても重要な神社であったということがわかりますね。
こうして大国魂神社は始まったのです。
そうして時がたち、大化の改新が起こります。その結果国家の組織が再編され、武蔵国の国府(今でいう市役所みたいな感じ)がこの大國魂神社付近の地に置かれることになりました。
その結果、大國魂神社は国府の斎場(お祀りを行うところ)となり、古代の天穂日命の子孫の方に代わり国司(今でいう市長)が祭祀を司ることになりました。そして、大國魂神社は武蔵国内の祭祀を総括する立場となったのです。
そしてその後の時代、武士の時代になっても、頼義義家父子,頼朝をはじめとする鎌倉幕府、徳川家康はじめとする江戸幕府が、神社で必勝祈願を行ったり、社殿改修を行ったりなど、数々の武士に崇敬されました。例えば現在の本殿は四代将軍徳川家綱によって造営されたものがもとになっています。
このように、大國魂神社は武蔵国内で、特に祭祀面でとても重要な神社であったということがわかります
2.The art of 大國魂神社

あれ、今回は社殿の写真じゃないの?と思われると思います。今回の大國魂神社の美術の主人公はこの木です。この木は何の木でしょうか?
正解はイチョウです。葉が緑色でわかりづらいですが、秋には黄色い葉が木の周りに降り積もり、広がります。そしてなんと、この大國魂神社にあるイチョウは東京都第2位の大きさのイチョウです。幹回りは9.1メートルだそうです。また写真を見ての通りしめ縄をまわしてあるので神木であるのはわかりますね。
今回はこの木の美について話すのではありません。今回の美的面の話は、「信仰の心の美」についての話です
この「信仰の心の美」というのは主に私が実際に大國魂神社に参拝した際に感じたものであります。
このイチョウの木、東京で二番目に大きいイチョウの木であると前回書きましたが、こんなに素晴らしい木で更に神木であるのに、大国魂神社のホームページには全く載ってないんです....
私はとても驚きました。こんなに立派な木であるのに、木の周りに囲いまでしてあるのに境内のマップに載っていなかったのです。
なので私はこの木について全く前もっての知識なしに参拝したのですが、この木を見つけた際に、地域のおばあちゃんが木に向かって熱心に拝まれていました。
此の時に私は「信仰の心の美」を感じたのです。
そしてこの姿に日本の信仰の美を感じました。
前回もお話しましたが、この木は大國魂神社のホームページには載っていない、地元の人ではない外部の人にとっては単なるイチョウの木なのですが、この地元においてはこの木は熱心に拝むほどの大変重要な木であったということなのです。
素晴らしいですよね。地元にしかない信仰を信じる心というとことに私は美を感じたのです。
これは日本のどの地域においてもあることだと思います。
外部の人にとってはなんでもない祭、小さな祠、木や岩が、地域の人々にとってはとても重要なものであるということは全国で見られると思います。
私は大学の授業で祭と祭礼の違いについて先生が次のようなことをおっしゃられていました。
「祭」は地域の人々のみで行われる、小規模なもの
それに対し「祭礼」は外部の人々が来訪することによって大規模に観光化したもの
日本の祭り、つまり祀りの原型は「祭」なのですが、この古くからある「祭」というものは現在だんだんと数を減らし続けています。
「信仰の心の美」を持つ「祭」というものをのちの時代にも守り継ぐためには、多くの人々がこの「信仰の心の美」をいち早く見出すことが重要ではないでしょうか
3.おまけ
ということでこの章では、実験的に様々な企画を行っております。
今回は大國魂神社につたわる七不思議というものがありまして、それがおもしろかったので取り上げようと思います!
大國魂神社にはその名の通り、境内で起きた七つの不思議な伝説があります。今日はそれを紹介していきます。
①御供田
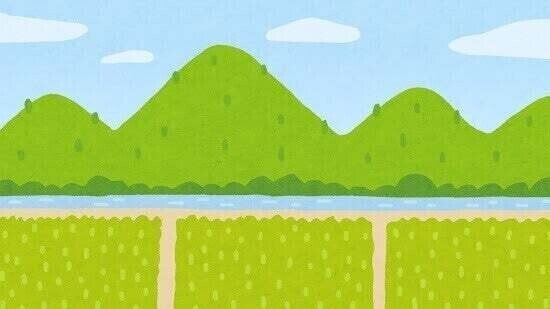
神社の所有する御供田という田んぼがあって、作物の豊穣を祈るために苗を植えたその田んぼのなかで相撲を行っていたのですが、その相撲で踏み荒らされた苗が翌日の朝になったらまっすぐに起き上がり、なおかつ踏み荒らされてばらばらになった苗がきれいに整列している…(すごい生命力!)
②樅(もみ)の雫

拝殿前にあるもみの木から、年中雫が落ちようとしているが落ちない…(毎日雫が落ちないか観察してた人がいたんでしょうか笑)
③大杉の根

参道両側にある大杉の根が、参道の地面に少しも現れてない…(確かに言われてみればそうでした)
④からす

境内に多くいる烏は、門内に入ることはなく、さらに本殿にフンをおとすことは絶対にない…(烏にも信仰心があるんですね)
⑤矢竹

拝殿前に竹があるのですが、この竹は戦勝祈願に来た源頼朝が地面に差した矢が成長してできたものだそうです。そしてこの竹の根は何年たっても石垣の外にでることがないそうです…(大杉の根の話と似ていますね)
⑥大銀杏の蜷貝(にながい)
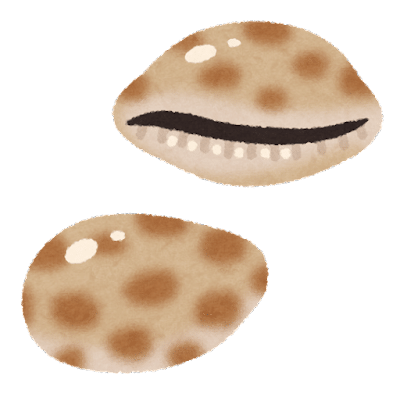
前回紹介した大銀杏の根本から出てくる貝のようなものを煎じて飲むと、産婦の乳の出がよくなるらしい…(私が大銀杏を見に行った時には貝なんかはついてなかったですね)
⑦松の木

大国魂大神が出現した際、ともに出現した八幡神にまず鎮座地を物色させたのですが、八幡神はその命令を無視して勝手に八幡山に鎮座されてしまい、物色した報告をするのが遅れてしまったため、大国魂大神が「待つはつらい」と仰られたという話から、「待つ=松はつらい」と解釈され、大国魂神社の境内には松の木が一つもなく、植えたとしてもすぐに枯れてしまうらしい。さらに社殿建築にも松は使用されず、正月には門松を建てず、竹のみを飾るという…(昔の言葉遊びは今見ると面白いと思いますが、当時の人々にとっては真面目な案件だったんですね)
というようなものです。結構面白いですよね。このような七不思議ができるということは、それだけ神社が古くから多くの人々に敬愛されてきたということがわかりますね。
ということで今回はこれでおしまいです。ここまで読んでくださり本当にありがとうございました。また明日から違う神社取り上げると思うのでよろしくお願いします!コメント等気軽に頂けると嬉しいです。
ではまた明日よろしくお願いします。
最後に私が撮影した大國魂神社の写真をあげて終わりにしたいと思います。
家の中であっても旅行気分を味わって頂けたらと思います!(狛犬の写真ブレブレですみません)

















この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
