ヤギのキモチが気になる、春の地域公開参観日|タロと3年2組の日常
※この文章は、2ヶ月程前に行われた参観日での出来事を記録しています。
2時間目「ヤギについて話し合い」
生まれたばかりの子ヤギたちの姿を見て満足したハナとともに、少し遅れて教室に到着。
教室内は、子どもたちの他に保護者や地域の方、来年度の入学希望者などであふれかえっており、教室エリアのやや外の辺りからのぞくことにした。
U字になって着席する子どもたちは、いつも通り手を挙げて順に意見を言い、それを先生が黒板に貼られた2枚の模造紙に書き留めているのだが、いつもとなんだか雰囲気がちがう。
よく見れば、何やらみんな神妙な顔つきだ。
しばらくして、「どうする?ちょっと考えてみる?」という先生の提案の後、各々が机の上のノートに向かい始めた。
周りの子と顔を合わせながら、相談している様子も見られる。
そんな子どもたちのざわつきに乗じて教室の中に移動し、黒板とモニターを見ると、
ヤギの頭を上部から大きく写し出した写真が目に入った。
そうか、ヤギの角の話か!
そういえば、タロが前日、子ヤギの角がうんちゃらと言っていたことを思い出す。
先に生まれた子(お姉ちゃん)の方が、すでに生え始めていると。
モニターには、「電気ゴテ」「苛性カリ」という何やら不穏な文字も書かれている。
なるほど。どうやら、先日生まれたばかりの子ヤギたちの角を温存するか否かについて話し合っているようだ。

母ヤギのシロ(仮名)には角がないので、なんとなく「メスは生えないのかな〜」なんて呑気に考えていたのだが、そういえば、シロは学校に連れてこられる前にすでにツノを焼かれていた、ということを先日おたよりで目にしたばかりだった。
参考:
おそらく、飼う側や自身を傷つけないためにそうされているのだろうけれど、さらっと読み流していた(ごめん、シロ🙏)「焼く」という言葉と、モニター上の「電気ゴテ」と言う言葉が、頭の中でガチャンと重なり、グググッと形を帯びた。
なるほど、先ほどチラリと聞こえた「痛そう」「キモチわるい」「なんか変」という子どもたちの声は、そういうことだったのか。
いつも授業中でも元気いっぱい話し動き回る子どもたちが、いつにも増して真剣な表情で黒板と先生を見つめているのも納得だ。
いつもなんでも話し合い。
タロのクラスでは、まだ生後数ヶ月だったシロを迎えたときも、その名前を決めるときも、小屋を建てるときも、お婿さんを迎えようと決めたときも、いつもこうした話し合いが行われている(らしい)。
まだ子ヤギだったシロをクラスに迎え、一緒に生活することになった2年生では「生活」の授業を中心に、3年生になった今は主に「総合学習」の時間が当てられているようだ。
毎回、子どもたちが手を挙げ、順々に意見を述べ、先生が書き留める。
小声で聞き取りづらい子もいるし、思ったままに発言し、意味や意図がわかりにくいこともある。
それを聴く先生は、時折「それは○○ってこと?」とみんながわかりやすいように言葉を置き換えたりしながら、基本的には子どもたちの声をひたすら書いていく。
挙手・発言しているのはいつも決まった顔ぶれ(せいぜい10人程度)なのだが、授業中または宿題としてノートやプリントに子どもたちが書き留めた答えを先生が拾い、次の授業では、紙やモニター等にまとめられた「みんなの意見」をみんなで確認しながら、意見をまとめていく。
集めて、書き出し、整理して、シェアする。
この繰り返しだ。
もちろん、整理するという過程↑で、先生の意見や視点、解釈が組み込まれることは当然起こるだろうし、
同じ意見のときには「先生もそれ思った」という同意は示されているので、「大きさ」でまさっている「声」が、子どもたちの判断に影響を全く与えないかというと、もちろんそうではないだろう。
それでも「先生(学校)が考えたこと・決めたこと」を伝え、それを「生徒が実行する」ような一方通行の構図には見えない。
話し合いの果て。
さて、今日の話し合いはと言うと、
結局、1時間の授業の中では結論までは到達できなかった。
と言うのも、はじめはヤギたちの安全のためにツノを取った方がいいと考えていた「取る派」の子どもたちが、「電気ゴテ」というキーワードを聞き、迷い始めたからだ。
賛成派(ツノを取る方がいいと思う)と反対派(取らない方がいいと思う)の意見が連なった2枚の模造紙の間に、「間」という新たなエリアが設けられ、
「こわがるかも」「痛いかもしれない」「危ないかもしれない」「人間じゃなくてヤギのキモチで決めた方がいいと思う」などの意見が並んだ。
授業時間、残り10分弱。
先生「どうする?どうやったら決められるかな?」
生徒「動画で実際に焼いているところを見てみたい。メエメエ泣いてるか」先生「ああ、泣いているかどうかを見ることで、ヤギの意見を知りたいってこと?」
生徒「そう」
先生「ちょっと調べてみる?どうやって調べようか?」
生徒「本」「タブレット」「育てた経験のある他の先生に聞いてみたい」「獣医さんとか」
先生「よし、じゃあちょっと(次の授業で)調べてみようか。」
授業が終わり、タロをつかまえ意見を聞いてみたところ、「迷ってるー」とのこと。
さぁ、どうなる子ヤギの角。
定期的にお世話に行く(希望者の当番制)たびに、ハナが頭突きされる様子を毎度目にしている母としては、角が残っているとちょっと怖いのだが。
ヤギの幸せを願うみんなの気持ちには、一票。
ちなみに子ヤギたち。名はまだない。
ツノの行方と子ヤギたちの名前については、また後日。
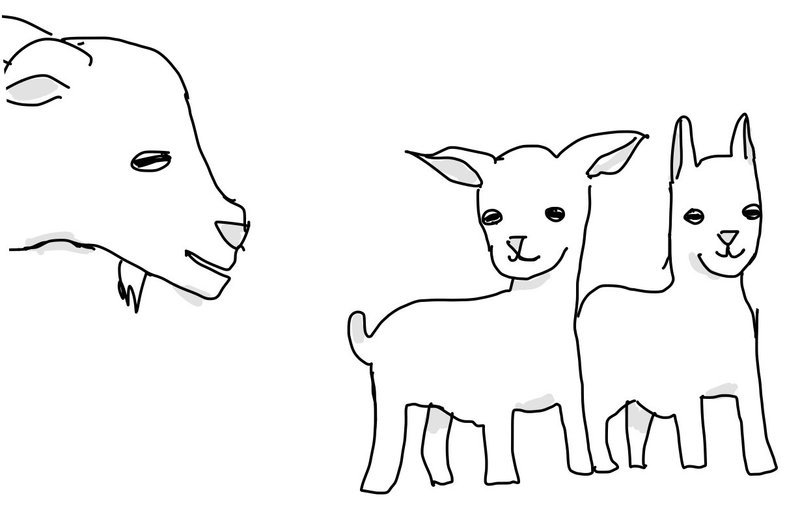
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
