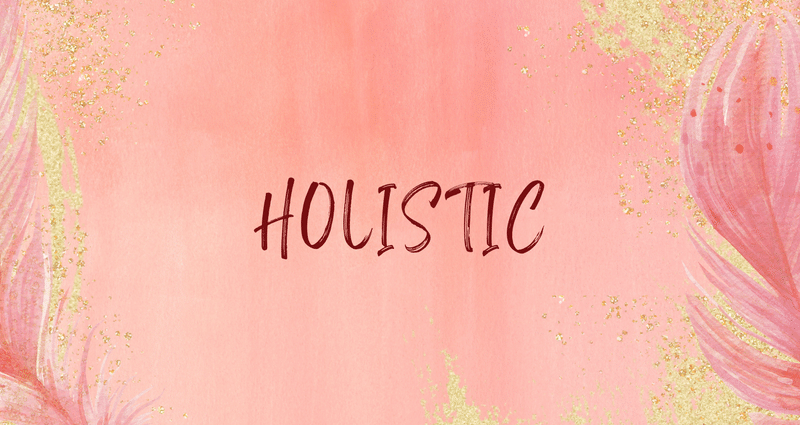2020年5月の記事一覧
脳内物質のセロトニン
「しあわせホルモン」って
聞いたことある?
このしあわせホルモンとは
脳内物質のセロトニンのことである。
セロトニンの役割は
集中力の維持や
自律神経のバランス調整
内臓機能への影響などである。
脳に対しては
興奮しすぎず
ぼーっとすすぎず
最適な覚醒状態を作る役割をはたす。
セロトニンが増えると
精神状態が安定するため
しあわせホルモンと呼ばれるそう。
セロトニンが足りなくなる
こころが震えること
このステイホームで
素敵な動画を見つけた
まさに
こころが震える
それはときめきであり
いのちのエネルギーに
つながる。
一生懸命で
楽しそうな姿と
グルーヴ感。
子供のときにか
歌えない歌があるし
大人になって
今だから歌える歌がある。
だから
今っていつでも尊い。
旅立った患者さんからの手紙
がんの切除術して
化学療法してがんばってきたけど
もうこれ以上の西洋医学の治療はしたくないと
うちの病院を訪ねてきた患者さん。
代替療法してて
毎日外出しては
銭湯にいってきたり
美味しいご飯食べてきたり。
まだ若いからって
主治医が
西洋医学の治療をすすめても
本人の意思で
副作用の続く治療は望まなかった
1ヶ月ほど病院で
過ごし退院。
その後、
自宅で過ごして亡くなったと
奥様か
病院受診のときのポイント
病院にかかるとき
何も準備していかないと
「3時間待ち、5分診察」
と言われるような
ドタバタな診察時間に
医師の言ってることもよくわからず
じぶんの言いたいことも言えず
ただ薬をもらって帰ってくるなんて
病院受診になりかねない。
だから、
聞きたいことや
医師にのぞむことを
具体的に数値的に
聞けるように
準備することが大切なのだ。
医師とのホリスティックな
コミュニケーションの
病気を癒す主体は患者さん
わたしは
ホリスティックを
意識する看護師だけど
ホリスティックな医療においては
病気を癒す主体は患者さんにある。
患者さん自身が
自分の病気について考えたり
何かいい治療法はないかと探したり
医師や治療者と
「どの治療法を取り入れる」
「この治療は行いたくない」など
コミュニケーションを
重ねながらホリスティックな癒しを
オーダーメイドでつくっていくのが理想である
実際の現場は
その人の生きる姿勢を 側で見守るっていうのは難しいことだなあと。
患者さんのニーズが
ただただ「生きる」ことだった
親がいるのに
まだ死ねない
子供は成人したけど
まだ心配だし
旦那とも
まだこれから
一緒に過ごしていきたい。
わたしが死ぬわけには
いかない。
まだまだ生きたい。
40代のがん患者さん。
苦しくて苦しくて…
でも
「治す、そして生きる」
という目標に向かって
化学療法したあと
ワクチン注射したり
サプリメント飲んだ
いのちを養う7日目(補薬物)
日々の暮らしの中での健康法を
大切にするのが「養生」の考え方である。
中国医学の養生の秘訣として以下の7つがある
1、勤運動(運動に勤しむ)
2、練気功(気功を練習する)
3、節飲食(飲食を節制する)
4、暢情志(心をのびやかにする)
5、慎起居(起居を慎む:丁寧に暮らす)
6、適環境(環境に合わせて暮らす)
7、補薬物(薬物で補う)
これから具体的方法について
毎日ひとつずつアクショ