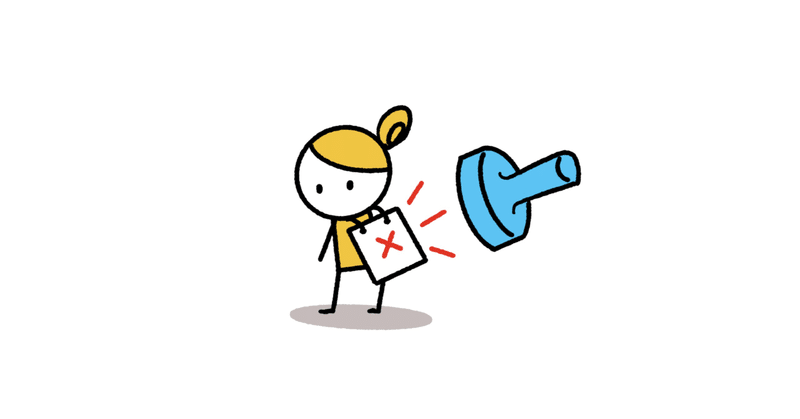
「精神病」の具合の悪さ
精神病というやつは、病気で状態が悪い上に、精神病である事実とも立ち会わなければならないので具合が悪い
いつだろう、この文章に出会ったのは。
ただ一つ確かなのは、私が「精神病」になってからであるということだ。
・・・・・・
数年のあいだ人生を共にしてきた「死にたい」「消えたい」という気持ち。
あるとき人にそれを勘付かれ、その気持ちは普通ではないと言われてその場で病院の予約を取らされた。
気持ちが追いつかないまま、1週間後には診察室で精神疾患だと宣告されていた。
私が人生を共にしてきた、当たり前のようにそこにあった感覚が、一気に「精神病」の症状になってしまった瞬間だった。
幸いにも、後に主治医となるその人は、混乱している私に無理やり薬を出そうとはしなかった。
その代わりに、その場で次の診察の約束をすることになった。
病院帰りの電車から、私は必死に宣告された病気のことを調べ始めた。
再発防止のために薬を飲み続けなければいけないらしい。
下手したら、一生。
この病気のある人の体験談もたくさん出てきた。
「一度どん底の体験をしたけれど、今はこういうサポートを受けて自分らしく生きています!」。
当時齢18だった私には、一生薬を飲み続けることも、どん底を体験することも、サポートを受けなければ生活できないくらいになってしまう可能性があることも、全てが恐怖でしかなかった。
実は身体の病気でもこういう症状が出るらしい、薬を飲まなくても生活習慣をただせば治るらしい……。
人は絶望の淵に叩き落とされたとき、こうして現実から目を背け、自分に都合の良いものを盲信して縋っていくのだろう。
私は、「薬を飲まなくてもよく寝てよく運動して食習慣を改善すれば治るだろう」という結論に至った。
この日の日記には、
「薬を飲まないでも大丈夫かもしれないという一縷の望みを自分から否定するのが怖い」
と書いてあった。
私は、精神病であるという事実に立ち会うには、あまりに幼かった。
・・・・・・
結局、私は数回の診察で説得されて、薬物療法を開始することになった。
過去について医師にいろいろ聞かれる中で、「病気で状態が悪い」時期があったと認めざるを得なくなった。
一番最初に死のうとしたのは中学生の時。
高校生の時には、保健室登校予備軍くらいになっていた。
保健室のベッドの上で数時間泣き続けた時もあった。
養護教諭が心配するのも当然である。
初めて「入院」「休学」という単語を提示されたのもその時期だった。
でもそれを拒む私と、保健室通いのことすら知らない私の親を前にして、実際にその時自殺未遂をしたわけではない私を入院させる力は養護教諭にはなかった。
ただ、今回の相手は医師である。
普段は元気に活動している優等生が数時間泣き続けた上で「死にたい」と言い出した状況で、あぁそうですかで済ますほど医師免許の重みは小さくないはずだった。
下手したら次こそ本当に入院になる。
私の「精神病」を知っているのは、私と、私の主治医だけ。
入院なんかになって親に「精神病」がバレるのは最悪のシナリオだった。
だったら、大人しく医師の言うことを聞いておくというのにも一理あった。
・・・・・・
なんだかんだ、あれから、行ったり来たりを繰り返しながら通院と服薬を続けている。
全てが順調だったわけではない。
1錠から始めた薬は、説得に説得を重ねられ、1錠、また1錠と、当初医師が処方したかったであろう正常な量に追いついていった。
調子が悪くて一応納得の上で追加された薬を家に帰ったら結局飲めなかった時も、自暴自棄になって一切薬を飲まなくなった時も、主治医は怒らなかった。
どうしたら良いかを一生懸命考えてくれた。
そして今は、私の病気を理解してくれる友人も数人出来た。
そのうち何人かは、同じ病気を持ちながらも、私の先を懸命に生きている尊敬する人だ。
主治医以外にも、私を支援してくれる人や機関が増えた。
「精神病」になった時の私が見たらどう思うだろうか。
今の私は毎日薬を飲み、たくさんの人に支えながら生きている。
なんとかして薬物療法を開始すべく私を説得しにかかっていた主治医が
「ずっと飲み続けなきゃいけないって言ってるけど、薬飲んで落ち着いたとして、その時のひなたさんはやめたいと思うかな?」
と言ったことの意味が、分かりはじめた気がする。
・・・・・・
私はようやく、「精神病である事実と立ち会う」ことができるようになった。
私は、自分の病気を、年月をかけてある程度受け入れた。
それでも、現実社会では数人にしか打ち明けていない。
精神疾患を理由に、腫物扱いされたことがある。
精神疾患を理由に、あしらわれて追い返されたことがある。
普通に生活していても、精神疾患のある人に対する差別や偏見があちこちで見られる。
私に「精神障害者がまた事件起こしたらしいよ、物騒だね〜」と言ってくる人は、私が精神障害者であることを知らない。
私は、精神病のある人が立ち会わなければならない「精神病である事実」は、社会があたかも事実かのように作り上げた呪縛であると思っている。
死にたい気持ちがある「普通の人」だった私は、精神科の診察室の椅子で医師の一言を以て「精神病のある人」になった。
「精神病のある人」である私は、ほとんどの時間を過ごしている社会では「精神障害者が事件を起こす世の中の物騒さ」に共感を求める相手にふさわしい「普通の人」なのである。
「病気で状態が悪い」というのは、ある程度仕方がない部分である。
「辛いよね、死んでもいいよ!」という受容・共感的な社会に変わったとして、死にたくて動けない辛さは、解決しない。
それでも、「精神病である事実とも立ち会わなければならない」具合の悪さは、社会が変わらなければならないと思う。
絲山秋子の小説の一節が、“時代遅れ”になる日を待ち望んでいる。
よろしければサポートお願いします
