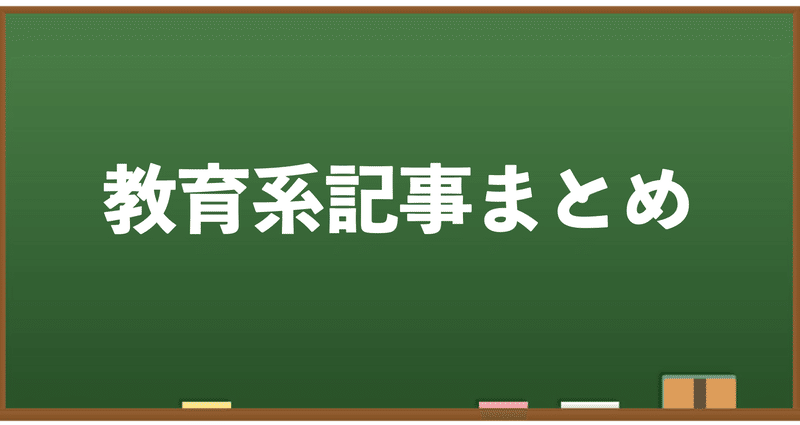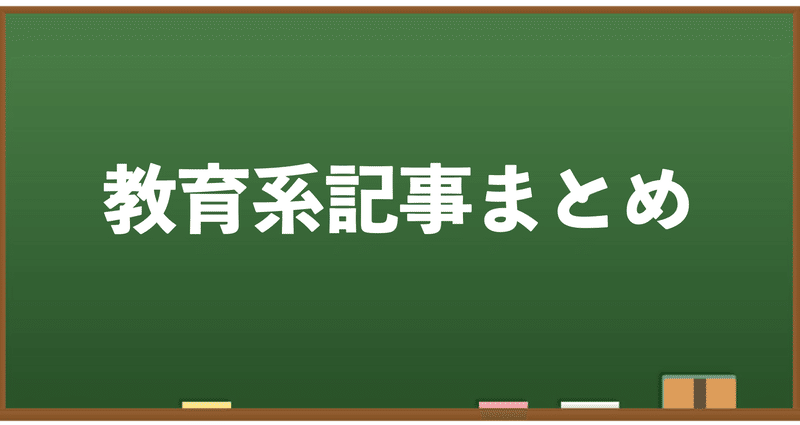「そんな校則おかしいだろ」と思う大人の人に、"今の社会"を変えていくことも、ともに引き受けてほしい。
※この記事はあくまで個人としての考えを綴ったものであり、所属団体を代表するものではありませんので、あらかじめご了承ください。※
都立学校が、地毛を黒髪に染めさせることやツーブロック禁止などの校則について、4月から全廃されるそうです。こちらのニュースを見て、少し、モヤモヤとしていました。
まず、大前提として、私は下着の色をチェックするとか、地毛が明るい色なのを黒髪に染めさせるとか、人権侵害に他ならない、「マジでありえん」と思っています。ツーブロック禁止も、ポニーテール禁止も