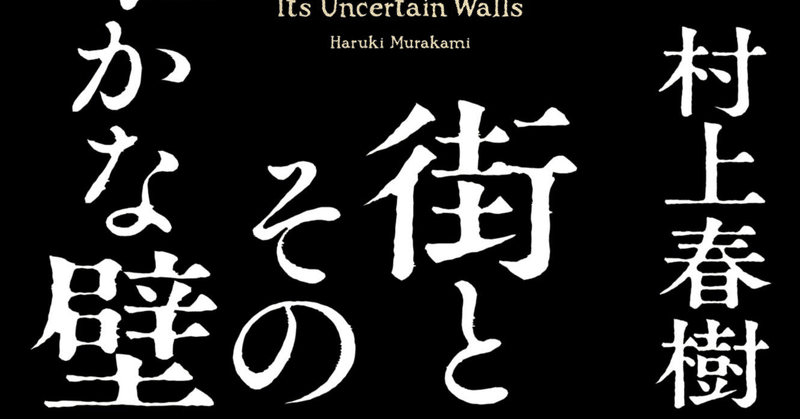
「街とその不確かな壁」村上春樹。個人的な共通点。

500点にも及ぶ絵画教室の展覧会が終わり、自分へのご褒美で本屋に走りました。そう、村上春樹の新作です。これ以上のご褒美はないかもしれません。
今、2巡目を読んでいますが、まず初読の感想をここに記していきたいと思っています。
(以後、ネタバレを含む)
ーーー
まずは、読後の率直な感想から。
モネの晩年の睡蓮のようだ。
これだけでは、ネタバレにもならないでしょう笑。
いろんな方が語っているように(そして繊細な書評はプロに任せるとして)、村上ワールドの集大成とも言える、登場人物や展開のてんこ盛り。まってました!と思うのか、またか、、と思うのかは読み手次第でしょうね。
先日読んだ「天路の旅人」沢木耕太郎と同じく、600ページを超える長編で、それぞれノンフィクションとファンタジー?という両極端の世界観ではありながも、世界に名だたる作家二人が、30-40年の歳月をかけて書き起こしたという、自身の半生をもう一度見つめ直すような二作。
どれほどの苦労があったことかと想像すると、私も表現家の端くれとして、命を尽くし、全人生を賭けたこの二作に出会えて、心からよかったと思えるのです。大きな祝福と、受容された心地よさ。先人の築き上げた道を歩んでいける有難さ。
1.総評
さて、今回の新作は、「救済と祈り」の集大成とも言えるような気がしました。静かに語られる「僕」と「ぼく」の物語は、お互いを「信じて」、奈落の底の暗い暗い壁の向こうへと落ちていき、突然終わります。しかしその先は描かれずとも、それまでの出会うべくして出会った一つ一つの破片が答えを示していました。
心の一部が焼き切って修復不可能、もう決して後戻りはできないことを知りながらも、壁を超え、再び少女と出会う。そして決別し、「自分自身」へと還っていく。すべて自分が作り出したものだから、自身で幕を閉じる。それを村上春樹は、生涯を通して、同じ登場人物と、同じ儀式と、同じ場所で紡いでいく。
高橋一生の言葉を借りるなら、「何度も何度も同じところを叩きながら・・」。まるでねじまき鳥のように。それがなんともいえないカタルシスを生み出すのでしょうね。
2.個人的な共通点
この新作を読みながら、ぞっとしたことがいくつかありました。「へぇ、そうなんだー」って笑われるくらいのことかもしれませんが、個人的には重大な話です。(そのように、それぞれの読者にも重大な発見があることが村上春樹作品の魅力でしょう。なぜなら村上春樹は実に個人的なことしか描いてないから。その暗く深い精神の地下世界は、すべての読者の個人的な水脈と繋がっています。)
【その1】
私は物語に登場する「僕」と同じ年齢ということ。彼は45歳で、いきなり穴に落ちて、壁の街へと移動します。これ、結構怖いことです・・。44歳でも、46歳でもなく、彼は45歳なんです。
【その2】
「僕」が面接を受ける図書館は、福島県会津市からローカル線で1時間くらいの場所。まさに私はこの本を、福島県会津市から1時間くらいの場所(正確には猪苗代湖)で読んでいたのです。怖すぎます。マジで。怖いよ。
【その3】
これが一番ゾッとしました。図書館の元館長の「子易さん」の人生。当時彼が45歳のとき(!)息子さんがいました。これが5歳。私の息子と同じで、まさに福島県で今目の前にいます。
子易さん家族のその後を読み進めたら、思わず背後に気配を感じて何度も振り返ったとしても、おかしくないですよね・・。道路には気をつけろ!。
【その4】
物語は、「ぼく」が壁の中の図書館にて「夢読み」の職についています。
ちょうど私も今年に入って、あるカウンセラーの助言を経て、夢日記を繊細に記録していたところでした。夢は、あの世と繋がっていて、人間は寝ている間にあの世に還っていき、大切なことを見聞きするようです。
ほとんどの夢は日常に起こった出来事の情報処理であり、そもそもが夢を覚えていない方も多いようですが、どうしても忘れられない鮮明な夢を見た時には、それこそがあの世であり、無意識(仏教でいうところの八識・阿頼耶識)に繋がってるのです。
3.夢の話
私は、日々育児に追われて、朝から息子や娘の世話で翻弄されながらも、カウンセラーの忠告通りに、できるだけ繊細に夢を記録し続けました。それはまるで、「夢読み」の記憶が掴みどころなく断片でしかすぎないとしても、それを読み解き、浄化し解き放つことが、世界を保つために必要なことであるように。(・・ように、が増えることはご了承ください笑)
私は毎日夢を見ます。それは絵に描く以上に繊細で、鮮明で(何かの意味)を含んでいます。言葉にできない、色彩にできないものであればあるほど、自分が画家であり、詩人から名前を受けた以上は、取り組まねばならない大切なことの1つだと感じています。
夢にまつわる話は、noteでもカテゴリーにしています。(※1)
そうして、この本を手に取る前に見た、自身の夢のワンシーンが、この本に出てくる壁の街の美しい景色と酷使していたのです。
真っ白の雪が降りしきる、鏡のように美しい沼。そこに「ぼく」と少女はたどり着く・・。私がみた夢は、雪のような桜吹雪であり、隣にいたのは老人ではありましたが・・(※2)。
「あれ、この風景知ってるな」と思える感覚は、誰しも体験してることだと思います。夢で見たのか、かつて幼少時代、はたまた前世の記憶なのか。どうしたってこの半生では知りようのない未体験のことでも「知っている!」という感覚。
例えば、初めて会った人にも感じることはありますよね。
村上春樹は自身の深い地下に危険を伴いながら潜っていき、それを美しい物語にしていく力があります。何度も何度も同じ設定で描くのは、ピアニストが、偉人たちが残した譜面を何度も演奏しながら深めていくことに近いかもしれません。
ここまでくると「何を弾くか」ではなく「誰が弾くか」ということになるのでしょうね。かつての偉人は、同じ魂の情景をみて、それぞれ与えられな肉体と心を使って表現していく。その情景をより繊細に描くためには、分離と統合を繰り返しながら、意識を超え、次元を超えて、何度も何度も作り上げて行く必要があるのでしょう。
その途方もない過程を俯瞰で見てしまったら、さっさと諦めてしまうでょうね。しかし秘密は少しずつしか明かされない。「何者か」によって。だから私たちは旅を続けられるのです。
「なんと無意味な」と門番は笑うかもしれません。完璧なルールのもと生きていれば何も問題はないのに。興味本位で見てはいけない女性の側面を見ることもない。形を変えながら、決して出ることはできない壁を、どうやって脱出し、影を取り戻すことが出来るのでしょうか。
一人一人、意識しようがしなかろうが、子易さんにせよ、単角獣にせよ、イエローサブマリンの少年にせよ、その家族にせよ、夢なのか現実なのか曖昧な、まるで「モネの晩年の睡蓮」のような世界を漂いながら、「僕」は「ぼく」となり「私」となり、一体となっていく。
そうして、真実が明らかになっていくのが人生なのかもしれません。あなただけの真実であり、すべての人々の真実が。
4.まずは私の真実を
まずは私の真実を。今日という一日、このnoteを通してしっかりと感じていきたいと思います。私の周りは、家族がいて、絵を描いて、人に出会い、別れる。繰り返し、繰り返し、全く新しく。それはとても大切な愛おしいものではないでしょうか。
そうして、またキャンバスに向かい絵を描いていく。「生と死の世界」を。ずっと小さい頃から変わらない世界。私の父も、そのまた父も、そのまた父も、死を弔う職業を通して、大いなる犠牲を伴い、苦悩しながら生きてきました。
私の父親は20年間も行方知れずで、まさに「神隠し」にあいました。それが、巫女的な存在である従兄姉の協力を経て、見つけ出すことが出来たのです。
父は、不確かな壁など存在しない、隙間風が通るボロボロの肋小屋に住んでいました。私は父と再会し、父の中にある「私の影」を見つけたのでした。父は、子易さんと同じ75歳で他界しました。
その後すぐに長男を授かったのも、偶然とは言い切れません。今度は私が受け渡す番なのでしょう。
5.信じること
ちょうど先日終了した絵画教室の展覧会でも、生徒さんたちに大部分のものを伝え続けてきました。根気よく、表現の自立を促しながら、信じて託していく。それはとても大変な作業でしたが、自分の絵を描くこと以上に尊いことだと感じていました。そうして開催された展覧会は、かつてないほど眩しく、あたたかく、あの場に飾られた数々の命が浄化された空間になりました。
そしてまた、新たな苦しみと悲しみの場所へと出向き、『カタチと色』を与えるために再び旅していくのだと思いました。
本書では「信じること」が強く語られています。これは、以前のnoteに描いた、息子から教わった絵本のお話(※3)についても述べました。本当に信じる。これは何よりも強い力になるのでしょう。祝福を受けて、人生の一歩を踏み出せるような気がします。
さて、3500文字も超えたあたりで、今日はこのへんで。繊細に関しては、また後日。
(おしまい)
ーーーー
(※1)夢の話カテゴリー
(※2)白い世界の夢
(※3)息子の絵本について
よろしければサポートお願いいいたします。こちらのサポートは、画家としての活動や創作の源として活用させていただきます。応援よろしくお願い致します。
