
- 運営しているクリエイター
#AozoraBunko
中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説
中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] 5月22日-1965年 [昭和40年] 5月3日) 小説家・詩人・随筆家。
🔍 青空文庫 中勘助の作品
🔍 青空文庫 和辻哲郎「古寺巡礼」(1946年改訂版 [初版は1919年])
七章、二十一章に出てくる、奈良帝室博物館 (現・奈良国立博物館) にほぼ毎朝行き、東大寺に宿泊し、當麻寺の塔の風鐸をどう思います、と聞くN君が
堀辰雄 ほり・たつお (1904年 [明治37年] - 1953年 [昭和28年]) の誕生日 (12月28日) 小説家
堀辰雄 ほり・たつお (1904年 [明治37年] 12月28日 - 1953年 [昭和28年] 5月28日) 小説家。
🔍 青空文庫 随筆「大和路・信濃路」堀辰雄 1941年執筆, 1943年-1944年初出
🔍 青空文庫 小説「曠野」(あらの) 堀辰雄 1941年初出
📝 上貼の「大和路・信濃路」で述べている1941年10月の奈良滞在の結果書かれた短編小説。
物
古事記が完成 712年3月9日 (和銅5年1月28日)
古事記が完成 712年3月9日 (和銅5年1月28日)
⚪️ 「古事記」 のリンク 🔍 青空文庫 「古事記」現代語訳 武田祐吉訳
🔍 上同 読み下し 武田祐吉註釈校訂
🔍 国立国会図書館デジタルコレクション 「古事記」 原文 [漢文] (柏悦堂 明治3年出版)
奈良関連読書記録 Reading History
📝 奈良がテーマとなる資料は「古事記」「日本書
薬師寺の金銅仏に感じる若干の不思議
「長屋王の変」に関する同日の記事
から関連したかたちで書いています。
🔸 以前から不思議に感じること
この薬師寺東院堂の「聖観音」 (銅造。国宝) と様式的・技法的に類似しているとされる
同じ薬師寺の金堂の本尊 (つまり薬師寺全体の本尊)「薬師三尊像」 (銅造。国宝) は、
「聖観音像」の鋳造技術や表現技法の更なる発展形、
「天平前期」(奈良時代前期) のモニュメントと見られることが一般
森鷗外 (1862年-1922年)の誕生日 (2月17日) 小説家
森鷗外 もり・おうがい (1862年2月17日 [文久2年1月19日]-1922年 [大正11年] 7月9日)小説家・著述家・軍医・官僚。
1917年 [大正6年] から東京、奈良、京都の帝室 [現・国立] 博物館の総長に就任し、
1918年から1921年までの4年間毎年秋に正倉院開封に立ち会うために1ヶ月ほど奈良に滞在したそうです。
(この期間、1918年に「古寺巡礼」の和辻哲郎が奈良を訪
高浜虚子 (1874年-1959年) の誕生日 (2月22日) 俳人・小説家
高浜虚子 たかはま・きょし (1874年 [明治7年] 2月22日-1959年 [昭和34年] 4月8日)俳人・小説家。
🔍 青空文庫 高浜虚子「斑鳩物語」
奈良の宿に関して、高浜虚子は「奈良ホテル」と題する「写生文」も書いています。
1916年 (大正5年) 國民新聞の記者としての宿泊時の、高級かつ最新式の設備に瞠目した状況を率直に記し、同年に国民新聞に9回に渡って掲載されました。
和辻哲郎 (1889年-1960年) の誕生日 (3月1日) 倫理学者・著述家
和辻哲郎 (わつじ・てつろう 1889年3月1日 - 1960年12月26日) 倫理学者・著述家
代表作「倫理学」「風土」「古寺巡礼」(こじじゅんれい)
🔍 青空文庫 和辻哲郎「古寺巡礼」1946年改訂版 (初版は1919年)
📝 1979年に岩波文庫にもなり広く読まれているバージョンは、この改訂版です。
私は文庫化される以前に「古寺巡礼」( なんと読むのかも分からず「ふるでらじ
正岡子規が 「根岸短歌会」 を創設 (1899年3月14日)
正岡子規 まさおか・しき (1867年10月14日 [慶応3年9月17日]-1902年[明治35年 9月19日])俳人・歌人。
正岡子規は、技巧に走らない万葉集の素朴な「ますらおぶり」を踏襲した写実的短歌の制作を提唱。
前年の1898年(明治31年)に門人の高浜虚子、河東碧梧桐 (かわひがし・へきごどう) ら俳人を東京根岸の自宅に集めて歌会を開いていますが、
おおよそ源流とみなされているのは
亀井勝一郎 かめい・かついちろう (1907年 - 1966年) の誕生日 (2月6日) 文芸評論家
亀井勝一郎 かめい・かついちろう (1907年 [明治40年] 2月6日 - 1966年 [昭和41年] 11月14日) 文芸評論家
やはりメディアでも「大和古寺風物誌」が代表作となっていますね。
新潮文庫版を購入してよく読んでました。
その口絵写真を撮った入江泰吉が、影響を受けた本として同書を挙げています。
🔍 青空文庫 亀井勝一郎作品集
🔍 青空文庫 大和古寺風物誌
「古事記」編者太安万侶の墓が発見される (1979年1月20日) / 津田左右吉の史料批判史学 / 一般的な史料批判の起こりは聖書学
「古事記」編者太安万侶の墓が発見される (1979年1月20日) 。
奈良市郊外の茶畑から太安万侶の墓誌が出土。 🍁
津田左右吉の史料批判史学
「古事記」「日本書紀」などにある「神話」に「史料批判」の手法を導入した
古代史家の津田左右吉の「神代史の研究法」(1919年)「建国の事情と万世一系の思想」(1946年) 等を読みました。
🔍 青空文庫にも収録されています。特に「神代史の研究法」
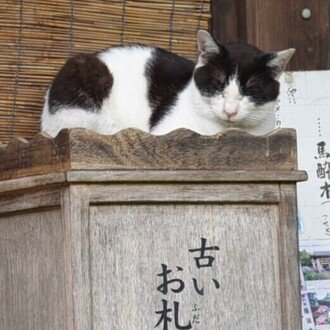

![中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/41799545/rectangle_large_type_2_4556d0cef7fff55eaf8a225b9e86f7e4.jpg?width=800)
![堀辰雄 ほり・たつお (1904年 [明治37年] - 1953年 [昭和28年]) の誕生日 (12月28日) 小説家](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/42143291/rectangle_large_type_2_cf5433e1b995c49a1df221e835a7d12b.jpg?width=800)







