
前触れ(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 18)
※画像では、「ルビつき縦書き文」をお読み頂けます。
前触れ
烏帽子親を務めた信長は、若い忠興の姿を満足そうに眺める。
「うむ、よき若武者ぶりよ。これからも励むがよい」
嬉しさに忠興の頬は真っ赤になっている。
信長としてはまだ前髪姿が名残惜しい。だが早く一人前となって働きたいとはやる心もまた可愛い。
小姓として側においてみれば信忠の言う通り、物を見る手腕には目を見張る才がある。花入れの置き方、反物の選別、調度品の始末。目が早いので取次も的確だ。武芸教養一般は、親が得意中の得意のことであるし、将としての心得、大名となるべき先を見据えての治世の面では、光秀の仕込みもよいようだ。
そもそも信長はこの年齢の生意気ざかりの少年が大好きなのだ。少年から大人に変わってゆく過程において、彼らは不思議な輝きを放っていた。
藤孝はさすがに万感込み上げたとみえ、信長に劣らぬ笑顔で息子を迎える。
「まあまあ、何とかおまえもそれなりに立派にはなりおった」
心の底からほっとしたような顔をして、はじめて父親らしい顔を見せた。忠興は不思議な心地がする。
「もうわしは与一郎の呼び名は返上じゃ」
◇
明智も関わっており、顔の広い藤孝のこととあって、次々に入れ代わり立ち代わり元服の祝いを述べていく諸将の顔ぶれは豪華だった。秀吉も現れた。小さい体でひょこひょこと、相変わらず精力的に駆け回っている。忙しい秀吉は顔を見せただけですぐに去り、藤孝は秀吉側近の黒田官兵衛と話し込んだ。
官兵衛とは気を使う必要がない。こちらが明智の内情を話すのと同時に、あちらは秀吉の周囲について語ってくれていた。自然と、人質として安土で生活をしている官兵衛の息子、松寿丸の話題になる。今年十歳の齢だった。
元気で過ごされているようで何よりだと挨拶すると、こんな返事が返ってきた。
「上様のお膝元とはいえ、ご子息のようなわけにはとてもとても」
藤孝は苦笑した。
父子の確執をたねに謙遜するにも限度があるし、明敏な官兵衛にそんな小手先技を披露してもしかたがない。
人質として集められた子息たちは、蒲生のような例もあるとみて一定の期待はするものだが、信長は松寿丸をちらっと見ただけで根暗そうな坊主だと特に気に入りもしなかった。
「謙信が亡くなったというのはどうやら本当でござるな」
「いかにも!春日山は大騒ぎになっておるようだ。なのに畿内がこの始末」
「かような際にあの竹中半兵衛どのが亡くなられたとか。秀吉どのもいま苦しいときであろうな」
「三木の城があの始末、上様は救援の願いを聞き届けられなんだ。上月城の尼子は助かるまい」
それはつい去年まで共に戦っていた山中鹿之助の死を意味している。立派な武人であり、光秀からも秀吉からも認められていた武将の悲劇の予感は二人の口調を重くした。
信玄に続き謙信も亡くなった。龍虎並び立つ両雄がどちらも消えてくれたのだ。
いよいよ織田の優勢が見えつつあるのに、畿内も内実はがたがたで、毛利の脅威は増している。四方を囲まれているというのに、信長の側近としての地位の争いはいよいよ熾烈になっていた。皆が先を争って安土へ押し寄せ、茶器を求め、阿諛追従を競うさまは見苦しいほどだ。そんなことをしとる場合ではないというのに!
藤孝は、得意満面で諸将に応対している忠興をちらっと見た。
このような権力闘争や思惑から藤孝が距離を取っていられるのは、おのれの得意とする武芸文芸のすべてと明智十兵衛との絆、そして最大の恩恵はこの忠興がいるからだった。
何がどう気に入られたのかわからないが、謁見すれば長々と熊千代の話をさせられ、あやつは信忠なぞにやらずにわしの小姓にすればよかったな、しまったことをしたと笑いながら言われて、藤孝はうまく返事ができず変な笑いかたになってしまった。挙げ句の果てに本当に小姓にされてしまい、本人は意気揚々と安土のど真ん中を闊歩している。
藤孝としても、これほどあからさまに気に入られた息子が嫡男であるというのが、ひそかにどれほど心強いか知れない。ときに誇らしく思うこともある。そのたびに心を鬼にして突き放す態度を取った。親が子を自慢すればばかにされ、妬みの種を撒くだけだ。今のところはそれがうまく働いている。いつまでもつのかは、誰にもわからない。
「七兵衛どの!」
忠興が喜色満面で立ち上がり、津田信澄が入ってきて少し周囲が緊張するのを感じた。我に返った藤孝が官兵衛と頭を下げると、信澄は鷹揚にうなずき、まっすぐに忠興の方に向かった。
磯野を放逐しての家督相続はまだ記憶に新しい。若くともすっかり威厳に満ちていて、岳父の明智の前でも臆する様子はなかった。
「いやはや、さすがですな」
苦笑ぎみの官兵衛の呟きが妙に藤孝の心に残った。
(津田坊どのか)
万見仙千代、堀久太郎、長谷川秀一、奉行をつとめ諸将に信長の意を伝え、取次をこなすのはみな小姓あがりの若手ばかり。それが百戦錬磨の将を顎でつかいよる。
あれが各地から集まった諸将の反感をかうひとつの原因ともなっておるのだと、藤孝はそう考えている。
特に長谷川秀一のような嵩に懸かって上から命令する態度が評判が悪いのは知っていたので、藤孝は父親の話を聞こうときくまいとこれだけはと、忠興に口をすっぱくして礼儀について注意していた。
とにかく信長にとっては、他人にはわからない本人の気まぐれによるお気に入りだというのが非常に重要であり、逆に一旦そのお気に入りから外れてしまえば、 もう日の目を見ることは叶わないだろうと思わせてしまうほどに態度にも待遇にも差があった。
信長本人はまったく気づいておらず、自分はみなにあれこれと気を配っていると思っているようだが、明らかに違う。
藤孝は、それなりに文のやりとりもこなし、洛中や朝廷の情報を流す一端を請け負って信頼を得ているとはいえ、十兵衛と並んだ時の明らかな差を感じずにはいられなかったので、諸将の抱いている不安がよくわかった。
癇性の信長と無事に会見をすませ、ほっとした所で贔屓の者が場に現れたとする。もう、ぐるりと体の向きを変え、存在も忘れたかのように二度と見向きもしない。屈辱に満ち面目を失った顔で苦痛を堪えながら下がっていく、あれは誰の顔だ?そうだ、荒木だ!
荒木村重が随分いらいらしている。感情を隠すことができない彼のこと、日の目を見ることがかないそうもない、先細りの絶望といらだちが体全体に満ちている。
ひそかな疑いが胸の奥の奥に兆した。
専横を極めてある地域の一大勢力ならば、たいした人物だと思っていたかもしれぬ。だが、まだその根っこはお山の大将から脱しきれておらないのではないか。
身内びいきで天下の主は勤まらぬ。各地の士豪をどうおさえ、扱うか、これから自分たちがどうなるか、日ノ本の誰もが息をつめて見守っておる。誰もが危惧している。そんな真っ只中でおきた北畠、磯野の事件だ。
いやな空気が広がりつつある。
◇
晴れて元服を終え、与一郎忠興となった熊千代は、信澄とともに、荒木の城に顔を出しに行くこととなった。三姉妹の夫である義兄弟が一堂に会してそろうことになる。
移動しながらの馬上で、信澄は忠興に言った。
「摂津の民、荒木の城の気配をよく見ておいてくれ。お前の意見が聞きたい」
若い忠興はきょとんとしたが、黙ってうなずいた。荒木の城は長岡の勝竜寺城から南へ下った位置にある。
村重の側室の千世保が訪れていて二人を迎えた。子を宿しており、腹を抱えている。
今楊貴妃と呼ばれるほどの上半身はなよやかな美人が、下腹部を膨らませて重そうにしている様子を、いつもとは違う目でしげしげと眺めてしまった。
信澄は村次とさっそく世間話を始めている。
「日向守どのは、側室をふたり入れられるそうな」
「ふたり!いきなりか」
「だれも煕子どのの代わりにはなれぬのだから、後添いのようになるのを避けるためは二人選んだとのの噂だ」
「それは、何ともよい言い訳だ!」
村次は笑ったが、忠興には笑えない。
亡くなった正妻と光秀の、いかにも仲良く寄り添う姿を見ていたからだ。明智の家の奥は、細川家の奥とはまるで違うし、父が表向き側室を持たない理由も明智とは違っていた。
いつか、家督を継ぐときが来る。そのときは、おれは明智の家のように皆がキッチリと折り目正しくいられるようにしよう。あの騒々しい騒ぎはたくさんだ。奥は珠子がもっとも好きなように、珠子が一番美しく、一番敬われるように設えよう。
うっとりと妄想している所に、ゆっくりと裾を引きずる音がきこえる。村次が立ち上がって、いたわるように手を添えた。
村次の妻、明智の長女のお岸が入ってきた。
「お初にお目にかかりまする」
忠興は挨拶をしながら、まざまざと珠子、そしてお聡を思い出していた。
ひどくやつれて顔色も悪く痩せているが、やはり美しい。線が細くたおやかだ。珠子の肉親であることがはっきりと意識された。
お岸の侍女たちも合流し、場はにわかに華やかになった。
一人が笑いを隠して村次に陽気に語りかける。
「若殿!その若いお方を我らにもご紹介下さいませ」
「与一郎どのも七兵衛さまもそろって素敵な殿御じゃなあ」
「噂通りでございますね」
「誰から噂を聞いたのだ?」
「さて誰であろうかの?」
お岸に寄り添いながら、知らん顔をして衣装のすそを整えている侍女を見て、忠興はどきっとした。つとめてなに食わぬ顔をしながらそっと伺う。目があってにっこり微笑まれ、思わず下を向いてしまった。
名は何だったか。忘れかけていた白状さを恥じた。確か、お藤と申したか。
◇
信澄の手引きで、忠興は婚儀指南役というその女性と二人きりにしてもらい、丁重に礼をした。
「世話になる。よく教えてくれ。頼む」
膝をそろえて真面目に頭を下げる。
「婚儀で絶対に失敗したくない。絶対にだ」
「大丈夫でございますよ。あまりお気張りなさるな」
腹を抱えるというほどではなかったが、心底おもしろそうに笑う。
「あのですね、おなごとて、はじめてなのですから、失敗も何もわからぬものなのですよ」
この女は、ちょっと語尾を伸ばすように発音した。
「若君は今のお気持ちを忘れずに、お好きな姫様におやさしゅう接してあげてくださいませ」
にこやかに言う女は、内心恐れていたような、宴席で垣間見る色気が匂いたち、しなだれかかって女を見せるようなことはなかった。こちらもきちっと膝に手を置いて武家の娘らしく、なおにこにこしている。
明るいな。
熊千代はほっとした。
容貌も悪くない。忠興よりは年上だがまだ若い。信澄と村次、兄貴分ふたりの配慮に感謝した。
「そのようにお相手をたいせつに思うお気持ちさえあれば、たとえ何があろうとも二人で乗り越えていけまする、さてまずは!婚礼でお二人になってからの流れを、口頭にてご説明申し上げますよ」
健康で丈夫、世話好きだが弁えている。
忠興は別れ際は師匠に対するようにきちんと座して深々と礼をした。
「誠にご苦労であった。礼を申す」
頬が赤くなって仕草がしどけなく、妙に心に残った。
◇
「与一郎どの」
村次の奥方から放たれた声に忠興は我に返った。病の床にあるとあっても、まったく弱々しさを感じない。村次があんな風に妻に傅いているのも合点がいく。
「お聞きしたいことがありまする」
「何なりと」
「結婚とはそもそも家と家とのつながりなれど、うまくゆかぬこともありまする。何かあったならば、そなたはどうなされる。たまがそなたの意に添わなんだら。子供ができなんだら?」
お岸はたたみかけた。
「たとゆれば病気に、それも重い病になって、奥方のお役目が果たせぬようになったならば、どうされる?側室をお持ちになるか?離縁されるか」
「奥……」
村次が困ったようになだめようとする仕草を見せる。だが、お岸は忠興の顔を鋭く、穴があくほど見つめていた。
「母上はもうおらぬ。わたくしはおたまの母代わりとして聞いておりまする」
そんなことをこの場で聞かれても、大切に致しますとしか答えようはあるまい。誰もがそう思う中で、忠興は珠子を思う気持ちを疑われていると匂わされただけでカッとなった。父以外の誰かから、この結婚についてあからさまな憂慮を示されたのははじめてだ。お聡はガミガミと小言を言うことはあっても、心配であって反対という感じはなかった。お岸の顔にはありありと反感の色がある。
忠興は、返答に困ることなど何もない。うまく宥めろよという村次の目配せなど気づきもせずに、まるで雄鳩のようにそっくり返ると胸を張って大威張りで答えた。
「そんなの、考えるまでもござらぬ!何があろうともわが妻は珠子どのただひとり。わたくしにとって、珠子どの以上の女子などこの天下に、来世にも宿世もございませぬ。病どころか命さえなかろうとも、わが命が尽きるまで変わりませぬ」
まだ祝言もあげていない相手にこの言い様、さすがの兄貴分ふたりも、場の侍女たちもあっけにとられて口を開け、忠興の顔を見ていた。
「だから申し上げましたでしょう。そんなにご心配なされずとも」
お藤が笑いを含んで、いたわるようにお岸の背中をさすった。張っていた気が急に憑き物がおちたようにがっくりとして、お岸は顔を歪めて泣きそうな顔になった。
「たまは、そなたに託さねばならぬのね」
千世保も寄り添い、ほとんど年の変わらない若い奥方の肩を抱く。
「妹御のことは大丈夫。な、あなた様はあなた様で早う元気になられて、ご自分の御子をもうけなされ」
お岸の顔がふいっと暗くなる。
「殿方などしかたなき者にて、子をいとおしむ心にこそ、おなごの真の喜びがありまする」
愛しげに腹を撫でる千世保に嫌味など微塵もなく、思いやり深く心からお岸を思いやっている様子が見て取れた。お岸の顔はいよいよ苦しくなる。
◇
信澄が行き際にささやいたことを忘れかけていた忠興も、帰り際には違和感を強く感じた。
なんと殺気に満ちた城下の雰囲気であろう。七兵衛どのはよく平気な顔で出入りできるものだ。
安土を離れれば、最近とみに感じる、織田家への不満なのか?
むらむらっと反感が湧いてきて、生意気な目つきをする奴の一人や二人、切り捨ててくれようと肩に力を入れた瞬間、信澄の手が触れた。
「毛利の手が延びておるのよ。摂津は交易で船がさかんだ」
空気が違う。以前来た時よりもはっきりと感じた。
城でも、ああして喜んで迎えてくれた女房衆の奥に、顔をしかめてこそこそ話をしている一派がいた。刀鍛冶がフル稼働なのも、荒くれ者の姿が多いのもいつものことだが、こちらを睨む眼が明らかに増えている。
「これは、何事か起きる前触れだ。荒木は、城下も城内も引き締めねばならぬ、それがお役目だ。だが……」
信澄の表情は険しい。
「荒木の親父の様子がおかしい。村次は苦しい立場に追い込まれているようだ」
毛利を迎え撃つべき摂津の荒木が腰砕けになっているとすれば問題だ。
「村次は良い奴だが、良い奴というだけでは家中を率いることはできぬ。場合によっては荒木の親父を捕縛し、奴が家中の実権を掌握すべきだ」
忠興は目を光らせて聴いていたが、ふと村次の顔を思い浮かべた。立派な茶人ではあるが、気のいい、押しの弱い彼にそのようなことはとても無理だと思った。
「できまいな」
忠興の内心が聞こえたかのように信澄は呟く。
「ここで見たこと、意見を率直に叔父上に申し上げる。それがこの七兵衛のお役目だ」
それからため息をついて彼には珍しく愚痴っぽく漏らした。
「いい顔をしすぎるのだ。おなごにもだらしない」
◇
都の方へ近づくにつれ、二人ともやっと緊張が抜けてきた。信澄はしみじみと言う。
「女子とは、まこと不思議な生き物よな。どれひとりとても同じとは思われぬ」
どうやら、病をおしてまで出てきて、妹のために忠興に食って掛かった三姉妹の長姉であるお岸のことを考えているらしかった。
忠興は自然と、そのお岸の横にいたお藤のことを思い出した。あの明るくおおらかな年上の娘の体臭がまだ肌の上にまとわりつき、残っていて、心にもその香りとともに存在を残している。戦によってもたらされた真っ赤に燃える血の世界がわずかに散漫になり、気持ちがすっきりして落ち着くのを感じた。
女人というものはは服の下にかような秘密を隠しているのだな。
「七兵衛どの、とても、とても」
「うむ?」
「おかげで合点がいった」
「そうか」
七兵衛が真面目でいてくれるのが有り難かった。こんなとき、顔見知りの小姓たちは囃し立ててあっという間に噂になる。
「あれは肝の太い、世話ずきで包容力のあるおなごだと村次が申していた。村次のおてかけであったらしいが室には入れられず、かというてご内室が嫌ったわけでもないらしく、ずっとああしてお岸どのの近習でいたようだ。奥の女たちの思惑はよくわからん。まあ、室がしっかりとしめておれば大丈夫だ」
このような話になったついでだと、忠興は今まで聞けなかったことを聞いてみることにした。
「あのな、七兵衛どのな」
「うん?」
「七兵衛どのはな、そのう、衆道したことはあるのか?」
信澄は慌てず騒がず、いたって普通に答えた。
「そうだなあ、あるな」
あるのか!?
「おれは、不如意ゆえ。どうにもそっちは……」
「ふーん。別に無理せんでもよいのではないか。付け文(告白)されたわけでもないのだろ」
「あれがそのう、たしなみだと言われているではないか。でもどうにもおれはなじめなくて……」
「おまえとおれがそうだと思っておる奴もいたぞ」
ええっ!?
「おまえはなついてきて可愛かったなあ」
「いやあ……」
「叔父上がおまえを可愛がるのもそうだという奴もいたな」
「ええええっ!?」
「でもなあ、おまえはなあ。何かちがうな」
「違うのか?」
「あれもな、好みがある。結局は、おなごの好みと同じよ。おなごは無理で男でないとだめ、おなごはすべて嫌じゃというやつもおるぞ」
「子が出来ぬではないか」
「養子をもらえばよいだろう。なりたい奴らなどそこらじゅうにおるわ」
こともなげに言う。それから声をひそめた。
「ここだけの、話だがな、おなごどうしというのもあるらしいぞ!」
「えええええええっ!?」
「まあ、色恋の形はいろいろよ」
豪快に笑う。からっとしていて、本当に気持ちがいいと忠興は思う。
一門の中でも皆が一目置き、頼りにされるのは七兵衛どのがこんなだからだ。血統の濃さよりも、過去のわだかまりよりも、行動と実力だ。
それから忠興の心は別の方向へとさまよった。
珠子はこのような世界とはまったく違う別の次元にいる。
ただ、珠子が妻になるということは、漠然と考えていたように部屋を祭壇として中に御神体のように収めておき、いつでも 好きな時に開いてみたりふれたりすることができる、ひそかに所持する茶器や書、そっと取っておいている不思議な形の石などとは違っていた。
明智の家と細川の家、親も子も、兄弟も郎党も、すべてを含めたふたりが近付いて手を取り合う。それは所有するしないではなくて、お互いを差し出し開け渡す。衣服はとけ、血や肉もとけ、からだの内部に食い込んでわかちがたい運命となる。
そうなってよい、あの子に何もかも明け渡してもかまわない。どうしても、そうなりたい、と忠興は考えた。
第十八話 終わり
次回のお話 第十九話「篝火」
画像(加筆あり・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。





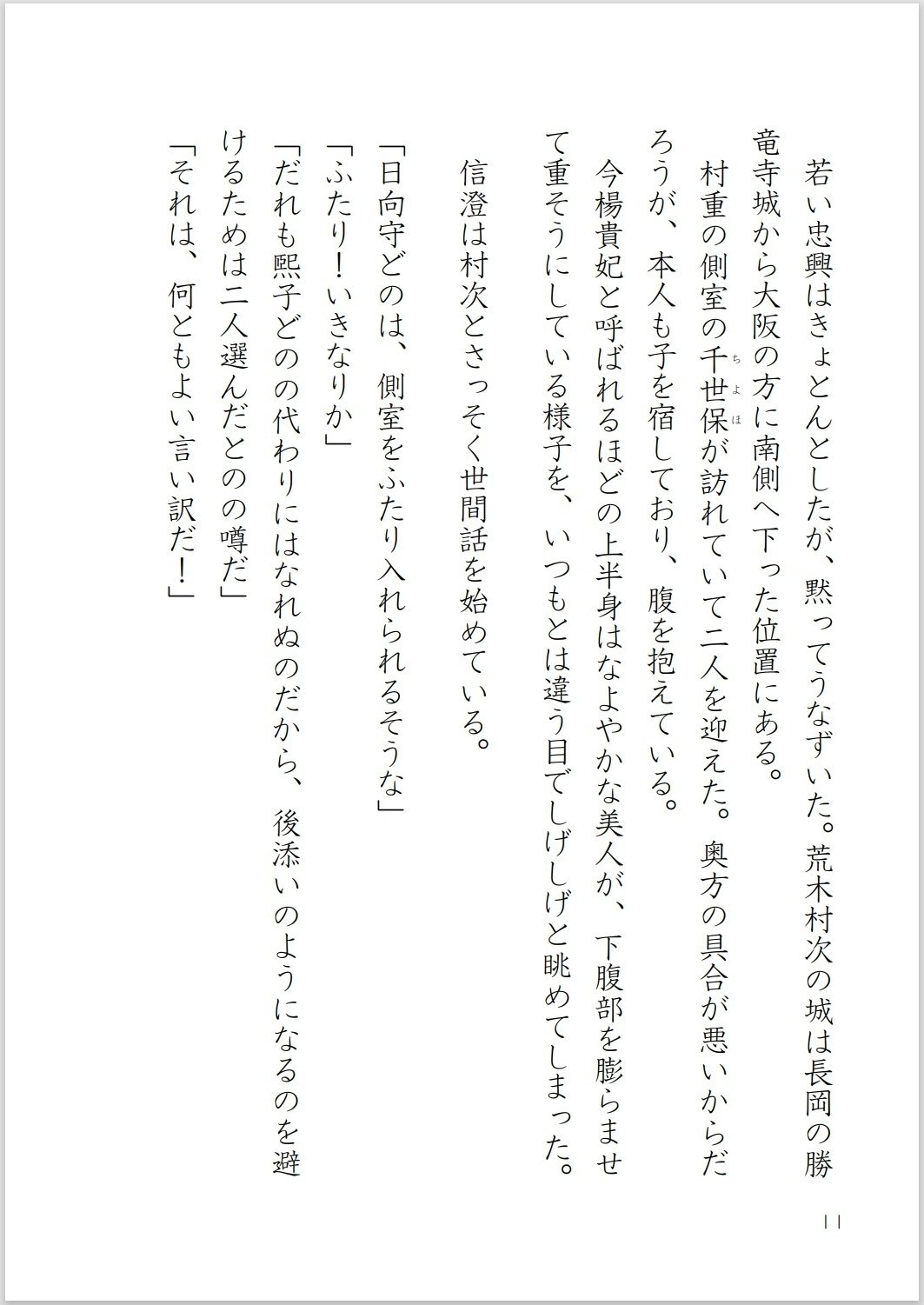




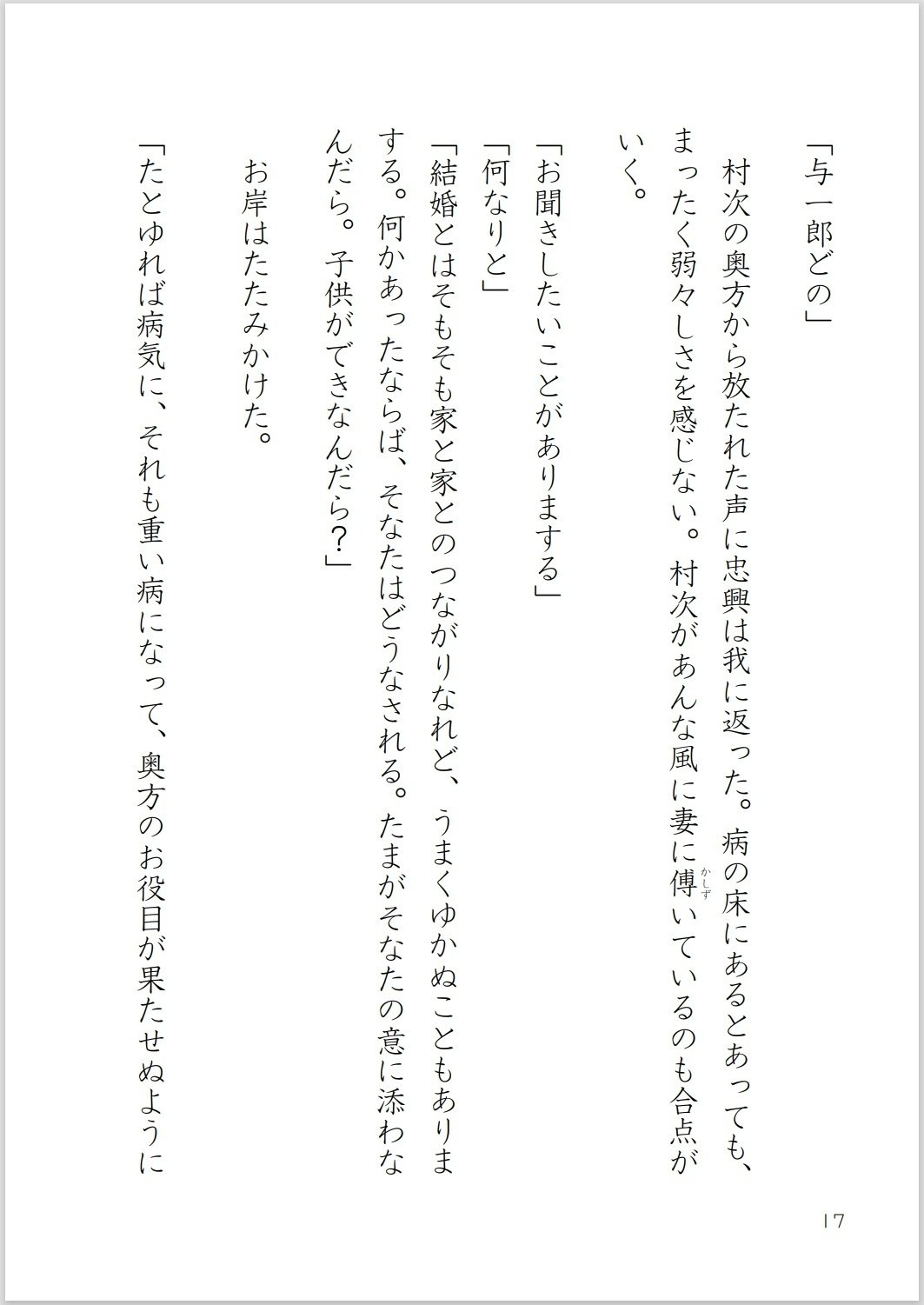

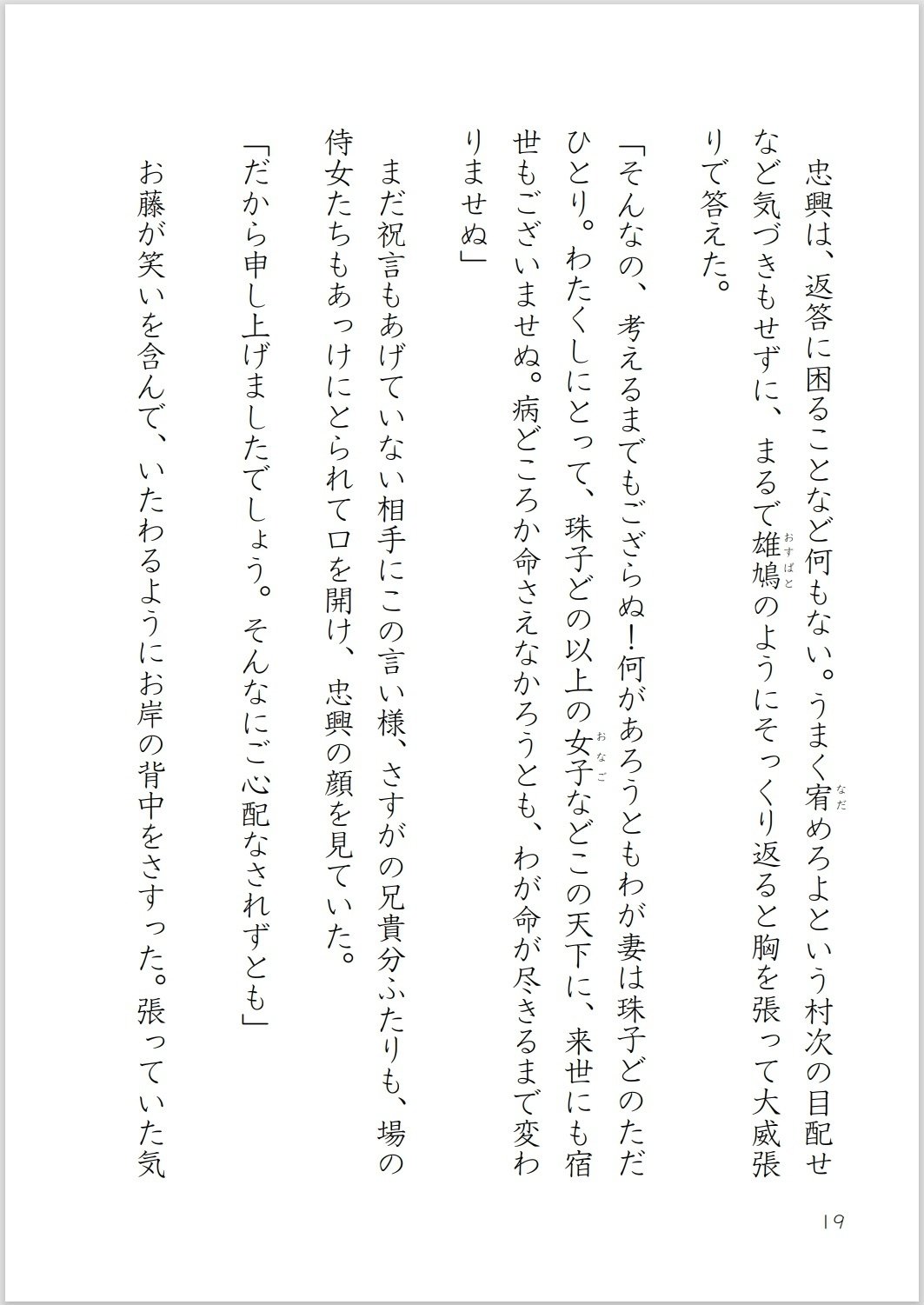
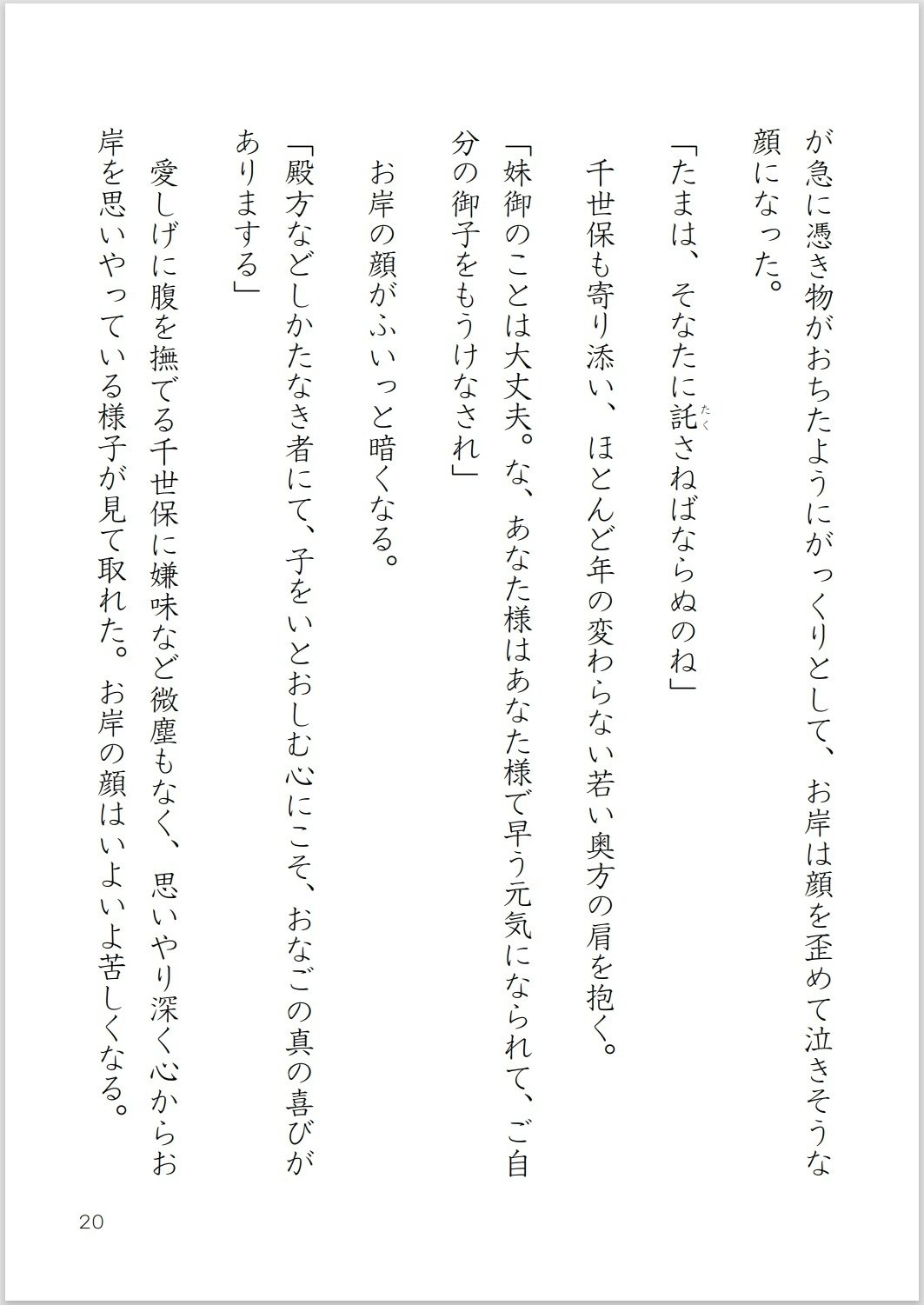


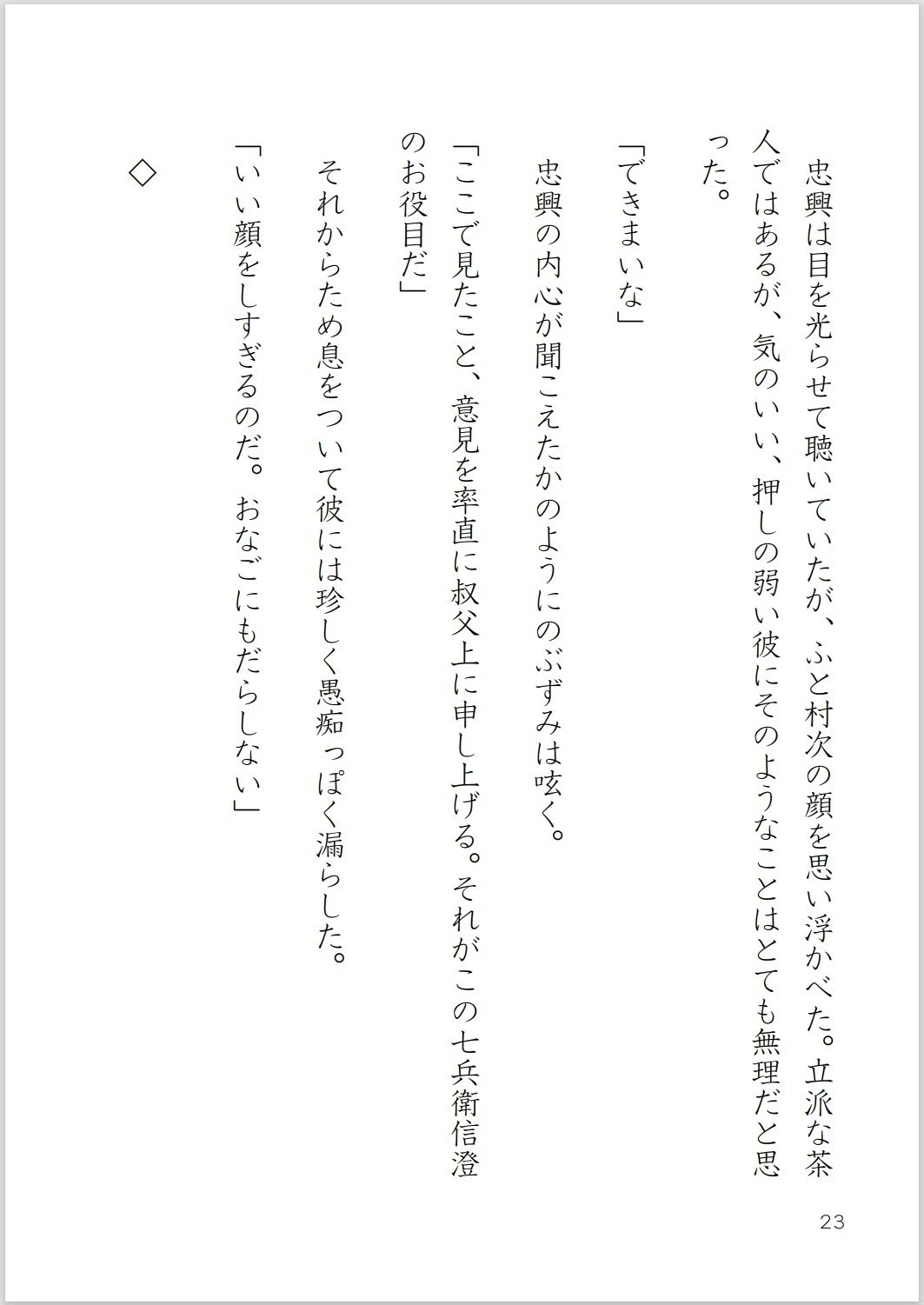



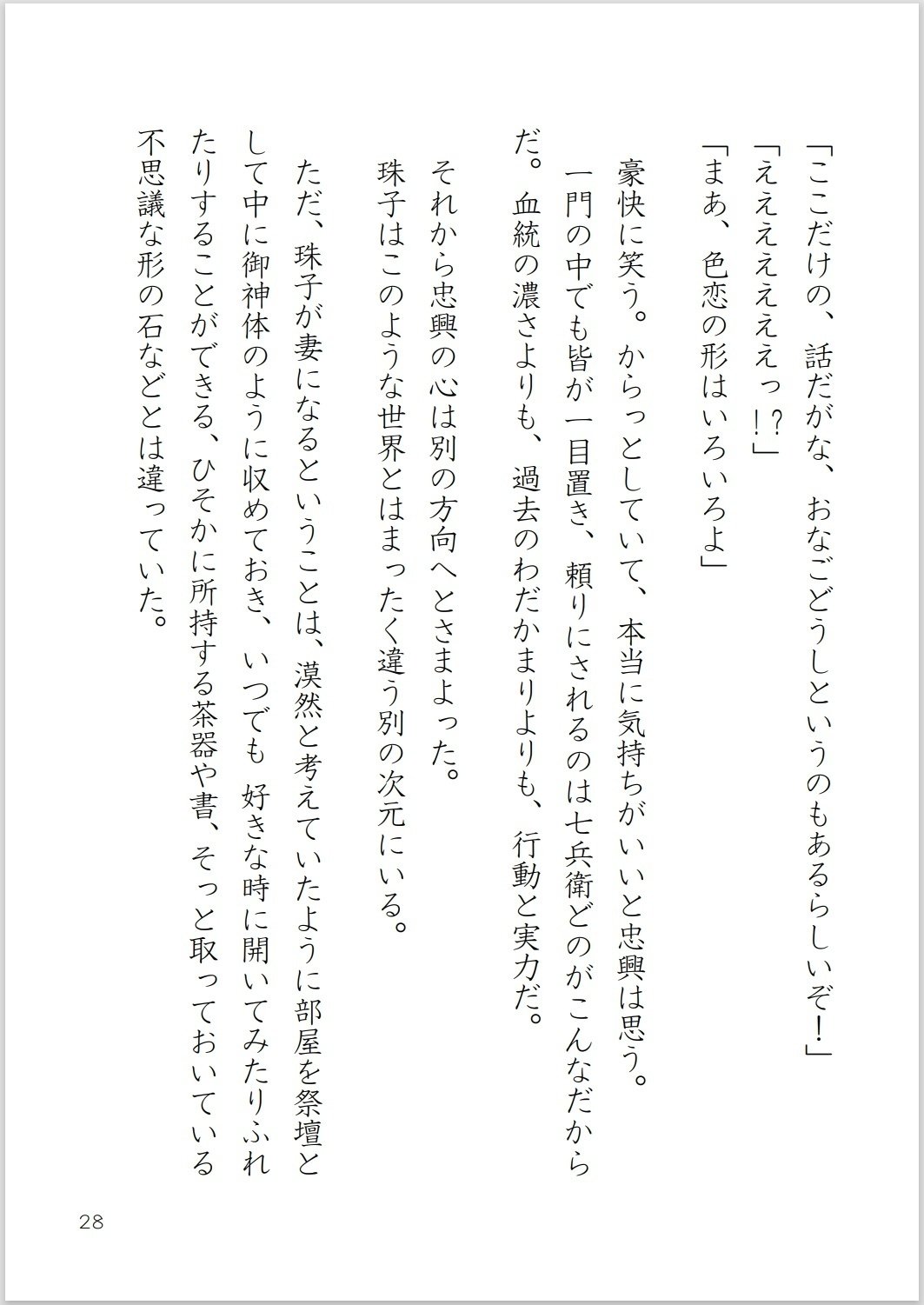


画像。本型。見開き版。





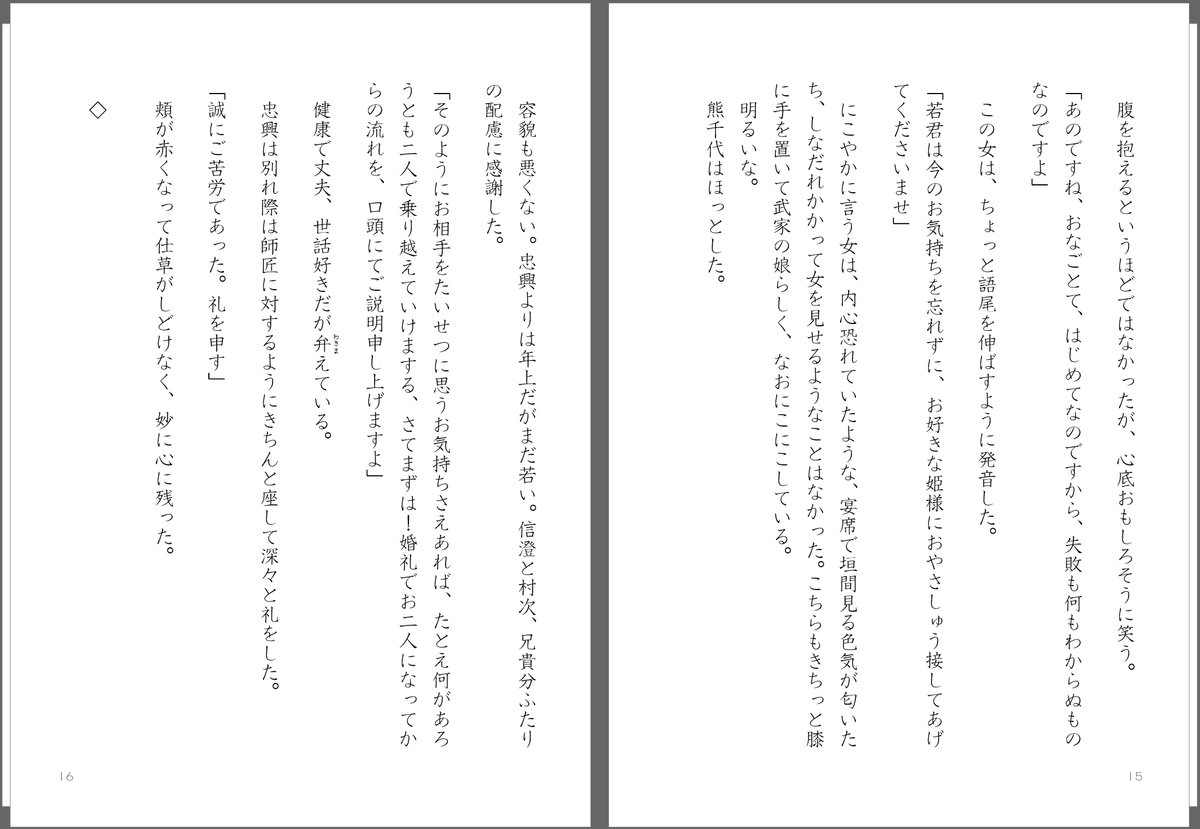






次回のお話 第十九話「篝火」
児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
