
陣の中の茶室(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 16)
※画像では、「ルビつき縦書き文」をお読み頂けます。
陣の中の茶室
翌年の天正五年(1577)二月、熊千代は念願の初陣を果たした。光秀とともに軍を率いて紀州征伐に向かう。明智が手痛い一撃をくらった雑賀衆が相手、奮起してよい所を見せたいのであろうと周囲は噂した。
信長におぼえがめでたいのは、明智の後ろ盾と後押しがあってのことだと思われているし、珠子との結婚も、信長にせがんでの明智への擦り寄りと見なされる。周囲の気配が気持ちを逆撫でして、熊千代は歯噛みをした。負けない!おれは負けない!負けるものか!
体格も良くなり、すっかり若者らしさがついてきた。元服は近い。みるみる大人になっていく心と体をもて余しながら、ピリピリとした空気を漂わせる細川の嫡子の前で、許嫁の話題を出すのは禁句と皆、心得ていた。
彼にも薄々わかりはじめている。個人の感情とは別次元の所で、結婚は家と家をよじれた綱のように結び合わせる。やがて綱が細い方が太い方に編み込まれていくのだった。
周囲の状況は目まぐるしく変わっていた。信長は信忠に岐阜城と織田家の家督を譲り、安土城がついに着工の運びとなって丹羽長秀が総奉行に任ぜられる。ほぼ時期を同じくして、信雄が養子として入った北畠の一族が粛清されていた。
◇
「あの貝塚の城に雑賀衆が籠っておる」
伯父の細川好重が、指をさして教えた。
二月十三日に京を出て、十五日には、松永久秀が守る天王寺砦から大坂を海沿いにさらに南へ下る。一揆とはいえ、雑賀衆は鉄砲の扱いに長けた一大勢力の地侍であり、天王寺の戦いの際に織田軍を苦しめた主力部隊でもある。
熊千代は藤孝の厳命で、逃がさないようにしっかり四隅を抑えられていた。
「こやつは何をするかわからん。突進していいきなり死なれては物笑いの種になる」
それでいながら、そばに置くと喧嘩になるのは目に見えているので、藤孝は自分の弟、好重におもりを頼んだ。孔雀の羽根を頭から突っ立つように生やしたかぶとと、鎧にうずもれたまま、くぐもった顔でじっとしていたが、眼球が右に、左にと走っている。
「雑賀衆は、銃をよく使う。変な動きをしては、狙い撃ちにされるぞ。よいな」
叔父の懇切丁寧な教えに、馬鹿にされているのかと熊千代はいよいよ腹を立てた。
「まずは雰囲気に慣れねば、ここからは連戦になるゆえ、いきなり力を使い果た……」
落ち着きのないこやつにしては、冷静でいる様子、なかなか結構なことだ、と好重が思った瞬間、もう熊千代は横にはいなかった。
「うおおおおおおお」
「あっ!若!若ー!」
いきなり物凄い勢いで突進する熊千代の背後で若い米田是政の仰天した叫びがつんざいて、後ろからガシャンと音がするほど殴られている。
「居場所を知らせるようなものだ!追え!早く捕まえよ!」
斥候か、先発隊か、熊千代の目は木々の間に数名の姿をとらえていた。
思ったように走れないであろうことは想定していた。岐阜の山道で鎧をつけて登り降りしたのは、そのための練習だ。甲斐があった、思ったより動けるではないかと安心して笑顔さえ浮かんたその瞬間に、ブウンと何かが頭上から降る。
石礫だと思い、さっと体ごとよけた瞬間、細長い光が反射して石ではなかったことを熊千代はさとった。
白刃だ。
もし、さきほど避けたのが体ではなく、首を右側に引いただけだったなら、左腕を斬り落とされていたかもしれない。
相手の姿などまるで見えぬまま、無我夢中で槍を引き、全身の力をこめて思いっ切り突いた。何の手ごたえもなく、勢い余った熊千代は口をひん曲げたまま前につんのめった。
数本の矢がどこからともなくばらばらと降り、やっとのことで駆け付けた米田が身を投げ出してこの無鉄砲な若君におおいかぶさった。有吉がぴたりとついて、周囲に潜んでいた数名を切り伏せている。
細川好重がふうふう言いながら追いついてきた。頭をばあんと叩かれて、熊千代は目が回る。
「いきなりそこまで突っ込むものかー!」
気を取り直した近習たちが取り囲んで、有吉以外はみな一斉に喋りはじめる。
「大将株は前線に出るものではない!」
「無鉄砲にも程がありまする!」
「何があるかわからぬのが戦場でござる!」
熊千代が跳ね起きたので皆、三歩ほど飛びのいて後ろに下がった。
数本、飛んできた矢が柔らかい土に刺さって震える。
「せ、説教など!」
好重が叫んだ。
「まだ来るぞ!盾かざせー!!」
「おおっ。若を守れー!」
その後織田軍は南下して、山手と浜手の二手に分かれることとなり、熊千代は父藤孝や明智と共に、浜手側に配属された。
今も仙千代どのと呼ばれている万見重元の姿を見て、熊千代は駆け寄った。戦場の場と言えども、顔を合わせ交流を重ねる外交の場だった。共にいたのは、信長の側近としては仙千代よりもさらに先輩の、堀秀政だった。丁重に挨拶をすませると仙千代がたずねる。
「最初の戦闘はどうであった」
「何が何だかわかりませぬ」
仙千代は笑った。
「配下たちがげっそりしておるようだが、熊千代のお守りはさぞ大変であろう」
目の下に隈をつくっている伯父や米田が頭を下げた。この無茶苦茶な勢いの嫡子を守るため、細川家の部隊には異常な結束が生まれており、奇妙な一体感があって統制が取れていた。熊千代はためらったが、正直に言った。取り繕っても仕方がない。
「頭がぐるぐるして……眩暈がしまする。あとで脚に震えが来て立てなくなっておるのに気がつきました。明智軍の山中鹿之助どのに、そんなものだと慰められましたが、いかにも悔しゅうございます!」
「ならば大丈夫」
万見仙千代は、親しげに背中を叩いてこの後輩を鼓舞した。
「恐れを知ったのだ。そなたは生き残れる」
◇
二十七日、長尾城攻めのために潜んだ山影の木の間に、敵が潜んでいると御注進があった。部隊はそばまで足を忍ばせながら寄っていき、熊千代は鋭い目で観察した。指をさす。
「あれが指揮を執っておるのではないか?」
皆、鎧の音が立たないよう体を潜め、気付かれないように散開した。
「ここから行けば、奇襲ができるぞ。やつを討ち取ろう」
有吉が音もなく傍に寄り、熊千代の袖をそっと引く。
「待てと申すか?」
有吉はうなずき、そぶりで鉄砲を頬にあてて引き金を引く真似をした。そして低い声で言う。
「今一度」
周囲は有吉が喋るのをはじめて聞いたと思い、驚いて顔を見合わせた。
「では、引きつけて待つ」
熊千代は配下に命令し、文句はないので伯父も含めてこの小さな若い主君の指示に従った。鉄砲が放たれきったそのとき、有吉はここです!と鋭い息とともにささやき、熊千代と共に走った。
◇
「与右衛門どの」
生け垣から、頭一つどころか胸まで突き出ている大男の姿をみて、お聡は声をかけて呼んだ。高島の新庄城に移ってから、忙しくも心穏やかな日々を送っていた。旧暦の五月はほぼ六月にあたり、梅雨がちで五月雨の語源ともなっている。今日は晴れ間がのぞいていた。
庭に膝をついて挨拶する藤堂与右衛門に、縁側まで出て行って気安く自ら冊子を手渡した。
「わたくしがよう使っておった碁の教本です。坂本の父上に伝えて写本を送ってもらいました」
笑いかける。
「あの時の礼をやっと渡せましたな」
「これは、三度のめしとおなじほど、ありがたく、頂戴つかまつりまする」
藤堂高虎はしかつめらしく、あくまで真面目に言う。
「一度盤上で手合わせをしてみたいものよ」
夫がお聡を探す、鋭い声が聞こえた。
ぴりぴりしておるな。
内へ入ると、信澄は見ていたとみえ苛々した調子で言う。
「あのような小者と何を話しておる。相手になぞするな!」
「小者とは」
お聡は笑った。あのような大男に可笑しな物言いをつけるものだ。
「磯野の義父上様の配下でございますよ。姉川の戦にても奮戦していたというではありませんか」
「あれは刃傷沙汰を起こしたこともあるといい、評判も悪い。それに何となく虫が好かぬ」
お聡は顔色を見て口をつぐんで何気ない顔をつくったが、なかなかの人物でよい家臣になるだろうにと惜しい心地がする。藤堂は人柄が真面目であるだけでなく算術の才もあり、成りからは似合わず文武両道だ。好き嫌いで家臣を見るはよくない、夫のこんな所が上様譲り、損をするだけだと内心思うものの、表屋敷のことと裏屋敷のことは別と口出しは控えていた。
「三七(信孝)から手紙が来ておる」
多少機嫌を直してから、信澄は妻の前でしか見せない心安さで脇息によりかかりながら読み上げた。
──往年の無礼なる振る舞いを心より反省しており、これからは七兵衛どのには仲良くして色々と教えてもらいたい。妻が寂しがっているので、奥方さまにもどうか心安く岐阜にも顔を見せて欲しい……という内容だった。
お聡は聞いているだけでげんなりしてきたが、行かないわけにはいかない。
◇
岐阜城で数多くの連枝、側室、赤子も含めた多くが、謁見のため待合の部屋で控えている。今この時が奧が最も華やぎ、もっとも火花を散らす瞬間だ。
女たちは容貌はもとよりお互いの衣装から髪型に到るまで仔細に観察し合い、検閲の結果は悪口の種になる。そんな中に聞こえてくるさまざまな各地の情報をお聡は耳をそばだてて得ては、父や夫に伝えていた。
そこへ新参者の小姓、森家の子供たちがやってきた。
「乱丸!」
「坊丸!」
「力丸!」
「よろしゅうおたのみ、もうしあげまする!」
場は瞬時に、笑顔と嬌声に沸き立った。
「まぁ可愛いこと!」
「ようお仕えなされよ」
「子の多いこと、まだ下がいるらしいのですよ」
近習の中には見慣れた熊千代の顔もあり、いつもよりも迫力が増して目が吊り上がっているようだ。初陣もすませたとのこと、大人になりつつあるのだろうとお聡は思った。信忠や信澄に囲まれている。
「今回の新顔の中では、乱が頭ひとつ抜きでておるな。出来もよく覚えが早い」
「だいたい、父上のお気に召すのは二種類だ。仙千代のごとき奉行向きの類い。それから勢いのよい、見ていて面白い奴。無論そなたは後者だ」
「まだあるぞ。容貌の美しい……」
「そこまででやめておきなされ」
蒲生忠三郎が助け船を入れている。
お聡の鋭い目は、その華やかな若者たちの中に、荒木村次の姿がいないことを見て取っていた。
◇
「降伏など認めぬ、絶対、絶対に認められぬ!全員、撫で切り(皆殺し)にすべきだ!」
熊千代は唾を飛ばして叫んでいる。
十月、明智軍は丹波攻略の足掛かりとするため、亀山城の明け渡しを求めていた。先日に内藤氏の城主が亡くなり、家臣の安村をはじめ家人たちがたて籠っている。
光秀が何度も使いをやった話し合いが実って、降伏の受け入れが整いつつあった。開城すると共に、全員を家臣に取り立てるとの約束を聞いて熊千代が激昂した。
「責め立てて全員切り捨ててしまえばよいものを!いやそうすべきだ!上様に言上仕る!きっと許して頂ける!」
みなごろしだぁー!
……と騒いでいるのは熊千代一人だった。
「いやどうすべきか」
熊千代のいない所で、皆は額を集めて相談した。
「血気に流行るにしても度を越しとる。尾張流の荒くれ作法に染まり切ってしまっておるようだ」
筒井順慶は優柔不断な顔をまげて周囲を伺いながら渋い顔をしているし、高山右近はじっと目を閉じて手を膝の上に組んだまま黙っている。
「困ったことは、アレが上様の大のお気に入りということだ」
「あの血に狂った状態で本気で直接に言上されては……」
撫で切りに許可が出てしまいかねない。
城の内部でことがすむ小姓の立場ならばまだしも、戦場においては厄介だった。容易ならぬ後ろ盾の力を背負ってしまっている。本人はまるで無自覚なので、さらに面倒だった。
せっかくまとまりかけた講和を前に、明智軍全体に不安が広がっている。
「おぬしが何とかせぬか!親父であろうが!」
手伝いに駆け付けていた荒木村重が腐ったように藤孝に言った。
「あやつは駄目!もう駄目だ。わしの言うことなどな~んにも聞かん!」
村重よりも輪をかけて腐ったような顔で藤孝は言う。
「誠に恥ずかしい。だからわしは反対したのだ!あ奴にはまだ早いと!」
それは、あなたが片岡攻めで頓五郎どのを、いけるとか何とか言って無理に初陣に押し込むから……、と松井は言いかねた。
熊千代の時にはあれほど反対してまだ早い早いと言っていたのにだ。確かに頓五郎は体も大きく力も強い。精神的にも落ち着いている。片岡攻めの時にお目付け役をこなしたのは松井だったが、熊千代が弟の存在にあからさまに神経を尖らせているのがわかった。
そして頓五郎は、兄のそばについて無我夢中で一緒に駆けて行き、兄弟で一番、二番に塀に取り付いて一緒に信長からお褒めの感状をもらってしまった。
ただの感状ではない。直筆だ。もちろんこの上ない名誉ではあるが、あのときは大将である日向守どのの命に背いての抜け駆け早駆けであったのにもろうてしまったのは非常にまずかった、と松井は思う。
熊千代は何とかして父や弟を振りぬきたいのだ。
山中鹿之助が口を出した。
「勇猛ゆえに忘れがちだが、皆々さま、まだ細川のご嫡男は若年ということを忘れてはなりませぬ。まだ今年初陣したばかりの方、まだ年すら越してはおらぬ。功をあせり夢中になれば、何も見えぬようになるものです」
光秀が立ち上がった。
「わたしが直接に話す」
「と言われても、何度も説得されたが無駄だったではないか」
「何度でも話し申す」
「懇切丁寧なことだ。だがそれも通じる相手と通じぬ相手がおるぞ」
それで結局は松永弾正も……。
場に暗さが増して、みな口を噤んだ。
「それでも話し申す。熊千代殿は、決して言ってわからぬ相手ではあり申さぬ」
◇
去年、明智の救出のために結束を固め突撃をした織田家中が、今年に入ってから一転して不協和音に晒されていた。越前では上杉との戦闘が起き、八月には年取った松永久秀が織田家から離反した。
政情を含んだ集団の思惑とは揺れ動くものだが、長引く石山合戦の影響が影を落としている。背後に義昭の扇動はあるものの、反信長の気鋭のそれだ。本願寺門徒はどこにでもいる。織田家や信長への反感がちょっとした紛糾やもつれで火が付き、誰もが信長への陰口をたたき、不満を口にしている。いやな空気だ。
ここのところ、たがをしめる役割の光秀が一向に冴えない。
相変わらず丁重で細部まで隙がないのは事実だが、どこか心あらずなのだ。
亀山がおさまればあちらへ移築して移ることに決めたのは、丹波攻略のためのようでありながら、奥方もおらず、娘たちも嫁に行ってしまう坂本城に戻るのがつらいのだろう。思い出がありすぎて耐えられずにいることを藤孝にはわかっていた。あやつは立派な武人ではあるが、冷静に見えてもあれで情に引きずられるところがあるからな。
肩を落とす彼を、冗談と政情の真剣な話で励ましながら、藤孝も好きであるこの男の人間らしい部分が、明智派とみなされている者らすべてを含めた命取りにならねばよいがと藤孝は危ぶんだ。
◇
童め!そっ首叩き落してくれる!
目がさめているのに、ここは自軍の幕内のはずなのに、耳の後ろから、前から、頭上から、声が聞こえる。
並んでいる首の中に、自分が斬った敵がいるのを見た。清められても口はよじれまがり、眉は上がり、ものすごい形相のままでいた。
明智に呼ばれ本陣へ向かいながら、突撃は絶対に譲らないと熊千代はかたく心に決めている。許されねば今度こそ上様に直接願い出る!
片岡攻めまではわけもわからず、ただひたすらついて行くのがやっとだった。まだ真に武功を上げたとは言えない。
若い熊千代は、軍全体を覆っている、信長に対するひそかな不満と恐れの気配に反発を感じていた。
上様のなされることに恐れ多くも文句をつけるなど言語道断だ!三介どのだって、(あんなに阿呆のような顔をしておるが)北畠の粛清に自ら参加したのだぞ。おれだって、ご命令あらば饗宴の席であってもやってみせる!三介どのに出来ておれに出来ぬということがあるものか!
油断させておいて……こう!抜く!
目をぎらつかせ、抜き打ちの練習をしながら足早に歩いている熊千代を見て、藤孝がいやな顔をして、またあやつは頭がおかしゅうなったか?と松井にささやく。
片岡城の塀にむきになって取り付いたとき、熊千代はそれがあのよく茶の話を彼にしてくれていた豪放磊落な鋭い顔つきの老人、松永弾正の城だということをほとんど意識していなかった。
今になって、もう彼はいないのだ、会うことも話すことも出来ないのだとじわじわと実感がわいて行き、首を見た時の我が身の腹を刺されるような思い、また六条河原で斬首された人質の松永の孫たちと、生きていたときに親しく語らった記憶が浮かんだ。胸は詰まり、吐き気を催しながらも、つきまとう影を振り払い、歯を食いしばって自らを駆り立てる。
命があるか、ないかなど考えて刀をふるうことなどあるものか、何をどれだけ斬ったかなどいちいち数えてはいない。どれもこれも、人の身体だなどとは思わなかった。藁袋を刺すのと同じだ。光秀殿がいたわるように、じきなれるとあったが、最初から無感覚だ。
ただ、斬れば斬るほど目の前が赤くなって、靄がかかり、視界が薄くなっていくような気がした。目をこすり、額を叩く。この目、目だ!おれの命をいつも救うてくれるのはこの目、しっかりせねば!
敵は完全に心の臓を突き、首を落として息の根を止めねばならぬ。二度と口が聞けぬように!動き出さぬように!
そう思う時の熊千代の顔は、あの悪鬼のようによじれた首が乗り移ったように、眼は吊り上がり、形相が変わっていた。
◇
「日向守どの!」
幕内に入るなり、熊千代はわめきたてた。
「投降兵を次々に迎えておる!開城が始まっておるではありませぬか!」
「座られよ」
湯が沸く音が響いている。光秀は陣中に簡素ながら茶の設えをした前に座っていた。
茶の湯!戦場で茶など。
吊り上がった目でずかずかと寄って行った熊千代に、明智は座るのを待たずに茶碗を差し出した。
「そなたは血に酔っておる。まずは落ち着きなされ」
仏頂面で茶碗を受け取ってしまい、取ってしまったからには作法どおりに座る。思わず気を取られたのは、差し出された茶碗の黒々と濡れ光る様が素晴らしく、有無を言わせない形をしていたからだ。
茶の色にも魅入られた。なんという深いみどりだ。
血と汗、死臭漂う中にいて忘れていた。自然の生み出す奇跡のような瞬間への思いがふっと戻ってきた。青葉がしなだれる流れに宿る露に、水面に輝く月、そのままにある静謐だ。
剣戟の響きが遠くなった。
自然と作法通りに座り、恥ずかしくない手前で頂いた。
うまい。
飲み干すと手にしっくりと馴染む茶碗をつくづくと眺めた。鼈口のある天目型で、仄昏い藍地の上に一面に霜が降りたような冷たい模様が散っており、いよいよ心醒まされる心地がする。
師匠の山上宗二の顔が浮かぶ。
──知らん、知らん!おれは口の聞き方を知らんからよう。改めようとも思わん、これが、わしだ!カネを撒く商人も血を降らす武人も、地を耕す百姓もみな、この一杯の茶の前では同じ。みんな、おなじだ!
「そなたは上様に気性がよう似ておられる。また、そうなろうと努力してもおる。だが、本当のそなたはどこにある」
熊千代は魅入られた別世界からも引き戻されて顔を上げた。
思わず聞き惚れる深い声音だ。変わっていない。
「この世は無情なもの。強力な力なくば生きていかれぬ。この世を一にするためには仕方なきこと、したがその後はどうなる?刀を取って戦っておるのは地つきの者たちです。戦いとは勝ったあとのほうが大事、この土地に根付き、地を耕し商いをして生業を立ててきた者たちを大切にせねば、敵は敵のままとなりまする」
──いいか。いい茶器だ、こいつが欲しい!と思う。いつしか心は囚われ、そのことのみを考え、名物に飲まれていくようになる。欲に流されるな!金に使われるな。おまえは、おまえを、見失うな!
「戦場の気配に飲まれずに、あらゆることに目を配るのです。将だけで終わってはならぬ。民を治めることを考えてこそ、大名になれるのです。上だけを見ていては、よき治世は出来ませぬ」
怒りが祓われ、意識が明瞭になる涼やかな声、ここのところ忘れかけていた、彼の神秘の気配が束の間、戻ってきたような気がした。
世間話でもするように茶を飲みながら座っていると、次第に胸のどす黒く溜まった厚いかさぶたのような澱が消えていくのを感じた。
「あいわかり申した」
深々と頭を下げたとき、反発はもうなかった。
出てきた熊千代は別人のように落ち着いていて、機嫌は良い悪いは別にごく普通の態度になっていた。周囲のあからさまにほっとした顔が癪にさわるものの、亀山城は無事に開城を果たすことが出来た。
◇
荒木の城のお岸から、珍しく長い手紙だった。
中身を見て、お聡は微かに眉を寄せた。
──七兵衛どのから熊千代どのの指南役に誰か丁度よいおなごはおらぬかとお尋ねあり、村次どのはわたくしに許可を求められました。
そういうのを気にせず共有する所が荒木の家風が開けっ広げで、またおそらく姉の性にあわぬところだ。信澄はお聡に匂わせすらしていない。
荒木は織田家に対して警戒心の強い家中であったが信澄は、今も村次とだけは交流があり、屋敷に出入りしている。元気な熊千代を伴うこともあるらしく、三姉妹を嫁に持つ者の横の繋がりが生きていた。
──お珠がどう思うのか、あれは癇の強い質ゆえ。お聡にはそっと知らせておきまする。
荒木家中の侍女たちの中では、お聡も見知っている娘だった。反感はない。大らかで、若さに似合わず気っぷよく、姉さん気質でいかにもようございます、一肌脱ぎましょうと言うだろう。問題がありそうには思えない。
姉のその筆使いと調子は、病が重いとされているお岸が決して気力も判断力も失っていないことを示している。
避けられぬことだ。仕方あるまい。お聡は念をいれて書を燃やし、お藤というその名前だけを胸にとどめた。
第十六話 終わり
画像(ルビつき・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。

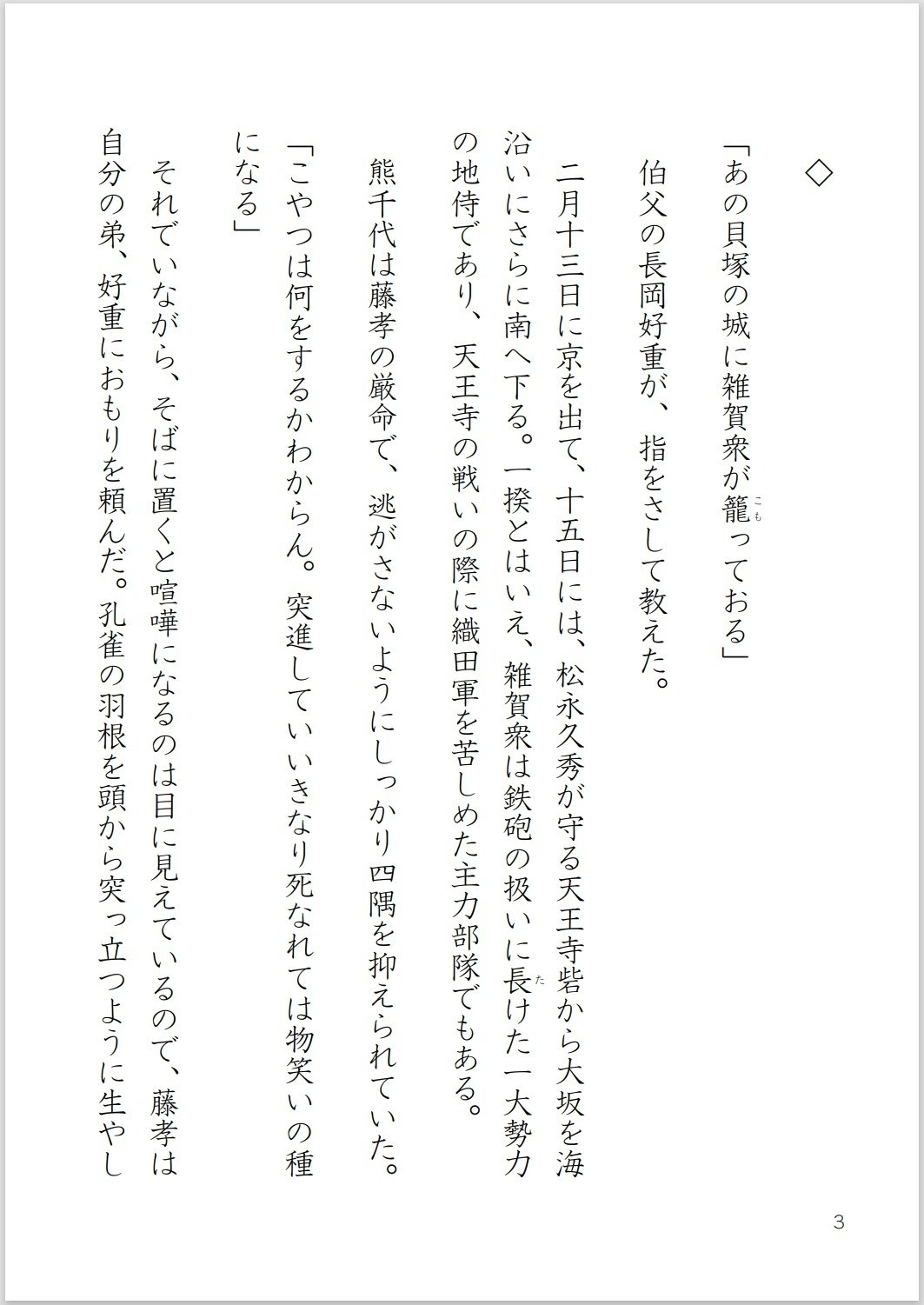



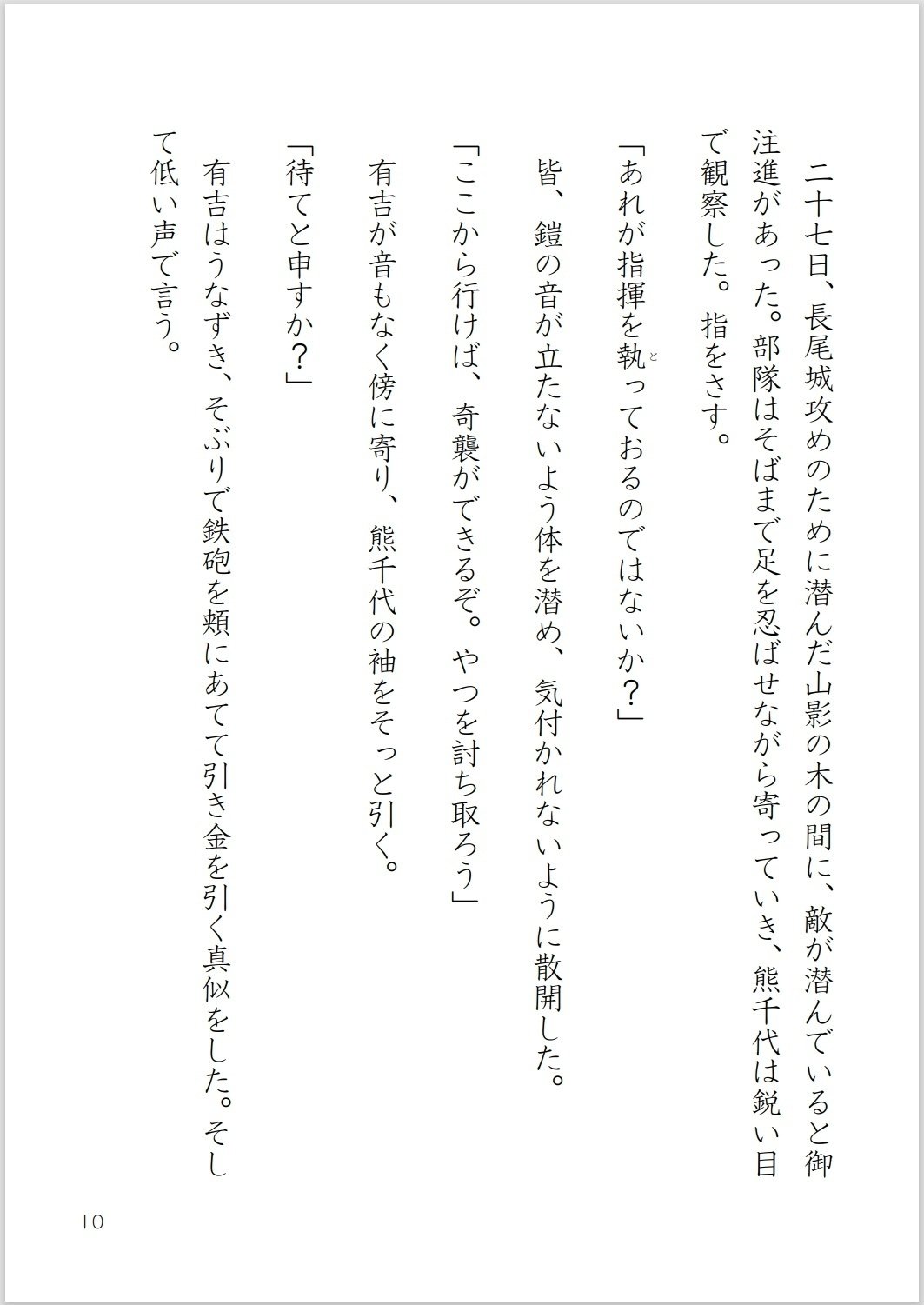

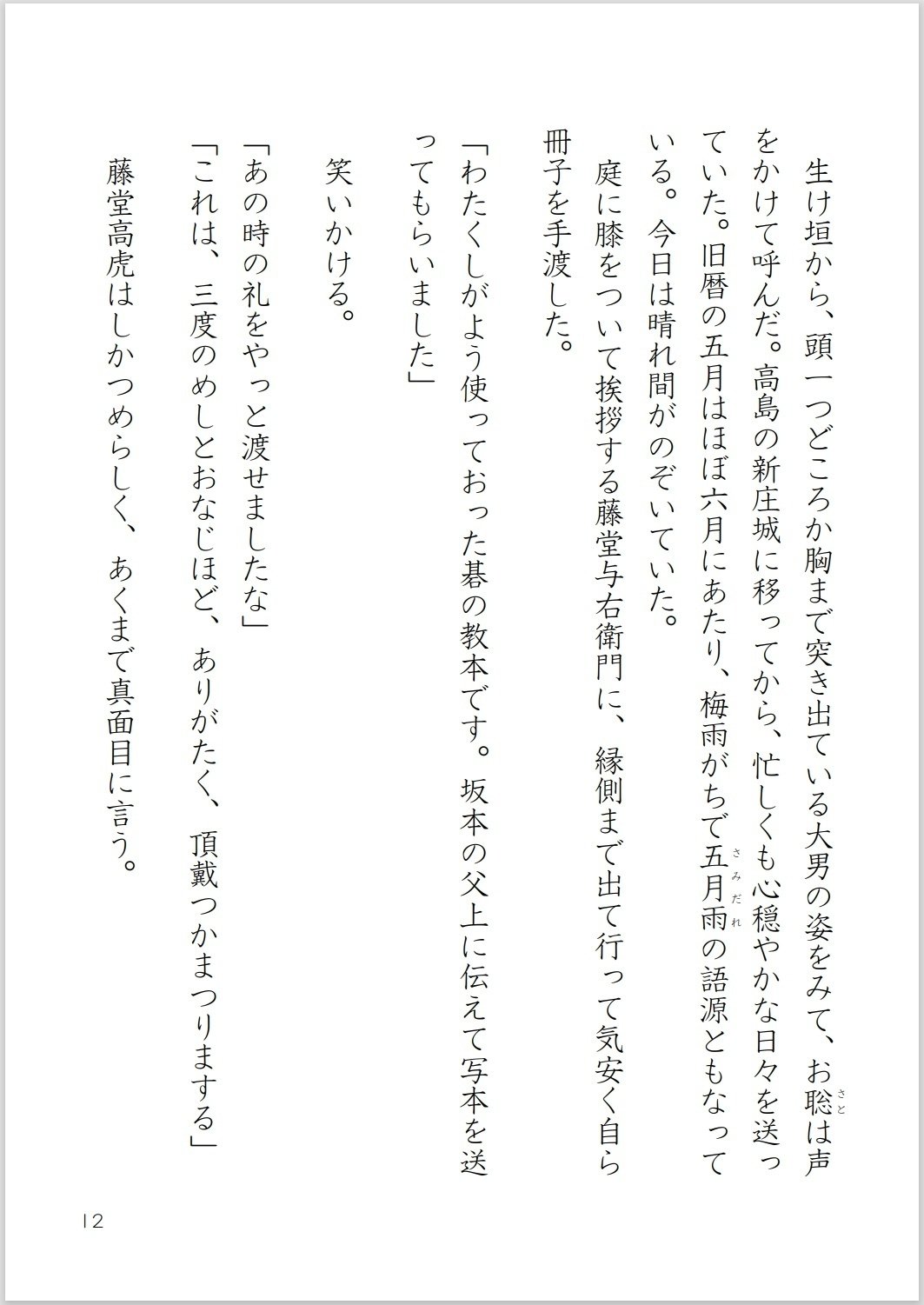






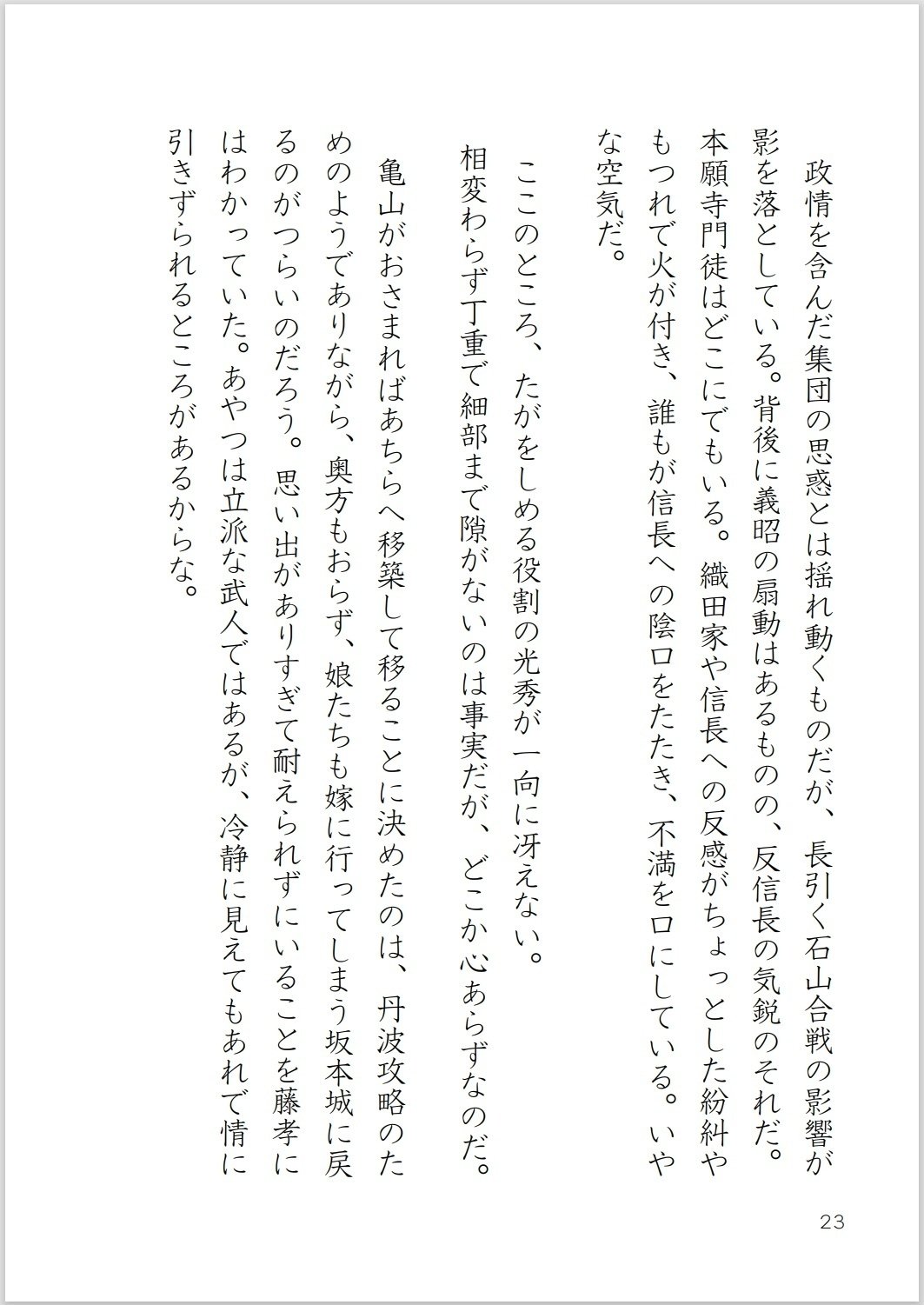
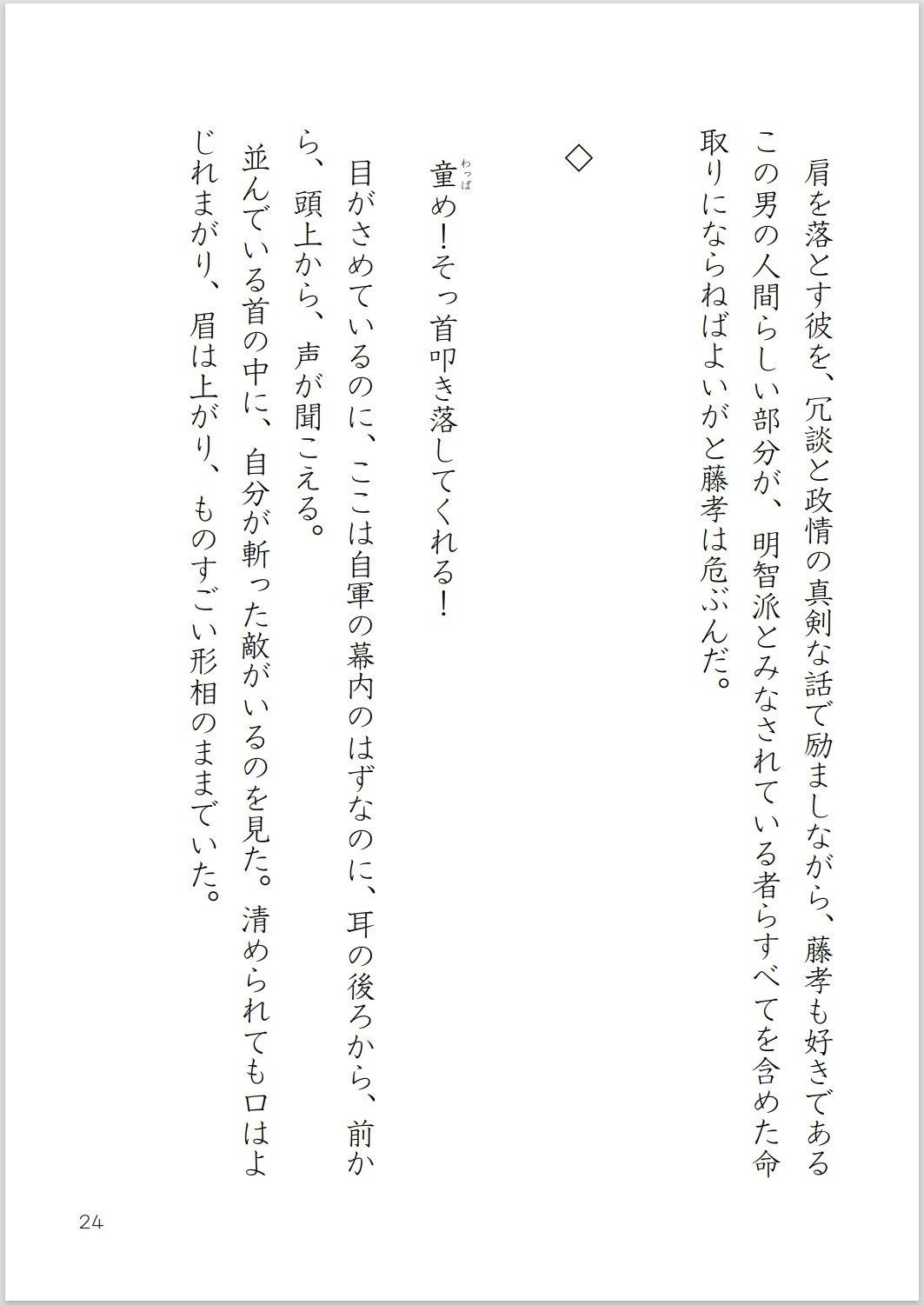

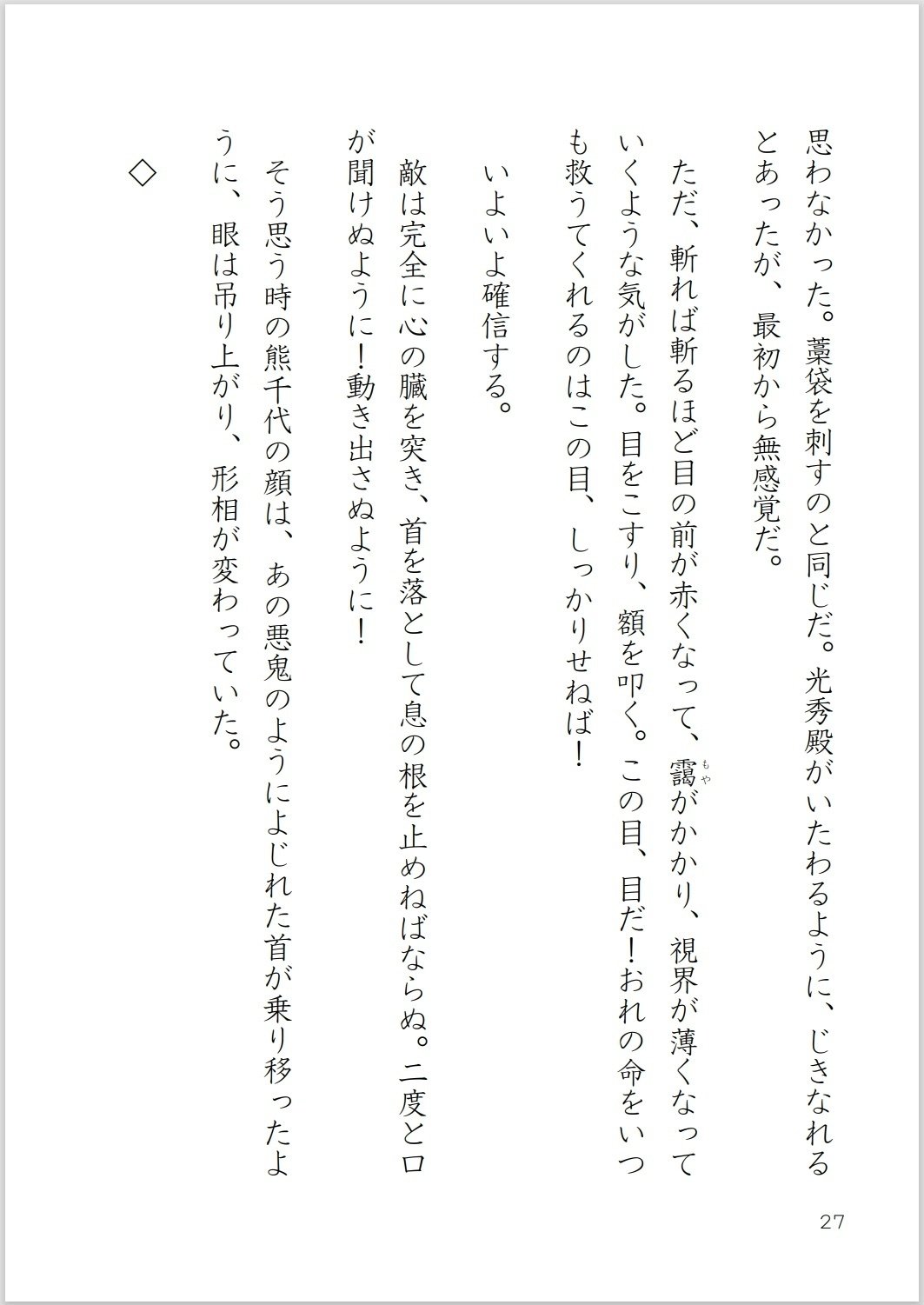






画像。本型。見開き版。




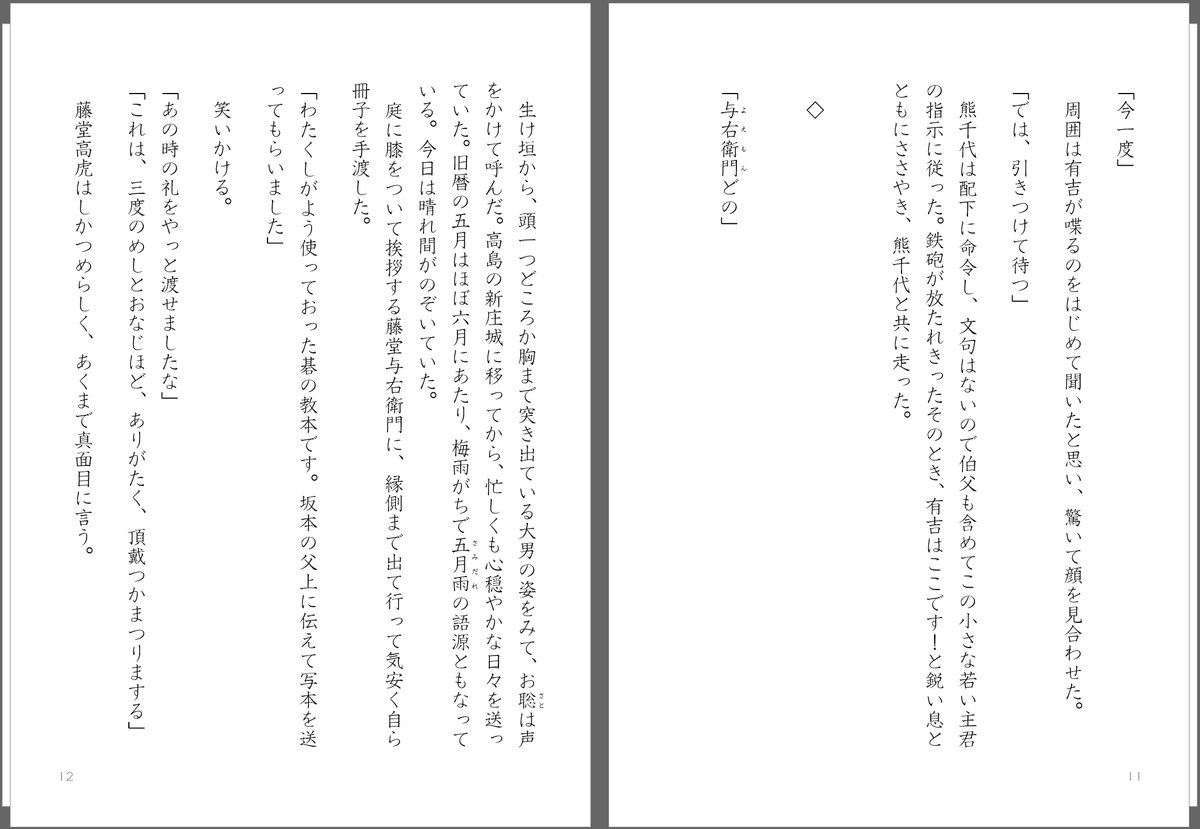







いいなと思ったら応援しよう!

