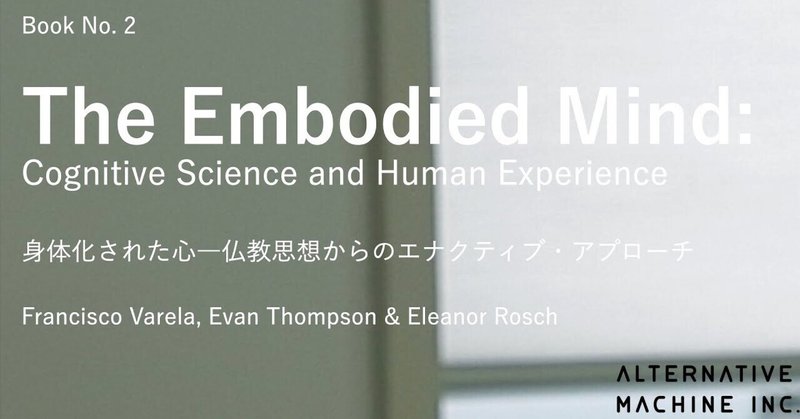
心の科学を徹底した結果、仏教思想がでてきてしまう話 (ヴァレラ「身体化された心」 #4, ALife Book Club 2-4)
こんにちは!Alternative Machine Inc.の小島です。
ついに「身体化された心」の最終回となりました。ここまで、心の科学を考えるために、エナクティヴィズムというアプローチにいたったものの、なぜそこで止まらずに仏教思想が出てきてしまうのかという話をしていこうと思います。
これまでの記事をお読みでない方は、ぜひこちら(#1, #2, #3)からご覧ください。
いまさらなんですが、心を科学したいと思う理由ってなんでしょう?
心というもの自体は身近なもので、科学を知らなくても普通に付き合っていけます。そこであえて科学を導入しようとする場合のモチベーションは、心のわからなさを科学ですっきりさせたい(そしてラクしたい)ということではないでしょうか。実際、第二回に説明した人工知能モデルはわりとスッキリした心のモデルです、ここで済めばその目標は達成できているといえます。
でも、ここで終われないというのが本書の特徴です。なんで終われないのか。それは筆者(ヴァレラら)が、心の科学は日常的な体験と結びつかなければならない、という信念を持っているからです。人工知能モデルはたしかに心の特徴の一部分を捉えているけれど、それと日常的に体験する心のあり方にはかなり距離があります。ふつうに暮らしていて体験する心と結びつかないような科学は無意味だろう、というわけです。
科学者としてはすっきりわかる範囲でなんとかおさめたい(そうじゃなきゃ科学じゃない)ので、そうはいってもどうしようもないよ、となるところを妥協しないでがんばろうというのが本書であり、その結果仏教思想になってしまう、、というあたりを今回はお話します。
エナクティヴィズム
まずは前回のおさらいと補足から始めます。
前回は「色」はどこにあるかという話から、今ここでの知覚体験をつくっているものは眼の前にあるものだけではなく、自分の神経細胞の性質や、これまでの自分の知覚、運動体験、さらには文化的なコンテクストまでも含んでいるということを見てきました。
そこででてきたキーワードが「エナクティヴィズム」です。これは知覚体験に身体的なものが含まれるという前回の話に対応するものですが、さらにそもそも知覚というものは行動を導くためにあるという考えも強調するものです。本文から引用してみます。
簡単に言えば、エナクティブ・アプローチは二つの点からなる。(1)知覚とは、知覚によって導かれる行為である。(2)認知構造は、行為が知覚に導かれることを可能にする反復性の感覚運動パターンから創発される。
全然簡単ではないですが、(2)の部分がおおまかにいうとこれまでの話に対応していて、(1)の部分が知覚が行為を導くためのものである、ということに相当します。
以上から、2回目でお話した人工知能モデルとの違いが見えてくるかと思います。すなわち、人工知能モデルでは、外界を感覚入力に基づいてどう認識するかが焦点だったのに対し、エナクティブ・アプローチでは、そもそも知覚と行動は分けられないもので、その結果、知覚には外界の特徴抽出にとどまらないさまざまな身体的なものが埋め込まれる、ということになるのです。
これで本書で紹介される3つの心の科学のアプローチ「認知主義」「コネクショニズム」「エナクティヴィズム」が出揃いました。そこでこれが日常の体験と結びつくかを考えるために、「私」という問題を考えてみます。
「私」がどこにも見つからない
さて、ここで「私」がどこにあるかという問題を考えてみます。「私」とはこれを書いている小島の話ではなくて、「私」というものそのものの話です。「自己」「自我」といってもいいです。
この「私」というものの特徴として、一貫性があり連続しているということがあります。つまり、なにかが変わらずにずっと存在していることが必要そうですが、このなにかはどこにあるのでしょうか?
一つの考え方は、「身体」にあるというものです。つまり自分の身体はずっと変わらず自分の身体でありつづけているだろうというわけです。しかし、これは物質レベルで考えると間違っていることがわかります。確かに、外見としては同じように見えるけれど、構成している物質はどんどん入れ替わっているからです。身体、特にその物質の同一性をもって「私」が変わっていないと主張することは難しそうです。
では「心」にあるといえるでしょうか?
しかし残念ながら、ここまでに導入した3つの考え方である「認知主義」「コネクショニズム」「エナクティヴィズム」のどれをみても、ずっと変わらない「私」に相当するものは見つかりません。
ということは、「エナクティヴィズム」でも日常的な体験としてある「私」を説明できておらず、新しい説明が必要ということでしょうか?
この本のユニークなところは、これについては日常の体験の方が間違っていると主張してしまうところです。そしてついに仏教思想の話になってきます。
日常の体験の変容まで考える
ここで初回に引用しておいた話に戻ってきます。
新しい心の科学は、生の経験だけではなくそこに秘められた変容の可能性まで包含する必要がある。この確信が本書の出発点であり、終着点である。
日常的な生の経験は慣れ親しんでいるだけで正しいとは限らない。そのことも心の科学と日常的な経験の接続を阻んでいたというのです。
つまり、これまでは科学側を工夫してきたわけですが、それだけではなく経験側も変える(「そこに秘められた変容の可能性」)必要があるということです。
ただし、あなたの日常的な経験は違いますよ、とかいわれても困ってしまいます。そこで筆者らが活路を見出そうとしたのが仏教思想になります。なぜかというと、禅の修行においておこなわれていたことは、経験の変容を体系的におこそうとするものだったからです。ここに体系が入れば、経験の部分も秩序立てて扱うことができ、さらにこれが科学と接続することで、より全体として理解を深めることができるはずと考えたのです。また先程話しにでてきた「私」がないということは仏教において「自我」はないとされることと対応します。そんなことからも、仏教思想に基づく経験の変容と、エナクティヴィズムによる科学を組み合わせることで、日常的な経験と科学が対応し連関する理想的な状況が作れるというわけです。
このモチベーションのもとにこの本では仏教思想の概念と、科学的な概念の対応や、両者をすり合わせるための経験の変容のありかたについて議論されていきます。ここの詳細は僕の手に余るので興味がある方はぜひ本書をお読みください。
じゃあ仏教をやらないといけないのか?
ということで、筆者の主張によれば心の科学を成立させるには科学側も心側も歩み寄らないといけない、そして心側の歩み寄りとして仏教思想を利用するべき、ということになりました。
これはわりと説得力のある議論ではあるのですが、じゃあこの分野のひとがみんな禅の修行をするようになったかというと、そんなことはありません。むしろ大抵の場合、本書は「エナクティヴィズム」の本として説明され、仏教部分は無視されることがほとんどに思います。それは科学者の態度してはまあ当然かなとは思います。ただし同時に、日常の体験と心の科学が結びつかないという問題から目を背けてはいけないのだろうとも思います。
ちなみに僕個人としては、「私」があると感じる日常的な体験をも肯定できる枠組みでなければ意味がないと思っています。エナクティヴィズム的にも、仏教的にも間違った状態であるとしても、その状態が現に生じている以上それを無視することはできないはずです。そしてそんな「間違っている」状態こそが人間なのではとすら思うのです。ただそのためにはさらなる科学の道具が必要ですし、この「間違い」を肯定することが倫理的にどうなのか(ヴァレラらはこの「間違い」こそが世界平和を壊していると論じていきます)ということも心にとめておく必要がありそうです。
というわけで、すっかり長くなってしまいましたが「身体化された心」の解説は以上になります。
弊社のYouTube動画のほうでは、今回の部分に対応する話だけを現代的なコンテクストを含めてお話しているので、もしよければご覧ください!
次回からはメイヤスーの「減算と縮約」についてお話していきます、が、準備が来週までに間に合わなさそうなので、次回はまた番外編を予定しています。
今週も最後までお読みいただきありがとうございました!また来週お会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
