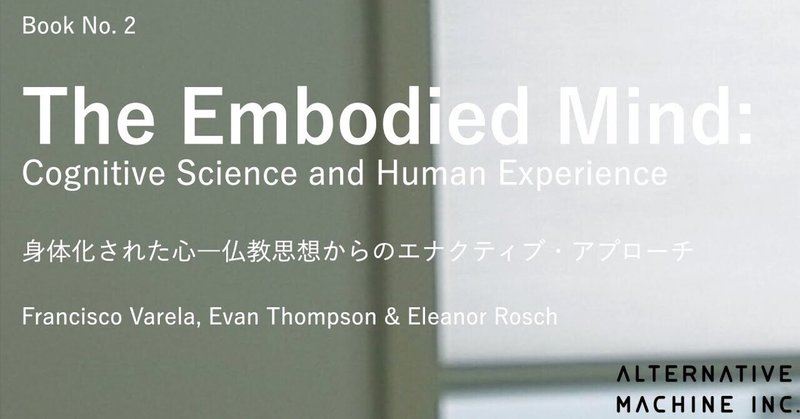
どうやったら心を科学で理解できるのか (ヴァレラ「身体化された心」 #1, ALife Book Club 2-1)
こんにちは!Alternative Machine Inc.の小島です。
前回の"Endophysics"に引き続いて、今回からヴァレラ、トンプソン、ロッシュ著「身体化された心(原題 "the Embodied Mind")」(1991)についてお話していきます。
この「身体化された心」は前回までの物理の話とうってかわって心についての本です。僕らの専門分野である「人工生命」はミニマルな生命体を作ろうとする分野に思われがちですが、脳や認知も研究の対象です。(ただし、神経科学とは違って、実際の脳を研究するというよりも、人工システムによるモデル化や理論によるアプローチをとります。)
この本の筆頭著者であるヴァレラは人工生命の分野ではスター研究者であり、マトゥラーナと一緒にオートポイエーシスという生命理論における重要概念を打ち立てた後、認知科学の研究へと移りそこでも大きな業績を上げた人です。
そんなヴァレラが書いた本で、なおかつ和訳も手に入りやすいということで、万人におすすめしたい、、、と言いたいところなのですが、実はかなりの要注意本です。なんと、科学の本のはずなのに、仏教の話が出てきてしまうのです。しかも、一部分だけではなく全編通して、です。
科学をやっている身としては、そんな本を普通はおすすめできないです。心の話は簡単にスピリチュアルになりがちで、そこに陥らないで頑張るというのが科学者としての矜持だからです。それでもこの本を今回取り上げる理由は、ヴァレラが有名だから特別扱いしているのではありません。心を科学的に取り扱うということそのものに根源的な難しさがあり、その難しさに正面から立ち向かっている数少ない本だからです。その難しさは一言で説明しにくいのですが、予告として本書の最初の文章を引用しておきます。
新しい心の科学は、生の経験だけではなくそこに秘められた変容の可能性まで包含する必要がある。この確信が本書の出発点であり、終着点である。
この「生の経験」や「変容の可能性」というのが厄介で普段は考えないようにしているのですが、それをまともに扱おうとしているのが本書なのです。この連載で少しずつその厄介さとヴァレラらのアプローチを解説していきますので、最後までお付き合いいただけるとうれしいです。特に以前本書を挫折した方は、本連載を読んでからぜひ再挑戦してみてください!
この本の目的
あらためて本書の目的を確認しておきます。それは、心をどうしたら科学的に扱えるか、ということです。
心というものは日常的には馴染みがあるものですし、僕らの重大な関心事であることは間違いありません。ところがこの心を科学はうまく取り扱えていません。大体の困りごとは科学の力で解決できる現代でも、心に関してはいまだに占いに幅をきかされている有様です。
万能なはずの科学が、心に刃が立たないのはなぜでしょうか。それは端的に言えば科学の得意分野が物質だからです。物質の振る舞いを予測するのが科学の得意技です。ところが、心は「物質ではないもの」とされています。実体がないものです。こうなると科学は途端にどうしたらいいかわからなくなります。科学がうまく扱えないものの総称を「心」と呼んでいる、といってもいいくらいかもしれません。
では、科学では永遠に心を取り扱えないのでしょうか?ここで必要なことは、「物質の振る舞い」とは違う切り口で物事を捉えることができるか、ということです。物質ではなくなにかもう少し抽象的なレベルのものが科学の記述対象になれば、それが心の記述にも使えるかもしれない、と考えることができます。
心は「計算」だと考えてみる
そこで、ここでは「計算」という概念を考えてみます。計算と言っても英語で言えば"Computation"なので、情報処理と言い換えてもいいかもしれません。なにか情報を受け取って、それを処理して、結果を出力する、そういう操作のことです。"2+2"を受け取って"4"を出力するみたいなことです。
計算は物質の記述よりも抽象的なものです。"2+2=4"という同じ計算は、石ころを並べても、そろばんを使っても、電卓を使ってもできます。この場合、物質の振る舞いとしては全く違っているけれど、「計算」としては全く同じことが起こっています。つまり「計算」という考え方は物質よりも抽象的なものです。よって「計算」という考え方は、心の記述の候補となり得ます。
一方で「計算」をどのように科学するか、という問題も残ります。これに関しては計算を人工システムで考えようという一大分野があります。それは「計算機科学(コンピューターサイエンス)」であり、特に知能に注目した場合には「人工知能」です。つまり、心を計算で考えるということは、心をコンピューター、特に人工知能でモデル化できるかということに繋がっていくのです。
次回は、こういったアプローチである「認知主義」や「コネクショニズム」の話とその限界についてお話しようと思います。お楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
