
ユニットケアの課題と打開策【福祉国家との比較、配置基準の緩和等】
こんにちは、アルゴです。
今回は、介護の『ユニットケア』における現状の課題と打開策についてお話します。
「従来型施設で働いていて、ユニット型施設に職場を変えようと迷っているんだよなぁ」
・・・という方に、特に参考になるかと思います。
この記事を書いている私(アルゴ)は、
従来型特養・ユニット型特養、デイサービスなどで、現場介護職、ユニットリーダーなど現場管理職、施設長補佐、相談員、施設CMなどを歴任してきました。
また過去に、ユニットケア推進センターの主催するリーダー研修も受講し、他施設実習などを通して、日本におけるユニットケアの理念についても学んできました。
本記事では、そんな私が、従来型とユニット型の違いと、双方のメリットデメリットについて詳しくお話いたします。
とんでもないボリュームの記事になってしまいましたが、ついてこれる方だけ無理せず読んでください。
人を人とも思わない、最低の介護からの脱却

日本におけるユニットケアの目指すところを箇条書きにすると
・家庭的な雰囲気をつくる
・職員とご利用者どうしはなじみの関係になれる
・職員は少人数を見ることにより、よりご利用者のことをよく知れる
というような感じです。
ユニットケアおいても、老人福祉法第33条、暮らしの継続という言葉はよく用いられます。
国が
「ユニットケア施設を作るなら、こういうふうなところを目指さないと駄目だよ」
と言っているのです。
日本の介護の歴史を紐解くと、昭和の時代には老人はひどい扱いを受けていました。恐らく介護を勉強する中で、歴史も学ぶでしょうから、皆さんもよくご存知のはずでしょう。
男性と女性が同じ風呂で入浴させられたり、入浴をする前に廊下でハダカで待たされていたというんですから、一番ひどかった時に比べると、比較にならないほど現在の福祉は進んでいるのでしょう。
そしてこの日本のユニットケアは、『従来型』のような、一律一斉の介護をやめて、個別ケアをしていこうという理念で始まっています。
ここまでは素晴らしいことです。『その人自身』を尊重していき、質が高いケアを行っていく考え方です。
そしてスウェーデンやフィンランドなど、福祉国家と呼ばれる国々を真似て、日本のユニットケアが始まりました。
北欧のユニットケアを真似て勝手にアレンジしちゃった日本のユニットケア

しかし、その取り入れ方がまずかったのです。
日本のユニットケアは、上でも述べたことをもう一度箇条書きにすると、
・家庭的な雰囲気をつくる
・職員とご利用者どうしはなじみの関係になれる
・職員は少人数を見ることにより、よりご利用者のことをよく知れる
これがポイントになります。
しかし残念ながら、これ全部、日本でユニットケアを推進した国の押し付けなのです。
それを説明するために、まず、日本のユニットケアと、北欧のユニットケアを比較してみましょう。
まず、日本のユニットケア。

(図があまりうまくなくてすみません。許してくださいね)
ユニット型で働く方ならご存知かと思いますが、基本はこのように、7人〜10人のご利用者が、ひとつのリビングや風呂、複数のトイレを共有するかたち。いわゆる、ひとつの家族とみなしケアが行われます。
ユニットケアじたいは北欧を参考にしたと言われていますし、推進センターの主催する研修でもこの点を繰り返し伝えられています。
ですが、この家族になる・・・とか・・家庭的な雰囲気というのは、日本人の勝手な解釈なのです。
北欧のユニットケアは、別に家族になるとかそういったことは求められていません。
そこで次に、北欧の施設のイメージを見てみましょう。

(また、図が下手ですみません)(笑
えっと、日本のユニットケア施設と違うのは、各ご利用者がトイレ、シャワー、リビングダイニングなどを共有していないというとこです。
「え?」
・・・て思いますよね。
図を見てわかるかと思いますが、各ご利用者が居住施設の中に自宅スペースを持っており、基本的な生活は他のご利用者とベッタリくっつくわけじゃありません。
(もともと、日本のように湯船に浸かる生活習慣はないようですが)
他のご利用者と生活をともにしたければ、共有スペースがあるよ・・・という感じしょう。どちらかというと、日本のユニット型施設よりも、サ高住などに近いのかもしれませんね。
つまり、
日本が参考にした北欧のケアは、別に家庭的な雰囲気など求めていないのです。
日本の介護の黒歴史であった『一律一斉の人を人とも思わない介護』をやめて個別性を重視するまでは良かったですね。
しかし行政がユニットケアを推進していく段階で、日本の家庭のイメージを無理くり介護施設に当てはめてしまったというわけです。
北欧では、死ぬまでご利用者その人自身の『自立』を尊重していますし、日本のように、子供が親を見るという習慣もありません。
職員自身もご利用者となじみの関係を作ろうともしていません。
文化的背景がまったく違うのです。
そして、日本のご利用者も『家庭的な雰囲気』で過ごしたいと願っているのでしょうか?
中にはそういった方もいるかもしれません。ですが、皆さんがケアをしていく中で、
「ワシは、他のひとたちの家族のような付き合いをしたいんだよ」
というような願望を一度でも聴いたことがあるでしょうか?
家庭的な雰囲気づくり・・・というのは、あくまで行政の押し付けにすぎないと私は思います。
北欧と日本・・・歴史的背景の違い

私は歴史や政治にそれほど詳しいわけじゃありませんが、『共産主義』とか『民主主義』の違いくらいなら、人並みにはわかります。
共産主義ってのは良さそうに見えてうまくいかないですよね。歴史が証明してますから。
そんで、スウェーデンとかデンマークというのは、第二次世界大戦が終わった後、ソ連の矢面にたって、共産主義が浸透しそうになった過去がありました。
これは危ないと思った国家は、国民をいわゆる『福祉中毒』『福祉漬け』にして、政府への信頼感を高めたのです。
いわば、北欧の福祉国家が福祉国家たるゆえんは、必然であり、歴史的な背景があるのですね。
日本は北欧の福祉国家を真似たうえ、『家庭的なケア』という勝手な解釈を押し付けてしまいましたが、そもそも、歴史的・文化的背景からいって、北欧と日本はまったく違うのです。

https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B091XPN678
北欧と日本・・・税制や職員配置基準の違い

日本のユニットケアは、職員の配置基準として・・・
1ユニット=常勤職員5人 がベースとなってます。職員1に対し、ご利用者2人という感じですね。
居室担当という点で、そのご利用者をじっくり見ていく・・・という点では良いです。
しかし、実際にそれだけの人数を確保できている施設はどれだけあるでしょうか?
仮に1ユニット常勤5人・・・協力ユニットで常勤10人を確保できていたとしても、早番、遅番、夜勤など、ワンオペ・・・つまり職員が一人で10人をいっせいに見なければならない時間が発生します。
とうぜん、ご利用者は自立した人ばかりではなく、認知症の進んだ方、重度の身体介助を要する方など様々であり、一人で十分な手厚い介護をいつもどこでもできるわけではありません。
いっぽう、北欧の配置基準はというと、実際は日本の3倍、4倍の手厚さなのです。
そもそもいつつぶれてもおかしくない日本の介護保険に比べ、北欧は消費税率が25%などべらぼうに高いです。
そのかわり、医療費、学費も無料で、国が福祉に使っているお金そのものが違うのです。
だから日本よりもはるかに手厚い介護職員を配置できてもおかしくありません。そして職員の休暇もしっかり取れており、1年に1ヶ月以上の長期休暇をとることができると言われています。
配置だけでなく、職員の心の持ちようも違うんじゃないでしょうか?
ここまでの話をまとめると・・・
・北欧と日本では文化的な背景が違う
・北欧と日本では税率や職員の配置人数が違う
・日本が勝手に家庭的な雰囲気をケアに落とし込んでしまった
という感じです。
次の項からは、現状のユニットケア・・・介護の課題を改善するために、国や私達ができることは何かを考えてみたいと思います。
改善案① ユニットケアの理念を改めて見直し、本質を見極める
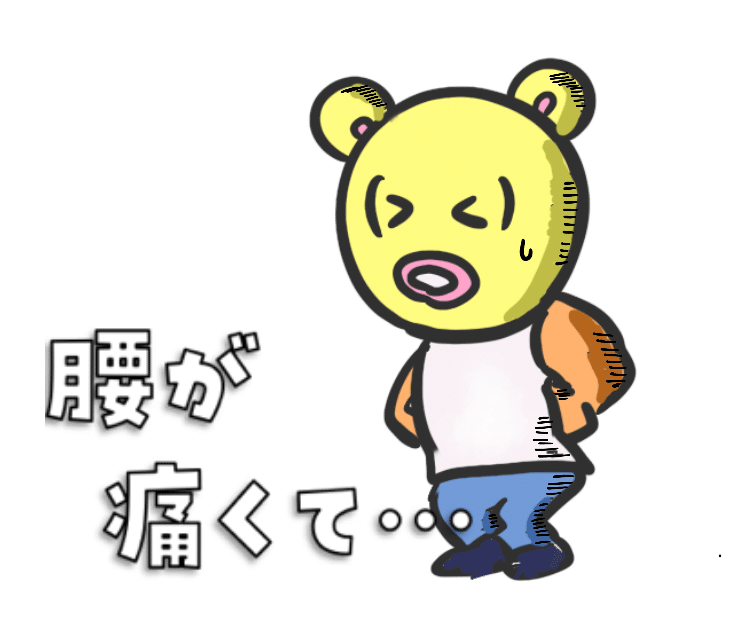
ユニット型施設というのは、一度作ったものを改築しない限り、基本的にはそのままです。
これから作られる施設を覗いて、施設のハードは変えることはほぼできませんから、ソフト面を変えるしかありません。
ユニットケアの理念の中に、『暮らしの継続』という言葉があり、ユニットケアを学ぶうえではまず誰もが知っていなければならない概念です。
介護施設に入っても、その人の暮らしを継続する・・・ということ。これ、大切かもしれません。
でも、この言葉、そっくり受け取ってしまうと、
「そんなの出来っこないよ。お風呂は週に何回かしか入れないし、家にいたときの生活とは違うんだよ」
このように思う職員が多いと思います。
ですが、大切なのは、生活様式を引き継ぐことではなくて、その人自身の人権を尊重することであると私は思います。
「長年、専業主婦をされていた方だから、ユニットに入居しても洗い物などをたくさんやってもらおう」
という考え方。やっぱり、これは職員の押し付けです。
そうではなくて、その人のニーズをきちんと聞き取るのです。本当にそのご利用者はそれをしたいのですか?・・ということを自問するのです。
もしかしたら、
「ワタシ、長年専業主婦で毎日家事ばかりしていたけど、夫と死別してるし、これからは自分の好きなことをやって趣味のある生活をしたいのよ」
こんなふうに思っている方もいるかもしれません。
ユニットケアの根本となる暮らしの継続は、その人自身の心の尊重、その人自身の継続であってほしいと私は願います。
そして、私もそのように介護をしてきました。これからもそのように努めます。
(ちなみにユニット特養では従来型特養のように、週2回入浴という規定はありませんし、あくまでご利用者が望むように入浴と示されています。しかし、仮に毎日入りたいというご利用者がいた場合、1ユニット5人の常勤配置でも不可能なレベルです)
改善案② 福祉医療の財源確保のため、増税、紙幣発行。

この、改善案②に関しては、私達個人ができることはほとんどなく、行政レベルでの取り組み案です。なので、ここは私個人の理想です、読み飛ばしてしまってもかまいません。
北欧を真似てユニットケアを作ったのなら、せめて真似できるところはもっと真似てほしいものです。
ひとつは福祉・医療にかける予算を増やすこと。
超高齢社会である日本において、今の介護保険はパンクすることは誰の目から見てもあきらかです。
手厚いケアを介護職員にさせたいのなら、それだけの資金を確保しなければなりません。
そうなると、真っ先に思い浮かぶのは消費税増税です。
しかし、増えた税収をそのまま医療福祉に当てられることを考えると、私たち介護職員以外の職種は、払う税金だけが増えてソンをすることになります。
北欧のように、介護以外の医療の負担をへらすなどの調整も必要となってきます。
第2に、インフレを覚悟して、大量の通貨を発行するとかです。
これに関しても、インフレになると困る職種がいるでしょう。ですが、介護職員と他の職業との給料差を縮めないことには、介護の仕事をしたいと思える職員も入りませんし、配置基準を増やすこともできません。
改善案③ 新規施設は従来型施設も建設する

新しくできる介護施設は、時代の流れから、圧倒的にユニット型施設や、個室型施設が多いです。
(厳密には、ユニット=個室でありません。私個人の意見は、現状のユニットケアには反対ですが、ご利用者のプライバシーが守られる個室には賛成です)
私は従来型施設からユニット型施設へと職場を変えた経験があり、最後の職場もユニット型特養でした。
その経験から、職員の配置人数や流れが全く違うことがわかります。
従来型しか経験したことのない介護職にとって、少人数=ラクという捉え方があるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
ユニットをこまかく分断し、少人数にすることにより、施設全体で見れば、各ユニットに必要な職員数・・・つまり一日に勤務が必要な職員数がユニットは多いのです。
そのためユニット型施設では、一人が欠けたら現場は火の車になります。定員10人のユニットで、入院者が5人いたとしても、残り5人のために必ず職員一人配置しなければなりません。
いっぽう、従来型はつぶしがききます。
職員一人あたりがいっぺんに見るご利用者の数は、ユニットは10人・・・それに比べて従来型はもっと多くなるはずです。
しかし、仮に職員一人が席を外しても、他の職員がフォローに入ってくれたり、協力ができます。
私個人の意見を言うと、全部一人でやらなければならないユニット型に対し、従来型は精神的負担は軽かったです。
そのかわり、夜勤はユニットのほうが負担が少なく感じましたが・・・。
以上、職員目線で従来型とユニットを比べてみましたが、日勤、夜勤の人数の違いなどにより、職員個人で意見がわかれます。
そこで施設内に、従来型居住区とユニット型居住区の両方を設けることを強くおすすめしたいです。
ご利用者にとっても、必ずしも個室を希望される方だけではありません。他の人と一緒にいるほうが安心するというご利用者・・・とくに女性が多いですが、確実にいるのです。
従来型特養とユニット型特養では料金体系も違います。資産の関係で四人部屋にしか入居できない方もいるはずです。生保の人とか特に。
ユニットケア・・・というイメージが先行して、それが介護の目指すべきところという洗脳がありましたが、職員やご利用者それぞれ、合う合わないがあります。
施設内で、職員の異動・協力・・・ができ、
施設内で、ご利用者の希望にそった居室形態を選択できる。
選択の余地を増やす意味でも、これから建設される特養は、あらためて従来型の良さを見直してみてほしいものです。
一方的にユニットケアを推進するより、よほど良いケアができると思います。
改善案④ 介護職から発信を!
信じられないことに、国は1ユニットご利用者15人あたりを認可しようとしています。
「え?1ユニット10名でもキツいのに・・・」
なぜ、こういう考え方が起こるのかと言うと、現場からの発信があまりにも少なすぎるために、トップ層の方々が現場の介護について理解をされていないからなのです。
配置基準を緩和して、ユニットを作りやすくしようという魂胆かもしれませんが、現場職員の負担が増えることなど、全く考えておりません。
そもそも、
「家庭的なケアをしよう」
「なじみの関係を作ろう」
と言っていたのに、配置基準だけを緩和するなんて、矛盾もいいとこです。
私の記事では結局最後にいつも同じようなことを書いていますが、やはりもっと現場の介護職は発信するべきだと思います。
国や同業者に伝えるためにも。
たとえば、『個別ケア』について。
私はこの記事でユニットケアに対する課題を取り上げてきましたが、すべてを批判するわけではありません。
過去に書いた記事を参照してほしいのですが、従来型の一律一斉の介護を辞めたら、圧倒的にラクになったこともあります。
↓↓↓<参照記事>↓↓↓
「自分達ががんばってもできなかったことは、きっと他の施設にも出来っこないよ」
こんなふうに思うのはナンセンス。
きっと私やあなたの施設よりも良いケアをしているところも、悪いケアをしているところもあるでしょう。
そのために、良いところ、できるところをもっと共有していけたら良いと思います。私はそのためにnoteで発信していきたいです。

このnoteのダッシュボードを見ていると分かることあります。
介護職の給料などについて取り上げた記事は、他の記事に比べかなり読まれています。
いっぽうで、こういったマニアックな記事はほとんど読まれませんし、いいねもつきません。
なので、そんな記事を、ここまで読んでくれている人は、私の記事を読んでいる中でも10%くらいしかいません。ふだんから熱意を持って仕事にあたっている方なのでしょう。
そんな仲間たちと、とにかく一緒に発信を続けていきたいと思います。
今日はユニットケアの話から、何だか飛躍しすぎてしまいました・・・。
それではまた。
著書『介護リーダーの『裏』教科書』
https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B091XPN678
発売中!
サポートですか・・・。人にお願いするまえに、自分が常に努力しなくては。
