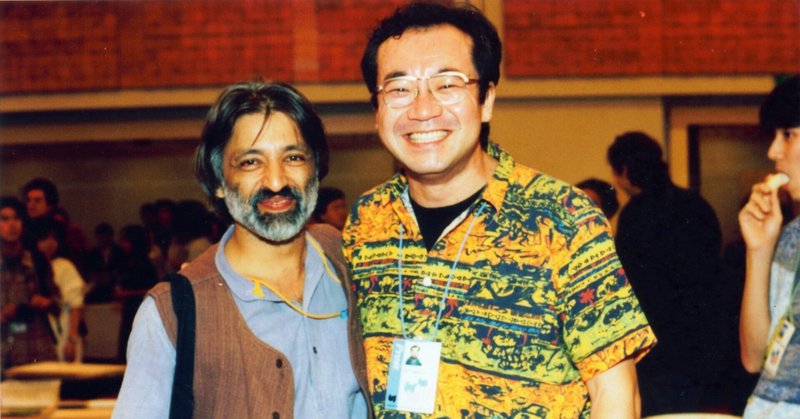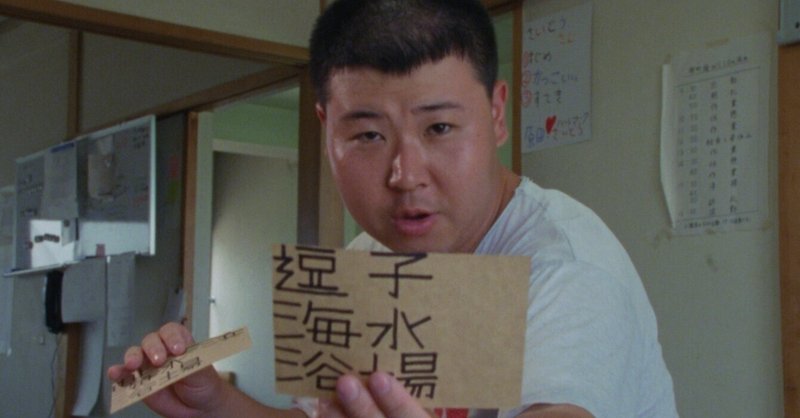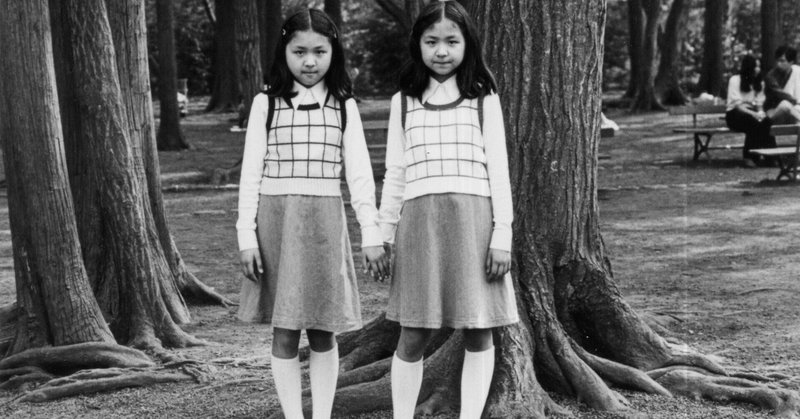最近の記事
マガジン
記事

佐藤さんの新しい映画を見ることはできない。でも、やかんの湯を沸かす囲炉裏の火が消えそうになったら、誰かがそこに薪をくべることならできる。 杉田協士(映画監督)
佐藤さんの新しい映画を見ることはできない。でも、やかんの湯を沸かす囲炉裏の火が消えそうになったら、誰かがそこに薪をくべることならできる。 いつでも泊まりに来なさいと声をかけられたように錯覚してしまう。 パレスチナ難民キャンプで、阿賀野川の流れる村で、佐藤真さんのチームが声をかけられたように、佐藤さんの映画からもそのような声が届きそうな気がしてしまう。 佐藤さんの新しい映画を見ることはできない。でも、やかんの湯を沸かす囲炉裏の火が消えそうになったら、誰かがそこに薪をくべること

無意識に持っている枠、既にある解りやすさに落とし込もうとするような軽率な手つき、考えの無さを見逃さなかった 飯岡幸子(撮影監督/『すべての夜を思いだす』『偶然と想像』)
佐藤さんは、生徒たちが撮ってきた映像に対して、こうしなさいああしなさいということを全く言わない人でした。 初めてカメラを持ったような私達が撮ってきた、振れていたりピントが外れていたり、そもそも何を撮っているのかすらよくわからないような映像を、どうやら佐藤さんは本気で見ていた。そして、撮った本人も気が付いていないようなその映像の面白さや美しさを見逃さず、同じように、撮り手やドキュメンタリーという形式が無意識に持っている枠、既にある解りやすさに落とし込もうとするような軽率な手つ