
【コラム】note1周年振り返り 釣りブログ(伸びる記事のコツ)
どうも、ぐっちあっきーです
釣りブログを始めて
note1周年振り返りと
筆者が考える
伸びる記事のコツを
筆者の1年間のnoteクリエイター
としての経験を元に
書いていこうと思います
よろしくお願いします
1.はじめに(1年間続けることができた理由)
①「書きたい!」という欲求があったから
筆者の釣りの「成功体験」と
「失敗体験」を伝えたい!
という思いで
「note記事を書く」
行動につながりました
② フォロワーさん(釣り関係)
投稿すると
「スキ!」を押していただける
フォロワーさんがいてくれたからこそ
PV数が伸びなくても
続けてこれたと思います
いつもありがとうございます
③ フォロワーさん(釣り関係以外)
結構筆者が目にしているのが
「マーケティング視点」
で記事を書かれる方です
筆者も
大学の経済学部を出てはいるものの
経済の方はきちんと勉強しなかったため
特にマーケティング
心理学・コーチングなどは
社会人になってから役立つことが多いです
「釣り視点」でも
「ブログ執筆視点」でも
とても参考になることが多いです
④ PV数
とはいうものの
やはりPV数は気になるもの
時間をかけて
執筆した記事のPV数が
伸びると素直に嬉しいですね
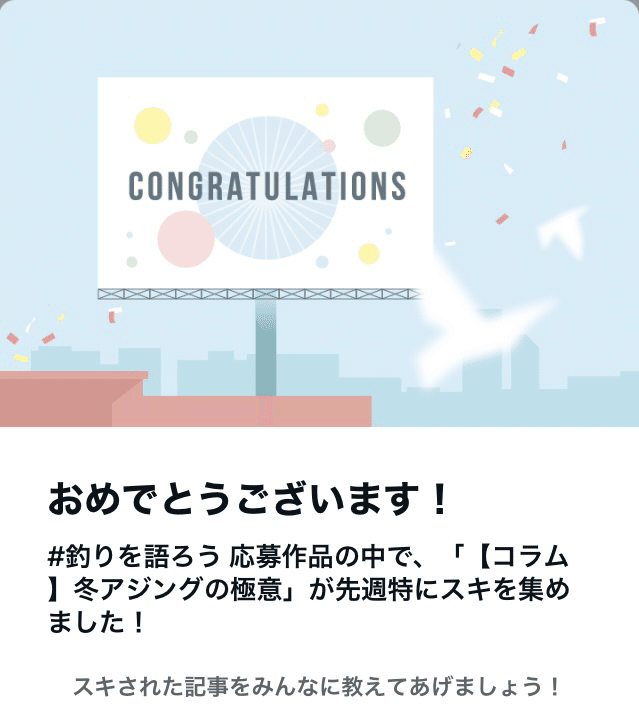
こういう評価をいただけるのは
素直に嬉しいし
クリエイターとして
モチベーションアップに
繋がります
⑤外部検索で上位
外部検索(Google)
で上位にヒットするということは
noteに登録されている方だけでなく
検索してわざわざ見ていただいている
(ニーズがある)
ということになります
クリエイターとして
こんなに嬉しいことはありません
⑥ SNS(インスタ、X、ディスコード、アングラーズ)
SNSでいわゆる記事の
宣伝もしているのですが
「こういう記事を書いてほしい」
という反響もいただきます
市場調査のツールですね
⑦ 記事のアイデアが枯渇しなかったから
地味に大きいと思いますが
ネタがないと創作意欲もわきません
「ネタ作りのために釣りに行く」
という方もいらっしゃいますが
筆者は
釣りに行く目的と
伝える手段は
ブレずに持っておこうと考えています
ニーズ(読者に必要とされること)
シーズ(クリエイターが書きたいこと)
をすり合わせていく作業も大切
⑧釣りに行けたから
そもそもですが
釣りに行けたから
アイデアが枯渇しなかったとも
いえます
当たり前だけど
当たり前じゃないので
あえて列挙しておきます
感謝ですね
⑨形にはめることができたから
筆者は
「釣果情報」
(毎週金~日曜日:週末)
①釣果
②実釣解説
③考察
④フィールド情報
⑤タックルデータ
と
「コラム」(釣りの考察)
(3か月に数回、または不定期)
に分けて執筆していますが
釣果情報の方は
書式というかあらかじめ
ワードで下書きを作っているので
データの方は
タイドグラフの
数字を打ち込んでいくだけなので
作業自体が苦痛でないです
スキマ時間に
実釣解説、考察を
スマホで書いています
執筆に取っかかりにくいと
モチベ低下になりかねません
投稿頻度が多すぎても
書く側も見る側もしんどくなるし
投稿頻度が少なすぎても
なかなか見てもらえないので
クリエイターの負担にならない
生活習慣に合った
投稿頻度を見つけるのも
大事だと思います
2.有料記事にしない理由
①読者さん側の理由
筆者のコンセプトが
「初~中級者向けに
釣りから学べる考え方を解説」
なので
「外部検索から来られた方が
見られなくなるから」です
今のやり方で
今のアカウントは継続予定です
(広告はつけるかも)
「クリエイターは相応の
対価(収益)を得るべき」
との意見もあるかと思いますが
もし収益化するなら
・別アカウント、または、釣り以外
・別媒体(YouTubeなど)
でやろうかと考えています
②クリエイター側の理由(無料で記事を書くと釣りがうまくなる!?)
→「ちょっと言っている
意味が分からない」
と思われるかもですが
有料記事で軌道に乗れば
いいかもしれませんが
今の筆者のPV数では
有料記事にすると
PV数が激減すると思います
釣りに行って
「考えて」
魚を釣り
「考えたこと」を言語化し
note記事を書き
投稿し
反響をもらう
この思考の言語化
は釣りのプロに
教えてもらうだけでは
できないし
お金を払っても得られない
魚が釣れるアドバンテージ
これは筆者にとって
かけがえのない「財産」だと
感じています
明らかに
noteを始める前(SNSの9年間)と
後(noteの1年間)では
後の方が
「釣りがうまくなった」
「論理的に釣れるようになった」
のです
3.note1周年振り返り
① 自己紹介
2023年5月中旬に初投稿しました
そこからいくつか「コラム」も執筆
② 実釣解説初回はチニングからスタート
気合を入れて
ホワイトボードで
図を書きながら解説
ナイロンラインでチニング
というアイデアも良かったのか
筆者のPV数では上位です
③ ライトゲームと語るも…
シーズン的に6~9月は
ライトゲームが厳しく
(釣れないわけではない)
チニング、シーバスを優先したため
そちらの投稿頻度が多くなりました
筆者は軽量ルアー(~14g)
を使うことがほとんどですが
皆さんが考える
ライトゲーム像からは
少しズレていたかもしれません…
④ アジング投稿頻度が増える
10月以降は
アジング投稿が増えました
筆者は元々
アジングが本職みたいな所がありますし
釣果も伴ったので
PV数が少しずつ伸びていきました
⑤ 総集編(まとめ)
年末に総集編を執筆したのですが
「まとめ」というタイトルが
分かりやすいのか
PV数は高かったです
⑥ 産卵期アジングの極意(アプローチ編)でプチバズり
1日で4200PV!
5000PVを超える
ダントツ1位の
PV数になりました
(分析は後述)
⑦釣りに関連したコラム
アイデアが枯渇してくると
どうしても「インプレ」
になりがちですが
筆者はnoteを始めて
こういう柔軟性のある
ことも書けるように
なったんだなーと感じています
⑧大台の1万ビュー達成!
noteを始めて10ヵ月
大台の1万ビューを
達成することができました
⑨初のコングラボード選出!
その後は
記事のビュー数も増えるようになり
2万ビューなどあっという間でしたね
1万ビューを超えると
noteオススメに
載りやすくなったのかもしれません
4.自己分析
① ライトゲーム(特にアジング)は強い
体感だと人気度は
アジング
>メバリング
>シーバス
>チニング
>その他
って感じです
② 釣果情報(爆釣)よりコラムが人気
これは分かりやすいのですが
「ツ抜け」とか
「ランカーシーバス」とか
いう見出しは
極端にPV数やスキ!が少ないです
「場所がいいから釣れたのでは?」
と聞こえてきそうな気がします(^^;
筆者的には
いい場所・タイミングを見つけるのも
釣りのスキルの1つと考えているのですが…
前向きに考えるとするならば
爆釣よりも
「どうやって釣ったのか」
または
「どういう場所・タイミングを
選んだのか」
教えてほしいということだと思います
筆者のコラムの書きがいがあります
③ マニアックな記事が後々ウケる
「言葉でなかなか説明
できないんだけど・・・」
というような
マニアックな内容を
筆者の経験を前面に出しつつも
多方面から書いてみた
というような記事です
X転載から来られている方が
多く、後日伸びたので
他の方があまり書かないような
記事が意外とウケたりするのも
「noteっておもしろいなー」
と感じます
5.伸びる記事のコツ
産卵期アジングの極意
(アプローチ編)
が顕著で分かりやすいのですが
Note公式「記事まとめ」
に掲載されること
(お墨付きをもらう)
→公式に拡散してもらうことにより
フォロワーさんだけでなく
多くのnoteクリエイターに
見てもらいやすくなる
外部検索で上位にヒットしやすくなる

お墨付きをもらうためには…
① クリエイター、オリジナルの記事であること
パクリでないことです
② 引用、主従関係をはっきりさせる
どれがクリエイターが
書いた文章なのか
明確にする
クリエイターの文章が(主)
引用が(従)
引用元を記載する
論文の書き方と同じですね
③ テーマ、ハッシュタグに沿った内容であること
公式さんも
ハッシュタグは
「2~4個に選んでみよう」
と言っているので
ハッシュタグ選びは
大事だと思います
④ 公序良俗に反しないこと
公式のお墨付きをもらうわけなので
あまりカチコチな文書も
どうかと思いますが
(批判はしても)
「誹謗中傷はしない」
これは当たり前ですね
⑤ 執筆の動機を書くこと
筆者が最近意識するように
なったのがこれ
釣りなら
「メーカーの宣伝文を
書いているだけなのでは?」
と言われないためにも
クリエイター個人の
執筆動機をしっかりと
書いておくことは大事
だと思います
⑥ 筆者の思い(熱意)を書くこと
コピペの文章か否かは
思い(主観)が入っているか
どうかも大事だと思います
6.今後に向けて
① 読みやすい工夫をする
記事を読みやすいかどうかは
リピーターを増やす上では
とても大事です
②タイトル、テーマから脱線しない
筆者もはじめの頃
かなりやりがちでしたが
書きたいことが多すぎて
脱線しすぎてしまうパターンです…
(用語の解説は必要かと思いますが)
そういう意味でも下書きは大事ですね
③目次
目次を入れることで
記事の全体像が分かりやすくなり
見たい部分だけ
クリックすれば
飛ぶこともできます
④段落(文節)
筆者が意識するようになったのが
スマホ(読者)です
(before)
以前は、PC(ワード)で作成していたこともあり、このような文章を書いていました。
(after)
以前は
PC(ワード)で
作成していたこともあり
このような文章を書いていました
PCで見るなら問題ありませんが
(before)文章はスマホで見る時読みにくいです
筆者は
(主語)
(動詞)
を見やすく
文節で段落分け
なるべく
句読点
「、」
「。」
を入れない
投稿前に
スマホで
プレビューで
確認する
ことをやっています
⑤文字数
スマホ視聴が多いということは
文字数が多いと苦痛になってきます
筆者は
「コラム」は3000~4000字
ガッツリ書きますが
「釣果情報」は
データの部分を抜いても
1000字以内で書く
ようにしています
⑥引用(動画、サイト)
引用は
動画だと
データ容量を気にされる方が
いると思うので
あまり載せません
サイトも
信用あるサイトを
引用させてもらっていますが
「あくまで参考にしてね」
のスタンスで載せています
どちらかというと
自分の過去の記事を載せて
「この話はここで書いています」
のやり方が多いですね
⑦写真、図
ずっと文章でも飽きてしまうし
文章だけで説明だと
分かりにくい部分もあるので
可能であれば
途中に
写真や図を適度に
挿入するようにしています
⑧専門用語の解説
釣りに関しては
難しい所なのですが
専門用語が分からないと
文章が分からない
でも
専門用語の説明の説明だと
文章がくどくなってしまう…
バランスが大事だと思います
⑨ ターゲット(読者層)に向けた発信
筆者の読者層は
釣り(中級者)がメイン
だと感じています
(外部検索で来られるから)
釣りプロ、テスターの方にも
見ていただいているようなのですが
基本的に
初心者、上級者の方は
外部検索してまでは来られない
あと普段「釣りアカウント」は
作っていないけれど
「釣りに興味がある」
という方にも
見ていただいているようなので
(クリエイター冥利につきます)
専門性も交えつつ
親しみやすさ
読みやすさ
も入れていけたらと思います
⑩他者との差別化(キーワード)
釣果情報のアイデアは
他の方でもできるので
模倣の可能性がありますが…
他者との差別化
筆者の場合は
「再現性」(アジング)
ある意味これには
絶対の自信があるから
「コラム」が書けるとも言えます
7.まとめ
他の方の記事もですが
やっぱりおもしろい記事って
時間を忘れて夢中で読んでしまいます
その理屈を色々と書いてきましたが
つまるところ
①記事がおもしろいかどうか
(読者側)
②執筆側が書いていて楽しいかどうか
(クリエイター側)
→そういうのは読む側に伝わります
この2点だと思います
この2点の相互循環が
良い記事を生み
クリエイターのモチベーション
につながると思うのです
また
思考の言語化
「再現性」
「考えて」釣りをし
「考えたこと」を
noteに言語化することで
「釣りがうまくなる」
「論理的に釣りができる」
これは筆者にとって「財産」です
釣果情報がPV数が伸びなくても
アイデアは日々の釣りに
詰まっているので
釣果情報⇔コラム
の好循環、バランスを
大事にしたいです
釣果情報でも
意図して書いていますが
魚が釣れるまでの過程
「釣りの臨場感」
これは釣りならではです
この体験
少年のような
「わくわく感」を
これからも言語化していきたいです
最後まで読んでいただき
ありがとうございました
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
