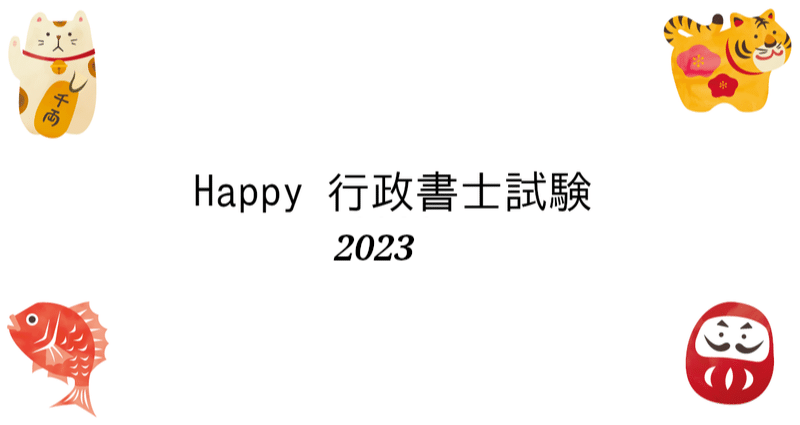
- 運営しているクリエイター
2024年6月の記事一覧
財政法(あくまでも一般知識なので深追いしません)
第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
はい。
一応国会の議決とかはちゃんとやってるのでしょうが、、、、、、
アベノミクスとかでの日銀による国債買い入れ、できれば避けたいもの、ってことになってます(例外規定の方を
行政書士試験日等(予定)
一応、今年(令和6年度)の試験日等の予定は発表されてましたね。
試験の公示:令和6年7月8日(月)
なので、きちんとした公示は7月8日。
受験願書・試験案内の配布:令和6年7月29日(月)~8月30日(金)
受験手数料:10,400円
受験申込受付期間
郵送申込み:令和6年7月29日(月)~8月30日(金)消印有効
インターネット申込み:令和6年7月29日(月)午前9時~8月27日(
会社法とライブドア事件
会社法の復習をしてます。
一般知識的なこと(2000年以降の法改正の年表見たりとか)と、基礎法学の融合みたいな感じになってますけどね。
なるほど、ってのが、ライブドア事件があった近辺で会社法整備がはじまっていて、事件後に法律が成立。
(リーマンショック直前期です)
なるほどねぇ、ってこと。
(これ、なんの役に立つの?と言われても困るけど。私なりの記憶の整理です)
金融商品とか、無茶苦茶な売り
民法改正点(試験対策なので、他のところもいじられてる可能性はあり。試験にしぼって書きます)
親権、結婚に関して微妙に改正点があります。
(女性の再婚禁止期間やら、親権での懲戒権とかがかわっております)
詳細な内容は、参考書等をご参照ください。
(YouTube等でも解説動画もあるでしょうし、学校とか行ってる人はそちらでご質問をお願いいたします<m(__)m>。あたしゃ、ただの受験生ですので)
法律上の事務管理:民法
先日、草ボーボーの在宅者がいる家のことを書きました。
んで、基本的に「不在者家屋等の事務管理」ってところが民法における規定。
(例外的に、行政介入ができる場合もあります。条例やなんかがある地域とかが例ですね。他にも国としての法律もあるでしょう、空き家とかはね←こっちはまだ詰め切ってません。)
んで、法律上(民法上)の事務管理。
社会生活上の共助主義を鑑みて、居住者が旅行に行ってる場合とかの修
委任、代理、使者(行政書士試験の横断)
あ、なるほど、ってお話。
今年の行政書士試験のためのライブスタディで、行政書士法の講義を受けたときの質問で出たこと(講師はそれにふれなかったので、今になって再学習してます)。
「行政書士ができる最大の独占業務は、官公庁に提出する書類の代理作成」
(一部例外あり。弁護士、税理士、弁理士、その他の士業の独占業務の場合もあるので、そこはそちらに任せることになります)
で
「提出は独占業務ではない」

