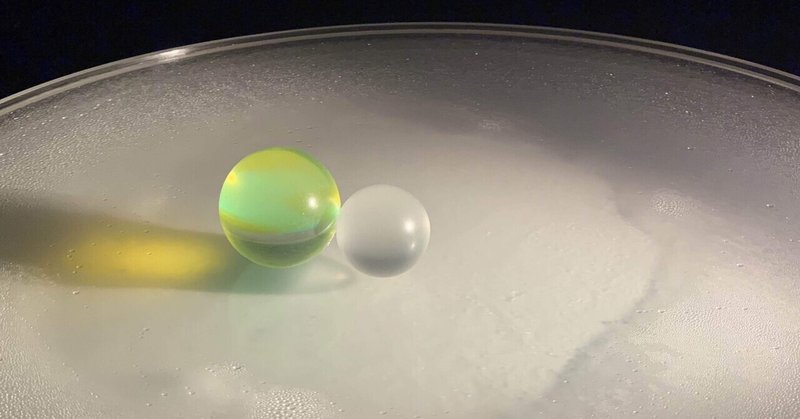
双極性障害:私が病気をオープンにする理由
初めて「双極性障害」の診断が下りたのは2023年10月18日。
私はそのわずか3日後にInstagramで自分が双極性障害と診断されたこと、それがどのような病気なのかということ、そして「この病気を抱えながらも必ず建築士試験に合格したい」という内容の投稿を公開した。
私のInstagramは家族や親戚、過去や現在の同僚、友人らが見ている。
当時はまだ病気を受け入れる心の余裕なんか全く無く、絶望しかなかった。
今でも病気を完全には受け入れられてない気もするが…。
それでも公開しようと思ったのにはいくつか理由がある。
まずは単純にその方が自分らしいと思ったからだ。
私は基本的に隠し事が苦手でそれが苦痛になるタイプだ。
双極性障害は完治しないので隠すとなると一生隠し続けることになる。
それは私にとってかなり苦しい。
鬱の時に同僚から「なんか調子悪そうだけどどうしたの?」と仮に聞かれたとして「今鬱なんですよ」と言わないとしたら何と言えばいいだろうと考えると、考えるだけでけっこう面倒くさい。
そして私はあらゆる差別に反対で、偏見も出来る限り持たない人間でいたいと思春期の頃から思っていた。
これは大好きで尊敬していた叔父の影響もあるし、フランスでの留学を経験して自分がその国の「外国人(マイノリティ)」として生活することを通して得た価値観・考え方でもある。
自分が双極性障害という精神疾患持ちであることを知って差別する人や離れていく人がいれば、それは私にとってむしろ都合が良いと思った。
「ああ、あなたはそういう人だったのね」と早く分かれば良いと思った。
でもこれに関してはラッキーなことに誰もそんな人は周りにいなく、むしろ温かい励ましの言葉をくれる人がいたくらいだった。
私の世界は平和らしい。
幸運なことだ。
そして最後に。
双極性障害になってみて感じたことは、この病気が一般的に認知されていなさすぎて生きにくいということ。
生きにくさというのは例えば
「早く治るといいですね」と言われたりね。
双極性障害は完治しないのでそう言われてもモヤっとしたりなんとなく悲しくなったりするのだ。
自分にも言えることだけど、人は無知であればあるほど人を傷つけてしまう。
その人が「双極性障害は完治しない病気だ」と分かっていれば「早く治るといいですね」とは言わないだろう。
「早く落ち着くといいですね」とか、
「寛解するといいですね」とか、言葉を選ぶだろう。
「双極性障害は脳の病気であり、精神的な病気の中でも最も身体的な病気に近い」と知っていれば、
「薬に頼るのは良くないよ」なんてアドバイスも「ストレス発散や気分転換や癒しの為に旅行してみたら?散歩してみたら?」なんてアドバイスもしてこないだろう。
私は対面でも自分が双極性障害であることを軽い感じで言うことがよくあるが驚くくらい皆んな知らない。
知ってるのは医療関係者くらい。
鬱病はかなり知られてるし統合失調症も知られているのに、双極性障害は認知度が低すぎると思った。
昔「躁うつ病」と呼ばれていたせいもあって余計に理解されていないし誤解されていると感じる。
そりゃみんな「鬱病と似てるんでしょ?」と思うよね。
実際は原因も治療法も薬も違うのに。
「双極性障害です。いわゆる躁うつです」と言ってるのに「うちの母も同じ病気でね、」って話を展開され、よくよく聞いているうちに「それ躁うつじゃなくてうつ病じゃん!」という事もあった。
このモヤモヤ感。
そんなモヤモヤが嫌で嫌で、私は「せめてうつ病と双極性障害の違いくらいは認知されたらいいな」と思い、話せるシチュエーションでは「この2つの病気は別物」ということをいちいち説明している。
たった1人でやってるから微力だけど。
面倒くさいけど。
それでも自分の周りのよく関わる人たち、自分の生きる生活圏内くらいは居心地良くしたいと思ってやっている。
私はこれ以上モヤモヤしたくないし、傷付くのも嫌なのだ。
誰も憎めないからこそ余計にね。
それに、この病気の認知度が高まることによってこの病気を抱える人たちのモヤモヤや傷付く機会が減るメリットもある。小さなことかもしれないけど。
そういえばこの街のけっこう大きな書店で興味本位で精神医学のコーナーを除いたことがあるが、こちらもうつ病と統合失調症の本ばかりで双極性障害に関する本はほぼ無かった。
マジかよ、と思い「わぉ笑」
と、1人で声に出して呟いた記憶がある。
「100人に1人かかる病気のはずなのになぁ」
と思いつつ、その日は店を出た。
10年後くらいには変わってるのかなぁ。
変わってて欲しいなぁ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
