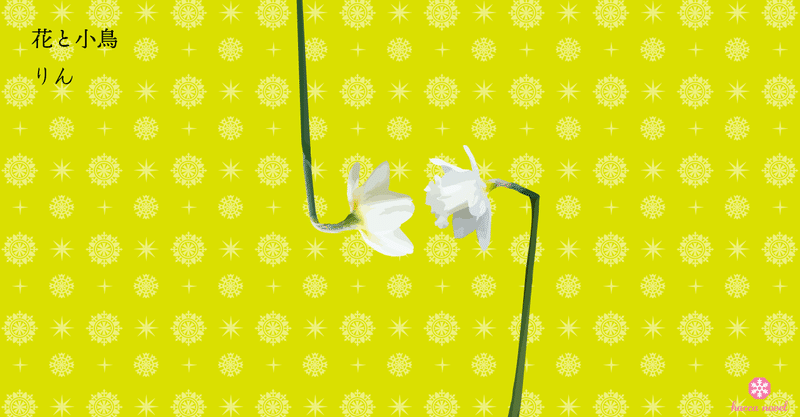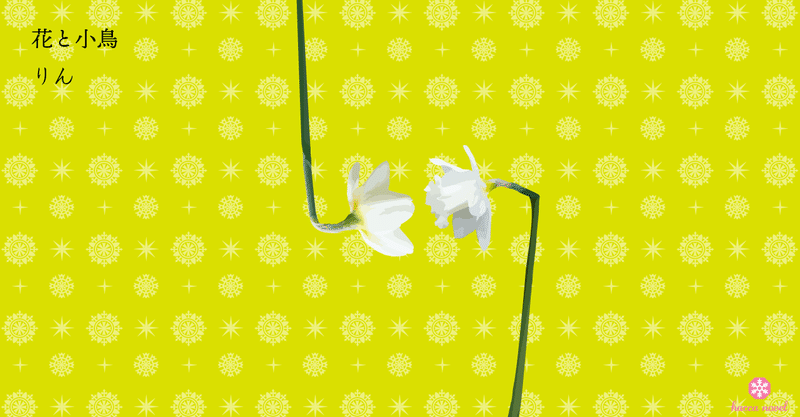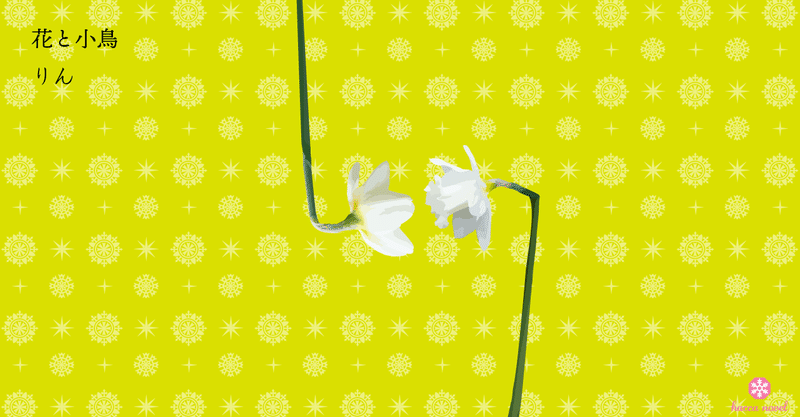記事一覧
すばらしい日々《6》
時計を見る。時刻は十八時半。みどりの予約した新幹線は十九時発。ここから鷺沢高校までの距離は三キロほどある。今出発したら確実に間に合わないだろう。
席を立ったところで私たちがためらっていると、見透かしたように関さんが言った。
「私ん家泊っていったらええよ」
それからまた母親のように続ける。
「もう暗いし気いつけて。何かあったら連絡して」
そう言って朝と同じように送り出してくれた。私たちはふりだし
すばらしい日々《5》
喫茶セキのドアノブにはクローズの札がかけてあった。店内は暗く、明かりの灯ったカウンターが劇場の舞台のようだった。そこで関さんがまるでなにかの役割を演じるように静かにカップを拭いている。彼女は私たちの姿を認めると「おかえり」と微笑んだ。私たちの表情から察したのか、旅がどうだったかは訊かれなかった。
「関さん、ちょっとだけ休ませてほしい。くるみと話したいんだ」
みどりの一言に心臓が跳ね上がる。
「え
すばらしい日々《4》
私たちは南に下り出町柳駅近くのパン屋に立ち寄った。そこはいかにも街のパン屋という質素な佇まいで、パン自体も素朴なものが多かった。種類は豊富、しかもどれも安価で、あさひがお気に入りだというのもよく分かった。
ふとたっぷりのクリームにみかんが埋め込まれたフルーツサンドが目に留まる。瑞々しいみかんに惹かれて手を伸ばそうとすると
「くるみパンだって! くるみのパンだよ」
みどりがそう言って、焦げ茶のぽっ
すばらしい日々《3》
私たちはただ右と左の脚を交互に出して漕いでいく。それは単純だけれど気持ちの良いことだった。
松原通を東へ進み鴨川を越える。松原橋を吹き抜ける風は冷たいけれど、どこかに春の気配を隠していた。ユニコーン後期の民生を真似たのだという、みどりの毛先がたっぷりとしたボブが揺れている。あと一週間が過ぎ四月になれば、京都は人で溢れる。静かな街はやがてくるその日を待ち望んでいるようだった。
「そろそろ左に曲がら
すばらしい日々《2》
パタパタとリノリウムの廊下を打つ足音が聞こえる。これはみどりの足音だ。みんなより少し速めなのに、せかせかした印象を受けないのが不思議だ。名は体を表すとはいうけれど、足音もその人の性質を表すと私は思う。足音が部屋の前で止まる。古ぼけた木戸がトントンと鳴り、返事をする間もなく開かれた。
「こんにちは、みかんだよ」
みかんを二つ、目元にあてたみどりがひょっこり顔を出した。
「なんかもっとひねったこ
すばらしい日々《1》
二〇〇九年一月五日。
寒い、寒い、寒い。京都の冬はどうしてこんなにも寒いのだろう。盆地だから、市内を鴨川が走っているから、琵琶湖ほどの水を地下に湛えているから。いろんな理由を聞いてきたけれど、私は思う。年頃なのに恋人の一人もいない学生たちのそこはかとない寂しさがこの街を覆っているからではないかと。葵橋西詰をさらに西へ入ったところにぽつねんと佇む簡素な学生アパートの一室で、私はそのような答えに至った