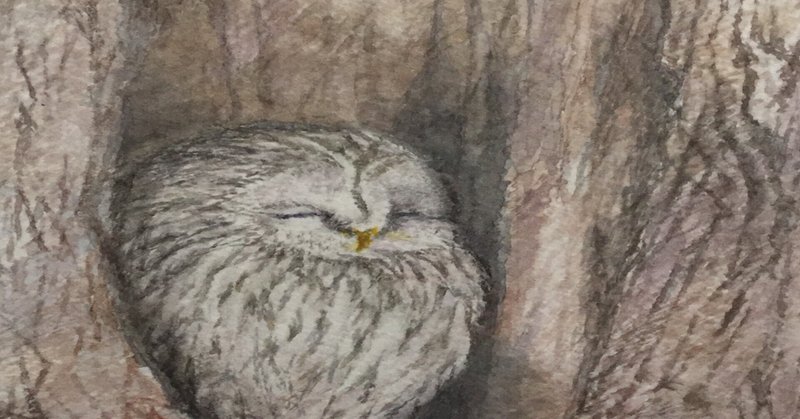
幸田露伴の評論「貧富幸不幸」
貧富幸不幸
もし、真の意味で言えば、貧と富は幸福と不幸とに対して直接には関係するところは無い。貧でも幸福で有り得、また不幸で有り得、富でも不幸で有り得、また幸福で有り得るからである。しかし世の中の普通の立場で言えば貧ということは不幸を意味し、富ということは幸福を意味することになって、貧富は幸不幸に関係するものとなっている。貧は不自由と少能力の顕れであり、富は自由と多能力の顕れであるからであり、また実際に於いて世の人の多数は、体験上に貧即ち不幸、富即ち幸福の感じを繰り返すことの少なくない記憶からそう認めて居るのである。
理屈は付け方次第のものである。感じは変移不定のものである。どちらも余り当てにはならない。貧富を幸不幸から引き離して仕舞うというのも、理屈はとにかく余り納得する人はあるまい。しかし貧富を幸不幸に関係させようするのもそんなに面白い見解ではない、俗過ぎる。
釈迦の弟子の中で優れた者が二人あった。その一人は富家の出であった。そしてその男は富者を憐れんだ、それは富者を可哀そうだと本当に感じていたからで、そこで済度(さいど・救い)の善い因縁を造り出すために、その男は貧者をそのままにして、富者だけに接して、これを善導しようと、托鉢は富者の家の前にだけ立った。他の一人は貧家の出というほどではないが貧者を憐み、真実貧者を幸福にしたいと思った。そこで自分の托鉢は貧者の家だけを選んで立って、伝道化度の好因縁を造ろうとした。富貴の家は顧み無かった。二人とも道理のある考えであり、美しい感情の流露であった。しかし釈迦は二人を叱った。それは傾くこと無く平らかに、私無く公(おおやけ)に、貧富を思わずに平等に化度するが善いという意(おもい)によってであった。これは勿論尤もなことで、人天の導師・一代の教主である以上はこうで無くてはならない筈である。釈迦の親族で勿論高貴の家柄で、そして二十相好を具備したと云われる美男で、かつ心の優しい、しかも道に進む望みを有して釈迦の弟子となっていた阿難(あなん)は、このことを目撃して、成程貧富を平等に見なければいけないと考えたので、どんな家にも選ぶこと無く接近した。ところで阿難はまだ前の二人の弟子にも劣っている境地の身であった。ただその行為のみ釈迦の言葉を実践したのだった。そこで偶然にも最も低い階級の家を訪れると、忽ちそこの家の女に惚れられて仕舞った。貧富の前で大手を振って歩いたのはよいが、恋という変なものに攻撃されたので、鉛の獅子が炎火に逢ったように忽ちグニャリとなって仕舞って、捕虜にされて危うく自分を失いかねないことになった。この魔鄧女(まとうじょ)因縁の話は面白いことを現わしている。貧富などということは恋の烈火の前には一片の塵程度のものなのだ。
それはさておき、貧者は多い。富者は少ない。貧のために嘆き悲しみ怨み怒る。甚だしくは自殺・殺人に至る者もある。であれば、同じ事なら貧のために何か言ったり考えたり行ったりした方が面白い。少なくとも多くの人は貧乏が大嫌いで、その嫌いなものが付き纏って来るので困苦しているのだから、貧即不幸などという迷信ぐらいは除却したいものだ。しかし自分も貧乏が大好きとも云いかねる。貧乏神の渋団扇(しぶうちわ)で煽がれて震えながら、アア涼しいと顎をなでるほど納まりかえっている訳にも行かない。また多くの人に対して貧乏宗の宣伝を試みるような料簡も無い。ただ貧の為に、貧即不幸と決めている人があったら、その妄心を妄心だとして排除したい。
貧乏は嫌がるから辛(つら)いので、辛いから不幸を感じるのだ。渋いものや苦いものを嫌がる人は多い。しかし嫌がらなければならないと定まった訳でも無い。嫌がらない人になれば銭を捨てて渋ウルカを買って食べて喜んでいる。フキノトウを温灰焼(ぬくばいやき)にして食えば苦いに違いない。しかし中々うまい味だ。甘いものを好む人が多いには相違ない。しかしサツマイモなどは、嫌がる人になれば随分恐ろしい刑罰ぐらいに思う者もある。ウジの生じているものは食いたがらない人が多い。しかしチーズを嗜む者は誰がウジを嫌がろう。蜂の卵を食うのはウジそのものを食うのだが、嫌がらない人などは高い価を払ったり、または蜂に刺されながらその品を得て喜んでいる。魚や鳥獣の肉は、人々皆その新鮮なのを自分等は食していると思っている。そして少しも嫌がっていないのであるが、何を知ろう、新鮮な肉を提供すれば、この魚は寄生虫がいると云ってカツオやブリを人々は避けるであろうし、この鶏肉は硬い、この牛肉は硬いと云って人々は喜ばないだろう。人々はやや古いカツオやブリや鶏肉牛肉を嫌がらないで、実際は自分等の嫌がらない程度のやや古い魚鳥獣肉を新鮮と名付けているのである。タバコを嫌わない動物は少ない。人間も初めて喫煙する時は咳をしたり涙をこぼしたりクラクラしたりしない者は少ない。しかし嫌がらない段になると驚くほど消費をして、獅子の香炉のように鼻の孔から白い煙を吐いて、こればかりはやめられないなどと喜んでいる。自分の今までを回顧してみれば。自分の最も喫緊事である食物において、その好悪の変化推移を驚かない者は無いだろう。初めは誰でもが甘いものを好み、次第に成長するにしたがい、砂糖の多い物即ち美味とするような幼稚な境地を脱して、甘味即美味の誤りを不知不識(しらずしらず)の間に会得し、また幼稚期において嫌がっていた多くの物に嘆美すべき真の美味が有ることを認めるようになるであろう。
嫌がる嫌がらないというのは主観である。そしてこの主観はただその時においてのみ真である。他の時においては真で無くなるのは争えない事実である。しかし長期にわたり多数の人に於いて同様ならば、堅固不動なもののように見え、習慣的惰力を生じるのも、また争えない事実である。貧を嫌がり、その嫌な貧に付き纏われ勝なところから、貧即不幸と感じるのもこの理屈によるのである。が、貧と不幸とは必ずしも徹頭徹尾切り離すことが出来ない関係にあるものではない。甘味即美味とする幼稚の味覚と、富即幸福とする多数人の考えとは、事情が甚だよく似ているのである。その事実を云えば、貧でも幸福があり得、富んでも不幸があることは、少しく世相を看破した人であれば誰もが認知していることである。このことは、例えば砂糖の有無や多少が必ずしも美味不美味に比例しないのと同様なのである。多数の主婦が砂糖や味醂の崇拝と妄用によって却って真の美味を害するのと同様に、多数の人々は富を崇拝し貧を嫌うことによって、却って真の幸福を自損している。貧を嫌がり富を喜ぶ念を今少し緩くするか、もしくはこれを放下しさえすれば、幸福は生じ、もしくは幸福になり得るものを、貧即不幸の俗見に囚われることの甚だしいために、却って幸福を失っていることが甚だ多い。貧即幸福と云っては極端になるが、貧を厭う念さえ忘れれば即座に幸福になり得るものを、貧を厭う念に駆られて悶々戚々としている者の甚だ多いのは、その人のために痛惜に堪えない。人は皆、原憲・顔回(共に孔子の弟子)のようになれというのでは無いが、あばら屋に住ん貧しい食事をしていても、幸福はあり得るものと会得出来て確信すれば、貧もそれほど嫌わなくてもよいのは明らかである。原憲・顔回の境地に至らなくても、遊外老人位でさえ、「貧は人を苦しめず、人貧に苦しむ」という句を吐いている。老人は貧の人を苦しめないことを知って幸福に朝暮を送り得たのである。語り物によれば、貧乏で名高い曽我の若殿に愛を捧げた美人も「貧の病は苦にならず、ほかの病の無かれかし」と喝破している。いい女だ、洒落ている。意気愛すべしだ。勿論恋愛というものは桂馬という将棋の駒がどのような他の駒の威厳をも無視して動くように、幽奇神奇の働きをするものだから、恋愛に憑かれた者は随分な俗物でも貧富位は容易に突破超越してしまうのであり、貧即不幸などと云う妄見はその霊光によって照破してしまうのである。里謡に「竹の柱に茅の檐(のき)」と唄うのも、「手鍋提げても」と唄うのも、貧即不幸の妄見を照破している手近い例だ。しかし貧乏嫌いの女房となると、亭主に対して「ほかの病気は苦でないが、貧乏の病気になって呉れるな」と願う。金運の無い夫を見ると、生命保険に入っていれば卒中で死んでもらった方が都合よいくらいに思わないことも無いかも知れない。それも中々洒落ているかも知れない。そこで亭主も富即幸福の宗門に帰依してしまう。しかし富には成り難い。即ち大抵は幸福を感じられずに、埋め地の足しにもならないアスガラ(アスファルトの殻)になってしまうのである。いよいよ面白くない事だ。むしろ貧富と幸不幸は比例するという妄見を脱却して、貧乏でも幸福だという見方をして、温灰払うウルメイワシ一枚を二人で飯のおかずにしても、清く面白く暮らした方が端的に美的生活即ち幸福生活である。「細工人は一生貧乏だと覚悟して」と云った彫金家の土屋安親の生活は幸福だっただろうと思われる。明治の某彫金家は富んだ」、しかしその生活は美的で幸福であったとも思われない。
貧即不幸の宗門者は、ともすれば食えなくては堪らないと説く、恋しさとひもじさを比べれば、ひもじさが身に沁みるという歌がある。また「死ぬほど惚れても貧乏人はいやだ、出来りゃ吾が児が寒晒し」などという里謡もある。何れも半面の真を表しているが全くの真では無い。半分は嘘だ。安心して善い、身を投げて死のうとしても大抵は死ねない世である。「肩あれば着ないことなく、口あれば食わないこと無し」という古語の通りで、肩が無くならない限り、口が無くならない限りは、飢寒で死ぬことは少ない。ロシアのような狂妄陋悪な思想や感情が行われる国情であれば飢餓で死ぬ人も沢山出るであろうが、そうでない限りは貧乏は生命と関係しないものだ。貧乏を嫌がる強迫観念の強烈なものに囚われた者だけが生命に別状を起こすのである。滔々とした世の中において、人は大なり小なり嫌貧の強迫観念に囚われ苦しんでいるのでは有るまいか。稀有な事例に属する病的苦悩を抱いている者を、医者も世人も強迫観念に囚われているというが、達人の眼から看たら大抵の人は貧即不幸の強迫観念所有者で、それは確かに病的では有るまいか。一ツ目小僧ばかりの国へ行ったら二ツ目のある普通人が見世物にされたというのと同じ話で、昔から貧乏をそれほどとも苦にしない人々は、貧乏を苦にする人が多い世の中では奇人変人とされているが、実は貧を苦しんでいる多くの人の方が、苦しんでいるだけ即ち病人なのでは有るまいか。貧乏で首をくくる人も無いことは無い。しかしそれは貧乏がその人を殺したというよりは、貧乏即不幸の強迫観念がその人を殺したと云った方が正しかろう。何故と云うに、貧に安んじているのであれば、必ず死に臨む以前から幸福と希望と勇気を得ているので、極端な場面に逢うことも無く済むであろう。貧乏を嫌がり嫌がりして日を送るから愈々貧乏になる。愈々貧乏になって極端な貧乏と対面する及んで、堪えられなくなって死を選ぶ。その心状は悲しむべきものがある。それなので、その死を選ぶ場面に直面して偶々或る事情によって死なずに済んだ時は、その病的観念から脱却し健常な人となって更生し、即ち勇気に満ち希望に生きる人と成って働き出して、社会における地平線上の人となり得た実例は、しばしば見受けるところである。
遠慮なく言えば、貧即不幸の妄信が生じて以来、人々は長い間沈淪している。しかしこれは世が未だ進歩していないからである。砂糖気の少ないものは美味でないと信じている程度の味覚の持主と同程度の人々であるからである。そして今日の人々は他人の持つ砂糖を自分も持てれば幸福であろうというような妄想を有している。学者も為政者も社会の真の幸福を希求する人々も、財の分配が全てよく行われたら社会は幸福になるだろうと思っている。しかしその根本には甘味偏重の幼稚な感じのような、財利偏重・貧乏大嫌いの幼稚な考えが強迫観念のように付き纏っている。真の幸福というものはそんなところから獲得されるものでは無い。バカバカしいほど遅れている世だ。快くその幼稚な境界を世が経過して終わらない間は、世は何時までも不幸を感じる人によって満たさているであろう。
富即幸福の信条に住して偶々富を得た人々の方はどうだ。この人々の中の聡明な資質を有する人々は、自分の妄信が自分を幸福にしなかった事に気付かない訳には行かない。極々愚鈍な富者は小間物屋の店先に立って、ああ悲しいかな、今は我が買いたいものは無くなったと嘆いて、買いたいものがあった昔の幸福を味わうと同時に、財に膨らむ財布を投げ捨てて落涙したという昔話そのままに終わらなくてはならない。それ以上に病的な富者は、既に富んでもなおその心は貧しくて、いやがうえにも富を欲して、一生貧乏人と同様に戚々汲々として終わる者もある。これはもとより痴愚瘋癲の類で、三度も生まれ代わらなければ貧乏人にもなれない程度の不幸な人で、論外である。そこで富者は富即幸福の妄信が破れると共に、或いは趣味に生きようとしたり、或いは道義に生きようとしたり、或いは名誉欲に生きようとしたり、或いは知識欲に生きようとしたりするのである。名誉や知識を欲するものは、なお他日再び背負い投げを食わされる。その名誉や知識を獲得した暁が心配であるが、これは中々満足を得難いものであるから、そのうちにお迎えに遭遇して厭々ながら引きずられて行く。もっとも聡明な者は犠牲的精神に満ちた月日を送るが、注意深く観察すればその日常は高貴ではあるが、貧乏人が富を得ようとして働くよりも中々楽ではない。楽をしたい、ノンビリを楽しみたいなどを思う者は、忘れても富者などになるものではない。最も粋な者は全部の富を抛り出して仕舞って、龐居士(ほうこじ)のようにその日暮らしの笊や味噌漉し造りなんぞになって仕舞うのである。いい。実にいい。富者になったところで最も粋なのが笊や味噌漉し造りになるのである。「味噌漉しの底に溜まれる大晦日こすにこされずこされずにこす」、貧乏の方が一寸面白味が有ろう。双六は上がらないうちが面白いのだ。貧富などは論じるも価値はない。ただ一日を誠実に働くだけである。幸福も不幸も忘れた時が真の幸福であろう。
(大正十二年一月)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
