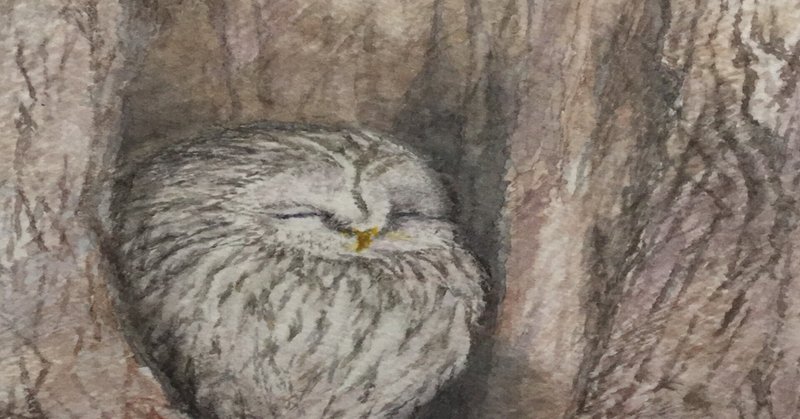
幸田露伴の論語「悦楽② 楽」
楽
人は世の中に孤立して、永久に孤独で居ることはできない。もし世界が一ツでその世界の王であったなら、或いは人中の最高尊者として永く友は無いであろう。しかし、古帝先王の英偉雄俊な者がその胸中に友として在りはしないか。釈迦が特別に優れた仏教の道を悟って天上天下唯我独尊と自尊して居ても、燃灯古仏(ねんとうこぶつ・釈迦が仏陀になる事を予言した仏)を始め、いわゆる過去七仏(釈迦以前の七人の仏陀)は、皆これ同志同心の友ではないか、仇敵の調達(ちょうだつ・釈迦の弟子で後に背く)も天王如来だった時は悟りの道の善友で、薬王菩薩・薬上菩薩・妙音菩薩・観音菩薩・曼珠菩薩・普賢菩薩等は勿論の事、遠い後の世の弥勒菩薩までもが、皆互いに主となり師弟となる朋友ではないか『妙法蓮華経意』。法王と称しても友無しでは居られない、「君子は独立して懼(おそ)れず、世を逃れて思い悩むこと無し」『易経(沢風大過卦・大象伝)』とあるが、それは一時(いっとき)の事で友無しで済むものでは無い。まして人は全能ではないので、群れを離れ独り住んでも他に頼むことも多い。どうして、孤独に頼る者もなく世に背くことが出来よう。人は自然に友の有ることを願う。これが已み難い人情では無いか。そうでないのであれば、そうでない特別な理由が無くてはならない。
その車を同じくし、その船を同じくし、その路を同じくし、その宿を同じくすれば、人は人と自然に伴(とも)となる。その事を共にし、その業を共にし、その職を共にし、その任務を共にすれば、人は人と自然に侶(とも)となる。人の世では伴侶は互いに益することが多い。鄭玄(じょうげん・中国、後漢の儒学者・訓詁学者)は云う、「同門の者を朋(とも)と云い、志(こころざし)を同じくする者を友と云う」と、師を同じくして教えを受け、願いを同じくして術芸を習い、道を同じくして学問に従い、志を同じくして徳の向上に努める、このような環境において人は自然に朋友と助け合い切磋琢磨して次第に成長する。相益(互いの利益)の意識は無くても、自然に磨き合って糠(ぬか)を取り去り純精となる。朋友切磋琢磨して、術芸は日々に進み、徳は日々に成ろうとする。我が人より受け、人が我から受けるものもまた多い。無心に伴侶となるのも有心に事を共にするのも、皆互いの益となる。朋友有って道を同じくすれば相益すること甚大、悦(よろこ)ばしく楽しいことである。道の友とは、ただ単に旅の道ずれ、事業の伴侶のようなものだけではない、将(まさ)に之に依って近くから遠くへ及ぼし、一心の小さなものを周囲に及ぼし、天地の善導を助け、神の徳を讃えようとするもので、道友を得る悦び楽しさは例えようも無い。この意義と光景において、聖賢の道に在る者は聖賢の道に在る者を得て喜び、仏陀の道に在る者は仏陀の道に在る者を得て喜び、キリストの教(おしえ)に在る者はキリストの教に在る者を得て喜び、手を携え合い力を合せて、ニコニコと喜び合い、ホクホクと悦び合う。事業を共にする者が相得て喜ぶその悦びは小さくない。情を同じくする者が相得て喜ぶその悦びは浅くない。しかし道を同じくし信じるものを等しくする者が相得て喜ぶことはこれに勝る。昔から異教を奉じ妖神に仕える者等がともすれば一団を形成して、王に背き、国を乱だし、世と相争い、敢然として固い誓いの下(もと)にその身を犠牲にするのを見ても、その道友を得る喜びの大きく、愛し合い譲り合う念(おもい)の深いことを知る。道において朋友を得ることは実に人生の一楽というべきである。
しかしながらこれも尚(なお)云うに足りない。これも尚(なお)旅の道連れのようなもの、これも尚(なお)事業の伴侶のようなものである。もし我と同じ道を志す人が、我に学ぼうと遠路を苦にせず、我を訪れ、我に質(ただ)し、我に問い、我が伝えるものから益を受け、我が得たものが彼を啓発するとすれば、その楽しさは言葉に尽くせない。学んでそして時に之を習い、日に進み、月に捗(はかど)り、次第に到達するものがあって、そして我の固く信ずるところがあり、深く実証するところがあり、看得(みえ)て徹底し、成し得て通じるところがある。ここにおいて我の悦びを人に推し、我の能くするところを人に教え、また信従する者があって、近くから遠くから集まり来る時は、例えば水が次第に増え、火が次第に盛んになるのを見る様なことである。我が一意の誠が寄り固まりそして満ち、満ちて溢れ、付近を浸潤し、遠方へと波及する。我が一心の真(まこと)が発しそして香り薫じ、薫じて暖め、暖めてやがて付近を輝かし、その灼光(しゃっこう)が遠方を照らす。その次第に増え次第に盛んになる様子は実に楽しいものである。そして我の徳が次第に高く、我の道が次第に行われることは、これまた実に楽しい事では無いか。この境地の消息を孔先生が、「朋あり、遠方より来る、また楽しからず乎(や)」と言われたのである。
この聖語と似ていて少し異なるが『易経』に言う、「麗沢(れいたく)は兌(だ)なり、君子以って朋友講習する」『易経(兌為沢卦・大象伝)』と、「兌は説(えつ)なり」『易経(兌為沢卦・彖(たん)伝)』と、心に悦びを含むこと、これが兌である。大象伝の言葉で兌の卦を解くと、まず兌は志を同じくする朋が集まり合うことで、内卦の兌と外卦の兌とは志望風格共に同じ、即ちこれは同志で朋友である。この同志の朋友が共に主人となって対座しているのが、兌の卦である。兌は沢(たく)であって、二ツの沢が連なるので麗沢(れいたく)という。麗は連という様なことである。兌は悦であって、嬉しくてホクホクと悦ぶことである。かの学んで時に之を習い、修得するところ有って悦ぶようなことは、正にこれ兌の象(かたち)であり、柔らかく優しく精細で若く美しいものは、正にこれ兌の徳である。内卦の兌は主体であり、道に進んで悦び、悦んで道に進み、その誠は溢れて外に現れる。外卦の兌は客体であり、その誠に感じて、そして遠方よりやって来て、道を共にし志を同じくして、悦び合って共に徳を高め成長を助けようとする。悦びで人々を先導すれば、人々はその苦労を忘れ、悦んでその困難を克服し、人々はその死を忘れる『易経(兌為沢卦・彖(たん)伝)』というのは、内兌と外兌の応接の状態を適切明白に説明する言葉であるが、これを君子(くんし・学問と徳が備わった人)と人々との間に例えると正にこの様である。これを朋友の間に例えると、我は自然に朋を求め朋も自然に我に来る。我先ず独り悦び、朋もまた悦び来る。朋が楽しみ来て我もまた楽しむ。古注にも「朋友集まり合って道義を講習する、悦び合う盛んな状(さま)、これを超えるものはない」『周易正義』と云う。
およそ学ぶ悦びは、自得自証(自力で会得する)より悦ばしいことはない。またその楽しさは自得自証が次第に積もって、そしてその徳の高さが人に知られるようになり、人がやって来て我に就いて教(おしえ)を請(こ)い、我が持つ善いところを人に及ぼすことほど楽しいことはない。まして「朋あり、遠方より来る」のであれば、その近くの者は勿論知るのである、我が徳の習得が次第に進んで、我に信従する者が多く、学業の効果は次第に現れる。真(まこと)に楽しいことである。易経の雷地豫の卦・九四にも、これに近い情状が有り、「由って予(たのし)む、大いに得ること有り、疑う勿れ、友集まり合う。」とあるものはこれである。予もまたゆったりと楽しむすがたである(予楽)。ことに九四の一陽に、五陰が或いは仰いで従い、或いは伏して就くのは、一人の徳の高い者があれば、これより低い者も従い、これより高い者も就く様なことである。我が人に就くのは我もこれに由って楽しみ、人が我に依るのは人もこれに由って楽しむ。火と炭が相得る様なことで、炭は未だ火ではないが、火は炭を得ればその勢いが盛んになる。火は未だ炭には無いが、炭は火を得ればその働きを成し遂げられる。志を同じくする朋が集まり合えば、徳の習得に厚薄あり、器(うつわ)に大小があり、功業に大小があり、学問に成・未成があったとしても、互いに頼り合い助け合って、共に進んで盛んになるのである。頼るものも無い孤火はその勢いが盛んで無く、火と火が寄り合って燃えれば烈々と炎を揚げて光を飛ばす。予の九四の爻(こう・卦のかたち)は火が炭の中に在る光景で、衆炭は孤火を奉じ、孤火は衆炭を率いる。「また楽しからず乎」というのと、言葉と相(すがた)は表裏をなしている。悦びの意味がある兌の卦に朋友共に学ぶとあり、予楽の意味がある予の卦に朋友相集まるとあるのに照らしても、聖語に二ツ無く、道情の趣旨は一ツである。
〇
「例えば井戸を掘っている時に、やがて湿った泥を見ることになれば、意気は上がり、ますます増進を加えて水を得ようとするものである。また火を起こす時に煙が出て来れば、ますます力を励まして火を得ようとするものである」『大智度論(巻十五)』という言葉がある。これは仏教の言葉で聖学を志す者の為の言葉ではないが、甚だ巧みに学問の光景を説明している。井戸を掘れば水を得、火を起こせば火を得ることを知って、そして井戸を掘ろうとし、火を起こそうとするところは、これ学問に志す初め、既に井戸を掘り、火を起こすところは、これ学問の途中、湿泥を見、煙を見るところは、これ学問が幾分か進歩した象(かたち)。努めて已まず、不断に井戸を掘り、休まずに火を起こすところは、これ「時に之を習う」ということである。終に水を見、火を見るのは、これ「時習」によって成果を得たところである。人が有り水を求め来て、我が水を人に分ち与えてその清涼の味わいを施し、また人が有り火を求め来て、我が火を与えてその温暖の恵みを贈るところは、これ「朋あり遠方より来る、また楽しからず乎」の光景である。学而の章を、前節とこの節とを別項の事として看る時は、これ別項の事であるが、一緒の事と看る時はこれ一緒の事で、その中に自然と気脈の通じるものがあると看る方が優れている。前節はただ学習の事を説明し、この節はただ朋友の事を説明すると看るのでは妙味が無い。
〇
ある人問いて言う。「朋遠方より来る」ということは、我の善いところが人に聞こえて、志を同じくする者が来て我に就くということで、真(まこと)にそうであろう。であれば、「また楽しからず乎」ということも、実にそうであると思われる。しかし学問に励み道に進む者が習熟成就しても、君子は売名によって自分の徳を示す事は無いので、朋はどのようにしてその人の徳の高いことを知り、そして遠方から来るのか不思議であると。答えて云う。疑いは真(まこと)に尤もである。学問に励み道に進めば必ず朋が遠方から来るという事では無い。朋が遠方から来ることもあるだろう。また自然と来ない事もあるだろう。ただ朋が有って遠方から来れば、楽しい事は勿論である。しかし、学問が成って徳を積めば、必ず朋が遠方より来ると断言することは出来ない。しかしながら、酒が出来れば自然と酒の気は発し、花が開けば自然と花の香りは広がる。まして聖人の学は、仏教や道教の学が空寂清虚を尊ぶのと異なって、全て皆これ実地のことで、現実離れしたことでは無いので、その学が次第に成熟するに従って、日常の行動の一挙手一投足にも、その徳光や道光は自然と溢れ出し、人の認めるところとなるのは自然な成り行きである。人に知られないということはあり得ない話である。仏者にあって修めるところは世間の事では無く出世間の事である。努めるところは有為の道では無くて無為の道である。それでも、「戒律を守る修行が次第に積もれば、戒律の功徳は外に薫じ、禅定の力が満つれば、禅定の光は自然と輝く」という。酒気や花香が隠せない様に、心の徳は密(ひそか)であっても顕れないで止むものでは無い。孔先生の七十人の弟子は、先生の高い徳を感知して、そして仰ぎ慕ってその門に入ったのである。朋が遠方より来るのも何の怪しむべき事では無い。しかしながら、これは君子の順境の時の事であって、偉大な聖賢も逆境の時に遇えば、苦しみ悩むことを免れない。朋が遠方より来ないどころか、恨み憎み誹謗されることもある。朋あり遠方より来るなどという事は中々もって有るはずも無く、古来の聖賢の身の上を見ると、その初期においては鬱屈し、中途においては挫折し、晩期においては険難を免れず、「また楽しからず乎」の境地に成れないことは明らかである。だとするとこの一節は、学問をして徳を積む人の順境の場合を説き示されたものとして観るべきである。
尤も有道有力の人は、独立して懼れず、世を逃れて思い悩む事も無い心境なので、時世に恵まれず険難に在っても、独立孤行するようなことも無く、「大いに悩むことが有っても朋は来る」『易経(水山蹇の卦・九五)』とあるように、甚だしい逆境の時に在っても朋を得ないことは無い。朋を得、朋を失う事は易にもその語は大変多い。一概にこれを語ることは出来ないが、諺にさえ「運去って佳人に遇い、時至って友を得る」というように、先ず順境好運の時は朋を得ることが有る。これに反し逆境否運の時は朋を得ることは覚束(おぼつか)ない。若(も)しそれが平穏無事の時ならば、学問をして徳を積む者の許(もと)には、自然と同志の朋が遠方より来ることが有る道理である。外を論じずに内より論じれば、朋の来る・来ないはたいした事ではない。ただ朋を来させるものが我に有るのは悦ぶべきことで、無いのは悲しむべきことである。しかし内を論じず外を論じれば、朋が来る・来ないを我の学問と徳の充足・不足の現れとして、その不足を残念に思いその充足を悦(よろこ)べば善いのである。
もちろん『論語』のこの節の趣旨は、このように自信で判断して、或いは悦び、或いは残念に思うというのでは無く、ただその「朋あり遠方より来る」ということは、例えば春の風が大空に渡り、春の水が辺りの沢に満つ様な光景であって、心に沁みるその楽しさは、「また楽しからず乎」と言われる通りなのである。しかしながら学問をする者に在っては、時習の悦びを体得しなくてはならないのと同様に、有朋(ゆうほう)の楽しみもまた自ら会得しなくてはならない。なのでこの様に理解しこの様に感ずるのも、また悪くないと思う。
すべて聖人の言葉は、特に我が孔先生の言葉は、温かく潤いが有って、情が篤く意(おもい)が遠大で、論じ尽くし説き諭して少しも余すところがない。示して強いて教えず、勧めて強制せず、志の有る者に考えて得させ、噛みしめて味わうように教えられているので、我が心を正して、十二分に思い取り、思い入り、思い拡げて、尽々(つくづく)と味わい、精しく味わい、細かに味わって、その尽きない妙旨を理解して、尽きない滋味を受けるが善いのである。程子が「某(それがし)十七八の頃より論語を読み、当時すでに文意を覚(さと)っていたが、之を永年読んでその意味の深長なことを益々覚える」と云うのも、謝氏が「論語の書、その辞(ことば)は簡単であるが、その意味するところは遠い。辞は理解できても、その意味するところは究まり無い。辞を理解できない者は字引きを索(ひ)くが善い。その意味するところに達しない者は、当然のこと之を理解するために全気全心をもって当たるべきである」と云うのも、つまり先生の教(おしえ)が意味深長で含むものが宏博である為に、澄んだ泉は底が見えても、汲んで尽きない様なもので、先生の教(おしえ)に接する者は、先に自分の見解を立てて、そして聖語をこれに牽き合わせる様なことをしないで、あくまでも聖語を玩味咀嚼し反復して、その意義の示すところを推及し拡充すべきなのである。碁の名人が一石を下ろすのも、その含むところは浅く無い。碁を学ぶ者がその意中の真処と深処を知らずに済ますことは残念である。先生の慈訓に接して、ウッカリ看過すようなことがあってはならない。器量が小さく才知の乏しい者は、思い取って味わい知ることの出来ない事を、残念に思うべきなのである。(悦楽③につづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
