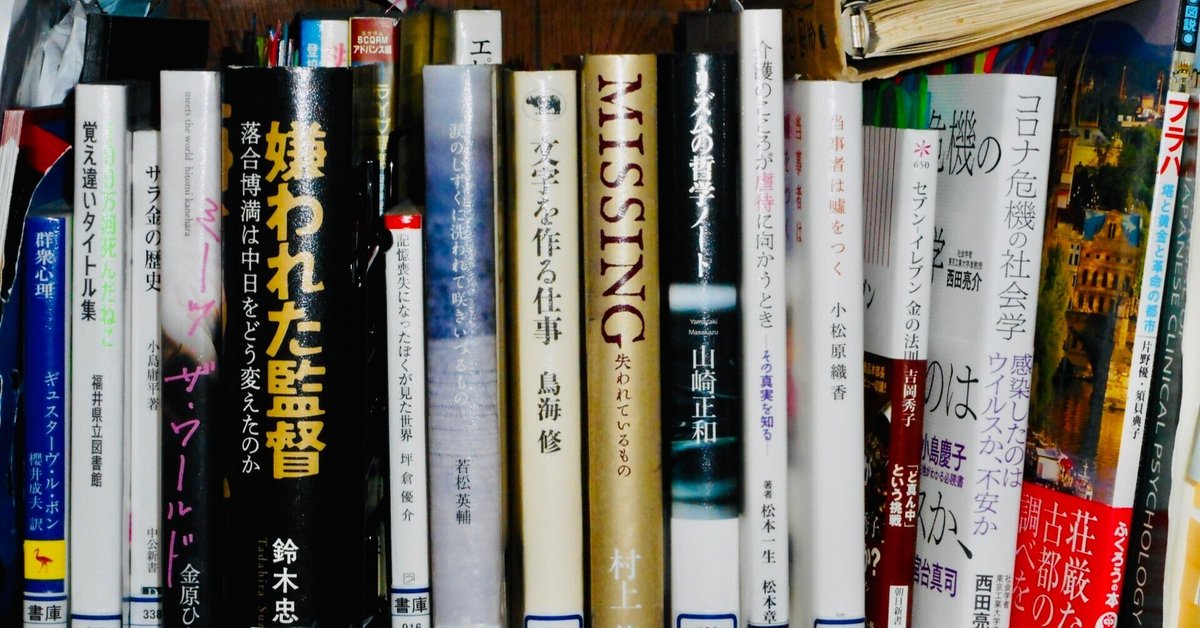
読書感想 『当事者は嘘をつく』 小松原織香 「これ以上ないほど切実な言葉」
毎回のことで、しかも偽善的な態度でもあるのだろうけど、自分が「当事者」でないことに関して書かれた作品を紹介するときに、微妙に後ろめたさがある。
その作品が、切実であればあるほど、分からないことに対して、分かったような態度を、知らないうちにとっていないだろうか、というような恐れも出てくる。
それでも、そんなことを感じながらも、それ以上に、もっと必要な誰かに届くようなことをしないと、いけないのではないか。そんなことを思ったときに、こうして紹介しようと試みる。
今回も、そう思える作品を読むことができた。
『当事者は嘘をつく』 小松原織香
私はずっと本当のことを語ることが怖かった。
私は一九歳のときにレイプされた。性暴力被害者であること自体は、私にとって大きな問題ではない。家族や身近な人たちは、みんな私がサバイバー(生存者)であったことを知っている。私は暴力のその後を生き延びたことを誇りに思っている。
ただ、私は「研究者」になってしまった。
これは、この作品の冒頭なのだけど、これが『「研究者」になった』という誇らしさと共に語られるのではく、『「研究者」になってしまった』という表現をするところに、そこに至るまでも、また、現在も続く苦しさや、辛さが、すでに表現されている。
さらには、性暴力の被害者の、そのあとの気持ちについて、ここまで苦しみが重なり続け、持続することを、全く当事者性がない人間にも、少しだけでも近寄らせてもらえるような表現をしている。
過去そのものではなく、私の手によって編集した一部の物語しか、私には提示できない。そのうえ、私はどんなに真摯に本当のことを語ろうとしても「自分は嘘をついているのではないか」という強迫観念を追い払えない。
「私は性暴力被害に遭いました」
そう告白したとしても、私はいまだに嘘をついているのではないかという、自己懐疑に囚われる。語っても、語っても、「あれは語らなかった」「これは違うかもしれない」「こんな言葉では表現できていない」という声が、自分の中から湧き上がる。他人から疑われることもつらいが、自責や自己批判も孤独で苦しいものだ。
こういう質の苦しさについては、これまで、想像が出来なかった。それだけに、著者自身が、考えが及びにくいほどの負荷をかけながら書いた文章だと思うし、とても貴重な言葉だと思う。
性暴力によって私が失ったものは、純潔さでも無垢さでもない。かつてあったはずの「私」である。それ以降の私は、性暴力の体験を源泉にして生み出されてきた。性暴力の記憶なしに、今の私は存在し得ない。
だからこそ、私は自分の記憶が誤りであることに恐怖する。性暴力被害の記憶が嘘であることは、今ここにある「私」の存在の否定であるのだ。
これらの私の心情を、セラピーの言葉で解釈することもできるだろう。もしかすると、私は心理カウンセリングにより、この恐怖から解放されるかもしれない。しかしながら、私が望むことは治療ではなく、懲りもせずに語ることである。
たとえ、語り得ない物語の「穴」がそこに開いていたとしても、私はその空洞の周囲をぐるぐると回りながら語ることで、「ここに穴がある」と示すことができるだろう。
「支援者」の姿
個人的な経験に過ぎないが、私は、家族の介護を始めて、仕事も辞めざるを得なくなり、ただ介護に専念する年月があった。そのときに、介護者の支援が不十分だと思い、自分でも資格を取り、そうした支援をしようと思った。どこか、支援者への不信感もあったからだ。
もちろん、その経験と安直に重ね合わせてしまうのは、失礼だとは思うし、今では、私自身が支援者の一人となっているから、とても他人事のように接してはいけないように感じるけれど、著書が、性被害の当事者として名乗らず、研究をしていこうと決めた理由の一つについて述べているが、この視点を忘れてはいけないように思えた。
私は支援者のまなざしに危機感を抱いていた。性暴力について議論する講座やシンポジウムに参加するようになり、私は休憩時間の支援者の会話を耳にするようになった。仲の良い支援者同士は、お昼ご飯を食べながら「めんどうくさい当事者」について愚痴りあっていた。「こういう被害者は厄介だ」「こんな人は被害者だと言えない」というような言葉が、私の耳には飛び込んできた。
かれらは表向きは当事者への敬意を示していたが、少し裏側に入れば平気で当事者の悪口を言っていた。もちろん、支援者も聖人ではないから当事者に対する悪感情くらい抱くだろう。だが、こうした自分たちが議論する場(専門家の集う場)には当事者はいないというナイーブな思い込みに、私はショックを受けた。
「当事者研究」について
どのような研究者になるべきか。そのビジョンは、著者の中では、とても明確で自分への要求も高く、それだからこそ、他の研究に関しての見方も、とても厳しいが鋭く、これまで他の人間も、どこかで微妙に感じていたことを、明確に言語化もしている。
例えば、当事者研究について、著者は、自身の「研究」は、「当事者研究」とは違うと断言する。
(この引用部分↓の向谷地は、この著者↑でもある向谷地生良である)
向谷地は当事者研究を既存の大学における研究のなかに参入させ、当事者や支援者が対立を超えて、ともに研究することを肯定的に概観している。この論稿のなかでは「和解の創造」というキーワードも出ている。
こうした発想は、「当事者主体」のスローガンを掲げられているものの、研究の世界に足を踏み入れた当時の私とは、まったく相容れないものであった。私は自分の研究を「当事者研究」と呼んだことは一度もないし、シンパシーを抱いたこともない。私は当事者でありながら、研究をしていただけである。
さらに、著者自身の研究は、「当事者研究」でない理由を、主に3つ挙げているが、その3つ目の指摘は、とても大事だと思った。
第三に、私は支援者との協力関係を望んでおらず、徹底的な対立関係を求めた。私の仮想敵は精神科医のジュディス・ハーマンであり、かれらのような専門家に拮抗する対抗言説を生み出すことが、私の研究の目的であった。そのため、当事者と支援者の和解を掲げる向谷地の発想とは、根本的な理念のレベルで相いれなかった。
私は、当事者が望んで自己の探求を行う手法として「当事者研究」を使うことには賛同するし、大きな価値があるのだろうと思う。しかしながら、私は「当事者研究」のなかに、当事者の生々しい言葉をすべて「回復」の言説に回収しようとする支援者の欲望の匂いを嗅ぎつける。
おすすめしたい人
性暴力被害の当事者の人にとって、もし、読んだ場合、この本の存在が、どのような意味を持つのかについては、私には、本当の意味ではわかっていないと思います。場合によっては、フラッシュバックなどを引き起こす可能性もあるので、おすすめしにくいものの、それでも、ここにしかない言葉があるのは、間違いないはずと、思います。
さらに、強めに、おすすめしたいのは、支援者という役割をしている人たちです。性暴力被害の支援者だけでなく、支援に関わっている方々であれば、ここまで引用したのは、本書の一部に過ぎませんので、ぜひ、一度は全部を読んでいただきたいと思っています。
(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。
