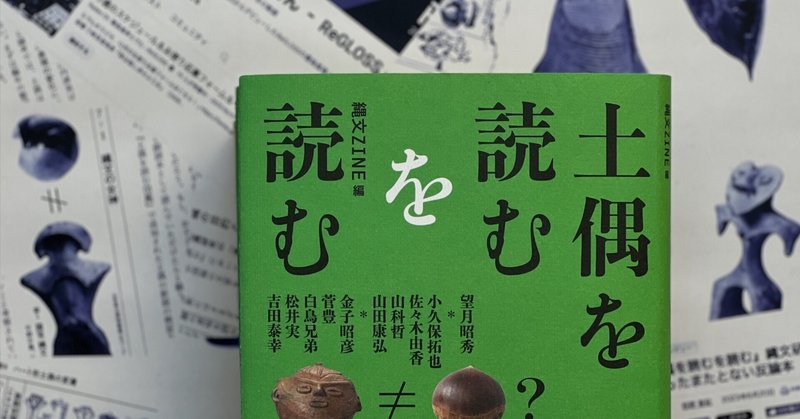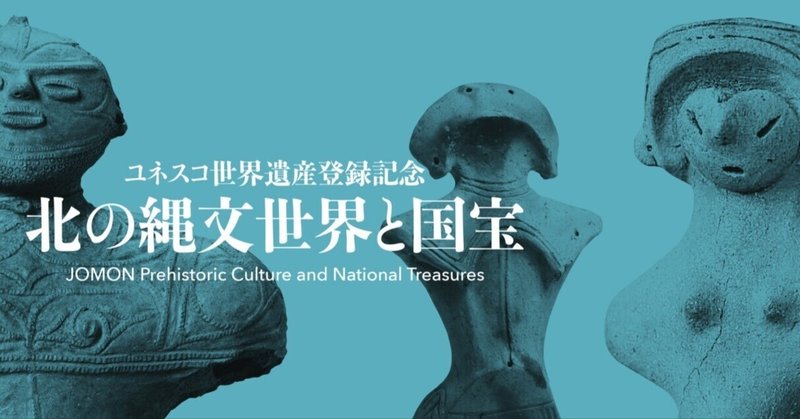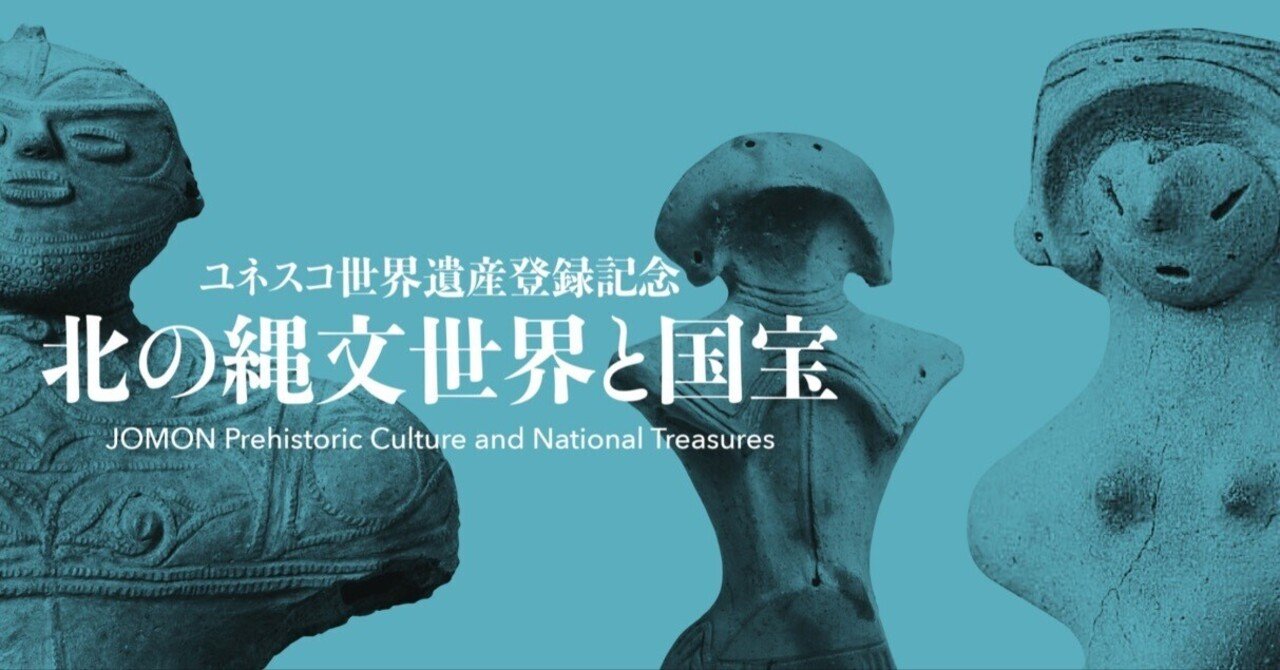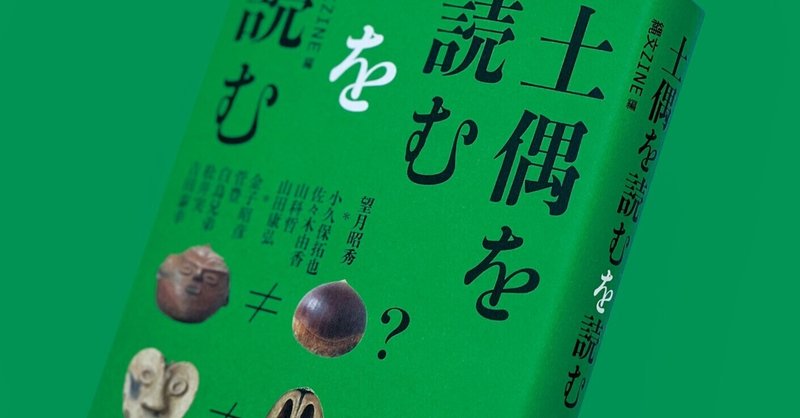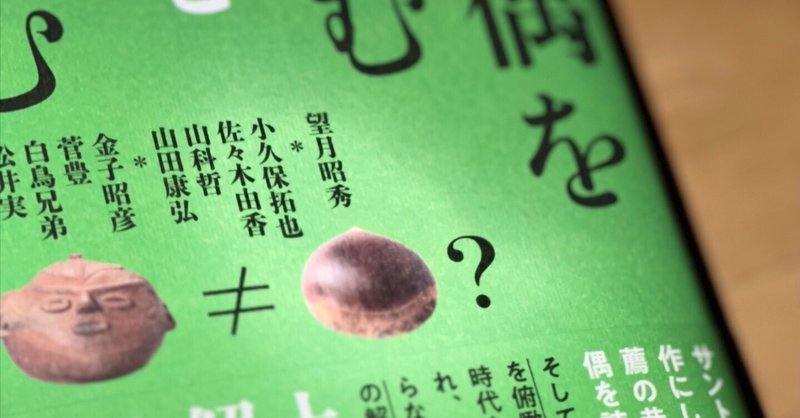縄文ZINE_note
フリーペーパー縄文ZINEのnoteです。縄文の楽しい話を主に。
http://jom…
最近の記事
-
-
-
-

国宝の火焔型土器の出土した笹山遺跡で実際に掘った人と語り合い、その後、国宝の火焔型土器を見に行って火焔型土器のクッションを物色して、〆に火焔型土器インスパイア系ラーメンを食べる火焔な1日
笹山遺跡 先日新潟県十日町市に伺い、こんな贅沢な体験をしてきました。 国宝の火焔型土器の遺跡、笹山遺跡で、その国宝の火焔型土器のNo.1(笹山の土器は全部で57点が国宝と指定されているが、その中でも代表的なものとしてNo.1がある)を掘った担当者だった、現在は十日町市の教育長の渡辺さんと話をする機会をセッティングしてもらい。しばし色々な話を聞く。 場所は笹山遺跡の復元の竪穴住居。 結構有名な話だけど、発掘調査終了の本当にギリギリの最終日にNo.1が見つかったこと、たくさん出