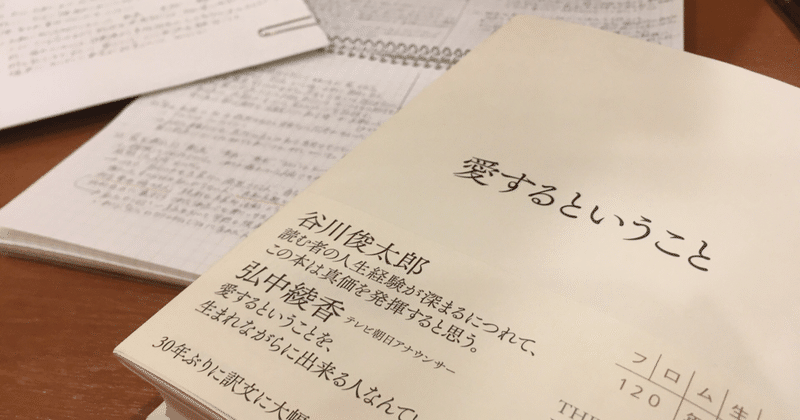
- 運営しているクリエイター
2021年1月の記事一覧
土方の連中の「意図せず知った非言語的な信念」の話
私土方の連中ってあんまり好きじゃないんですよ。
(なにぶんそう言う連中に散々やられたので。)
そんで、そういう「曲がりなりにも結婚して子供がいて、仕事が辛くても家族のために働けるから頑張れる人」というのは、自分と何が違うのか考えたんですよ。
結論、「非言語的で感覚的に自分の信念を知ってるから、愛を育み逆境でも立ち続けることができる」ということかと。
アウトサイダーだとしても信念を知ってるか
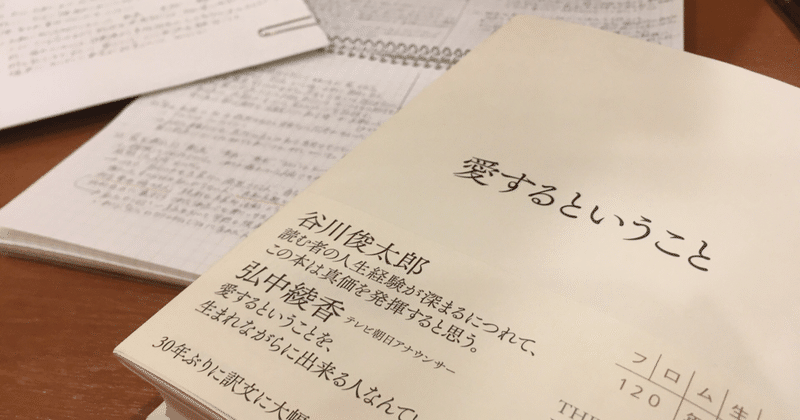
私土方の連中ってあんまり好きじゃないんですよ。
(なにぶんそう言う連中に散々やられたので。)
そんで、そういう「曲がりなりにも結婚して子供がいて、仕事が辛くても家族のために働けるから頑張れる人」というのは、自分と何が違うのか考えたんですよ。
結論、「非言語的で感覚的に自分の信念を知ってるから、愛を育み逆境でも立ち続けることができる」ということかと。
アウトサイダーだとしても信念を知ってるか