
GOOD LIFEという幸福に人生を生きるための方法をまとめた本を読んだぞ!という話
最近どうも幸福じゃないな〜なんて思い悩んでおりまして幸福に生きる方法を本とかネットで漁っていた私でありますが「自分に欠けていたのはこれなんじゃないか!」ってハッとさせられた本があったので軽く紹介しまーす。
その本というのがこれ「GOOD LIFE」という本。
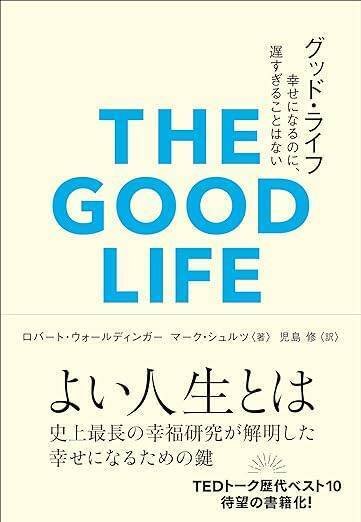
今年の6月30日に発売された新しい本でお金のない私は図書館で借りようとしたものの30人待ちで今回ようやく手にとれた本でございます。いやー長かった。
そしてこの本のすごいところはなんと言っても「ハーバード成人発達研究」という同一家族を2世代にわたって80年以上追跡してきた研究をベースに書かれているところ。80年って長すぎやしないか💦
そして80年って言ったら人生のほぼ大部分を追っているわけでそこから得られる「幸福に生きるノウハウ、コツ」を学べるって最強すぎやしねえか!と感心しておりました。
当然30人待ちで待っていたので読む前からこの本への期待度はかなり高まっておりましてページをめくる前、図書館に借りに行く前からかなり興奮しておりました。「この本を読んで俺は幸福になるんや」とも意気込んでおりました。
どんなことが書いてあるんだろうなと目次を開くと自分にとっては予想外なことが書かれていました。
結論:幸福度を高めるには「人間関係」が一番大切
いやわかってるよ!と思わず反論したくなりましたがやっぱり幸福に人生を生きるには「人間関係」が一番重要みたいです。「幸せな人生の条件とは何か?」という質問の答えはデータから健康的な食生活、運動習慣や所得水準まで様々な予測因子があるが一番際立っているた予測因子が「人間関係」だったそうな。
そして健康についても
「50歳の時の人間関係の満足度が高い人程、精神的にも肉体的にも健康な80歳を迎えていた」
のだそう。
(もう「人間関係」神サプリじゃねえか)
ソーシャルフィットネスを高める
幸福度と健康に大きく「人間関係」が起因するということがわかったがこの本ではこの人間関係を維持、高め幸福度ともに健康のためにソーシャルフィットネスという概念を提唱している。現代ではデスクワークなどで慢性的な運動不足が健康を害しいるという主張だけが一人歩きし「ジムに行きましょう」や「ランニングをしましょう」などの通常のフィットネスが重要視されている。もちろんフィットネスも大事であるが「人間関係」も健康に大きな影響を与えるため筆者はソーシャルフィットネス(人間関係の健全度)をエクササイズ同様同時に行う必要があると述べている。
孤独恐るべし
孤独は精神的な痛みだけでなく肉体的な痛みももたらします。
最近の研究では高齢者にとって孤独感は肥満の2倍健康に悪く慢性的な孤独感は死亡率を26%も高めるのだとか。いやまさしく
孤独恐るべし
って感じですね。夫に先立たれた老妻がその後にコテっと逝ってしまうパターンなんかこれ関係してるんじゃないと個人的に思うわけです。
このことからとりあえず筆者は良好な人間関係を作って孤独を解消してソーシャルフィットネスを高めましょうやって主張しているわけですな。
どうやってソーシャルフィットネスを高めるか
ソーシャルフィットネスを高めるにはまず
人間関係の全体図ソーシャルユニバースを描くということ
「自分の人生には誰がいるのか?」
を把握することが第一ステップです。
家族、友人、親類など自分の身の周りにいる親しい人を書き出してみることが大事なのだそう。10人ぐらい挙げるだけでもいろんなことが明らかになるみたい。
この際大事なのが良い人間関係だけでなく良くも悪くも自分に影響のある人をリストアップすることが大事。 上司や同僚など
そしてリストアップしたらこれらの人間関係の特徴は何か?を考える。
そのために紙とペンを用意して以下の画像の図を書いてリストで炙り出した人を当てはめてみよう。

この図は幸福の二大因子である他者との交流の「頻度」と「質」を客観的に把握するための図であり
縦軸が会った時元気をもらえるのか消耗するのか横軸が合う頻度が多いのか少ないのかという図になっている。
この図に自分の人間関係を書き出してみるとといろんなことが明らかになる。
例えば私の例だと
会えば元気をもらえる友人Aがいましたが会う機会がかなり少なかっため図のかなり左上に友人Aが位置する形になりました。
この図から私は友人Aとの会う頻度を高めれば今よりもソーシャルフィットネスを高めることができるとわかりました。逆に会う機会が多いが消耗する友人もいることが判明したため会う頻度を減らしてみようというアイデアも湧きました。
また留意しておきたい点は消耗する人間関係が分かったとしてもその人間関係を断ち切るのではなく減らしたり付き合い方を変えるのが得策という点だ。心地よい人間関係だけでは何らかのチャンスは掴めないため消耗するが自分にとってプラスになる人間関係も何かチャンスを掴むためには必要だと本書では述べられている。
生き生きとした人間関係を取り戻す
ソーシャルフィットネスを高めるために先ほどはソーシャルユニバースを描いたわけですけども会う機会が少なかった人と突然会う頻度を増やして人間関係をすぐに深めるのは困難な話。(私も少し人見知りなところがありましてどんなに仲が良い友人でも久しぶりに会うと少し戸惑っちゃう時なんかがあったりします)
そこで筆者は人間関係を取り戻すための効果的な人付き合いの原則を紹介しております
寛大になる
新しいダンスのステップを習う
好奇心を強く持つ
こんな感じです
寛大になる
人間関係への無力感や絶望感への対処法は「自分がしてもらいたいことを相手にする」という考え方が必須。自分に対する相手の関わり方を変えることはできなくても自分が相手とどう関わるかは変えられる。寛大さと幸福の間には客観的かつ直接的な関係があるため自分の利益優先で人間関係を築くのではなく他者をまず助けて人間関係を築こうぜって話。そしたら自ずと自分の利益にもなって帰ってくるよ〜なんてことを筆者はおっしゃられております。
確かに自分の身の回りのGIVE精神が溢れている人を見つめ直すとみな幸福そうだよな〜なんて思ったりします。
新しいダンスのステップを学ぶ
新しいダンスのステップを覚える時は皆、悪戦苦闘するが学んでいくうちにだんだんと慣れていく。人間関係も同じことが言える。新しい人間関係を作ろうと思えば最初は誰でも不安や緊張が襲ってくるがだんだんと慣れていくものだ。だから最初の不安や緊張を恐れず人間関係作りをトライして学んで行こうや!って感じ
え、そんなの怖くて出来っこないと思う、、、と思いましたが
そんな人のための次の案が
好奇心を強く持つ
多くの人が人間関係で苦労しているのは自分のことばかり考えているからなのだそう。自分のことに執着しすぎると他の人の人生に目が行かなくなりその結果良好な人間関係が気づけなくとのこと。
不安や緊張で新しい人間関係を築けないのも「嫌われたらどうしよう」とかそんな自分しか見えてない状況に陥るからかもしれないっすね。
他者へ目を向けて他者に対して好奇心を向けることで会話の幅が広がって相手をより理解できるため話しているうちに相手も「理解されている」「自分に興味を持ってくれている」など信頼関係が生まれい良い人間関係が生まれると筆者は述べています。
いや好奇心めちゃくちゃ大事っすな。
確かに自分の経験でも興味を持った相手の方が会話できるし話しているうちに相手もどんどん心を開いてくれているななんてことがありました。
まとめ
というわけで幸せに生きるには「人間関係」が大事だよ〜なんてことを書きましたがその人間関係を良くするためにソーシャルフィットネスを高めようぜってことを紹介しました。
具体的には
ソーシャルユニバースを書いてみて自分の今の人間関係を把握し付き合い方や会う頻度を考えてみる
他者に与える人間関係を築けるよう寛大になる
新しいダンスのステップ(人間関係)を学ぶ
好奇心を強く持って接する
以下の感じでソーシャルフィットネスを高められれば「幸福度」は増すんじゃないかと、、、
私はちょうど実践中です(友人AからLINEが帰ってこなくて激萎え中笑)
皆さんも今回紹介した教訓というか方法を実践してソーシャルフィットネスを高めてみてはいかがでしょうか。
長い読みにくい文ではありましたが最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
