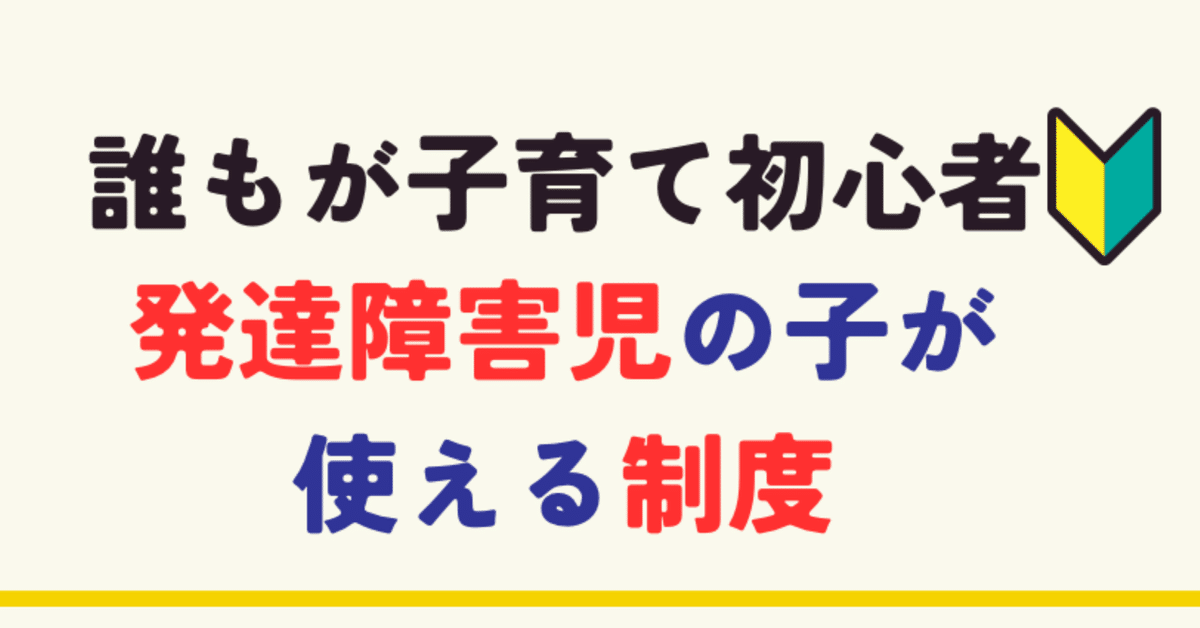
発達障害児の子が使える制度
こんにちは!
今回は発達障害児の子がどのようなサービスを使えるか簡単にまとめてみたいと思います。
制度のことは役所に行って聞いてみても
たらい回しにされてしまったり
説明を受けてもよくわからなかったり
諦めてしまう親御さんも多いことが現状です。
もちろん全ての地域で同じサービスが受けられるわけではなく、その地域に今回お伝えするサービスを行なっているところがない場合ももちろんあるのでご了承頂ければと思います。
また今回は18歳までの子を対象に
お伝えできればと思っているのでその点もご理解いただければと思います。
今回参考にさせて頂いたものは
厚生労働省の政策に関わるホームページの資料を参考にまとめさせて頂きました。
児童福祉法に基づくサービスとして
今回は通所サービスの
以下の4つを紹介していきたいと思います。
聞き覚えのあるものから聞いたことのないサービスもあるのではないでしょうか。
・児童発達支援
・放課後デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
一つずつ説明していきたいと思います。
・児童発達支援
まず児童発達支援についてです。
対象児童は集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学(小学校になる前)の障害児のかたが対象になります。
認められるとはどういうことかというと
この場合必ずしも医学的診断名や障害手帳を有することは必須条件ではありません。
市町村保健センター、児童相談所、保健所などの意見で使用が可能になるので
一度相談に行ってみるのも良いかと思います。
サービスの内容としては
各事業所で違いはありますが
定められているものとして
・日常生活の基本的な動作の指導
・知識技能の付与
・集団生活への適応訓練
・その他必要な支援
と定められています。
事業の担い手としては
児童発達支援センターをはじめ
民間の事業所などが多くなっています。
人員配置で定められているものとして
児童発達支援センターの場合は
児童発達支援管理責任者1名
児童指導員1人以上
保育士1人以上
児童指導員及び保育士4:1以上
となっています。
児童発達支援センター以外の場合
児童発達支援管理責任者1人以上
児童指導員又は保育士又は障害福祉サービス経験者10:2以上となっています。
実際にどんな人が働いているのか
リハビリの専門職の方が働いているのか
どんなことをしているのか(中にはただ預かっているだけでなにもしないようなところもあるようなので)
実際に見学に行ったり情報収集をすることがお子様のためになるかと思います。
送迎なども行ってくれるので安心です。
・放課後デイサービス
次は放課後デイサービスです。
本当に昔に比べて数が増えてきたと思います。
対象児童としては
幼稚園、大学を除いた学校に就学している障害児の子が対象になります。
特例で満20歳まで認められるケースもあるようです。
概要としては
放課後や夏休みなどの長期休暇中に
生活能力向上ための訓練などを継続的に提供することにより
学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに放課後などにおける支援(社会的な交流)を推進する事業になります。
具体的には
・日常生活を営むための訓練
・創作的活動、作業活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
などです。
学校と事業所間の送迎や事業所からお家まで送ってくれるところもあるので親御さんの負担も減らせます。
・居宅訪問型児童発達支援
こちらの制度は重度の障害などの状態にある障害児の方で、障害児通所支援を利用するための外出することが困難な子に対して、居宅を訪問して発達を支援する制度になります。
例えば人工呼吸器を装着しているこや重い障害のために感染症にかかってしまう危険性がある子が対象となります。
注意して頂きたいのは見守る方の不在や送迎が行えないなどの理由の場合は除外されてしまうこともあるので気をつけて頂ければと思います。
提供できるサービス内容は先に書かせて頂いた児童発達支援や放課後デイサービスと同様の支援を在宅で提供するかたちになります。
支援の日数は状態が不安定であることが想定されるため週2回と定められていますが、今後通所支援の方に移行していく目標がある場合は集中して支援を行える場合があります。
・保育所等訪問支援
今回ご紹介するサービスの最後になります。
この制度の概要は、保育所(保育園や学校、特別支援学校、乳児院や児童養護施設など地方自治体が認めたもの)に現在通っているお子様や、今後通う予定があるお子様に対して提供されます。
集団生活に適応するための専門的な支援を要する場合に、実際に支援員が保育所を訪問して
実際の活動場面を見学し先生方にアドバイスやフィードバックする事業になります。
本人に対する支援はもちろん訪問先のスタッフに対する支援でもあることがポイントになります。
支援回数は2週に1度とされていますが
本人や保育所の状況や時期によって
頻度は変化します。
はじめのうちは頻回に行い徐々に集団生活に慣れてきた際に頻度を減らし様子をみることもあります。
訪問支援員には児童指導員や保育士、療法士(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)などが行います。
今回は大まかなサービスの種類を紹介させて頂きました。
僕自身が行なっている訪問リハビリについてはまた改めて書いてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
