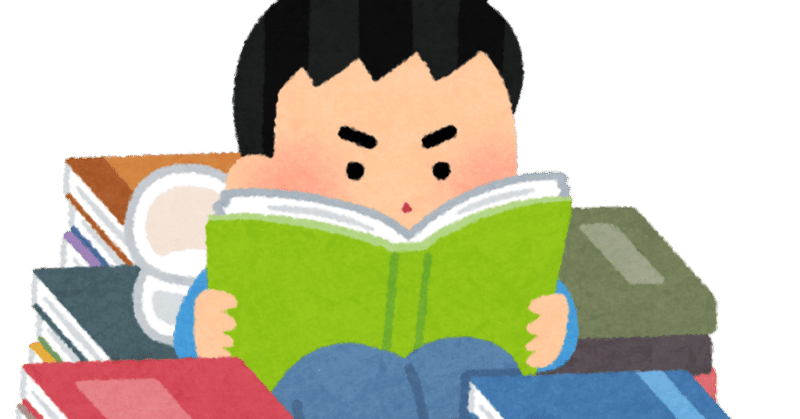
【僕なりの読書メモ】2040年の未来予測
表題の通り、『2040年の未来予測』という書籍を読みましたので、個人的に学びになった点をメモしました。
筆者は成毛眞さんで、元日本マイクロソフト代表取締役社長をされていた方です。
読み終わり、僕が抱いた感想は
「やはり一流の人は多方面への知識を持っているのだな」
でした。
色々な視点で、約20年後の日本の未来を予測されています。勿論全てが本当に予想通りに行くことはないかもしれません。
しかしこれほどまでに説得力を持たせながら、文章に表すことができる能力の高さをヒシヒシと感じました。
また、文章がダラダラと長くなく、非常に簡潔でスマートにまとめられている点も、個人的には驚いた点でした。
僕自身も文章を書くときは
「できるだけ短く、集中力が保てる程度の長さにまとめる」
を常に意識しております。
その大きな理由としては、自分がADHD気質であり、一つのことに長時間集中することが苦手だからというのが、最も大きいのですが…
どんなタイプの人間でも集中力をしっかり保ちながら、次々と話題を進めていけるような文章構成は、今後、僕も身につけていきたいと思います。
以下、とくに医師の未来に関して書かれた部分です。引用および、僕なりの書き換え表現が含まれます。
ーーーーーーーー
●2040年までの医師について
・1人の医師が必死に頑張っても、一生で対面診察できる人数は100万人程度。AIが診断しデータを集めると、そのような人数はあっという間に抜き去ってしまう。
・わかりやすい症例や典型的な経過を辿る症例であれば、AIの方が精度が高くなることは明らか。
・問題点は「AI診断により生じた誤診の責任がどうなるか」などの法整備が必要なこと。
・医師法は1984年に制定されたものであり、AIおよびコンピューターの存在を踏まえたものに変化させていく必要がある。
・実際にAI普及が進むと、生身の医師が診察するのは、非典型的な不確定要素を多く含んだ患者が中心となる。
・医師には、それに対応できるような豊富な経験の有無が重要となる。今以上に臨床経験年数の差異が大きく影響するようになるかもしれない。
・医者の未来は次の二つ
①AIで対応できない非典型的な難症例へ取り組む係
②AIが示した診断を、患者へ優しく説明したり、相談に乗る係
・グローバル化が進み、国と国との移動が活発化するほど、新しい病原体とウイルスが生まれる。1970年以降、毎年新しい疾患が生まれているとWHOは発表している。
・しかし膨大なデータの蓄積と、技術進歩によるワクチン製造速度の上昇により、間違いなく人類の余命は伸びていくだろう。
●まとめ:AIを上手に利用できるように今後も頭の柔軟性を持ち続けるべき
ここ数年で、学生の勉強法が急激にデジタル化されているところを見ても、若い人の方が新しいものを取り入れる能力は高いと考えられます。
僕もまだ医師としては新米ではあり、デジタルへの対応能力も低い方ではないように思っていますが、今後も絶えず新しいデバイスやアプリケーションなどが現れることは容易に想像できます。
AIの医療界への進出も含め、患者へより良いものを提供できるような選択肢が今後現れれば、積極的に自分の生活および仕事に取り入れていく柔軟な姿勢を、歳を重ねても持ち続けていきたい所存です。
医師として、社会人として、大勝ちはしなくても、しっかり生き残っていけるように、今後も多方面の情報収集を怠らないようにしようと、気持ちが引き締まりました。
医師の未来以外にも、沢山の話題が簡潔に書かれておりますので、興味のある方は是非、手に取ってみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーー
▼note
▼ブログ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
