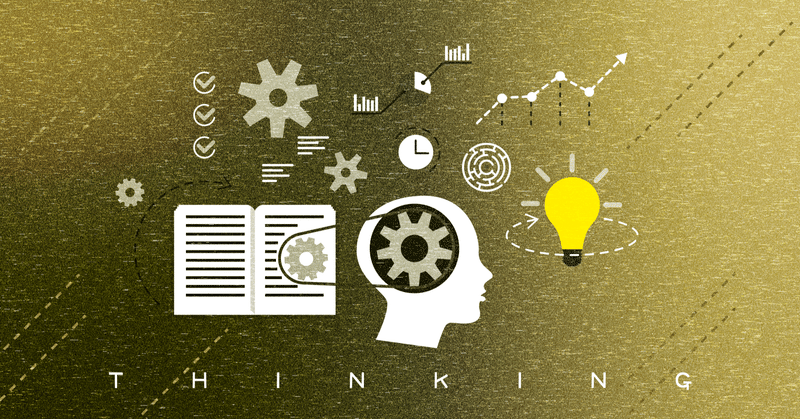
心理学を使って妹に宿題をやらせてみた
今年の夏休みは毎年同様、8月上旬から実家に帰省した。
大学生は宿題と言うものが基本的に皆無の為、暇を持て余していた。
僕には妹がいるのだが、とにかく勉強が嫌いらしい
いつも母親に怒鳴り散らされながら机に向かっている。
僕が帰省するといつものように「夏休みの宿題は終わったの?」
と母の怒号が響く。そのデカいつんざくような声を聞くたびに僕は
うんざりして気持ちが萎える。
幸いにも宿題があるのは僕ではなく妹のため、自分は怒鳴られなくて済む
大学生って親から口酸っぱく言われることもないし、宿題もないし、
お金は好きなだけ使えるし、とにかく小さな子供にとってあこがれの存在であるのに間違いはない。
今回は母からの罵声にうんざりしている妹に同情したため、
妹の夏休みの宿題を楽に最短で終わらせる手伝いをすることにした。
心理学を使って…
※あくまでこの方法は勉強嫌いのお子様に該当します。
勉強が得意で自主的に勉強することができる優秀なお子さんをお元の方にはあまり参考にならないと思います。
※僕の独断と偏見も交えて解説します。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
まず初めになぜ妹が宿題をするのが嫌なのか、その理由を聞いていった。
自分も高校までは毎日のように宿題をしてテスト勉強をして
勉強三昧だったので、その経験を生かして相手に共感して寄り添う姿勢で
質問した。
一番大きな障壁は、自分自身が夏休みの宿題の全てを把握しきれてない点にあった。どれが宿題でどれを優先して終わらすべきかの区別が未だつけられてなかった。そのため、宿題が無限にあるように思われて、何も行動する気になれなかったらしい。
これは激しく同意する。僕自身、テスト勉強する際はまずやるべき範囲や
覚えるべきものを洗いざらい勉強机までもってきて、全体でどれだけあるのかを確認する。それから、勉強する順番を決める。これを知らぬ間にルーティーン化していた。
その為、まずは妹に学校で出された宿題を全て自分の勉強机まで運ぶように催促して何から手を付けるのかを自分で決めさせた。
「今日は英語のワークと、数学の問題集」
「明日は社会のワーク全部と、読書感想文」…
ここでポイントは僕ではなく、妹に決めさせた点にある。
勉強させる側、つまり親御さんが全て決めてしまうと子供は自主性が乏しくなり言い訳を作って勉強に手がつかなくなる。
「自分で決めたこと、自分でやると覚悟したこと」、
この「自分で決めた」
という事実が責任感を伴って後々有効に働く。親が介入するのは最小限にしてほとんどは本人に委ねるのが正しい対処法だと信じている。
後は本人が決めた計画通りに事が進んでいるかを随時確認しに行くだけで充分である。親が離れたらスマホを触ったり、ダラダラして集中が出来なくなる子も多いので、できれば見守る側も同じ部屋で本を読んだり新聞を読んだりして共に勉強しているムードを作り出すと最適である。
なぜ見守る側がスマホを触ったりテレビを見るのがNGなのか?
子供目線で考えると「何で僕私は勉強している、
勉強させられているのに親はテレビ見ていいんだろう?
なぜ親はスマホを触っても誰にも怒られないんだろう?」
僕も小さい頃は常にこう感じていた。
親に反論してもはぐらかされるだけで納得できる回答を得られることはなかった。つまり、親と子供の行っていることが違うと子供はそれを「不公平」と感じてイライラする、勉強をやらないい訳にしようとしてくる。
それを失くすために見守る側も読書などをして勉強する。
一緒に勉強するのが本当に重要
一日で決めた課題を終わらせたら心から褒める
ここで褒めるのをためらってはいけない
確かに宿題をするのは当たり前で、
毎日コツコツするのも当然かもしれない。
しかし、勉強が死ぬほど嫌いな彼らにとって
宿題に真摯に向き合って何かを終わらせたという事実はこの上ない努力の賜物であり、褒められて当然だとまで思っている。
素直に頑張りを称えて何か小さなご褒美をあげてもいいと思う。
また褒めると同時に「本気でやればこれだけ集中して取り組めて、
計画通りにこ◯◯と◯◯の宿題を終わらすことができたね!
やればできるじゃん!」
と彼らの自主的な能力と、頑張ったプロセスを褒めるのがミソ
そうすることで「自分は宿題をこんなに短時間で終わらせられるんだ」
という小さな成功体験となり、自身がついて勉強が好きになる一助になると信じている。
そんなこんなでいろんな方法を組み合わせて妹に宿題をやってもらい、
とうとう宿題完遂率0%の状態から1週間で全ての宿題を終えることに
成功した。本人も1週間で終わったことに心底驚いている様子だった。
早く宿題が終われば、残りの休みは宿題のことなど気にせずに
存分に遊べる。それが、どれほどすがすがしく快感なのかを本人は強く実感したに違いない。
本人だけでなく、「宿題はやったのか?」と何度も問いかけていた母親の労力も必要なくなり、家の中で罵声が飛び交うこともなくなって僕自身も気持ちが良くなった。ウィンウィンの結果になって非常に良かったと思う。
本音で言えば、妹には自分から宿題に取り掛かって欲しいし、
勉強自体を好きになって欲しい。だけどそれはかなり厳しいことも知っている。僕自身、大学に入るまで勉強がまるっきり好きではなかった。
「やらされ勉強」が染みついており、先生からは宿題をやらされるし、
家に帰れば親から耳にタコができるほど勉強しろと言われる。
今やっている勉強は興味を持てないし、テストでもいい点が取れない
もう最悪だった…
大学に入学して自分が使える時間が膨大に増えてからいろいろと考えた。
読書も自主的にするようになり、勉強の楽しさを初めて見出すことが出来た。
本来は勉強は楽しいはずであり、自分から好奇心の赴くままに調べ尽くし、
掘り下げていくのが理想だと思う。しかし、僕が経験した義務教育をはじめとする学校教育はそんなに楽しいシステムは構築されていなかった。
全部学校のせいにするのも違うと思うが、何か改善すべきことがあることは間違いないと思う。
なぜ自分たちは勉強するのか、
勉強したら何かメリットはあるのか
何を求めて毎日宿題をしているのか
これらの問いを生徒自ら考える機会を設けて、教師も共に真剣に
議論し合って納得の行く解答を模索する。そうすることで、学校での教育活動の全てに意味づけがされ、生徒たちも自分から勉強する意欲が出るのではないかと思っている。
今行われている、暗記型の詰め込み教育は果たして教育といていいのだろうか甚だ疑問に残る。勉強を好きになれない人が圧倒的に多く、目的もないまま言われるがままにテストの為だけに丸暗記する。一夜漬けの記憶はもろく、テスト明けにはきれいさっぱり記憶が無くなっている。
こんな勉強をしていても何も身につかないし、楽しいと感じられるはずはない。自分の高校生までの学校生活を振り返ると、まだまだ改善の余地はあると感じる。僕ができる最大限のことは、こうしてnoteで自分の意見を述べること。
どこかで辛く悲しんでいる人が記事を読んで、ホット一息つけるような、
私は私のままでいいんだと安心できるような記事を書けるように
日々精進していこうと思う。
勉強する意義を考えた記事があるので、
ぜひ興味のある方に読んでいただきたい👇
今日はこの辺で(^▽^)/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
