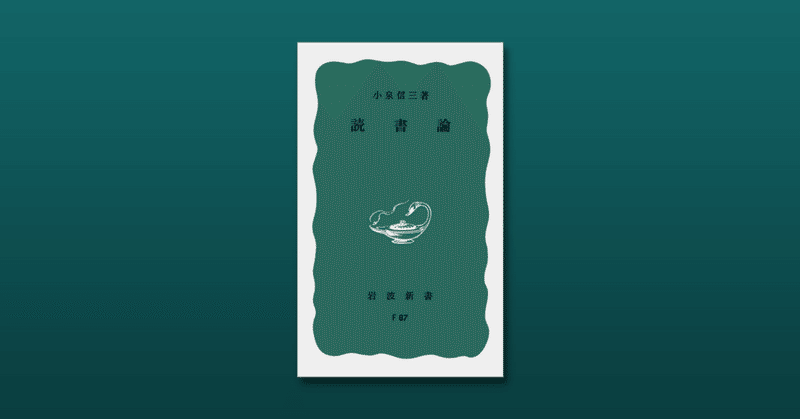
【読書感想】どんな本をいかに読むべきか?~小泉信三『読書論』~
読書をテーマとした本は多い。その中でも、僕が読書論の古典だと考えている本が3冊ある。
ショウペンハウエルの『読書について 他二篇 改版』とM.J.アドラー・C.V.ドーレン『本を読む本』は有名どころであろう。前者が読書という行為を論じているのに対し、後者は読書の技術を説いている。
そして3冊目が今回取り上げる小泉信三の『読書論』である。
本書では、どんな本を読むべきか、いかに読むべきかという話から始まり、語学力、書き込み、文章術、思索などにも及んでいる。先に挙げた書籍の中間に位置づけることが出来るだろう。
どんな本を読むべきか?
この世には、一生掛けてでも到底読破できないほどの本がある。人生は限られているのだから、あれもこれもと読んでいるわけにはいかない。
したがって良書の選択が必要となってくる。良書とは古典的名著を指す。そして小泉は、この良書=古典的名著を読むことを薦めている。
ここでいう古典とは、ただ単に古いという意味ではない。小泉によれば古典(classic)という言葉には、①ギリシア・ローマ的古代に属する、という意味の他に、②或いは承認されたる、第一流の標準的なもの、という意味がある。小泉のいう古典的名著とは、この②の意味である。
小泉は読書の利益についても触れている。小泉は、ここで言う利益とは手っ取り早い実用という意味ではない、と注意書きをしている。小泉が述べるように、世の中には手っ取り早く利益を得られる本が多く存在する。例えば、料理本を読めばレシピが手に入る。六法全書を読めば、契約や法律について書いてある。
このようにすぐに役に立つという意味において、古典的名著はすぐには役に立たない。しかしすぐに役に立つ本は、「吾々の精神的栄養を増してはくれぬ」と述べる。また、古典的名著について「人を眼界広き思想の山頂に登らしめ、精神を飛翔せしめ、人に思索と省察を促して、人類の運命に影響を与えてきた」とも言っている。ここから古典的名著の利益とは、人間の精神に関わってくることが想像できる。
名著は必ずしも大冊ならず、大冊は必ずしも名著ではないが、しかしそれぞれの時代を劃した名著の多くは大冊であり、そしてこれらの大冊に、偉大なる著者の創始と刻苦と精励とが体化されるのが常である。それを読むことによって、吾々は単にその書の内容を知るとばかりでなく、辛苦耐忍、いわば格闘してものを学ぶという、貴重な体験を得るのである。読む本のページ数のみを数えて喜ぶのは無意義であるが、努力して大冊を制服することは、人生の勉強としても大切なことであり、十数日、或いは数十日わき目もふらず一冊の本に取りついて、それを読み、且つ読みおえるという努力と忍耐とは、必ず人に何者かを与えずにはおかない。
実用的な本を読めば確かにすぐに方法や解決策が手に入る。しかし、すぐに役に立つ本は人間の精神に影響を与えることはない。一方の古典は、すぐには役に立たなくとも、人間に精神的な栄養を与え、思索と省察を促す。そして、古典を時間をかけて読み通すことで、忍耐と努力、人生の勉強という利益が得られる。
古典的名著をどう読むべきか?
そうなると、次に問題となってくるのは、古典的名著をどのように読むべきか、ということである。古典はとても難しい。少なくとも一読了解というわけにはいかない。その証拠に、書店に行けば古典の解説書、場合によってはそのまた解説書が多数売られている。
そんな古典に対して僕たちはどのように向き合ったら良いのか。小泉はこの問題に対して2つの解答を出しているが、どちらも至ってシンプルである。
1つは、とにかく読み進めるというものだ。読み進めることで難しいと思った部分が理解できたり、全部読み終えることで初めて部分が理解できるからである。
要するに、本を恐れずに読むこと、難解の箇処に出逢っても、それに辟易しないで読み進むことを、私はすすめたいのである。進んで先きを読んでいる中に、前に難解と思った語句や章節の意味が自然に会得されることは、非常にしばしばあるものである。(中略)もちろん解らない箇処に出逢えば、すぐ飛ばして先きを読むというような、横着なやり方で、名著や大著が自分のものになる筈はないが、しかしまた、あまり局部の字句に拘泥して、それに屈託していると、気分が饐えてしまって、解るものも解らなくなってしまう。
もう1つは、繰り返し何度も読むことである。古典的名著を1度読んだだけで理解するというのは、おそらく不可能だろう。もしかしたら一部の天才はそれが可能かもしれない。しかしそうした人を除けば、1度だけでなく2度、3度読もうというのである。
斯く難解の章節に屈託するな、というと共に、特にすすめたいのは、難解と平易とを問わず、同じ本を再読三読することである。実際相当の大著を、ただ一度読過したばかりで理解しようとするのは無理である。難解の章句が一読過では解せられないという外に、一回の読了ではどうしても書籍の部分に囚われて、それと全体の関係が分からない。二度或いは三度読んで見て、始めて著者の思想の全体、その全体における個々章節の意義または重要性というものが把握される。
読んだ感想~僕の経験から~
小泉は古典的名著を読むことを勧めていたのはすでに見たとおりだ。ただし注意したいのは、古典だけを読めと言ってないということである。すなわち古典以外の書籍を読むなとは言っていないということは、覚えておきたい。
生きていればどうしてもすぐに知りたいとか、知る必要があるという場面に遭遇する。そんなときに、そういった書籍はとても役に立つ。ただし、だからといってそういった本ばかり読んでいては、小泉の言うように人間の精神的な成長は望めないだろう。両者のバランスが大切となってくる。
また古典の読み方として、①読み進める、②何回も読む、ということを挙げていた。確かに、小泉のアドバイスには賛同する部分がある。一方で、この2つだけでは不十分ではないか、というのが僕の意見である。この点に関して僕自身の経験も交えながら考えてみたい。
僕は、昨年の6月から先生と僕の2人で読書会を行っている。課題本はオルテガの『大衆の反逆』である。
これまで『大衆の反逆』を読み進めてきたが、とても難しい。難しいのだけれど、小泉の言うように読み進めてきたことで理解できたことは何回もあった。また最初から繰り返し読むことで1回目には不明瞭だった部分が理解できたこともあった。
その一方で、古典はただ単に古い本ではないとはいうものの、その多くが時代的に古い。何十年前、あるいは何百年前に書かれた本はとても多い。つまり現代と書かれた当時の状況とではかなり異なるということだ。
オルテガの『大衆の反逆』も1930年ごろに書かれた。今から約100年ほど前である。したがって、現代の視点から『大衆の反逆』を読んでも、意味が分からないという部分も多い。現代ではなく、当時と同じ目線でその本を読むことが必要となってくる。そこで必要なのが背景知識だと僕は思う。背景知識とはその本が書かれた当時の状況や、著者の想定などがそれに当たる。
オルテガを例にすれば、彼は『大衆の反逆』を、彼と同じ時代を生きていた人々を批判するために書いた。より厳密に言えば、1930年代のヨーロッパに住む人々を批判するために書いた。なぜ批判するのか、それはどんな批判なのかについては幅の都合上割愛する。気になる方は是非読んでみて欲しい。
1930年を考えてみると、1922年にはイタリアでファシスト党が政権を取った。1933年にはドイツでナチスが政権の座に就いた。また彼はスペイン出身であるが、1936年から1939年にかけてスペイン内部では内戦が起きていた。同じ1939年には、ドイツがポーランドに侵攻し第2次世界大戦が勃発している。
つまり1930年というのは、革命とファシズムの真っ最中ということになる。これは僕の想像であるが、イタリアやドイツで独裁的な政権が誕生し、人々がそれに熱狂し戦争へと突き進んでいく様子を踏まえて、『大衆の反逆』を書いたのではないだろうか。
話を戻せば、このような情報は、『大衆の反逆』だけ読んでいても分からない。他の本や情報を参照する必要がある。それによって初めて著者と同じ目線に立つことができる。小泉のアドバイスに加えて、こうした背景知識があることで、より古典を読むことが出来るのではないだろうか。
終りに
本書の第1刷は1950年に出版された。今からおよそ70年も前である。当時と今とでは世界は全く異なるにも関わらず、その内容は輝きを失っていない。むしろ日々大量の情報が行き交う現代だからこそ、通ずる教訓がある。
情報の洪水と呼ばれる今だからこそ読みたい1冊である。
読んでいただきありがとうございます! 他の記事も読んでいただけたり、コメントしてくださると嬉しいです
