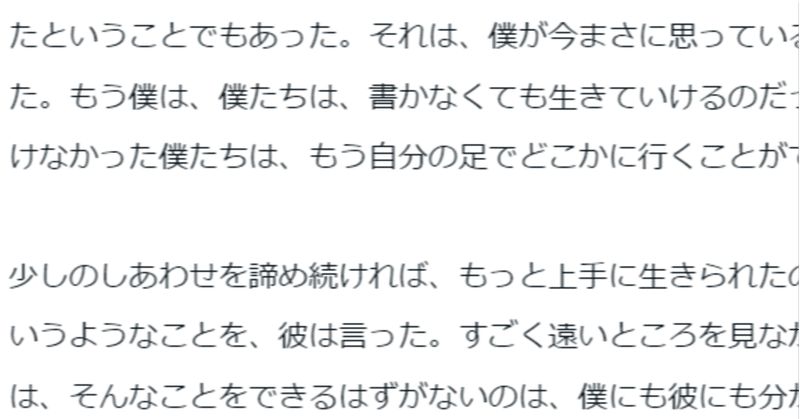
2022/12/11 かける
体調不良で倒れたお客さんの脇を抱えているとき、僕は生きているんだと思った。床に撒かれたドリンクがスニーカーの底を湿らせて、多分それはソフトドリンクだったから、足を踏み出す度にねちっこかった。生きているというのは、こういう感じだった。どこにも行けない僕たちは、何かのふりばかりを繰り返していたのだった。そう、そういえば、こういう感じだった。
彼はもう、書くことがなくなったのだった。それは、書かなくてもよくなったということでもあった。それは、僕が今まさに思っていることでもあった。もう僕は、僕たちは、書かなくても生きていけるのだった。どこにも行けなかった僕たちは、もう自分の足でどこかに行くことができるのだった。
少しのしあわせを諦め続ければ、もっと上手に生きられたのかもしれないというようなことを、彼は言った。すごく遠いところを見ながら言った。本当は、そんなことをできるはずがないのは、僕にも彼にも分かっていた。ペットボトルの水の、小さく揺れるその音が、やけに鮮明に拡大されて耳に届いた。喉を小さく鳴らすその音が、大事なセリフのように空間を満たした。マイクは振動を拡大させるけれど、そのことを忘れてしまいそうになるけれど、その振動を生み出す僕たちはこんなにも小さく揺れているのだった。
書かなくても生きていける僕は、それでもなお、書くのだろうか。書けるのだろうか。かける、駆ける、駆けこむ、駆けこみ、駆けこみ乗車はおやめください、おやめください!駅員さんの声が、マイクで拡大される。駆ける、書ける、語り掛ける、そう、欠けているのは、世界の方ではないか。僕らはこんなにも満たされているのだから。
最寄りの駅に着いたら、地面が濡れていた。スニーカーの底がまた湿って、多分それは雨だったから、足を踏み出すたびに嫌悪感が募った。土日はずっと晴れると聞いていたからわざわざ布団を干したのに、結局雨で濡れてしまった。こんなことばかりを繰り返して、やっぱり僕は生きている。雨は一生嫌いだと思う。
おつかれさまなどという言葉をかけるのが、ずっと悔しくてならなかった。けれど、今は自然と書ける。掛ける。語り掛ける。どうか、君が思うように好きなことを始めてほしい。もう僕たちは、自分の足でどこへでも行けるのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
