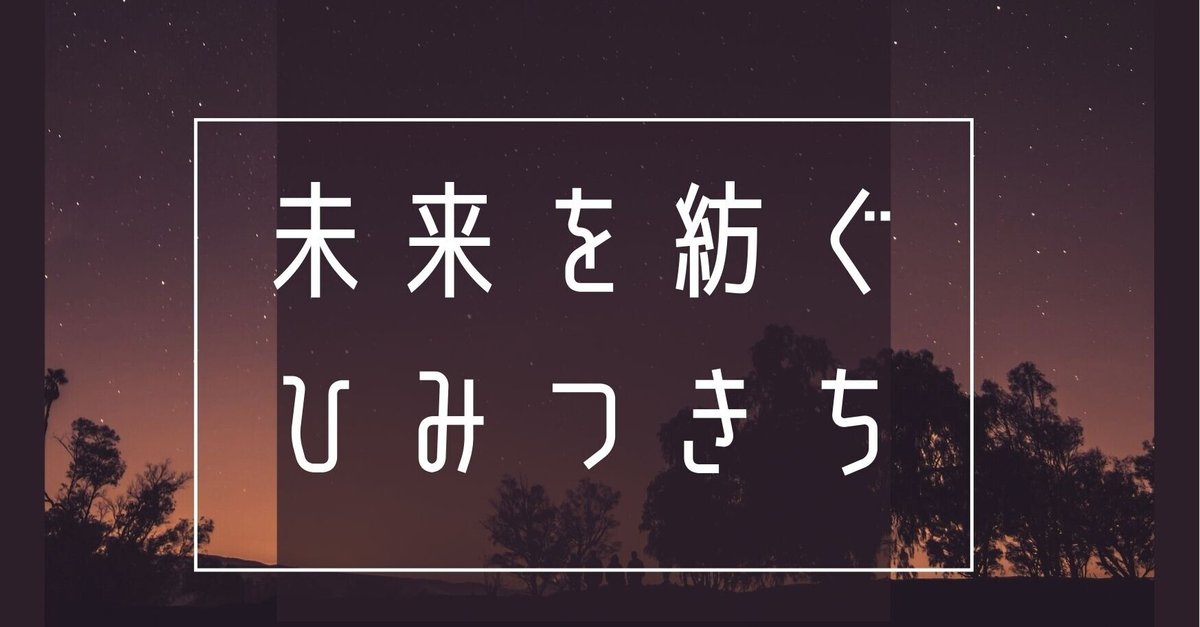
未来を紡ぐひみつきち #3
その後、リディオたちはすぐに泉を離れた。マグィは、合議の席についた父親の後ろに巌のごとく佇んで、互いが見えなくなるまでリディオを睨み続けていた。
木から木へ、ヤンが器用に跳び移る。
ゲンランがとことこと地面を走って追いかける。
リディオは彼らの後ろを翔んでいた。
濡れた枝と土のぬかるみに足をとられ、二人は何度も転がった。リディオが手を貸し身を起こして、また進む。
だれも、なにも言わなかった。
やがて視界がひらけたところで、ヤンが止まった。
美しい――沢である。
ごつごつとした大きな岩のあいだを縫うように、小川が静かに流れている。幅は狭く、深さもそんなにないらしい。澄んだ水の匂いと、両岸から張り出した木の葉の茂る枝が、薄緑色の天幕を作っている。洩れてくる陽光が、白い模様となってそこらじゅうに散っていた。
「いいところだろ。俺が見つけたんだぜ」
振り返って笑ったヤンは、ぴょいと枝から飛び降りた。川下のほうを指さす。
「あっちのほうにはラミン(野苺)がたくさん生ってるんだ。穴場だぜ。すげぇ甘くてさ。森でいちばんじゃねぇかな」
誰も――なにも、言わない。
ヤンは笑顔のまま、眉を下げた。
「……なんだよ。感動して声も出ねぇか?」
うつむいていたゲンランが、力なく首を振った。ヤンのそばまで歩みを進めて、手の傷みせて、と呟くように言う。
ヤンをその場に――木の根元に座らせると、自分もしゃがんで、腰につけていた袋の中から小さな包みを取り出した。サク――森でよく見かける、ぎざぎざした葉をもつ蔓草である――から作成した傷薬らしい。
しみるよ、と言ってから丁寧に傷口に塗りこみ始めた。
ヤンが顔をしかめる。
ゲンランは黙々と手当てをすすめる。
そしてふたたび、呟くように。
「……ごめんよ、ヤン。リディオも」
「なにが」
ぶっきらぼうにヤンが返す。ゲンランは、彼の手に巻くために取りだしたのだろう手巾を、膝の上で握りしめて、言った。
「あのとき、ぼく、恐くてなんにもできなかった」
「べつに――俺だって恐かったし。おまえが謝ることねぇよ、なあリディオ」
リディオは頷く。
今になって思えば――むしろ、止めてくれて良かったのだ。
感情のままに暴れていたらどうなっていたかわからない、自分一人の問題では済まなくなっていたかもしれない。父の低頭した後ろ姿を浮かべそう思った。
いくら厭うたところで自分は嗣子であるに違いなく、父と並んで代表者であり――であればこそ、邑に累が及ぶ可能性だって少なからずあったのだ。
到底、納得などできないけれど。
するとそれを代弁するかのように、ヤンが続けて声をあげた。
「っつーか。あいつが生意気なのがいけねぇんだよ。馬鹿にしやがって。なにが」
言いかけて、口を噤む。うつむいた目許に翳が落ちる。
卑小な栗鼠(ワンリー)族ふぜいが――。
マグィの侮辱が、リディオの耳にもよみがえった。
ヤンは一度唇を噛むと「くそぉ」と今度は威勢よくわめく。
「いッちばん年下のくせに威張り散らしやがって。腹立つったらねぇぜ、まったく」
リディオとゲンランは、互いを盗み見るように視線を交わした。
成年は、種族によって違いがある。寿命に差があるからである。四ツ族の中では栗鼠族がもっとも短く、ゆえに成長ももっとも早い。数え年でいうのなら――ヤンがいちばん若かった。
二人とも、わかっている。
たぶん当人もわかっている。
「おまえもふてぶてしかったけどな、リディオ」
「うるせぇな」
「おまえソレばっかだな」
「……うるせぇな」
あは、と声をあげてヤンが笑う。
普段よりも明るく、饒舌で――それがやけに痛々しく見えてしまう。リディオは余計に気が塞いで、外した視線を沢へと向けた。
本当に、綺麗な沢である。
ヤンは一人で森を駆けまわり、ここを見つけ――きっと、今日を心待ちにしていたのだろう。胸がつくんと痛んだ。
「――俺たちはさ」
ヤンがふと、静かに言った。
「俺たち栗鼠族はすぐに死んじまうから、合議に参加しても、顔も名前も覚えてもらえねぇんだよ。あっというまに代替わりしちまうからさ。……小せぇし力もねぇし、だから発言権もないも同然で――いつも、肩身が狭い。祖父ちゃんも父ちゃんも、ずっと言ってた。……ま、しょうがねぇんだけどな、こればっかりはさ」
調子を戻して、肩をすくめる。
でもさ、と。
ヤンの眸はまた静かになって、
「できることはあると思ったんだよ――」
遥か遠くを見るように、沢のほうへと動いていく。
「俺が邑長として、おまえらと合議の席につけるのは――きっと、多くたって一回だ。……俺から代替わりしたあと……俺の子供や、その子供たちのこと――気に掛けてやってくれねぇかな。ほんのちょびッとでいいからさ」
少し迷うように、躊躇するように言ったあと、ヤンははにかむように笑ってこちらを向いた。とたん、ぎょっとした顔で――手当てが済んだのだろう、しっかりと手巾でくるまれた――手を引っ込める。
「な、なんだよ。なんで泣いてんだよおまえ」
「だって、だって」
鼻をぐしぐし鳴らすなり、ゲンランは、うわあんと弾けるように泣きだしてヤンに横から飛びついた。倒れる二人。ぎゃあつぶれる、とふくよかな腹の下からヤンの悲鳴が聞こえてくる。
栗鼠族は――本来とても臆病な性格なのだと――初めて合議に参加した帰り途、父がひとり言のように言っていた。いったいどこが臆病なんだと、リディオはずっと思っていた。
でも――。
――できること、か。
考えたこともなかったけれど。
リディオは二人のもとへ行き、
「つぶれる」
抱え上げるようにしてゲンランをはがした。すると今度は、身をひるがえしてこちらに抱き着き、おいおい泣きだす。洟と涙で服が大変なことになっていく――と他人事のように思いながら、ふっくりとした肩を慰め程度にたたいてやっていると、ふと、ヤンと目が合った。
リディオは少しだけ口元を緩めた。
ヤンが目をまるくする。けれどすぐに、いつものように、屈託なく笑った。
跳ねるように立ちあがると、脇の茂みに上半身ごと腕を突っ込んだ。すぐに葉くずだらけの頭が出てくる。隠し置いていたらしい、手巾の結ばれた手には長い枯れ枝に襤褸布を括りつけただけの――旗のようなものを持っていた。
いいか、とヤンが目をきらきらさせる。
「今日からここが俺たちのひみつきちだぜ!」
「――クソだせぇ」
六ツや七ツの子供でもあるまいに――と、リディオは思う。
「でも――まんざらでもなさそうだ」
いつのまにか泣き止んでいたらしいゲンランが、目をこすりながら含み笑いを返してきた。
二人を見、沢を見わたし、まあな、と呟いたリディオは――彼にしてはめずらしく、ふッと小さな笑みをこぼした。
―――――――――――――
*1話めはこちらから🐿🐿🐿
ここから先は

【完結】未来を紡ぐひみつきち #1~#7
*邑長を継ぎたくないわがままリディオの成長記* 森にすむ四ツの異種族間の交流や格差を描いたファンタジーです。 翼をもつ黒烏(スマル)族の…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
