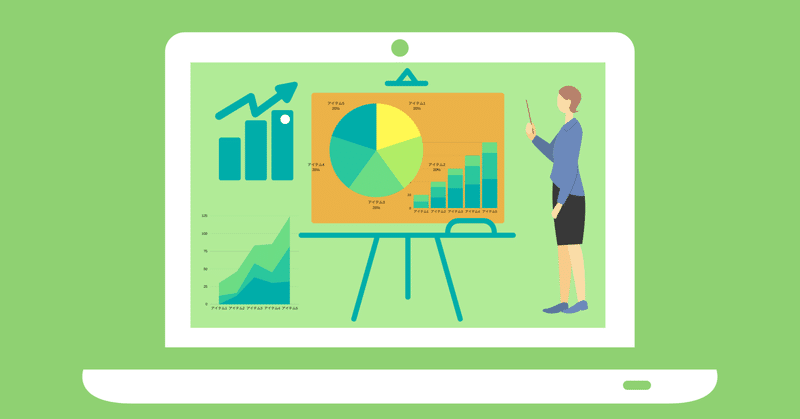
第6回大学教育イノベーションフォーラム「若手からみた大学教育とFD・SDの未来」への参加から考えたこと
2021年10月28日(金)にオンラインで開催された第6回大学教育イノベーションフォーラム「若手からみた大学教育とFD・SDの未来」を視聴した。この会は全国各地の教育関係共同利用拠点(大学の職員の組織的な研修等の実施機関)が加盟している大学教育イノベーション日本が主催しているものだ。
参加直後にTwitterにもメモを書いたのだが、大変興味深い会でいろいろと考えさせられた。ので、改めて、このnoteにも当該フォーラムへの参加から考えたことを綴りたいと思う。
今日は第6回大学教育イノベーションフォーラム「若手からみた大学教育とFD・SDの未来」(https://t.co/26kHH8Yzt7)を視聴した。FD・SDについて「若手」が語るという形式で珍しい会だと思って参加した。6名の「若手」からの報告はどれも大変興味深い内容だった。
— 小林良彦(こばやしよしひこ) (@yoshikoba113) October 22, 2021
さて、今回のフォーラムに参加しようと思ったのは、知り合いが登壇することもあったのだが、「若手」というキーワードに魅かれたためだった。魅かれた理由は、自分も「若手」であることや、こういった大学教育に関するフォーラムでは、ベテランの教員が登壇することが多い印象なので、「若手」を中心とした会は貴重だなと思ったためだ。
ちなみに、開催ポスターにも、以下の文章が書かれており、「シニア~ミドル層」以外の声も取り上げるための会であったことが分かる。「シニア~ミドル層」からの発信も欠かせないことは言うまでもないが、こういった「若手」からの発信を扱う会もあると良いと思う。
これまでの大学教育界の未来像をめぐる議論においては、高等教育界において一定の経験を積んだシニア~ミドル層からの発信は少なくないものの、大学教育の未来を当事者として長く担っていくであろう若手の側からの意見が、十分に拾い上げられてこなかったのではないか、との認識を持つところです。
実際に参加して、とても有意義だった。登壇された5名の「若手」の方々からの報告はどれも興味深く、かつ、重要な指摘ばかりだった。なかなか突っ込んだ指摘もあり、報告者の皆さんの気概を垣間見た。
今回のnoteでは、特に印象に残った、以下の3点について書きたい。
オンライン化が進んだ中で教育関係共同利用拠点の地域における役割
大学教職員が自身の価値観を言語化することへの支援
ファカルティ・デベロッパーのアイデンティティの問題についての指摘
オンライン化が進んだ中で教育関係共同利用拠点の地域における役割について
1点目の「地域拠点」としての教育関係共同利用拠点については、かくいう僕も教育関係共同利用拠点の業務に従事していたことがあるので、重要な指摘だなと再認識した。
研修会やセミナーのオンライン開催が常態化した現在、参加や講師招聘に伴う出張が(ほとんど)必要なくなった。参加する側としても「あのセミナーに参加したいけど北海道大学かぁ。さすがに札幌まで行くのは難しいかなぁ」とか「お!あの先生が今度、九州大学でセミナーをするんだ。福岡なら参加できそう」といった開催場所による検討がなくなったのだ。また、講師招聘する側としても「福岡に呼ぶとなると前泊してもらう必要があるかなぁ」などという悩みもなくなった。
つまりは、内容が同じであれば、北海道大学で開催することと九州大学で開催することの差は、オフラインのときと比べると格段に少なくなっただ。となると、開催する側は当日の内容や開催時期などをより工夫せざるを得なくなったのかな、とも感じる。学外にも広く公開された研修会やセミナーを開催するという面については、全国各地に教育関係共同利用拠点がある意義を再考する必要があるのかもしれない。
大学教職員が自身の価値観を言語化することへの支援について
2点目に挙げた「支援」は異なる価値観を持った者同士が協働していく上では欠かせないことだ。価値観が違う者同士で議論をするときには、まず、お互いの価値観を共有する必要がある。それは大学教育についても同様だ。
「大学教育はこうした方が良い」や「大学はこうあるべき」といった感じで、大学教育ひいては大学について一家言を持つ大学関係者は少なくないはずだ。しかし、自分が持つ大学教育に関する価値観を他者と共有できるレベルで言語化することは簡単なことではない。そもそも、言語化する機会も多くないことも一因だと思うが。
だから、より良い大学教育や大学について考えるために、自身の価値観を言語化することへの支援が必要となる。大学教職員がその支援を受ける機会を提供する機能を大学が兼ね備えていることは大切なのだな、と報告を聞いて感じた。その一例がティーチングポートフォリオの作成支援なのだろうと思った。
ファカルティ・デベロッパーのアイデンティティの問題について
3点目のファカルティ・デベロッパーのアイデンティティの問題については、今回のフォーラムの中で最も深刻な指摘だったのかなと感じた。事実、僕も教育関係共同利用拠点で働いているときに自身のアイデンティティについて悩んでいた。
ファカルティ・デベロッパーは学部や研究科といった部局の所属ではなく、学生指導にも携わらない場合もあるので、世間がイメージする大学教員とは少し性質が違う。もちろん、比較的新しい職種なので、「仕方ないよね」という面もあるが。また、ファカルティ・デベロッパーのポストも他の大学教員ポストと同様に任期が数年のものが多いことも問題だ。
報告では、任期を少し長めにすることや、学部や研究科にも所属を置くこと、教育や研究に関する業務にも携わることが必要だという指摘があった。そして、それらについて公募要領に明記した方が良いのではないかという指摘もあった。こういった指摘や提案に僕も同意する。キャリア形成にも関わる重大な問題なので、これこそ、若手からの問題提起という印象だった。すぐに対応可能なものではないとも重々承知しているが、今回のようなフォーラムで明確な問題提起がなされたことは非常に重要なことだと感じた。
以上が第6回大学教育イノベーションフォーラム「若手からみた大学教育とFD・SDの未来」に参加して、僕が感じたり考えたりしたことだ。僕は既に教育関係共同利用拠点の業務には携わっていないが、一大学教員として、これからも大学教育には問題意識を持ち続けていきたい。また同様の会があれば参加してみようと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
