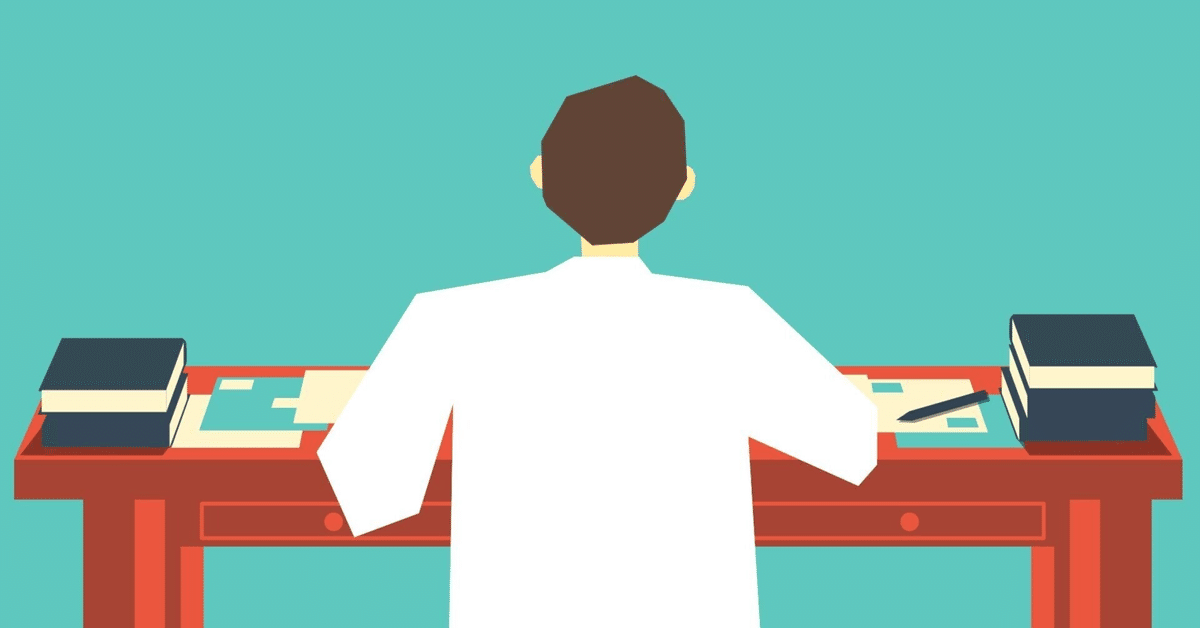
『数学文章作法 基礎編・推敲編』(結城浩 著 筑摩書房 2013・2014)読書感想文
論理的でかつ平易な文章を書きたい。いつもそう思う。それはつまり、自らの考えや伝えたい情報を、相手に正確にかつ分かり易く伝えたい、という願望だ。今回のnote記事では、そのための指針を与えてくれる書籍『数学文章作法』を紹介したい。
『数学文章作法』に通底するテーマ
今回紹介する『数学文章作法』は基礎編と推敲編の2冊から成る。以下ではそれぞれを『基礎編』『推敲編』と表す。また、2冊を合わせて指す場合は『数学文章作法』とする。
さて、『数学文章作法』には通底するテーマがある。それは、
読者のことを考える
である。文章を書くに当たっては当たり前のことだと思うかもしれない。しかし、「読者のことを考える」ことを執筆や推敲へとどう反映すれば良いのか。これは意外と難しい。
『数学文章作法』では、「読者のことを考える」ことを前提に、具体的にどのような工夫をすると、正確にかつ平易に読者へと伝わる文章が書けるのかが説明されている。
『基礎編』『推敲編』の相互の関係
さて、『数学文章作法』を成す2冊、『基礎編』および『推敲編』、はそれぞれどのような役割を担っているのだろうか。著者である結城氏は以下のように説明している。
『基礎編』・・・正確で読み易い文章を書くこと
『推敲編』・・・より正確で読み易い文章に書き直すこと
つまり、『基礎編』は書く前に読む、『推敲編』は書いた後に読む、といったところだろう。2冊それぞれに役割分担されている点も『数学文章作法』の特徴だと思う。
以下では、『基礎編』『推敲編』を読んで、筆者が印象に残ったポイントについていくつか紹介したい。
『基礎編』で印象に残ったポイント
『基礎編』では、文章を書く際に気を付けねばならないことを学べる。まず、先に挙げた通底するテーマ「読者のことを考える」だが、以下のように三つに腑分けされている【『基礎編』p18】。
読者の知識・・・読者は何を知っているか
読者の意欲・・・読者はどれだけ読みたがっているか
読者の目的・・・読者は何を求めているか
この三つの観点で読者に寄り添うことが欠かせないのだ。また、結城氏はそれぞれが不変なものではなく、読み進めていく上で変化していくものだとも書いている。この点もとても印象に残った。
「読者の知識」に寄り添うためには、考えを示す順序が大切になる。ここまで読んだ読者はこの内容を理解できるだろうか、とチェックしながら情報や考えを提示していく必要がある。
「読者の意欲」を向上させるためには「変化」を織り交ぜることが大切だ。どのような変化かというと、以下のようなものである【『基礎編』p20】。
抽象的な話が続いたなら、具体例を出す。
具体的な話が続いたなら、まとめを出す。
言葉の説明が続いたなら、図・グラフ・表を出す。
最後の「読者の目的」に寄り添うためには、目次を分かり易い構造に整備することが欠かせない。また、読者が調べるためには索引も欠かせない。結城氏は索引について以下のようにも書いている。
読者が調べるときに使う長い説明文なら、索引は必須であると心得てください。索引がなかったら、読者は文章の中から特定の用語が出てくるところを探さなくてはなりません。それはたいへんな労力ですね。著者が索引を用意する必要がないのは、その文章が短い場合か、調べるときに使わない文章の場合か、索引の代わりとなる検索機能などがある場合だけです。
結城氏の「読者のことを考える」が伝わる文章だと感じた。
『基礎編』の目次
参考のために『基礎編』の章立てを書いておく。
第1章 読者
第2章 基本
第3章 順序と階層
第4章 数式と命題
第5章 例
第6章 問いと答え
第7章 目次と索引
第8章 たったひとつの伝えたいこと
『推敲編』で印象に残ったポイント
『推敲編』では、文章を書き直す際の心構えだけでなく、「悪い例」を提示した上で具体的な「改善例」が随所に散りばめられているのが特徴だ。なので、「確かにそうすると読み易い」と頷きながら読み進めることができる。
「読者の知識」に寄り添う文章として、読者が積み木を積むように考えを進められるよう、長い一文は短い文を重ねる形式に変更すると良い。そうすると読者が一文一文を「なるほど」と思いながら読めるようになる。
続いて、以下の三つの点について紹介したい。
主張をぼかす言葉
誤解を招く複文
言外の意味
「主張をぼかす言葉」は「など」「したりする」などの表現を指す。これを使った例文は以下である。
悪い例:主張をぼかす言葉が残ってる
最後にshowなどのコマンドを入力したりすると、枠で囲まれたような文字列が画面に表示されるようになるのです。
改善例:主張をぼかす言葉を削った
最後にshowコマンドを入力すると、枠で囲まれた文字列が画面に表示されます。
文章をすっきりさせるためにも、不要な「など」「したりする」「ような」「~といった感じ」「~といえないこともない」などを削った方が良い。
続いて「誤解を招く複文」。複文とは複数の動詞(述語)が一文に含まれる文のことだ。例を見てみよう。
悪い例:誤解を招く文
私はカメラを抱えたまま寄ってきたリスにクルミをあげた。
改善例1:読点を打つ
私はカメラを抱えたまま、寄ってきたリスにクルミをあげた。
改善例2:語順を変える
寄ってきたリスに、私はカメラを抱えたままクルミをあげた。
「悪い例」の場合、「私」と「リス」について、以下のように異なる解釈が可能になる。
解釈1:「カメラを抱えたまま寄ってきたリス」と「クルミをあげた私」
解釈2:「寄ってきたリス」と「カメラを抱えたままクルミをあげた私」
読者は解釈1は違うだろうと思い、解釈2を採用するだろう。しかし、この例のように判別が自明でない文章の場合は混乱を生むので、複文を使う際は注意が必要になる。
最後に「言外の意味」について取り上げる。結城氏は「言外の意味」について「文字としては書かれていないのに、自然と心に浮かんでくる意味」と説明している【『推敲編』p96】。また、別の言葉で「自然に浮かぶ疑問」「可能性の雲」「暗黙の主張」とも表している【『推敲編』p98】。
例えば、以下の例は「言外の意味」を含んでしまっている。
例 薬品Aは、薬品Bとは反応しない。
改善例
薬品Aは、薬品Bとは反応しない。それは薬品Bに含まれている成分のうち・・・だからである。
このように、薬品Aは薬品Bとは反応しないが、薬品Cとは反応する。なぜなら、薬品Cは薬品Bとは違い、・・・だからである。
「薬品Bとは反応しない」と書かれると、読者は「他の薬品とは反応するのか」と疑問を持つ。そのモヤモヤを直後で解決するような説明にすると、読者も気持ち良く文章を読み進めることができる。
以上のように『推敲編』でも「読者のことを考える」が徹底されている。
『推敲編』の目次
参考のために『推敲編』の章立てを書いておく。
第1章 読者の迷い
第2章 推敲の基本
第3章 語句
第4章 文の推敲
第5章 文章全体のバランス
第6章 レビュー
第7章 推敲のコツ
第8章 推敲を終えるとき
第9章 推敲のチェックリスト
『数学文章作法』は座右の書としておすすめ
『数学文章作法』には「読者のことを考える」ためにすべきことがたくさん書いてある。なので、辞書のように座右において、事あるごとに参照する方が良いと思う。
筆者も『数学文章作法』に座右に置き、読者により正確にかつ分かり易く伝わる文章を書くことを心掛け続けたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
