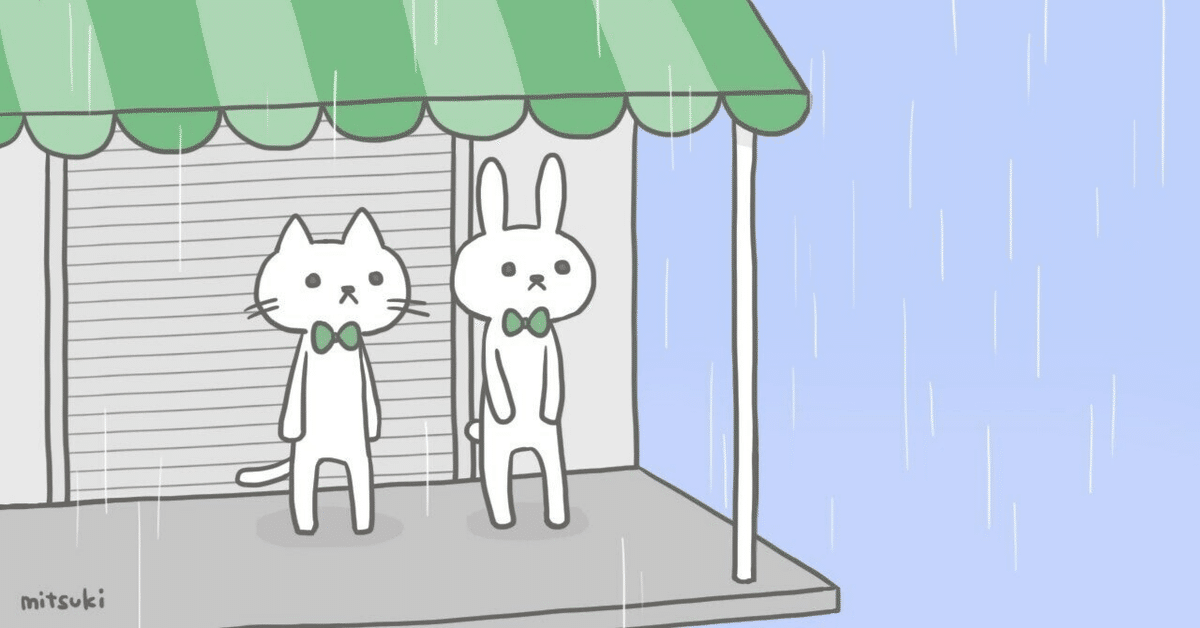
noteの距離感と雨宿り
先日の、海人さんの記事。
「あなたの記事が話題です」というnoteからの通知だったのですが、渡邊有さんの小説の紹介の後に、まさか自分の「創作作品」が紹介されるとは思ってもみませんでした。エッセイはご紹介いただいたり引用していただいたことがありましたが、創作作品を取り上げていただいたのは初めてでした。
「とても面白い」。
目のかすみが原因で良く見えてないのでなければ、間違いなくそう書いてあります。
嬉しくて、心臓がどきどきしました。
動悸がした時は恋より心臓の心配をする年齢ですが、年甲斐もなく胸がどんどこ高鳴りました。
海人さん、ありがとうございます!
noteを始めた時は、小説や映画の感想文を中心に読んでいました。あまりにも読むジャンルを広げると、note沼にハマって他のものが読めなくなると思ったからです。
このくだりを読んだときは、ううむさすが海人さん、と思いました。私は最初は読み専で、正直なところnoteのことはよくわからなかったので、手当たり次第に読みはじめて完全なる沼っ子になっていたからです。
加減がよくわかりませんでした。
ただ最初、小説はできるだけ、すでに完結しているものを読んでいました。それこそ連載は、どのくらい追えばいいのか果てしない感じがしたものです。毎日投稿されても自分のペースで読んでいいのだと気づき、連載ものを読み始めたのは比較的時間が経ってからです。
当時はnoteで小説を読むつもりはありませんでした。家にも積読になっている小説が多数ある中、これ以上読む作品を増やしたくないという理由です。
これについても全くその通りで、私の場合は「note小説を楽しみながらも、本が読めないジレンマ」に直面することになりました。実際、自宅や書店、図書館の本を読む量は確実に減り、当初の「自称:読書ブロガー」も返上だなこれは、と思うに至るほどです。
noteは「読む」「書く」媒体。
まずは自分が読むことと書くことのバランスを取る難しさに直面します。その後、「読むにしても、どんなジャンルの誰の何を読むか」「どのくらいフォローしている、あるいはされている相手と交流するか」という問題に突き当たります。
海人さんがおっしゃる「職業作家が書く小説と、note小説は別種の楽しみ」「note小説は作品世界を超えた部分まで楽しめる小説」というのはまさしくその通りだと思いました。
noteは、日々の投稿などで作品よりも「その人」を先に知ることがあります。「作家」としての出会いというよりも、「noteの知り合いが書いた作品」という目線があっての出会い。これは不思議な感覚です。また、先に作品を知っても、「ああ、この方はこんな感じの方なんだ」と感じることのできる投稿があると安心したり意外に感じたりします。
「noteの知り合い」という距離感。
それがちょうどいいのではないかという海人さんの言葉がとても腑に落ちました。
これが現実に知っている相手だと、ちょっと生々しくなりすぎるかも。職場の後輩に小説を見せられたら、「こんなの書いている暇があったら、報告書を書く練習しようよ」などと思ってしまうかもしれません。モデルはあの人…? などと邪推してしまう危険もあります。
これこれ。これですよね。
普通に生活している中で「つ、ついに小説を書きあげましたぁっ。読んでくださいぃぃ―――!」と、堂々と自分の原稿を家族や親せき、友人知古、上司や部下に渡せるか、というと、普通はなかなかできません。ものすごい葛藤に苛まれると思います。出版社に送ったり、公募に応募するときにも、初めてなら相当に悩むと思います。
これを小説にしてしまったのが、この作品。
この本、少々違和感を感じるのは、そもそも「無名の新人」と言いながら、この小説の主人公は放送作家として仕事をしていて、小説と言う形式は取っていなくても日々自分の文章を他人に読まれているのですよね。そのうえ、実際に書いたご本人は芸人さんです。他者の前に自分をさらけ出すことにある意味慣れていて、身バレも恐れていない人、と言えます。正真正銘の「無名」ではないわけです。
それでも「創作」を他人に読んでもらうという壁は高いわけで、私のような正真正銘の「無名人」には、作者おぎすさんよりも大きな葛藤があると断言できます。
そこを、大幅にハードルを下げ、葛藤を緩和してくれるのがnoteの存在なのだろうと思います。
私の創作作品のことを、家族はついぞ知りません。「みらっち」で書いているのは知っていますが、「吉穂みらい」が『駐妻記』以外の創作をしているとは思っていないと思います。おそらく「読んで」と頼んでも「はいはい。それより餃子キボンヌ」と流されることでしょう。
逆に言うと、身近な人が書いたものを、冷静に読めるかという問題も発生すると言えます。やはり作品そのものを受け止めるには、作者の分量が濃すぎて無理、入ってこない、という場合もありそうです。
noteの距離感は、職業作家ほど遠くはないけれど、身近な人よりは遠い。
それが、書くにも読むにも、ちょうどよいのかもしれないと思います。
また、最近は「時期」というのも関係していると思っています。
タイミングというのでしょうか。
コロナ禍以前にnoteをしていたかたもたくさんいらっしゃいますが、おそらくコロナ禍にnoteを始めた人は相当数にのぼるのではないかと思います。
なにしろ、暇がありました。仕事に制限が加わったり、世の中全体の動きが淀み、停滞していて、読み書きする時間があったのです。
そもそも、noteは続けるのが難しい媒体と言われています。先に書いたように、読み書きのバランスや交流が難しいからです。書いたものが大変よいものでも、スキやフォローが付かない場合もあるし、内容のない残念なものでも商業的なやり方次第でバズったり桁の違うフォロワーがついたりもしている現状に、意欲を失ってしまう人も多いと思います。
この春から、急激に仕事が忙しくなった人を何人も知っています。noteを離れた人も離れざるを得なかった人も多いです。全く離れなくても休止、あるいはちょっと休むつもりが自然に心がnoteから離れた人もいると思います。
世の中が動き始めて、潮目が大きく変わっているようです。
コロナ禍のnoteはまるで、雨に降られて雨宿りしていた軒下のようだな、と感じることがあります。
人生とは、嵐が過ぎ去るのを待つことではない。雨の中で、どんなふうに踊るかを学ぶことだ。
Life’s not about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.
「雨の日の格言」などで知りましたが、私はこの言葉の本来の出典を知りません。コロナ禍、よく取り上げられていた言葉だったと思います。コロナ禍を「荒天」「困難」ととらえていた人が多かったのでしょう。
今はようやく雨がやみ始めて、それぞれに軒下から出て歩き出すような感じがしています。
雨が上がっても、創作を発表することや読むことを選んだ人は、雨の中で「踊ることを学んだ」人たちかもしれません。
おそらく今後、SNSではより短くて端的な、それでいて面白く心を動かされるものを求める傾向はいっそう強まるように思います。
しかし、良いものは残っていくし、読まれると信じます。溜まった水が流れ出すような勢いの良い流れのあるときは、それに疲れてしまう人も多いと思うから。
noteの距離感を大切にしつつ、noteで出会える小説をもっと楽しみたいという、海人さんの記事。
心を動かされました。
私も、読み書きの時間をうまく工夫しながら、楽しんでいきたいと思います。
海人さん、改めて、ありがとうございます!
そしてこれからも、よろしくお願いします。
海人さんの記事で知った渡邊さんの小説には、私もすでにハマっております。
これがまた、noteの醍醐味と言えましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
