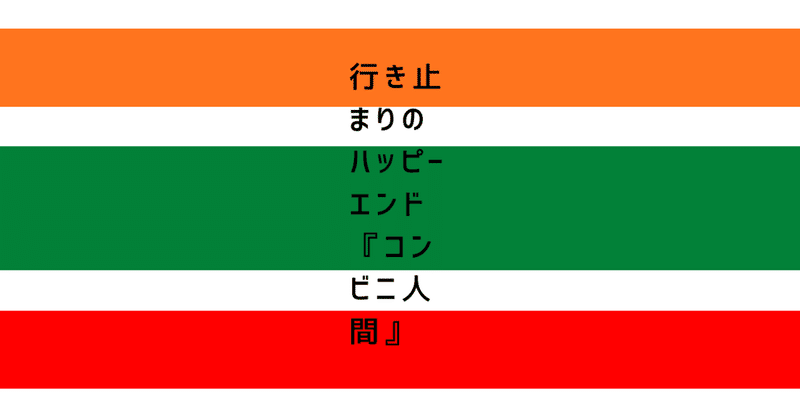
行き止まりのハッピーエンド『コンビニ人間』
こんにちは、シノです。今回は最近読んだ小説について、けっこうな熱量で感想を書きました。わたしにこの本を譲ってくれたデザイナーのS先輩ありがとうございます!この記事、読んでくれるといいな。
日本でいちばん有名な”店”
それはコンビニだ。コンビニ、と聞いてイメージできない人はいないと思う。
在宅勤務になってからコンビニでランチを買うことが増えた。近所のセブンイレブンにはほぼ毎日行くので、店員さんとなんとなく顔なじみになる。顔なじみ、と書いたがそれはわたしサイドの問題で、店員さんは別になじんでない可能性も大いにある。セブンイレブンの一日の来店者数は全国平均で1000人を超えるという(「セブン‐イレブンの横顔 2019-2020」より)。1000人の中の1人を憶えるのは、よほど特徴的な場合だけだろう。
セブンイレブンのお兄さん
わたしより年上かどうかもわからないが「お兄さん」とひそかに呼んでいる店員さんがいる。明るい茶髪を肩くらいまで伸ばしていて、たまたま制服を着ていない姿を見かけた時はロックな出立ちだったのでバンドマンかもしれない。
お兄さんは動作にムダがなく、客の動きをよく見ているので察しが早い。店員さんによっては矢継ぎ早に定型文でしか聞いてこない「袋いりますか」「お箸つけますか」も、わたしがマイバッグをゴソゴソ出しているのに気づくと言わないで待ってくれるし、「あ、お箸とか大丈夫です」という曖昧な日本語でも理解してくれる。これはちょっとしたことだけど高度なコミニュケーションで、お兄さんがレジ担当だと気持ちよく店を出られる。
コンビニは商品、客、店員、それぞれが決まった役割をまっとうする秩序ある世界だ。わたしの人生においてお兄さんは「セブンイレブンの店員」という明確な輪郭を持った役で登場する。逆に考えると、お兄さんの人生においてわたしは「客の女」という役で登場している。ただの通行人と同じ匿名の存在、言わば端役として。お兄さんから見たコンビニは、いったいどんな場所なのだろう。
そのヒントを得られる傑作を読んだ。2016年に芥川賞に輝いた村田沙耶香の『コンビニ人間』である。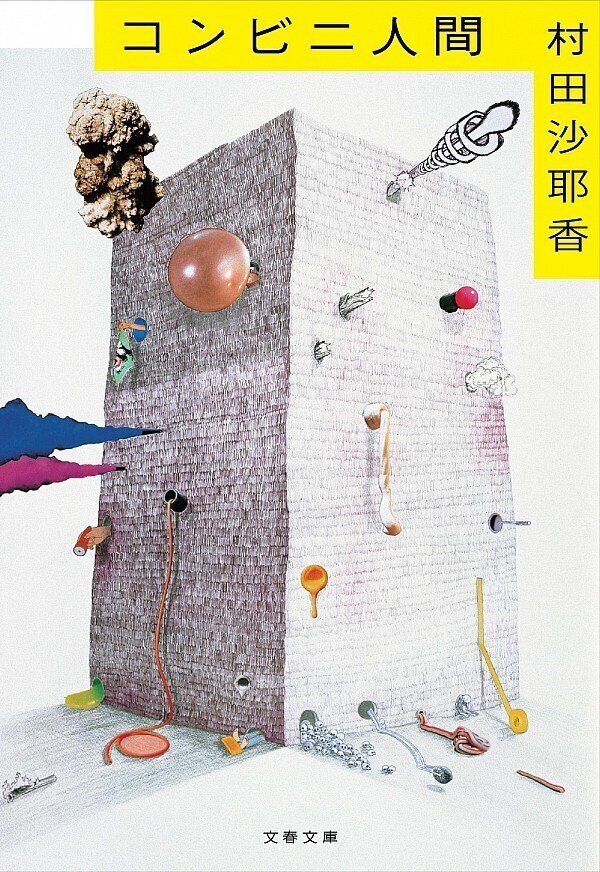
コンビニ店員に擬態する女
この本の主人公は古倉(ふるくら)恵子。コンビニバイト歴18年、36歳の独身女性だ。日本に住む人にとって最も身近なコンビニを舞台に、社会から奇妙にずれた感覚を持つ恵子が「コンビニ店員」として擬態しながら生きる日常が描かれる。
擬態という表現は誇張ではない。恵子のキャラクターを物語るエピソードは端々に登場するが、それは文章の心地よい流れに不気味な裂け目として現れ、読者の神経をやわらかく逆撫でする。例えばこんなシーン。
働く前の泉さんは少し派手だが三十代女性らしい服装をしているので、履いている靴の名前やロッカーの中のコートのタグを見て参考にしている。一度だけ、バックルームに置きっぱなしになっていたポーチの中を覗き、化粧品の名前とブランドもメモした。それをそのまま真似してはすぐにバレてしまうので、ブランド名で検索し、そこの服を着ている人がブログで紹介したり、どちらのストールを買おうかな、と名前をあげている他のブランドを着ることにしている。
雑誌を見て服装や化粧品を参考にするのと似ていてスルーしそうになるが、ちょっと変だ。恵子はバイト先の泉さんという同世代の女性に直接聞くのではなく、本人のいないところで持ち物を黙って手に取り、盗み見て、一般的な三十代女性の格好をトレースしている。
なぜそんなことをするのか。「普通」がわからないからだ。「普通」が欠落した恵子が思ったことを口にしたり、したいことを行動に移したり、つまり自分らしくふるまってしまうと、他人の目には常軌を逸した奇行に映る。だから周りの人間を観察し、意識的に言動を真似て風景になじもうとする。それは周囲から浮かないため(むしろ沈んだままでいるため)に身につけた処世術なのだ。
そんな恵子の「異質さ」がもっと劇的に描写されるくだりもあるが(死んでいる小鳥を見て食べよう、と言った少女時代の話とか)そこよりも、上に挙げたシーンのようによく読むと変だな…と気づく瞬間に背筋がヒヤリとする。
“普通”が群れをなして襲ってくる
恵子はコンビニ店員に擬態する時、水を得た魚のように生き生きとしている。「初めて、世界の部品になることができた」と安心する。だが結婚や就職で社会と接続することなく高校卒業後からずっとコンビニバイトを続ける人生を、周りは放っておいてくれない。
地元の友人たちと会えば土足で詮索され、乱暴に推測され、求めていないのにジャッジされる。自分たちの日常おいてエラーと認識したらその存在を簡単に排除する人たち。恵子はなんとか当たり障りのない会話を取り繕おうとするが、うまくいかない。
気が付くと、小学校のあのときのように、皆、少し遠ざかりながら私に身体を背け、それでも目だけはどこか好奇心を交えながら不気味な生き物を見るように、こちらに向けられていた。あ、私、異物になっている。ぼんやりと私は思った。
物語の序盤こそ恵子の異物感は際立つが、読み進めていくうち、段々と「普通の人間たち」に潜む暴力性があらわになっていく。彼らは張り付いた笑顔の表情ひとつ変えずに普通という凶器で殴りかかる。さながらゾンビ映画だ。その豹変ぶりもおどろおどろしいというよりパッケージ化されたコンビニ商品のように人工的で清潔に見えるのが面白く、同時に恐ろしい。
不適合者は海を越えて
芥川賞受賞だけでもものすごいが、GQの記事によれば2018年にはサリンジャーやカポーティなど名だたる作家を輩出したアメリカの『ザ・ニューヨーカー』という歴史ある雑誌で「THE BEST BOOKS」に選ばれ、現在までに約30ヶ国語に翻訳されている。
記事の内容がとても興味深い。イギリスだとこの『Convenience Store Woman』は「フェミニズム小説」の文脈で読まれるのだという。一方、アメリカでは「爆笑した」という感想も多いとか。どちらの意見もなるほど、と思う。マニュアル化された女性の生き方に興味を示さない恵子にはある種の自由さを感じるし、普通だと思っていた登場人物たちが突然牙を剥く展開は(ゾンビ映画が時々そうであるように)コミカルでもある。
目を引くのはこの本を「THE BEST BOOKS」に選出した記者のケイティ・ヴァルドマン氏が使ったミスフィット(misfit)というワードだ。「主流から外れた人、環境に適応できない人」のことを指すこの英語に、わたしはいたく感動した。
たとえばこれを日本語に置き換えると「不適合者」になってしまう。あきらかに印象が異なる。不も適合も者もすべての単語が重すぎるし、こうなったのはお前の責任だとでも言いたげな突き放した感じすら漂う。「自分もちょっと恵子っぽいところあるな…」と共感する人は日本でも多い気がするが、じゃああなたは不適合者ですか?と聞いたらギョッとさせてしまうだろう。
ミスフィットと不適合者、二つを並べてみるとミスフィットのほうが圧倒的にキャッチーで、どこにでもいそうだし誰にでもあてはまりそうな雰囲気がある。恵子は不適合者として海を渡り、ミスフィットとして紹介され世界でファンを得た。ケイティ・ヴァルドマン氏の作品への読解力と卓越したワードセンスが一役買ったのは間違いないと思う。
結末部分をどう読み解くかは意見が分かれるだろう。勝手にキャッチコピーをつけるなら”行き止まりのハッピーエンド”としたい。自分にとってなくてはならない場所を見つけたら、そこがどこであろうと光は射す。わたしはいつのまにか不適合者、いやミスフィットの恵子にエールを送っていた。どうか思うまま生きてほしい、と。それは自分自身への励ましでもあることに読み終わってふと気づくのだった。
「ありがとうございましたまたお越しくださいませー」
本を閉じ、わたしはセブンイレブンへ向かった。恵子の目を通して、もう一度コンビニという空間を見てみたくなったからだ。
「いらっしゃいませー」
あのお兄さんは今日もレジで待っていた。茶髪を一つに結びさらに清潔感が増している。わたしが近づくと隣にいる女性の店員さんとの話を自然に終わらせて商品をスキャンしていく。流れるようなスムーズなレジ打ち、過不足のない対応、わずかににじむ人間らしさ。完璧である。だからこそ気になる。彼もまたコンビニ店員に擬態した「コンビニ人間」なのだろうか? そう思って好奇の目を向ける客の女を、お兄さんはバックルームで「ヤベー奴」と噂しているのかもしれない。
ここまでよりみちしてくださり、ありがとうございます!左下のスキボタン(♡)を押してくださると嬉しいです。ビジネスに役立つ記事、エッセイなどもマガジンにまとめています。ぜひ読んでみてください。
