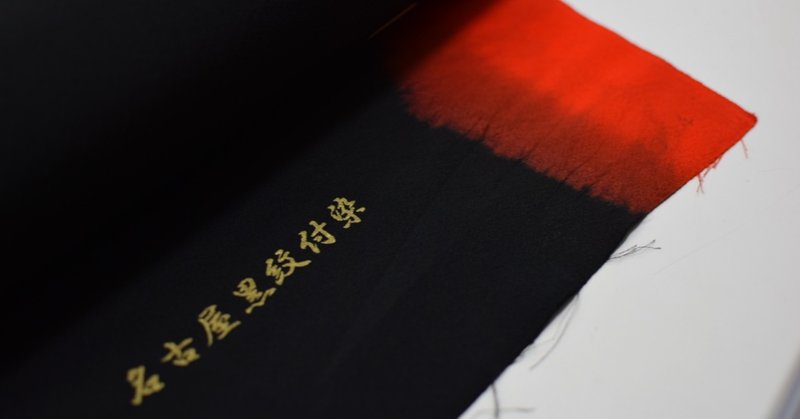#やっとかめ文化祭
閉幕!やっとかめ文化祭2020
8年目にして多くが新しい形となったやっとかめ文化祭も閉幕を迎えました。
誰もが初めて経験することばかりで試行錯誤の連続だったことでしょう。
最後のまちなか披露も演目は事前収録によるオンライン配信、開終演と幕間に星ヶ丘テラスからの生配信となりました。
画面の中のお客さまに思いを託し、オンライン配信を知らずに来てしまった客かのように、充電やデータ容量の都合で演目を見られぬまま、あいち戦国姫隊の方々
芸どころ名古屋舞台〜狂言「蟹山伏」、能「安達原」〜
観覧できる公演が絞られた今年のやっとかめ文化祭、芸どころ名古屋舞台に狂言と能が組まれました。
毎年人気の辻狂言はオンライン配信となりましたが、今年唯一の公開公演を舞台で、能はろうそく能として、一席開けた前売完売の名古屋能楽堂で行われました。
クール・ジャパンの一環とされたクール要素のある狂言や能とは?
狂言「蟹山伏」。山の中に大きな蟹が現れるだけで恐怖ですが、耳をめがけて襲ってくる姿はハンター
名古屋城調査研究センター公開講座 石垣から語る名古屋城 午後の部
どこから石を運んでいたのだろう?どうやったら、あんなにキレイに積むことができるのだろう?石垣のしくみ、歴史について学び、刻印探しを楽しみました。
名古屋城調査研究センターは、名古屋城の歴史を明らかにするために各分野の多くの学芸員が終結。この講座にも、文献史学の木村さんのほか、美術史学、考古学の専門家のお二人も参加されていました。貴重な講座です。
まずは、木村さんの講義から。名古屋城の石垣につい